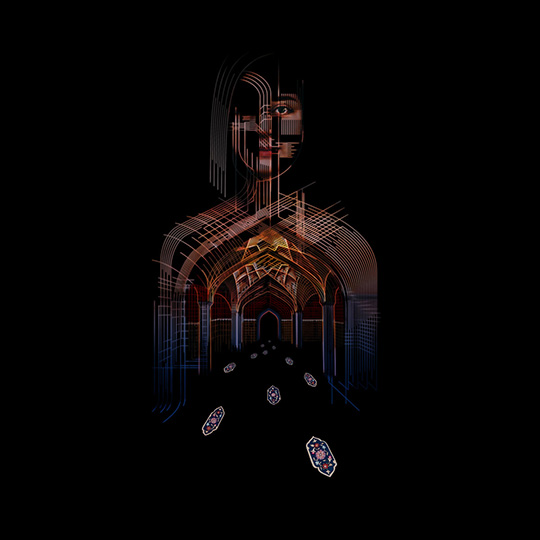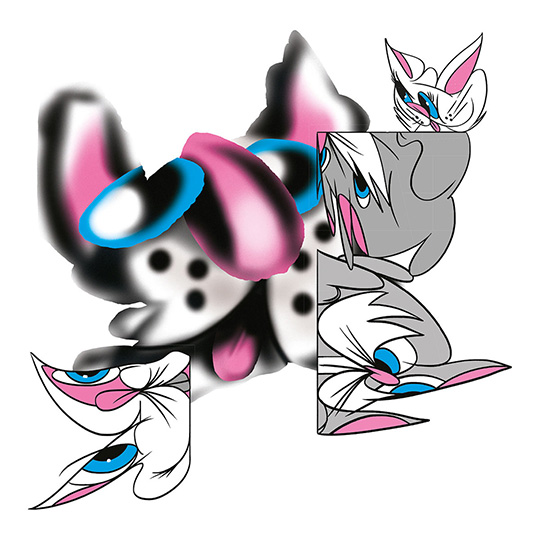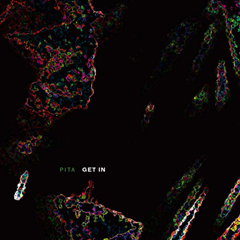MOST READ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- Beyoncé - Renaissance
Home >
Interviews > interview with Jim O'Rourke - なにかが正しくない
『シンプル・ソングズ』の周縁〜完全読本こぼれ話
 Jim O’Rourke Simple Songs Drag City / Pヴァイン |
 別冊ele-king ジム・オルーク完全読本 ~all About Jim O'Rourke~ ele-king books |
1999年の『ユリイカ』は、80年代末から90年代初頭、ハードコアな作風で頭角をあらわした彼のポップな側面を示したもので、実験性とポップさとの混淆は当時音響とも呼ばれ、往時を偲ぶよすがにいまはなっている。そこから16年、『ユリイカ』を継いだ『インシグニフィカンス』(2001年)から数えても干支がひとまわりしてあまりあるあいだ、ジム・オルークは自身の名義のポップ・アルバムを江湖に問うことはなかった。ブランクを感じさせないのは、彼はプロデュースやコラボレーション、あるいは企画ものの作品に精を出してきたからだろうし、おそらくそこには心境と環境の変化もあった。ひとついえるのは、『シンプル・ソングズ』ほど、「待望の」という冠を戴くアルバムは年内はもう望めないだろうということだ。そしてその形容は過大でも誇大でもないことはこのアルバムを手にとったみなさんはよくわかってらっしゃる。まだの方は、わるいことはいわない、PCのフタを閉じてレコ屋に走るがよろしい。ついでに本屋に立ち寄って『別冊ele-king ジム・オルーク完全読本』をレジにお持ちいただくのがよいのではないでしょうか。『シンプル・ソングズ』のあれやこれやはそこに書いてある。
余談になるが、今回の別エレでつきあいの古い方々に多く発注したのは、彼らが信頼のおける書き手であるのはもちろん、かつて勤めていた媒体が復活すると耳にはさんだせいかもしれない、とさっき思った。対抗するつもりは毛の先ほどもなかったけれども、意識下では気分はもうぼくたちの好きな隣町の七日間戦争ほどのものがなかったとはいいきれない。つーか内ゲバか。と書いてまた思いだした、『完全読本』の巻頭インタヴューでジムさんは「Defeatism」つまり「敗北主義」なる単語を日本語でも英語でも思い出せなかった。話はそのまま流れたので、そのことばはどの文脈に乗せたものか、もはやわからないが、メジャーとマイナーという二項対立では断じてなかった。
本稿は『完全読本』掲載のインタヴューより紙幅の都合で割愛した部分と、別日に収録したものをミックスしたものであり、『シンプル・ソングズ』のサブテキストのサブテキストの位置づけだが、ジム・オルークにはこのような夥しい聴取の来歴があることをみなさんにお伝えしたかった。まったくシンプルにはみえないが、すべては音楽の話であるという意味ではシンプルこのうえない。
当時は〈Staalplaat〉が勢いがあった時期で、毎日レーベルのオフィスに顔を出していたね。
■ジムさんがヨーロッパによくいたのは何年から何年ですか?
ジム・オルーク(以下JO):88年からですね。そのときはまだ大学生だったので、学校が休みになったときにヨーロッパにいっていました。
■アイルランドに行ったついでに大陸に足を伸ばしたということですか?
JO:アイルランドは高校生のときですね。大学のときはまっすぐアッヘンに行っていました。アッヘンを拠点にしていました。
■アッヘンに行ったのは――
JO:クリストフ(・ヒーマン)さんがそこに住んでいたからです。彼のご両親はビルをもっていて、その1階は狭かったのでドイツの法律ではたぶん賃貸に適さなかった。それで倉庫というか、実際はクリストフさんのスタジオになっていたんですが、彼はあまりそこを使っていなくて、それで欧州滞在時の私の部屋になったんですね。あのときはライヴをするといっても、一ヶ月の間に2回、せいぜい3回くらいで、アムステルダムでライヴがある場合は当時アムステルダムに住んでいたジョン・ダンカンさんのところに2、3週間やっかいになる、そんな生活でした。アンドリュー・マッケンジーさんも近くに住んでいました。当時は〈Staalplaat〉が勢いがあった時期で、毎日レーベルのオフィスに顔を出していたね。
■クリストフ・ヒーマンと出会ったきっかけはなんだったんですか?
JO:88年だったと思いますが、クリストフがオルガナムとスプリットの12インチを出すことになっていたんですね。オルナガムのデイヴ・ジャックマンはそのとき私の出したカセットを聴いていたらしく、ジャックマンがクリストフに「ジム・オルークといっしょにやったほうがいい」と手紙を書いたんですね。それでクリストフさんに誘われて、船に乗ってアッヘンに行ったんです。
■デイヴィッド・ジャックマンがつなげたことになりますね。
JO:その大元はエディ・プレヴォーさんです。私は13歳のときにデレク・ベイリーと知り合って、15歳のときにエディさんとも面識ができました。私はエディ・プレヴォーとデイヴィッド・ジャックマンとスプリットLP(『Crux / Flayed』1987年)が大好きでしたから、エディさんにそういったら「じゃあデイヴィッドと会ったほうがいいよ」と。デイヴィッドさんに会ったら、オルガナムを手伝ってくさい、となり、デイヴィッドさんがクリストフさんに紹介して――といった感じですね。オルガナムには6、7年間参加していました。クレジットはあったりなかったりですが。
■なぜクレジットがあったりなかったりするんですか?
JO:それがデイヴィッドさんのスタイルなんです。彼の音楽なのでクレジットは私は気にしない。でもときどき書いてありました。だから私もどのレコードに自分が参加したのが100%はわからないんですね。
■憶えていない?
JO:録音したのは憶えていますが、音楽を聴いてもわからない(笑)。
■オルガナムではジムさんはなにをやったんですか?
JO:ギターとベース。ですが演奏というよりミックスでした。最初にやったときは演奏だけだったんですが、そのとき録っていたスタジオのエンジニアのミックスをデイヴィッドさんは気に入らなかったらしく、私に試してみてくれといったんですね。それで私のほうを気に入ったから、それからお願いされるようになりました。94、95年くらいまではやっていたと思います。でもそれは仕事ではありません。チャンスがあればいつでも参加しました。
■デイヴィッド・ジャックマンはどういうひとですか?
JO:いわゆる「英国人」です(笑)。60年代の共産主義ラディカルを体現したようなひとでした。キース・ロウと同じ世代ですから。
■コーネリアス・カーデューもそうですね。
JO:そうです。キース・ロウさんはスクラッチ・オーケストラですから。でもじつはキースさんよりデイヴィッド・ジャックマンのほうがキンタマがあったね(笑)。これは簡単にはいえませんが、彼らの政治的なスタンスにかんしては、そういうひとたちは反対意見にたいして、自分たちが正しいと意固地になる傾向があると思うんです。ところがデイヴィッドさんは相手が共産主義者であるかそうでないか気にしない。かたいひとですが、かたいだけじゃない。
■いまでも連絡することがありますか?
JO:ときどきありますが、彼は頻繁に連絡をとりあうタイプの方ではないです。私はあのとき、イギリスにいましたから連絡は簡単でしたが、いまは日本ですからほとんど連絡しません。彼はインターネット世代ではない。インターネットを使ったこともほとんどないでしょう。連絡はもっぱら手紙。電話もなかったかもしれない。私もいまはすこしそういった感じですが(笑)。
メディアがひとの聴き方をコントロールする時代ではなかったのですから。いまの日本のようにAKB一色じゃなかった。どうしてフランク・ザッパを知ったんですか、と訊かれることがありますが、フランク・ザッパはファッキン人気だった。
■ジムさんはそういう世代から考え方の面で影響は受けましたか?
JO:もちろん受けました。意識してはいませんでしたが。というか、私はまだ10代でしたから、なにもわかりませんよ。私はアメリカ生まれでしたが、両親はアイルランド人でアメリカは関係なかったですから、あのひとたちのほうがかえってわかりやすかったんです。
■ヒーマンさんなんかはエディさんやデイヴィッドさんより、近い世代ですよね?
JO:ヒーマンさんは私より年上ですが、私と会ったとき、私は18、19で彼は23、24。ちかい感じはありました。あのとき彼はまだH.N.A.S.をやっていましたね。
■H.N.A.S.についてはどう思いました?
JO:『Im Schatten Der Möhre』は好きでした。クリストフさんの先生はスティーヴン・ステイプルトンなんですね。でも私はそのとき彼は好きではなかった。
■でもジムさんはナース・ウィズ・ウーンドといっしょにやっていますよね?
JO:うぅ。でも会ったことはありません。一度だけ電話で話しました。いいひとだと思うけど、NWWは私は好きじゃない。
■どういうところが?
JO:スティーヴン・ステイプルトンはすごくレコードを蒐集しているんですが、彼がつくるほとんどの音楽は現代音楽のコピーだと思う。たとえば、この曲はロバート・アシュリーの“シー・ワズ・ア・ヴィジター”とかね。クリストフさんはスティーヴン・ステイプルトンのお陰で現代音楽にめざめたところがある。私は逆でした。コピーするのは問題ないんですよ。でもなにかが足りないだね。現代音楽のカヴァー・バンドに聞こえる。当時私は大学でそういった音楽を勉強していましたから、なおさらコピー、チープなコピーに思えたんです。それでよくクリストフとケンカなった(笑)。それでNWWは好きじゃなかったんですが、ときどきほんとうに音楽が彼のものになることがあって、それはおもしろかった。
■ジムさんは10代の頃から現代音楽には深く親しんでいたんですね。
JO:そうですが、現代音楽はけっしてアングラなものではありませんよ。ジョン・ケージは生きていましたし――
■だからといってだれもが聴くわけではないですよね。
JO:それは関係ない。メディアがひとの聴き方をコントロールする時代ではなかったのですから。新聞で雑誌でそういうものを読むこともできました。いまの日本のようにAKB一色じゃなかった。どうしてフランク・ザッパを知ったんですか、と訊かれることがありますが、フランク・ザッパはファッキン人気だった。彼は有名人。普通のレコード屋にも彼のポスターが貼っていたんですよ。これは30年前の話ですが、いまから30年後には「どうしてあの時代、灰野敬二を聴いていたんですか?」ともしかしたら訊かれるかもしれませんが、灰野さんは現役でライヴもやっています。レコード屋にはいればレコードがある。ふつうのレコード屋にもジョン・ケージもフィリップ・グラスもヘンリー・カウの仕切りもあったんです。まったくヘンなものではなかった、だれもが見つけることができる音楽。
そう訊かれるのが私のいちばんのフラストレーションでもあります。私とだれかが同じタイミングでレコード屋にはいれば、そのひとがヒット曲のレコードを買うように、私はオーネット・コールマンのレコードを買うことができた。私がえらいわけではありません。もしそのひとが左に曲がれば、同じようにオーネット・コールマンのレコードを買ったかもしれない。フィリップ・グラスもスティーヴ・ライヒもCBS、メジャー・レーベル・アーティストですよ。インディペンデント・レーベルの文化がまだない時代のことですね。独立レーベル、プライベート・プレスはありましたが。
私は最初のカセットには「Composed by Jim O’Rourke」と書きましたが、それ以来書かなくなったのは、最初のカセットではシュトックハウゼンとか、そういった作曲家の影響があったにしても、20歳のころ、あの世界とは関係しないと決めたからです。
■ジムさんはそういったインディペンデント・レーベルができたことで音楽が区別されるようになったと思いますか?
JO:たとえば大学では、音楽を勉強して修士になり博士になる。大学に残りつづけて先生になり、生徒が自分の作品を演奏する。死ぬまでの目的が決まっている感じがしました。同時にハフラー・トリオやP16.D4のような音楽、RRRレコーズのような音楽とピエール・アンリやリュック・フェラーリのどこがちがうのか。そこから私は、自分をコンポーザーと定義するのが好きじゃなくなったんです。現代音楽の世界――それは音楽そのものではなくて、そのやり方です――にアレルギーを覚えはじめた。これは正しい言い方ではないと思いますが、ブルジョワジーの歴史をつづけることに荷担するのがイヤになったんです。彼らがそれに気づいているかどうかは関係ありません。ただそこには参加したくなった。それで、私は最初のカセットには「Composed by Jim O’Rourke」と書きましたが、それ以来書かなくなったのは、最初のカセットではシュトックハウゼンとか、そういった作曲家の影響があったにしても、20歳のころ、あの世界とは関係しないと決めたからです。私が電子音楽をやる場合でも、私が自分の曲をコンポジションと定義し、そういうひとに評価され、その世界で仕事するようになればその世界の住人になる。そこには参加したくないから意識的に「Composed by」のクレジットはいれないことにしました。これはほんとうに私の人生ですごく大事なことです。
■心情的にイヤ?
JO:その世界の10%はいいものですが、のこりの90%はゴミです。そんな世界、ゴメンです。大事なのは作品です。私が人間として大事なのではない。あのゲームはやりたくない。
■ジムさんが好きだった作曲家といえば当時どういったひとでした? フィリップ・グラスとか――
JO:グラスは75年までですね。だって私はそれまでずっとそんな音楽ばっかり聴いていたんですよ。チャールズ・アイヴズはもちろん好き。電子音楽はもっといっぱいいます。リュク・フェラーリだってそうですし、ローランド・ケインは電子音楽のなかでもいちばん好きで、オブセッションさえあります。彼の音楽だけは、どうしてそうなっているのか、まだわからない、秘密の音楽なんですね。ほとんど毎日勉強する、ちゃんと聴いていますよ。彼は電子音楽についてはもっとも影響力のあるひとだと思います。影響という言葉とはちがうかもしれない。彼の音楽はそうなっている理由がわかりませんから、具体的な影響とはいえないかもしれない。大学のころに聴いていた現代音楽の作曲家の作品はほとんど聴かなくなりました。
■いま、たとえばトータル・セリエル、ミュジーク・コンクレート、偶然性の音楽、そういった現代音楽の分野でいまだ有効性があるものはどれだと思いますか?
JO:大学のころ、私はピエール・ブーレーズにすごいアレルギーがありました。ぜんぜん好きではなかった。それが過去5年の間に、偶然入口を見つけました。もちろん全部の作品が突然好きになったのではなくて、とくに“レポン”という作品はよく聴いていて、すこしわかるようになりました。
トータル・セリエルの問題は音楽がスコアにはいっているということです。100%そうだとはいいませんよ。でもそれはすごい問題です。
■ミュジーク・コンクレートのようなスコアで表せない音楽を、ジムさんは評価するということですか?
JO:そういう意味じゃない。セリエルのスコア、コンポジションの考え方は、八分音符から三連符になり、その逆行形になって――という考えを捨てない。とくにアカデミックなコンポーザーは。考え方が全部スコアにはいっている。そう考えると彼らの言語はほんとうに「細い」と思う。だから彼らは彼らの音楽を聴いたひとが「わからない」というと、それを聴いたひとのせいにするのです。でもわからない理由の半分は彼らの側にもあると思う。スコアにC(ド)の音を書く、しかしそれはただのCではない。そこには音色がありニュアンスがあります。彼らのスコアを音楽にするにも次の翻訳の段階が必要なんだと思う。どうしてそれをやらないか、私はわかりません。そういう音楽をやることがまちがっていると私はいいたいのではありません。ただそれをわからないのを聴いたひとのせいにするのは失礼です。
99.9%、ケージの音楽はフリーではありません。チャンスの音楽といいますが、ケージは彼の言葉をスコアに注ぎたくない。彼の立場は、音楽から自分の言葉や存在を消し去るということなんです。
■ケージの偶然の音楽はどうです?
JO:ケージの音楽は偶然ではありません。それを語りはじめるとそれだけで本になります(笑)。ケージの音楽をやったことがないひとはたぶんわからないと思う。ケージの音楽はかなり難しい。問題は彼のスコアは表面的に理解するには苦労しません。でも簡単じゃないんです。
■簡単じゃないというのは自由がないということですか?
JO:99.9%、ケージの音楽はフリーではありません。チャンスの音楽といいますが、ケージは彼の言葉をスコアに注ぎたくない。彼の立場は、音楽から自分の言葉や存在をどうやって消し去るかということなんです。それはチャンスではない。正しくとりくめばそれがわかるはずです。私は音楽家としてケージの作品を何度か演奏しましたが、いっしょに演奏したひとたちがまったくわかっていなくて、ムカついたこともありますし、逆に勉強しすぎて音楽がかたくなったこともあります(笑)。その意味でもケージの音楽は難しい。
■勉強しすぎてもダメだし勉強しすぎてもダメ?
JO:しないのはいちばんダメで(笑)、でも勉強やりすぎてもね。両方地獄だね(笑)。でも私のこの考えが100%正しいといいたいのではない。
■フルクサスとジョン・ケージは同じくくりに入れられることがありますが、同じだと思いますか?
JO:まったくちがいます。
■フルクサスはどう思います?
JO:あんまり興味がない。ボンボンの遊び。若いときにそういった考えになるのはわからなくもないですよ、でも50代でも同じことをやっているのはちょっとどうかと思う。
■ハプニングはどうですか?
JO:歴史的に、次の段階に向かうためにそういったことが必要だったのはよくわかりますよ。歴史に敬意を払うことは、いま現在、作品をどう聴くかということと無関係です。ハプニングのような作品は尊敬はしても、(私には)ほんとうに関係がないんです。それにフルクサスはアートの世界のものです。
取材・文:松村正人(2015年5月21日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE