MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル
Home > Interviews > interview with D.A.N. - 凍るような、燃えるような、平熱
 D.A.N. EP SSWB / BAYON PRODUCTION |
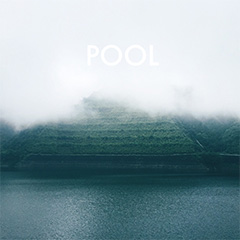 D.A.N. POOL SSWB / BAYON PRODUCTION |
「D」の文字だけがあしらわれたジャケットは、この3ピース──D.A.N.の矜持と美意識をミニマルに表現している。東京を拠点として活動するそれぞれまだ二十歳そこそこの彼らは、ポーティスヘッドといえば『サード』からの記憶がリアルタイム。あきらかに本作「EP」のジャケットからは『サード』やトリップホップ的なものへの共感が見てとられるが、あのベタ塗りのビリジアンをぼんやりとした靄の奥に沈めたのは、彼らと、たとえばウォーペイントとを結ぶ2010年代のフィーリングだ。
甘やかな倦怠とサイケデリア、同時に清潔でひんやりとした空気をまとったプロダクション、芯に燃えるような音楽的情熱。……倦怠が微弱な幸福感と見まちがわれるような、クールで起伏の少ない現代的感情の奥に、凍ったり燃えたりするための燃料源が音楽のかたちをして揺れている。ひたすら反復しながら、しかしそれによってトランシーな高まりを期待するのでもない“Ghana”などを聴いていると、現代の純潔とはここにあるのだとさえ言いたくなってしまう。
よく聴くとすべて日本語で、詞は押し付けられることなく、しかし引くこともなく耳裏に流れ込んでくる。ことさらヨウガクともホウガクとも感じることなく、たとえば〈キャプチャード・トラックス〉や〈4AD〉の新譜を聴くように聴けて、かつ「東京インディ」というひとつの現代性の表象をリアルに感じとることもできる。なるほど世界標準とはこういうことなのだと思わせられる──それはまずよそ様ではなく自分たちのリアルへの感性の高さを条件として、表現として外のシーンへと開かれている。〈コズ・ミー・ペイン〉の感動から、さらに時計の針は進んでいる。
前置きばかり長くなってしまったが、東京を拠点として、いままさにインディ・シーンを静かに騒がせようとしているこの3人組の音と言葉を聴いていただきたい。時代性についての言及が多くなってしまったが、音のトレンドも汲みながら、スタイリッシュな佇まいも強く持ちながら、しかし根本にあるのは本当にウォーペイントに比較すべきオーソドックスなギター・バンドの魅力でもある。あまり考えず構えず、何度も何度も再生ボタンを押せる作品だ。これがデビューEPということになるが、ウォッシュト・アウトの「ライフ・オブ・レジャー」しかり、ある意味ではすでにフル・アルバムに等しい価値と象徴性を持っていると言えるかもしれない。これをリリースしてしまったことが、彼らの壁になりませんように──。
■D.A.N / ダン
東京出身、21歳の3人組。メンバーはDaigo Sakuragi(Vocal,guitar,synth)、Jinya Ichikawa(Bass)、Teru Kawakami(Drum)。ライヴ活動を通じて注目を集め、2015年には〈フジ・ロック・フェスティバル〉の《Rookie A Go Go》に出演するなど活躍の幅を広げている。同年7月には、自身らの自主レーベル《Super Shy Without Beer》通称《SSWB》を立ち上げ、Yogee New Waves、never young beachを手掛けるBAYON PRODUCTIONのバックアップの下、初の公式音源『EP』をリリースした。9月には配信限定でファースト・シングル「POOL」も発表されている。
僕は前からトリップホップが好きで聴いていたんです。(市川)
■ジャケットをもらって最初に思ったのが、「うわーポーティスヘッドだなー」っていう(笑)。みなさん的に、いまポーティスヘッドなんですか? それとも3人の音楽体験の深いところにあるものなんですか?
川上輝(以下、川上):ジャケに関しては、音楽的なところとはあんまり関係ないかもしれないですね。
■でも何がしかの影響はある?
川上:影響はありますね。ありますけど、ジャケに関してはヴィジュアルでもう、かっこいいなと思いました。
桜木大悟(以下、桜木):どういうジャケットが好きか、って話し合ったときに、サード(ポーティスヘッド『サード』、2008年)がすごくいいなと。
市川仁也(以下、市川):最初に店頭に並んだときにインパクトがあって、かつシンプルなのがいいって思ったんです。ポーティスヘッドの「P」って書いてある『サード』はその点でずっと頭に残っていて、「こういうのもいいんじゃない?」って案を出して、そこからより膨らんでいって。
■ジャケットってひとつの勝負をするところでもあるじゃないですか? そこに自分たちを主張したくてたまらないってもののはずなのに、「Dだけ?」みたいな。ある意味では最強の主張かもしれないですけどね。メッセージとかスタンスを感じるいいジャケだなと思いました。
話を戻しますと、ポーティスヘッドって、いま来てる感じなんですか? それとももっとパーソナルなものです?
市川:僕は前からトリップホップが好きで聴いていたんですけど。
桜木:僕も仁也の影響で意識して聴くようになったんですけど、それはわりと最近。聴き直してますね。
川上:僕もです。
■リアルタイムじゃないですよね?
桜木:ぜんぜんちがいますね。僕らが生まれたくらい。
■ちょうど2、3号前の『ele-king』で、ブリストル特集をやったんですよ。ベースミュージックなんかを中心に、リヴァイヴァルのタイミングではあると思います。そういう時代感がどこかにあったりでもなく?
桜木:自然とじゃないですかね。音楽から抜けるというか、そういう流れとはまたちがうのが好きなんじゃないかみたいな。作曲をしているときにふと出てきて、「うわぁ、めっちゃこれじゃん!」みたいな。
市川:「いま何がやりたいんだろう? 自分たちがどんな音楽を作りたいんだろう?」って模索していたときに、「あっ、これ」みたいにビビっときて。まんまこれをやろうってやったわけじゃないんですけど。
川上:やっと理解できるようになったっていうところはあるかもしれない。まじめに音楽をやってきて、行き詰まって、「俺は何をやりたいんだろう?」って思っていたとき、そういうのを聴いたら「かっこいいじゃん」ってちゃんと認識できるようになったと思います。
ある程度やっていたんだけど、「これじゃないかもしれない……、この音楽をやる意味は何なんだろう?」みたいな。(川上)
■そんなに若いのに、もうすでに行き詰まりがあったと(笑)。私は、なんとなく自分と同じ世代なのかなという感覚で聴いていたんですけど、実際は皆さんとひとまわりも歳が離れているんですよね。しかも結成は去年でしょう? 同級生的な感じですか?
市川:僕と大悟が小学生からの同級生で。僕らはバンドを高1くらいからはじめて、そのときに輝と知り合ったんです。僕と輝はバンドを別で組んでいたんですよ。
川上:彼らの幼なじみで高校からはじめたバンドがふたつあって、その片方に仁也がいて、そのバンドのドラムが抜けて、たまたまそのとき僕が出会って入って、高校から大2くらいまでそのバンドをずっとやっていたんです。
でも、ある程度やっていたんだけど、「これじゃないかもしれない……、この音楽をやる意味は何なんだろう?」みたいな。
市川:先がないというか。
川上:奇をてらうことにバンドで徹していたというか……。
■たしかにそれは行き詰まりっぽいですね(笑)。ひとの名前を借りるのは嫌かもしれないですけど、だいたいどんな音楽をやっていたんですか?
桜木:ニューウェーヴでした。完全に。ポスト・パンク……ギャング・オブ・フォーとか。
■奇抜な格好をして冷蔵庫をぶっ壊したりとか?
市川:それはないです(笑)。フリクションっぽいのとかやっていましたね。
桜木:あとはナンバー・ガールとかザゼン・ボーイズとか。
川上:高校生のとき、ナンバガはみんなめちゃくちゃ聴いていた。
桜木:僕らの青春です。
■ポスト・パンクって、2000年代はじめに盛大なリヴァイヴァルがあったわけで、たしかに皆さんから遠い存在でもないかもしれないですね。しかるに桜木さんのバンドはどうなんですか?
桜木:もともとアジアン・カンフー・ジェネレーションとか、エルレ・ガーデンとかそういうのが好きで、中学生のときに音楽をはじめました。高校生のときもそのままの流れで、日本語ロックっていうのかな。そういうのをずっとやってました。
■曲もずっと作っていたんですか?
桜木:そうですね。くるりとかそういうのをマネしながら、やっていました。
■なるほど。D.A.Nはミニマルとも謳われていたりしますけど、そこにギターがすごく色を乗せるじゃないですか? エモーションというか、情緒というか。そのへんの感覚というのはきっと桜木さんなんですね。
桜木:はい。
■いざこの体制になったのは去年ということですか?
桜木:はい。去年の夏ごろだったような気がするんですけど。
■そうするとみんなで同じ方向を見ていたというよりは、もう少し偶然的にいまの音楽ができあがっていると。
川上:前にやっていたバンドが2年くらい前に同じタイミングで解散したんです。「このメンバーでやる意味」とかそういうことを考えてましたね。
■けっこう考えますね。
川上:この音をこいつが出してるみたいな。そのあたりの信頼関係が揺らいでいたというか。「こいつが出している意味があるのか?」とかって考えていたから。それで話し合って解散して、1年くらいひとりでやったりとか、他のバンドで活動したりもしてました。そういう考える時期があって。それで大3くらいに、結局バンドをやりたいってなったんです。そしたら6人くらい集まったんですよ。
市川:去年の1月とかですね。
川上:そこでまた直面したのが、やっぱり音が多すぎるってことで(笑)。いままでとはまったくちがう面白いことをやりたかったから──ドラムがふたりいたりとか。
桜木:当時はツイン・ドラムが流行っていたんです(笑)。パーカッシヴなものを作りたいという意味でツイン・ドラムだったんですけど。ポーティスヘッドとかもいるじゃないですか? レディオヘッドもそうだし。トクマル・シューゴさんも普通にドラムを叩いてましたから、それに影響されて「いいんじゃない?」みたいな。
音楽をずっとやっていきたいって気持ちがあるからこそ、話し合いが何回もあったと思います。「自信を持っていいものを作るには、お前とじゃない。他のやり方が合っているんじゃないのか?」みたいなのを。(川上)
■なるほど。いろんな試行錯誤があったと。
川上:がっつりふたりともドラマーだったから、音がぶつかり合いまくって(笑)。お互いすごく気を使わないといけないというか、どこまでやっていいかわからないので……。それを考えている時点で前といっしょだな、みたいな。その時点でもう自由にのびのびと創造できないというか。そんなこんなで3ヶ月くらい曲ができなくて。それが去年の1月から4月くらいにかけてですね。もう、ずっと「どうする?」って話し合って。
桜木:いわゆる産みの苦しみとは別で、幼なじみだったので変な情とかもあったし。抜けていった3人のうちふたりも小学校からの同級生で、「何かちがうな」と思ってもはっきり言えないんですよね。言えないわけじゃないんですけど、情が介入していたというか……。
■6人もいれば、なんというか、それはもう社会ですもんね。サステナブルなものにするのは難しいですよね。
川上:それで踏み切って、7月に「もうさすがに決めよう!」ってデッカい話し合いがあって。
■その話し合いのエピソードもそうですけど、けっこうコンセプトをカチッと固めてるバンドだなって感じまして。一瞬、「なんとなくやってます」とか「意味とかないです」みたいな、そういう態度がこのアンビエントでダウナーな音楽性のうしろにはあるのかなと感じるんですけど、実際すごく決められている。
たとえば資料の文言──「このドライな3人で、無駄のない柔軟な活動を目指す」とか(笑)。
川上:それ僕が書きました(笑)。
■「いつの時代でも聴ける、ジャパニーズ・ミニマル・メロウを追求することをテーマにする」とか。
川上:それっぽく書いたんですよ(笑)。
■いやいや、そういうのって「べつに何も考えてないですよ」って言うのもアーティストのひとつの態度じゃないですか? それに対して、このゴリっと考えてる感じが新鮮だったというか。コンセプチュアルなバンドなのかなと思ったんですけどね。
桜木:これに関して言えば、野心が全面に出てます。
■すごくいいことなんじゃないですか。ロックなんてけっこう伝統的にみんなうつむいてたし、インタヴューなんて「はっ?」みたいなところがありましたけども。でも、ギラギラしてないのにしている感じが(笑)。
川上:音楽をずっとやっていきたいって気持ちがあるからこそ、話し合いが何回もあったと思います。「自信を持っていいものを作るには、お前とじゃない。他のやり方が合っているんじゃないのか?」みたいなのを、みんなうすうす感じていて、3人になる前に、それをはっきりと言おうという話し合いが最後にありました。本当に食っていきたいって思っていたので。
■そういう意味での野心ですか。ちょっと意地悪な質問をあえてすると、皆さんが本当に「ドライで無駄のない柔軟」なひとたちだとすれば、そう言わないと思うんですよね。これはそうでありたいという意思であって、実際は逆というか、ぜんぜんちがうみたいな意識があったりします?
桜木:ものすごく熱いです、自分。
ゴチャゴチャしてたりとか、あったかい音楽とか大好きですけど、自分たちが音楽をする上での美意識っていうのをひとつ決めてやっているんです。(桜木)
■ぜんぜん冷たくないんだ(笑)。
市川:6人のときの苦い経験があったので、ドライに、本当にいいものを作るために、同じ方法論でやるために、という意識というか。
川上:そう言っておいたほうがいいと思うんですよ。その謳い文句を。本当にそう思うし。
■それは自分たちにとって?
川上:外からの見え方とかそういうものを考えると。
■なるほど、戦略的な部分でもある。……なんか、ロック・ヒーローとかってどっちかというと「ウエットで無駄が多くてガチガチに凝り固まっている」ものだったりするじゃないですか(笑)。そういうのは自分たちのクールとはちがう感じなんですかね?
川上:その譬えから考えると、本来の姿はそうであるけど、言っているのはそれ(ドライで柔軟で無駄がない)だったらよくないですか?
■あー、ギャップがある方が?
川上:それが逆だとなんか……
■「熱い」と言っているのに「冷たい」みたいなやつよりもってことですか(笑)?
川上:そうですね。それが逆だとなんか変じゃないですか。
桜木:ゴチャゴチャしてたりとか、あったかい音楽とか大好きですけど、自分たちが音楽をする上での美意識っていうのをひとつ決めてやっているんです。
川上:かなり幅広く書いているつもりですね。
■音楽的な部分以外でも?
市川:ジャンルをまたぐっていうだけじゃなくて、姿勢もというか。こういう姿勢も持っているというのを出して。音楽というのはそのときの趣味もありますし、変わっていくものだとは思うんですけど。
■あとは「スーパー・シャイ」みたいなことも標榜されていますけれども(笑)。「あ、シャイであることっていまはカッコいいんだ!」みたいなことを感じましたね。
桜木:それは、この缶バッチ(「Super Shy」と書かれたバッジ)からとったんですよ。
■あ、そうなんですか? どれどれ……そのまんまじゃないですか!
桜木:これ古着屋さんに置いてあったやつで。
■えー。でもグッときましたよ。自分たちを「スーパー・シャイ」だと思います?
川上:それは何も考えないで決めたので、突っ込まれてもって感じですね(笑)。
■本当ですか? シューゲイズとかって、あのクツ見つめる感は、シャイっていうんじゃなくて、コミュニケーションをシャットダウンする感じじゃないですか。けど、シャイであるならば繋がれる可能性がある……ビールを飲んだりとかすれば(笑)。そういう、拒絶じゃない熱さみたいなものはどこかに感じます。
桜木:ただ、ビールというものは、いろんな言葉に置き換えられると思うんです。音楽もそうだし、何かのきっかけとかアクションだけで「スーパー・シャイ」から解き放たれるというか。
■ペダルを踏むみたいな感じで。
桜木:僕はそういうふうに解釈していますけど、そんなに深い意味はないですよ。後付けですから(笑)。
■いやいや。そうだったとしても、つい深読みたくなるのは、音楽にそれだけの厚みがあるってことだと思いますけどね。それに、それぞれのコンセプトも提起的ですよ。いろいろ語りたくなってしまう。
どこかしらウォー・ペイントだったり、ポーティスヘッドだったりジ・XXだったりとかに似ているもの出てきた、みたいなことはあります。でもそれは、「これはカッコいいよね」って出てきたものが、結果的に似てたって感じですね。(市川)
■さて、好きなバンドにウォー・ペイントの名も挙がってましたけど、すごくそれも感じますね。
桜木:ウォー・ペイント大好きっす。
川上:超好き。ちょうどいいところをホント突くんですよね。
■めっちゃくちゃわかります。でも不思議じゃないですか? ウォー・ペイントって日本でそこまでは盛り上がっていなかったし。
市川:僕らホント好きですよ。一時期ずっと聴いていました。
川上:「自分たちと同じじゃないか」って勝手に思ってます。
■私もすごく好きなんですけど、D.A.N.はめちゃくちゃウォー・ペイントだと思いました。
川上:ウォー・ペイントが日本人だったらぜったいに話が合うと思います(笑)。
■日本にはD.A.Nがいるからウォー・ペイントはいいか、というくらい、似たものを感じますね。ウォー・ペイントって、なんの時代性も象徴していないというか。ひたすらいいバンドなんですよ。だから真似するときに「チル・ウェイヴです」、「フットワークです」とかならマネしやすいですけど、「ウォー・ペイント」ですっていうのは難しい。本当に好きなんだなと思いましたね。
川上:ウォー・ペイントを特別に意識しているとかはとくにないですね。「これだ!」という感じに決めていることはないというか、決められたくはないというか。何にでも溶け込むものでありたいので。
市川:曲を作っているときでも「これよくない?」ってなって作っていくと、そこにどこかしらウォー・ペイントだったり、ポーティスヘッドだったりジ・XXだったりとかに似ているもの出てきた、みたいなことはあります。でもそれは、「これはカッコいいよね」って出てきたものが、結果的に似てたって感じですね。
■きっと彼女たちもそういうモチヴェーションなんだろうなって思うんですよね。うしろにジョン・フルシアンテがいたりするじゃないですか? ああいうちょっとしたギターのテーマみたいなものが、ときどき聴こえる感じとか──「冷たいけど熱い」みたいなところも似てるかなと思うんですけどね。
自分たちのなかの「熱さ」についてもうちょっと聴きたいんですけど、どのへんだと思いますか?
川上:精神的な部分だけど熱さはありますよ。僕はサッカー選手をとてもリスペクトしているので。すごく学ぶことが多いです。
■えっ、そうなんですか!
川上:姿勢についてとか、「音楽をやっているひとたちはみんな見習った方がいいんじゃないか」って思います。やっぱり彼らはつねにサヴァイヴァルなので。
■そうですよね。チームの戦いという意味ではなくて個人のという意味ですか?
川上:はい。チームとかはバンド全体のことになってきますよね。いろんな部分で似ていると感じるので、僕は音楽とサッカーがイコールだなと思っています(笑)。本気でそう思ってます。
市川:僕は自分がいいと思えるものを作るっていうところです。そこをとにかく追求していきたいし、そこができないならやっていても意味がないし。……音楽が本当に好きなんで。そこだけは絶対に曲げたくないというか。まずいいものを作るっていうところです。
川上:お互いをリスペクトしながら高め合える3人でやっているのがこの音楽ですから。そこはつねに基本ですよね。
取材:橋元優歩(2015年10月05日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE

