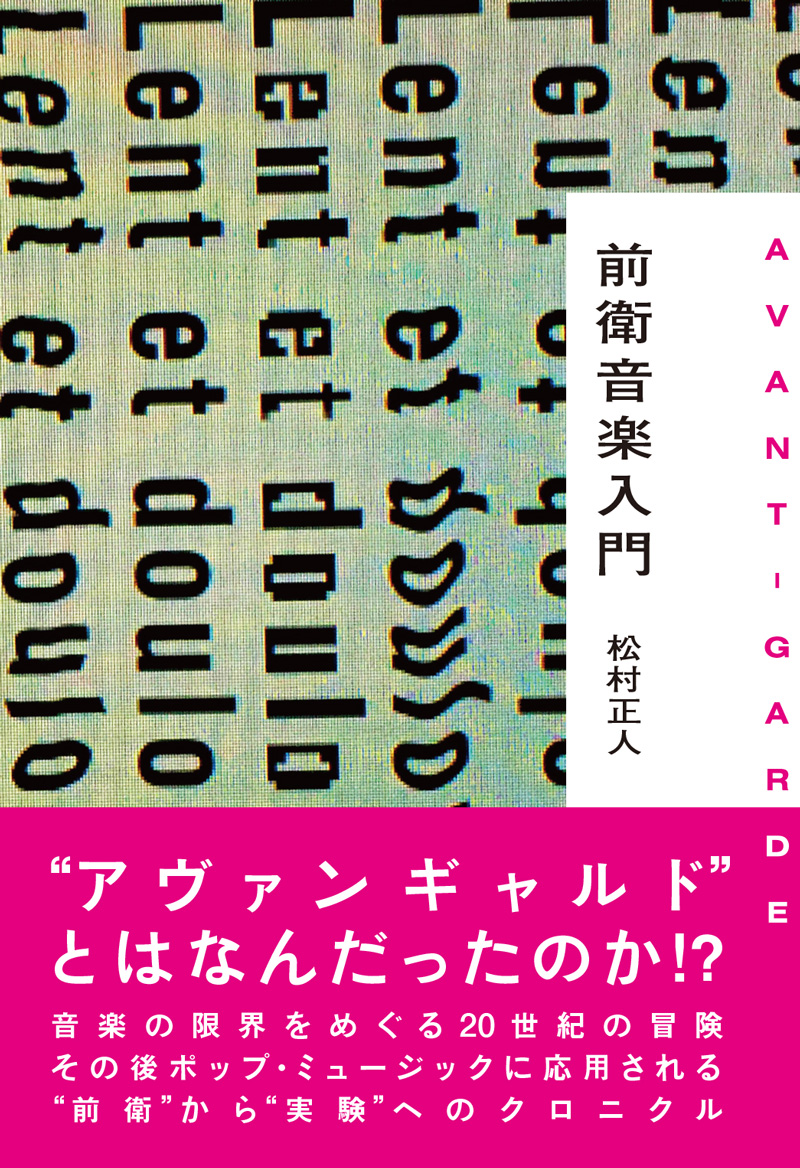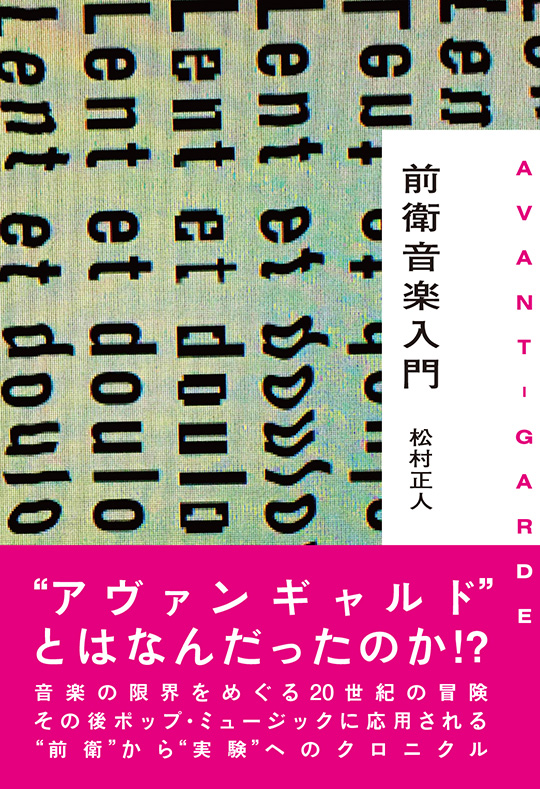MOST READ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- Beyoncé - Renaissance
Home > Interviews > interview with Masato Matsumura - これからの前衛音楽のために
前衛音楽という言葉を用いることにはどこか抵抗感があった。理由は二つある。一つ目は狭義の「前衛音楽」に関するものだ。そこでは結果の確定できない音楽を指す「実験音楽」と対比されるものとして、音の結果をどこまでも管理する西洋芸術音楽の理性の結晶のようなものとして「前衛音楽」は使われていた。そこに仄見えているある種の思い上がりとも言える優越心に嫌悪感があった。それに進取の精神に富んだ音楽実践であったとしても、必ずしも西洋芸術音楽の文脈に基づいているわけではない。にもかかわらず「前衛音楽」と名指した途端に、こうした理性的表現を追求する西洋由来の価値観に従うことになる。それは音の具体的実践を捉え損ね、ただひたすら権威におもねることになるだろう。そして二つ目は広義の「前衛音楽」に関わるものだ。より一般的に言って、「前衛音楽」とは「難解」「高尚」「奇妙」「異常」などとされる音楽の総称を指している。ここで「前衛音楽」はもはや実質を欠いた記号と化していて、そのラベルが嫌悪の対象に安易に貼られることもあれば──そこには「正統なるこちらの音楽」を安定的に維持しようとする欲望があるのだろうが──、その裏返しとして、この記号に吸い寄せられて個人的嗜好を満たす者もいるだろう。パブロフの犬のように反射的に拒むのも浸かるのもそれとしては構わないのだが、記号へと還元された言葉は内容を欠いて空虚であり、それは当の音楽の実際を示し得ない。どちらの意味においても「前衛音楽」には近寄りがたいところがあった。
『Tokion』『STUDIO VOICE』にて編集長を務め、各所で尖鋭的な音楽について執筆してきた松村正人による待望の単著『前衛音楽入門』は、こうした「前衛音楽」の意味をあらためて問い直し、その歴史を辿り直していく。むろん本書はまずもって万人に向けて開かれた入門書であり、前衛音楽なるものを知るきっかけとしても、あるいは教科書として学ぶためにも活用し得るだろう。しかし20世紀の前衛を眺めることは単なる懐古趣味ではなく、その核たる部分では、使い古された「前衛音楽」という言葉をもう一度肯定的に捉え返し、これからの時代へと差し向けるように読者を誘っていく。本書では軍隊用語から転用された音楽用語としての「前衛」を、20世紀音楽に特有のモダニズムの一つの系譜として描き出していくものの、見られるようにそこには実験音楽もミニマル・ミュージックもポストモダン・ミュージックも含み込まれている。考えてみれば「形式の絶えざる更新」は必ずしも理性による支配を必要としないのだ。そしてそこから出て来た「前衛」の意味合いは、西洋的眼差しの優越心でも単純化された記号でもない、音のごく楽しげな触れ合いと厳しさを兼ね備えたダイナミズムとして立ち現れることだろう。本書を通して「前衛音楽」という言葉が蘇るのだとしたら、著者の松村にはどのような執筆の背景や目論見があったのだろうか。「前衛」の定義から現状認識、あるいはモダニズムについて、先達の音楽批評家たちについて、そしてなによりも「前衛音楽」の音の悦びについて、語っていただいた。
前衛音楽とは何か
けれどもケージに対する批判も一方からはあるわけですよ。ルイジ・ノーノのように「そこまでいったら音楽じゃないんじゃない?」みたいにいうひとたちも一方にはいた。
■これまで現代音楽を中心に書かれた概説書や広義のポピュラー音楽を対象としたもの、あるいはカタログやディスクガイドのような本はあったものの、20世紀全体を前衛音楽というテーマで辿り直した入門書というのは、ありそうでなかったのではないかと思います。どのような経緯で入門書という体裁になったのかといったところからお話いただけますか。
松村:最初は前衛的な音楽、実験的な音楽、それこそポピュラー音楽全般をふくめて、思いつくままに書き進めていきました。私は音楽について書くときに、なるべく対象を作り出した人物はもちろん、時代や政治や文化の状況をふまえたいと考えているのね。だから最初はいろいろなものを織り込んで、しかもメインの事象が登場するまでの前提の部分、『前衛音楽入門』だったら、前衛音楽というものが登場する前提みたいなものから書き起こして、当時の文学や宗教や社会情勢をふまえて書きすすめると、話がぜんぜんはじまらないということに、ある日ふと気づいたの(笑)。200枚書いたのに本題のとば口にも到達していないではないか、この調子だといつ終わるか見当もつかないと。それで編集を担当した野田さんに相談したら、「入門の体裁で、わかりやすく書くのがよいのではないか」と言われて、ああなるほどと。入門書というのは、いわゆる功なり名を遂げた方が書くことで説得力をもつものだと思うのだけど、簡便に語る構えをとれば、迂遠になりがちな私でも論を進められるのではないかということです。そう考えて、うちの書棚をみてみると、伊福部昭の『音楽入門』という本があって、あとがきに「以上、私は不要なことに饒舌にわたり、必要なことを簡略に、あるいはまた全然触れませんでした」の一節があったのを思い出したんです。この名著にして、そのようなことをいうのは、大作曲家一流の韜晦や含羞もあるかもしれないですが「入門とはこういうことかもしれない」とも思ったんですね。カフカの「掟の門」じゃないけど、読者ひとりひとりにそれぞれの門があるにちがいない。著者の役割はとくに聴くことが最終目的である音楽という分野においては門前に誘うことであろう、そう考えたのでした。
■『前衛音楽入門』は入門書であり、同時に20世紀音楽の一つの系譜を描いた歴史書でもありますよね。
松村:仮にも入門書であるならば、前後関係ははっきりしていたほうがいい。そうなると歴史を辿る必要があるなと思ったんですね。以前細田くんと話したとき、20世紀の音楽についての本があると便利じゃないかといったら、そんなのダサいですよ、若い子は前世紀なんて気にしませんよ、といわれ打ちのめされたのだけど、私はやっぱりモダニズムが好きなんですよ。ダダとかシュルレアリズムとかロシア・アヴァンギャルドとかバウハウスとか近代文学とか。YouTubeにアップされている昔の歌謡曲の映像についたコメントによく、この時代に生まれたかったってのがあるじゃない。それをいったら、私だって1920年代の東欧で青春を送りたかったよと思うもんね。でも、それをノスタルジーで語るとたんにないものねだりになっちゃうから、そのときそこにあって、いまはもう喪われたと思われているものも、歴史を辿り直すと、21世紀の現在もちがうかたちで見出されるのではないかということですよね。
■なぜタイトルに前衛音楽という言葉を付したんでしょうか。
松村:当初は『モダーン・ミュージック』というタイトルを考えていて、それは近代の音楽という意味と、かつて明大前にあったレコード店の名前のダブルミーニングのつもりだったのだけど、羊頭狗肉になりはしまいかと思って止めました。それに近代=モダニズムだと読者もイメージが結びづらいかもしれない。あくまで音楽の本であって、とりあげる対象がアヴァンギャルドな音楽であれば、前衛の呼び名はあるかもしれない。あとがきでも書きましたが、「前衛」という言葉は微妙な位置づけだとも思うんですね。アヴァンギャルドというレコード店の棚の仕切りにはあったとしても「前衛」とは謳わない。要するに死語なんですよ。画数多いしね。わがことをふりかえっても、昔は前衛的な音楽が好きですと合コンでいっていたのがあるときを境にぴったり言わなくなった。その一方で、現代音楽、実験的やエクスペリメンタルという用語は誰もが普通に使っている。オルタナティヴでもいいですけど、それらと前衛とのちがいはなんなのか。そのような言葉の曖昧さの裏には、時代ごとの音楽の形式の変遷と、それにたいする見方のようなものがあるはずで、前衛の語はその原点として働くのではないか。そこから考えると、みなさんがいま聴いているエクスペリメンタルな音楽の実相がより鮮明になるのではないか、目論見としてはそういうのはあったけどね。
■本書での前衛音楽の定義を教えてください。
松村:本でも何度か言及していますが、ジョン・ケージは『サイレンス』のなかで、結果が予測できない音楽が実験音楽だといっているじゃない。スコア(譜面)が音楽の見取り図だとすると、見取り図があっても結果がわからない音楽。最終的に実験音楽は見取り図そのものも偶然や演奏家にゆだねたりするんだけど、そこから考えると前衛音楽はどれだけすごい見取り図を描けるかの競い合いなんじゃなかったかな。形式の新しい領域を探すというか、誰も手をつけていない場所に新しい領土を開拓するというか。今回一番難しかったのが、その線引きをどうするかということだったの。マイケル・ナイマンも『実験音楽』で、前衛と実験の区別を慎重しているのだけど、「ケージとその後」が副題のあの本からももう何十年も経っていて、ケージやナイマンの定義はすくなくとも一般的にはぼんやりしてしまったのはあると思う。それは開拓すべき領土ももはや存在しないということかもしれないし、レコードという記録媒体ができたからかもしれない。
■取り上げる音楽家や作品はどのように選んでいったんですか?
松村:それこそ最初の見取り図は壮大なものだったよ(笑)。日本や、海外も西ヨーロッパやアメリカ以外の作曲家とか、サウンド・アートやパフォーマンス・アートとか。ノイズや日本のロックについても書こうと思っていたけど、それらの分野には専門の方がおられて、先駆的な本もいっぱいあるじゃない。川崎(弘二)さんや畠中(実)さんだってそうだし、金子智太郎さんの研究もすばらしいと思う。そして書物は特定の形式を掘りさげるにはすごく便利な形式だけど、一方で言葉は羅列的にしか語れない。私は歴史が好きで、学生だったころ、日本史や世界史の教科書をくりかえし読んだのだけど、歴史の出来事で最大の発見ってヨーロッパで宗教改革が起こっていたとき、日本は南北朝時代だったとか、横軸のつながりだったの。「そのころ一方~」の感覚といえばいいのかな。出来事が世界中で散発しているのに想像をいたく刺激される。本だとそれは順番に書かないといけないのだけど、たとえばケージがこう考えていたとき、シュトックハウゼンはこう考えていた、大西洋のこちら側である作品が評判をとっていたとき、反対側ではどういう動きがあった――と書くと、読んでいる時間が巻き戻ったり、重なり合ったりする。一歩すすんで二歩さがる目線には探求的な視点とはちがう風景が映るかもしれない。ひとつの事象を掘りさげるより広がりを描きたいというのがまずあって、でもあまりに広げすぎると分量の問題もあるから、コンパクトにまとまる範囲でということで、このかたちになったの。
■コンパクトとはいえ、数多くの音楽家や作品が登場しますよね。100年の歴史を膨大な音盤を聴き返しながら辿っていくという作業もあったかと思われます。
松村:前衛音楽って聴きやすい音楽じゃないじゃない? ブーレーズの全集を頭からお尻まで通して聴いてごらんなさい、しおしおになりますよ。
■松村さんにも前衛音楽は聴きづらいという感覚があるんですね。
松村:いや聴きづらいというのとはちょっとちがう。人間が集中して聴けるのは限度があるということだよ。でもたしかにBGMにはなりにくいもんね。三田(格)さんが仕事場に来たとき、松村くんはいつもピキンとかガシュとかいう音をかけているけど、きみは楽しいのかと訊かれたことがあるもん。
■「聴きづらさ」というのは、時代の先をいっていたという側面もあるじゃないですか。同時代の人には受け入れ難かったけど、いまとなってはすんなり聴けてしまうという。第1章に出てくるエリック・サティとかクロード・ドビュッシーっていうのは、当時は不協和音だったかもしれませんが、いまとなってはイージー・リスニングと括られたりもしますよね。けれども第2章以降には、いまの耳で聴いてもハードな音楽が数多く出てきます。
松村:アルノルト・シェーンベルク以降だよね。新ウィーン楽派の十二音技法は調性を否定したから必然的に聴きづらい聴感になるのだと思う。調性や自然というのも『前衛音楽入門』のテーマのひとつでした。自然に対する人工は近代の特徴で、調性から逃れようとする意志が前衛を決定づけて、その逃走/闘争の歩みがシェーンベルク以降に明確に始まっていく。すると鋭い印象の音楽になっていく。歴史を辿って聴くとそのことはとりわけわかりやすい。
■本書の執筆を通して、前衛音楽というものに対する考え方や捉え方は変わりましたか?
松村:いまシェーンベルクは聴きづらいっていう話になったけど、リズムはそうでもないよね。リズムはものすごくわかりやすい。それがもっと時代を降っていって、オリヴィエ・メシアンあたりになるとリズムも入り組んでくる。さらに降ってカールハインツ・シュトックハウゼンとかピエール・ブーレーズのあたりになると、もっと細かいパラメーターで音楽はどんどん複雑になっていく。一口に前衛音楽といっても、あるいは現代音楽とひとしなみにとらえただけではわからないダイナミックな変化があの時代には起こっていたことに、あらためて気づいたのは収穫でした。それって、特定の対象を押さえるだけだとみえにくいポイントだとも思うの。前衛って先行する音楽のある部分を革(あらた)める、っていうことを突き詰めていくわけじゃないですか。それをたんに進歩史観でとらえるとエリーティズムやアカデミズムに陥ってしまうけど、20世紀前半の音楽家たちの試みが、実験音楽の時代を経て、最終的にポピュラー音楽やクラブ・ミュージック、おそらくは私たちがいま聴いている音楽にも流れ込んでいる、その運動もふくめて、私は前衛的だと思う。
クラバーのための前衛音楽
■現在のテクノやアンビエントと形容される音楽の多くは、ミュジーク・コンクレートやミニマル・ミュージックの成果を当たり前に取り入れていますよね。それらがもともといつ頃から出てきたのだろうとか、最初はどういう意図で用いられていたのだろうとか、そういうことを知る楽しみも本書にはあると思います。
松村:いまの音楽にも先人の努力の痕跡というのはなにかしら絶対にありますから、無意識にせよね。クラブ・ミュージックやエレクトロニック・ミュージックから遡行して20世紀の前衛を聴いていくのはけっこう発見があると思いますよ。
■「シュトックハウゼンに聴かせるべきはエイフェックス・ツインではなくオウテカだった」という一節も出てきます。
松村:オウテカはテクノロジーを対象化することに長けていると思う。ソフトウェアを更新していって、その力量を引き出しながら彼らの音楽に落とし込むじゃない。おそらくその作業は最初感覚的なものであっても、スタイルやロジックにおとしこまれるのだと思うんですよ。でもエイフェックス・ツインは本能が表現に直結している。
■実験的でハードコアな印象もあるいわゆる音響派が、テクノ、ハウス、ヒップホップなどのクラブ・ミュージックをその前提として含み込んでいる、と指摘されていた箇所も印象的でした。
松村:デイヴィッド・トゥープ的といいますか、彼みたいな音楽の聴き方が大きかったと思うんですよ。トゥープの本で『音の海(Ocean of Sound)』ってあるじゃない。あの本はアンビエントが中心だけど、サウンド・アートから実験音楽、ロック、ジャズ、レゲエまでおよそ考えつく音楽をとりあげているのだけど、一方で彼は『ラップ・アタック』というヒップホップの本も書いている。文学やアートへの広範な知見もあって、ビザールでストレンジな表現にも目端が利き、自分でも音楽をやっているわけじゃない。あの博覧強記と横断性は90年代という時代を象徴していた。トゥープが代表する価値観は彼も寄稿していた雑誌の『The Wire』的なものでもあって、前後関係はさておき、それらがクラブ・ミュージックにアヴァンギャルドを接続したのではないかということです。たしか2001年だったと思うのだけど、岸野(雄一)さんにご協力いただいて『Studio Voice』という雑誌で「日本の作曲家」という特集を組んだとき、外からみた日本の音楽への視線という切り口で、日本の音楽家の作品を15枚ずつ選んでレヴューするというコーナーの原稿をジム(・オルーク)さんに書いてもらったことがあったのね。原稿は『別冊ele-king』の「ジム・オルーク完全読本」に転載したので読まれた方もおられるかもしれないけど、同じ主旨でトゥープさんにも原稿を依頼していたんですよ。ふたりのセレクトはおおまかにいえば傾向は同じで、武満徹とか細野さんのように重複するミュージシャンもいたのだけど、同じ音楽家の作品でも、ジムさんは武満徹は『コロナ』で細野さんは『コチンの月』をあげ、トゥープさんは映画音楽集と『トロピカル・ダンディ』をあげたことが、トゥープさんのポピュラー音楽よりの志向をあらわしていて、それがクラブ・ミュージックとアヴァンギャルドを接続したという論拠なんだけど、わかりづらいか(笑)。他方ではね、これも「別冊ele-king」でポストロックと音響派を特集したとき、いろいろな方にご寄稿いただいたなかで、著者ごとに音響派の定義というか、来歴の捉え方がちがうと思ったのもある。大谷(能生)さんと虹釜(太郎)さんの史観はべつのものだし、『前衛音楽入門』の第9章でもふれましたが、佐々木(敦)さんの定義からして、私はむしろその行間を読むべきものだと思う。
取材:細田成嗣(2019年2月14日)
| 12 |
Profile
 細田成嗣/Narushi Hosoda
細田成嗣/Narushi Hosoda1989年生まれ。ライター/音楽批評。佐々木敦が主宰する批評家養成ギブス修了後、2013年より執筆活動を開始。『ele-king』『JazzTokyo』『Jazz The New Chapter』『ユリイカ』などに寄稿。主な論考に「即興音楽の新しい波 ──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド」、「来たるべき「非在の音」に向けて──特殊音楽考、アジアン・ミーティング・フェスティバルでの体験から」など。2018年5月より国分寺M’sにて「ポスト・インプロヴィゼーションの地平を探る」と題したイベント・シリーズを企画/開催。
INTERVIEWS
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE