「死んだ方がマシなときもある/銃を自分のこめかみに当てて」という歌い出しからはじまるHi-NRGサウンド。ペット・ショップ・ボーイズの永遠の名曲“ウェスト・エンド・ガールズ”を、なんとスリーフォード・モッズがカヴァーし、Bandcampや配信で発表した。そもそも1980年代半ばのこの大ヒット曲は、サッチャー政権下のヤッピー文化(小金持ちの若者文化)を風刺した曲と言われている。「ぼくたちに未来はなく過去もない。ただ今日だけがある」、いかにも英国風のひねりの利いたこの曲をスリーフォード・モッズがカヴァーすることが面白い(先行発表のMVはオリジナルのパロディで、笑える)。しかも、この曲の収益は、ホームレスを支援している団体に寄付される。ペット・ショップ・ボーイズ本人たちもこのシングルを讃え、シングルでは自らリミキサーとしても参加。そしてこうコメントしている。「スリーフォード・モッズは、大義のためにイースト・エンド(労働者階級)の少年たちをウエスト・エンド(繁華街)のストリートに呼び戻してくれた」
ちなみにジェイソン・ウィリアムソンは、「ペット・ショップ・ボーイズのアルバム『Please』と『Actually』をよく聴いている」そうだが、この2枚、ほんとうに名作です。PSBといえば、この2枚さえ聴いておけばいいくらいに。
なお、フィジカルの発売は12月15日。
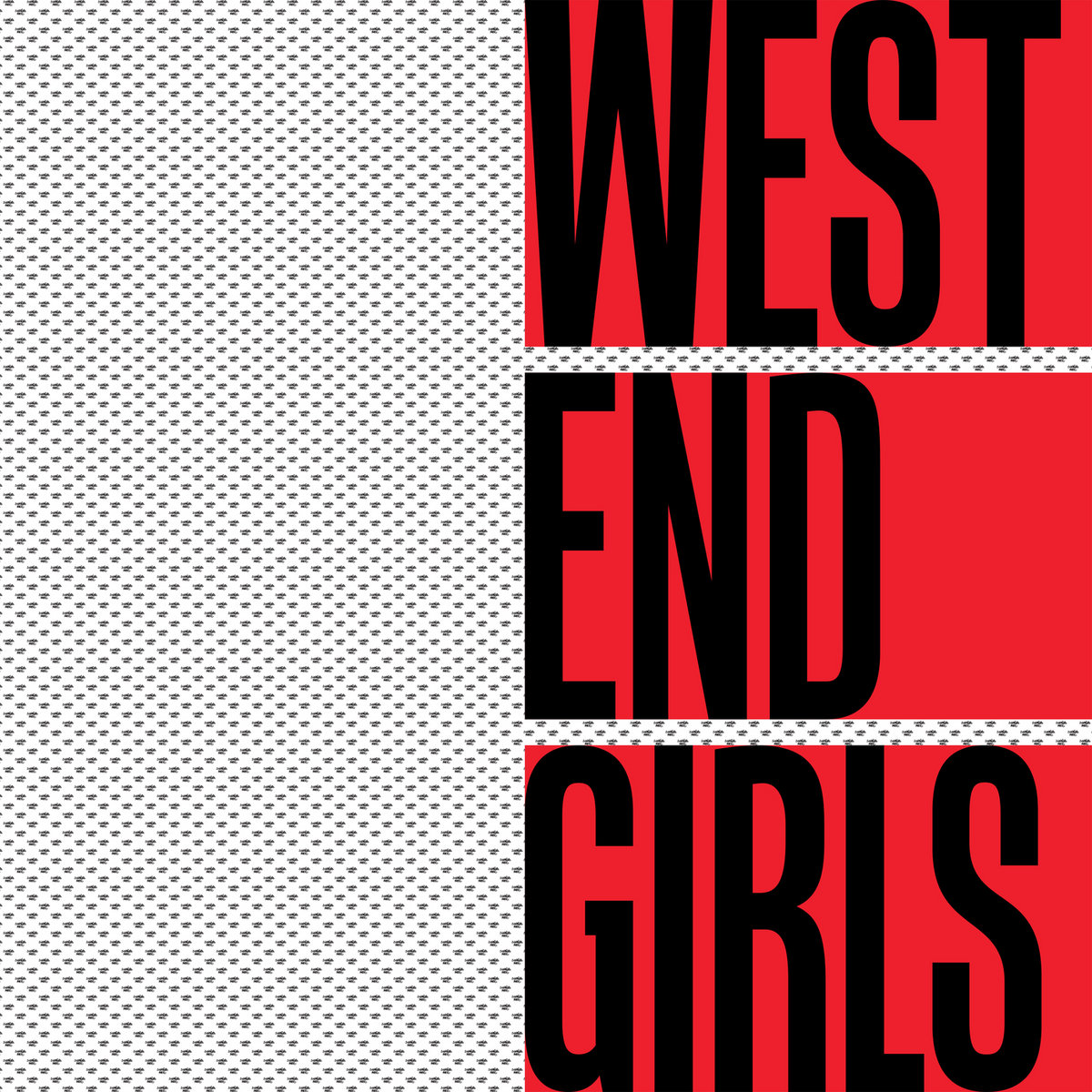
また、スリーフォード・モッズは最近は、ドイツのミニマリスト、Poleのリミックスも発表している。これが結構いいんです。

















