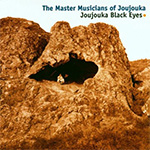■ピクシーズ、まさかの新譜『インディ・シンディ』をクロス・レヴュー
Pixies - Indie Cindy
Pixies Music / ホステス
結成から29年、再結成から10年。「オルタナ」あるいは「グランジ」といった音楽的潮流の下、90年代以降のインディ・ロックに多大なる影響を及ぼしたバンド、ピクシーズの新譜がリリースされた。「本当に新譜が出るとは……!」という往年のファンから、「オルタナ」がオルタナティヴではなくなってしまった時代に聴きはじめた若いリスナーまで、もちろんその反応は一様ではない。しかし、どの聴き方にも真実がある。合評スタイルで多角的にアプローチしてみよう。
黒田隆憲、久保正樹、天野龍太郎による渾身のクロス・レヴュー!
■ピクシーズ、名盤Pick Up
文章:天野龍太郎、加藤直宏、久保正樹、黒田隆憲
映画『キャリー』でもっとも怖く印象に残るのは、クライマックスのキャリーの暴走ではなく、キリスト教原理主義のあの母親だ。アメリカの病理というべきか、歪んだ正義に息苦しさ、いや狂気を感じた子どもたちによる逆襲。ピクシーズというバンドもそうしたアメリカのダークサイドに唾を吐きかけたバンドのひとつだ。ジャケットを見てほしい。女装をした男の背中に、獣のような体毛が生えている。キリスト教右派たちからすれば、すぐさまに火をつけて、燃やしたくなるだろういかがわしいヴィジュアルだ。歌詞においても高く評価されるフランシス・ブラックがキリスト教社会や学歴社会に対してアンチを投げかけてきたことはよく知られているところだが、バンドの結成から間もない1887年に名門〈4AD〉との契約を勝ち取り、デビュー・アルバムに先駆けてのリリースとなったこのEP『カモン・ピルグリム(ピルグリムとは巡礼者のこと)』のジャケットは、ピクシーズというバンドの存在を見事に説明しているように感じられる。そして本作に収められたサウンドはこのジャケット以上に、聴く者に何か切実なものを訴えかけてくる。
ピクシーズ史上もっとも美しいメロディを持つ曲のひとつ“カリブー”、パール・ジャムの“スピン・ザ・ブラック・サークル”を思わせる“イスラ・デ・エンカンタ”(彼らはこの曲ヒントにしたのかもしれない)、“エド・イズ・デッド”、乾いたスパニッシュ系のギター・リフに痺れる“ニムロッズ・サン”、ラップのようなフランシスのヴォーカルが特徴的な“アイヴ・ビーン・タイヤード”など、結成から1、2年のバンドとは思えないほど、アイディアに溢れ、完成度の高い楽曲が並んでいる。ピクシーズを聴くなら、本作も必ず押さえておくべき。(加藤直宏)
いま聴いてもゾクゾクする。ブラック・フランシスのささくれだった金切り声、頭を掻きむしっているかのように鳴らされるギターのノイズ、混沌のサウンドの中にふいのカウンターパンチのように散りばめられたポップなメロディやコーラス……、若き4人の匂い立つような初期衝動がスティーヴ・アルビニのプロデュースによって、生々しく記録されている。1988年に〈4AD〉からリリースされたこのファースト・アルバムは、グランジはもとより、その後のギター・ロックに大きな影響を与えたオルタナティヴ・ロックの金字塔として知られている。カート・コバーンが『ネヴァーマインド』を制作する際に本作から多くのヒントを得たというのは有名な話だし、2002年にチャンネル4で放送されたドキュメンタリー『Gouge』ではデヴィッド・ボウイ、ボノ、トム・ヨーク、ブラー、PJハーヴェイ、トラヴィスといった面々がピクシーズへの想いを語っていたが、本国を超えてそのサウンドは多くのミュージシャンたちに影響を与えている。アルビニのプロデュースも手伝ってか、本作ではとりわけ彼らのアルバムの中でもパンキッシュで攻撃的なサウンドが展開されている。どの曲も短くソリッドで、しかし強烈なフックを持っている。ピクシーズでもっとも有名な曲のひとつであり、後にブリーダーズを結成するキム・ディールが歌う“ギガンティック”(アップルの最新CMでも使われていているのはこの曲)、映画『ファイトクラブ』のエンディングで流れる“ホエア・イズ・マイ・マインド?”など名曲揃い。サイモン・ラーバレスティア(Simon Larbalestier)による退廃的なジャケットの写真も素晴らしい。(加藤直宏)
スティーヴ・アルビニを迎えた前作『サーファー・ローザ』でUKインディー・チャートのトップに躍り出た彼らは、通算2枚めとなる本作でさらなる飛躍を遂げる。ルイス・ブニュエルの短編映画『アンダルシアの犬』からインスパイアされたという冒頭曲 “ディベイサー(Debaser)”は、まるでグランジ〜オルタナの「幕開け」を告げるかのようなインパクト。キム・ディールのベースライン/コード進行は、その後のインディ・ギター・バンドにとって、一種の「ひな形」になったといっても過言ではないだろう。不気味なうめき声と制御不能な咆哮を、1曲の中で目まぐるしく使い分ける“テイム”や“アイ・ブリード”など、ブラック・フランシスのヴォーカル・スタイルはもはや唯我独尊の域に達し、我関せずとばかりにレスポンスするキムのクールな声とのコントラストも、楽曲を立体的に際立たせている。変態的で、どこかオリエンタルな響きを持つジョーイ・サンチャゴのギターももちろん絶好調だ。ガールズポップのようなポップ・ソング“ヒア・カムズ・ユア・マン”や、屈指の名曲“モンキー・ゴーン・トゥ・ヘヴン”も収録された本作を、彼らの「最高傑作」と呼ぶファンは多い。(黒田隆憲)
1990年リリースの通算3作め。『ドリトル』の延長上にある作品だが、楽曲はよりシンプルに、ストレンジながらもクリアな音作りも優れたバランス感覚で鳴っている。冒頭、オルタナティヴ版ベンチャーズのようなサーフ・ロック調のインストゥルメンタル“セシリア・アン”が意表を突く。全編にわたってブラックが叫び散らす「ロック・ミュージック」の行き詰まった焦燥は、ピクシーズとブラックの真骨頂ともいえる美しい瞬間を捉えている。黄金のリフを奏でる“ヴェロリア”、ロックンロールに駆け抜ける“アリソン”、ポエトリー・リーディングとギターのファンキーなカッティングからじつに美しいメロディへと流れこむ“ディグ・フォー・ファイア”には色褪せない輝きが。スペーシーなジャケットにも表れているとおり、宇宙やUFOが登場するリリックも興味深い。メインストリーム寄りのアルバムとして批判する向きもあるが、僕にとっては重要なアルバム。(天野龍太郎)
■
前作『ボサノヴァ』でアレンジ/サウンド・プロダクションの幅を一気に広げ、全英でヒットを記録した彼らが、リハーサル・スタジオから漏れ聴こえるヘヴィ・メタル(オジー・オズボーンやラット)に触発され、ヘヴィメタ要素を大々的にフィーチャーした通算4枚め(ちなみに邦題は『世界を騙せ』)。16ビートのギター・バッキングやライト・ハンドの早弾きなどヘヴィメタ奏法で聴き手の血をたぎらせつつも、いきなりワルツをぶち込んで意表を突くアルバム表題曲をはじめ、随所で顔を見せる天の邪鬼っぷりは健在。キャプテン・ビーフハートやスネイクフィンガーとの共演経験を持つキーボード奏者、エリック・ドリュー・フェルドマンを迎え、これまで以上にシンセ・サウンドを取り入れたのも印象的だ。畳み掛けるような前半のテンションはとにかく異様で、アルバム全体のメタリックな感触にリリース当時は少々戸惑ったものだが、人を食ったようなジザメリのカヴァー“ヘッド・オン”をはじめ、いま聴くと親しみやすい曲もけっこう多い。何より、ナンバーガールやART-SCHOOLなど90年代以降に登場した日本のギター・バンドに多大なる影響を与えたアルバム、という意味でも重要な一枚だ。(黒田隆憲)
■
サーフ・ポップがねじれをこじらし、波乗りしていたらうっかり宇宙の哲学にまでたどり着いてしまった問題作『ボサノヴァ』の後にリリースされた5枚め。当時、最新ファッションとまで化していたグランジ・ブームのど真ん中で、もろに直球な“プラネット・オブ・サウンド”、幻想的にひた走る“ちびのエイフェル”あたりにシーンとのリンクを聴くことができるものの(というかシーンが追いついたのだが)、UKの〈4AD〉(←当時はデカダンな意匠をまとっていた)からのリリースというところにほかのUS産とはちがうワイアードな恍惚を感じたものだ。ミクスチャー風なグルーヴを採り入れた“スペース” “サバカルチャー”など、これまでにない骨太感も聴こえるが、やっぱり、インパクトのあるギターリフ、そして、妙ちきなくせに鮮やかなメロディをなぞるてろてろしたヴォーカルからの脂肪分たっぷりの絶叫に骨抜きにされてしまう。“モーター・ウェイ・トゥ・ロズウェル”の美しさもさることながら、シーンをともに築いた盟友ジーザス&メリー・チェイン“ヘッド・オン”のカヴァーを、悪意も皮肉もなくストレートに披露する懐の広さにもじんときたものだ。(久保正樹)
■
「世界を騙せ」と題された本作は、彼らの4枚めのフル・アルバムであり、今回の『インディ・シンディ』がリリースされるまでは、彼らのラスト・アルバムとして記憶されていた。本作を最後にして、1993年にバンドは解散。フランシス・ブラックはソロでの活動をスタートさせ、ベースのキム・ディールはすでに人気のあったブリーダーズでの活動に本格シフトしていくようになる。しかしながら、だからといって本作が輝きを失うわけではない。これほどの作品が作れるというのに、これで解散してしまうのはあまりにもったいないと思った人も多かったことだろう。それぐらい本作にはいい曲がたくさんある。“アレック・エッフェル”“プラネット・オブ・サウンド”“レター・トゥ・メンフィス”といった名曲に加え、ジーザス&メリーチェインの“ヘッド・オン”のカヴァーも収録。サード・アルバム『ボサノヴァ』でのサーフ・ロック的な路線から一転、本作では『サーファー・ローザ』時代に戻ったような、パンキッシュでささくれだったギター・サウンドが展開されている。フロントマンのブラック・フランシスはバンドを結成する際に「ハスカー・ドゥとピーター・ポール&マリー(1960年代にUSで大成功を収めたフォーク・バンド)が好きなメンバーを求む」と募集をかけたそうだが、ピクシーズというバンドは本当にそんな感じのサウンドだ。歪んだギターの轟音の中に、とてつもなくポップなメロディが潜んでいる。『トゥロンプ・ル・モンド』もそんなピクシーズの魅力を存分に味わえるアルバムだ。(加藤直宏)
当時からライヴの良し悪しがその日の状態によって大違いなバンドとして定評(?)のあるピクシーズ。妙々たる奇跡のようなパフォーマンスの傍に──いつがっかりさせられてもおかしくない──垢抜けない要素がべっとり貼りついているところが、彼らを信頼できる所以であったりする。88年から91年までのBBCライヴを収めた本作は、テンション高く、キレも抜群で、アルバム以上にムキ出しズルむけとなったピクシーズのセンスとユーモアを存分に味わうことができる。フランシスの乾いたギターと、サンティアゴの艶っぽいギターの絡みもいつになくスリリングで、キムのコーラスもぱっと華やか。『サーファー・ローザ』以外の各作品から、ライヴ映えよろしい楽曲が選りすぐられていて、ピクシーズ初心者にも心の底からオススメできる内容だ。そして、玄人のあなたにはこちら。締めを飾るピーター・アイヴァースのカヴァー“イン・ヘヴン”(デヴィッド・リンチ監督『イレイザーヘッド』のなかで、おたふく娘が歌い上げる悪夢の幻想バラード)のフランシスの咆哮にまみれ、世にも美しい後味の悪さに浸ることをオススメする。(久保正樹)







 BLAZEだからジャパニーズ・ハウスじゃないじゃん! って思う人も当然いるだろうけど、僕にとってヴォーカルが日本語だったので、それだけでも充分面白くて、ジャパニーズ・ハウスだったんです。日本語のヴォーカルがハウスにMixされている、これだけでとても衝撃的だったんです! 格好いい! って思ったんですね。ヨーロッパでプレイしたら、絶対にクラバーやDJたちは「なにこれ? なにこれ??!!」ってなると思ったんですね。もう、聴いた瞬間、とてもわくわくしました。
BLAZEだからジャパニーズ・ハウスじゃないじゃん! って思う人も当然いるだろうけど、僕にとってヴォーカルが日本語だったので、それだけでも充分面白くて、ジャパニーズ・ハウスだったんです。日本語のヴォーカルがハウスにMixされている、これだけでとても衝撃的だったんです! 格好いい! って思ったんですね。ヨーロッパでプレイしたら、絶対にクラバーやDJたちは「なにこれ? なにこれ??!!」ってなると思ったんですね。もう、聴いた瞬間、とてもわくわくしました。 Pizzicato Fiveのことは当時すでに知っていたけれど、僕は渋谷系のバンドとしてしか認識してませんでした。ただし、その盤は「Remixes」という言葉をアピールしています。で、クレジットを見たら、富家哲さん、Tei Towaさんなどの名前があります。リリース日付を見たら93年。90年代ハウスの大ファンである僕にとって必須な1枚です。
Pizzicato Fiveのことは当時すでに知っていたけれど、僕は渋谷系のバンドとしてしか認識してませんでした。ただし、その盤は「Remixes」という言葉をアピールしています。で、クレジットを見たら、富家哲さん、Tei Towaさんなどの名前があります。リリース日付を見たら93年。90年代ハウスの大ファンである僕にとって必須な1枚です。