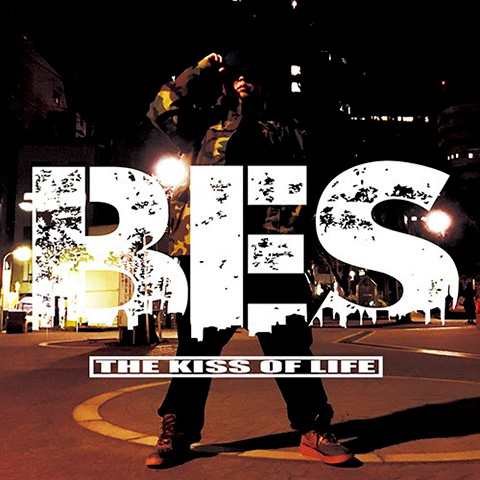 BES - THE KISS OF LIFE ILL LOUNGE |
 仙人掌 - VOICE Pヴァイン |
BESと仙人掌というふたりのラッパーがいなければ、少なくとも2000年代中盤以降の東京の街から生まれるラップ・ミュージックはまた別の形になっていただろう。ふたりは恐縮して否定するかもしれないが、これは大袈裟な煽りではなく、厳然たる事実である。BESと仙人掌はそれぞれ独自のラップ・スタイルを発明して多くのフォロワーも生んだ。どういうことか?
作品や彼らのキャリアや表現について個人的な論や説明を展開する誘惑にも駆られるが、ここでは多くを語るまい。ひとつだけ端的に言わせてもらえれば、余計な飾りつけなしの、1本のマイクとヴォイスとリズムのみでラップの表現を深化させたのがBESと仙人掌だった。ここにその両者の対談が実現した。ふたりを愛するヘッズはもちろん、彼らをまだよく知らない『ele-king』読者の音楽フリークにもぜひ読んでほしい。そして、仙人掌が2016年に発表した一般流通として初となるオリジナル・ソロ・アルバム『VOICE』、BESが3月に出したサード・アルバム『THE KISS OF LIFE』を聴いてみてほしい。『THE KISS OF LIFE』のプロデューサー、I-DeAにも同席してもらった。ふたりのラッパーの物語は、今年20周年をむかえた池袋のクラブ〈bed〉からはじまる。

ラップをあえてレゲエ風にしようとかではなくて、ヒップホップとレゲエが俺のフロウのなかで自然といっしょになっていった。そういう俺の感覚と合致していたのが仙人掌だった。 (BES)
BES from Swanky Swipe feat. 仙人掌, SHAKU“Check Me Out Yo!! Listen!!”
■ふたりの最初の出会いをおぼえてますか?
BES:〈bed〉ですね。仙人掌は昔からラップが上手くて、初めてライヴを観てすげぇ食らったのをおぼえてる。それで気づいたらウチに来て遊んだりするようになってた。メシア(the フライ)がまだDOWN NORTH CAMP(以下、DNC)にいたときで、CENJU(DNC)もTAMUくん(DNC)もいた。
仙人掌:最初に遊んだのはその4人だったかもしれないっすね。SORAくん(DNC)もちょっといたと思う。そのとき俺は〈bed〉でライヴしてて、気づいたらタカさん(BES)が「そうとう酔っぱらってらっしゃいますね」みたいな感じでいきなり肩組まれて、「お前、とにかくウチ来い」って。俺、まだ高校生だった。
BES:ははははは。17とか?
仙人掌:そうっすね。タカさんの自由ヶ丘の家にいそいそと遊びに行って、それからホント全部教えてもらいましたね。
BES:教えてもらいましたよ、俺も。ENYCEの読み方とかね。俺が「エニシー」って読んでたら、仙人掌に「いや、違います。エニーチェです」って言われてさ。
仙人掌:ははははは。〈bed〉で〈ELEVATION〉(2001年にスタート、2012年にファイナルを迎えた)っていう長く続いたパーティがあったんですけど、そのパーティの第4月曜日にSWANKY SWIPEと俺らが出てたんですよね。当時はまだSWANKYじゃなくて、SPICY SWIPEって名前でやってましたっけ?
BES:そうそうそう。
仙人掌:SWANKY SWIPEに名前が変わったころになると、〈bed〉の人たちはみんな「ヤバいラッパーはBESでしょ!」みたいな感じだった。DJのサイドMCでバリバリカマしているタカさんをフロアで観てましたね。
BES:〈ELEVATION〉がはじまる前に〈bed〉で〈URBAN CHAMPION〉(1999年スタート、現在まで続く)っていうパーティがあったんですよ。そこで“煽りMC”って言うんですか? それをやりまくって盛り上げまくってた。そこにPorsche(SWANKY SWIPEのDJ)もDJ MOTAI(〈URBAN CHAMPION〉のオーガナイザー)もいた。あとIKDくん(NOISE2 SOUND SYSTEM)もいたね。
仙人掌:Gatchaくん(〈bed〉でおこなわれているパーティ〈the River〉のオーガナイザー)もいましたね。〈bed〉がとにかくヤバいラップの見本市だった。そのなかでSWANKYは俺にとって特別だった。SWANKYが新曲をやると、当たり前にフロアのいちばん前に行っていた。突発的に出演者同士がライヴでヴァースに混ざったり、次のライヴでサイドMCやりあったり普通にありましたね。
■BESさんの曲のなかでいま思いつく印象的な曲はありますか?
仙人掌:1曲にしぼるのはなかなか難しいですね。ただ、『Bunks Marmalade』(SWANKY SWIPEのファースト・アルバム。2006年)の前にもたくさん曲があって、“Check Me Out Yo!! Listen!!”でも当時の曲のフックを引用させてもらったりしてますね。ライヴもいちばん観ていたし、当時の印象が強いんですよね。タカさんもEISHINくん(SWANKY SWIPEのビートメイカー/ラッパー)もステージでふらふらで壮絶でしたね。
BES:ははははは。
■2006年にSEEDA & DJ ISSOの『CONCRETE GREEN.1(改)』がリリースされて、あのコンピ・シリーズが本格的に動き始めますね。そういうなかで、BESと仙人掌というラッパーはそれまでの日本語ラップとは異なるラップのスタイルを打ち出していったと思うんです。自分たちのスタイルをどのような意識で作り上げていきましたか?
仙人掌:『CONCRETE GREEN』は俺らにとっては“第2段階”って感じなんです。その前があるんです。いちばん最初にタカさんの家でラップの話をしているときに、タカさんが強調していたのは「とにかくノれるラップ、フロウなんだよ」ってことです。「いかに“フロウを崩せるか”なんだ」って。それで、ブーキャン(ブート・キャンプ・クリック)とかいろんなダンスホール・レゲエとかを見て、聴いて、学んでいった感じですね。
BES:昔、レゲエの現場に行ったね。バスタ(・ライムス)もメソッドマンもレッドマンもフージーズもみんなレゲエを使うじゃないですか。俺もレゲエが大好きだったからヒップホップとレゲエのふたつを押さえときゃ間違いないと考えてた。だから、ラップをあえてレゲエ風にしようとかではなくて、ヒップホップとレゲエが俺のフロウのなかで自然といっしょになっていった。そういう俺の感覚と合致していたのが仙人掌だった。あと、SIMONだね。「こういうことするヤツいた! 見つけた!」って。
仙人掌:SIMONは俺と同い年で、18、19のころに出会ってるはずですね。SIMONも当時からずば抜けてヤバかった。
BES:USの流行にただ流されるんじゃなくて、自分の好きなことをやっていたよね。〈SON〉(〈SON OF NINJA〉という〈ニンジャ・チューン〉傘下のレーベル)っていうアンダーグラウンド・レーベルがあって、そういうレコードを〈ギネス・レコード〉とかで買ったりもしていたね。
仙人掌:〈ギネス・レコード〉で日本人のブレイクビーツを2枚買いしたりもしてましたよね。
BES:知らないレコードでも試聴して「かっけー! これ2枚買いだ!」って買ってDJにライヴで2枚使いしてもらってたね。
仙人掌:「このビートはヤバイ!」って反応したときのタカさんの体の動きはすぐわかった。SWANKY SWIPEはライヴで使ってるビートも他と違ってた。俺らの周りでネプチューンズやカニエ、ジャスト・ブレイズなんかにいちばん最初に反応してたのもタカさんだった。ユニークなビートに対しての嗅覚がありましたね。ブーキャンとかの裏ノリを維持しつつ新しいビートのフォーマットにハメていくフロウを作り出していったラッパーは、俺の知る限りでは間違いなくタカさんですね。EISHINくんの存在もデカかったですよね。
BES:超デカかった。EISHINは俺よりもアンテナを広げてるヤツで、のちにヒップホップ以外も大好きになっていって、ソウルを聴きながらチルしてゆっくりする時間を設けたりするようなヤツだった(笑)。ネプチューンズがプロデュースしたバスタの曲が流行ったときにEISHINとふたりでトライトンでビートを作ったりもしたね。
仙人掌:EISHINくん、J・ゾーンが超好きでしたよね。何かと言うと、「J・ゾーン、聴いたか?」って言っていた記憶がある。そういうセンスがすごく面白かった。
BES:グレイヴディガズのアルバムに入ってる、(体を捻らせながら)こんなんなっちゃうようなリズムのビートが超好きで、そういうのをDJでかけたりしてたよね。
仙人掌:俺、EISHINくんとタカさんとの会話でいまでもおぼえていることがあるんですよ。Shing02が『400』(2002年)を出したときに、EISHINくんが「Shing02のラップはキレてる。上手いよね」みたいなことを語っていたんですよ。そういう、変わったリズムへの嗅覚のあるEISHINくんのShing02の聴き方とかも新鮮だった。ラップやリズムの捉え方が圧倒的に独特だった。
BES:俺ら、韻の数とか数えてたしね。例えば「あいう」の母音の単語でヴァースをはじめたら、ヴァースの最後も「あいう」の母音の単語をもってくるとかね。そういう作業もしていたから当時はラップを作るのに超時間がかかった。
SEEDA feat. 仙人掌“山手通り”
SEEDAくんやタカさんやSCARSのラッパーの人たちの何が圧倒的にすごいかって、スピードなんですよ。何が正しい、何が間違っているではなくて、その瞬間をラップでパッケージするスピードなんです。 (仙人掌)
■ふたりが共作した曲はいくつもありますが、いちばん最初はどの曲でしたか?
仙人掌:盛岡のDJ R.I.Pさんとの曲ですね。
BES:あれ? 何だっけなぁ。俺、超ド忘れしてるぞ(笑)。
仙人掌:未発表曲だけど、俺も盛岡の人たちもみんな持ってますね。IKDくんの家で録りましたね。
BES:今度聴かせて。俺が当時の仙人掌でおぼえてるのはファボラスの曲のトラックに乗せてラップしてて超かっこよかったことだね。
仙人掌:ああ、ありましたね。それはたしか、〈ELEVATION〉の6周年か7周年のときに作ったエクスクルーシヴ音源ですね。あのときはエクスクルーシヴをかましまくってましたよね。やっとラップを録ることをおぼえたぐらいじゃないですか。
BES:そうそうそう。いまはRECの仕方もリリックの書き方も当時とは変わっちゃってるけど、あのときが基礎になっているね。『CONCRETE GREEN』ぐらいからちょっとスタイルや描写の仕方も変わって、スキル的にも上手くなっていった。
仙人掌:『CONCRETE GREEN』からタカさんもラッパーとして加速していったと思う。レコーディングの仕事も増えていきましたね。〈bed〉の人たちだけじゃなくて、メジャーでやっているようなアーティストからも「BESとSWANKYがヤベえぞ」という雰囲気が出てきた。そこで俺はちょっとさびしい気持ちになるというね(笑)。
BES:ははははは。俺も行く先々でDNCの宣伝をして歩いてたんだよね。「仙人掌っていうヤバいラッパーがいる」ってさ。
仙人掌:SEEDAくんを紹介してもらったのもタカさんの家でしたね。元々SEEDAくんはTAMUくんを昔から知っていて(SEEDA、TAMU、EGUOでMANEWVAというグループを組んでいた)、俺が会ったのはそのときが初めてだった。
BES:SEEDAと仙人掌はその後“山手通り”(SEEDAのメジャー・デビュー作『街風』収録。2007年)を作ったりしたよね。
仙人掌:そうですね。タカさんにはいろんな人を紹介してもらった。
BES:あのカナダ人に会ったことおぼえてる?
仙人掌:え? え? ああぁぁぁー、わかります! うわー!(笑)
BES:俺とSEEDAといっしょに会いに行ったでしょ。
仙人掌:あの双子のラッパーの! 彼に「ラップ持ってないか?」って訊いたら、「ラップ? いまやってやろうか?」って答えてきて、「違ぇ、違ぇ、そのラップじゃなくてサランラップだよ!」って(笑)。
BES:そんなこともあったね(笑)。
仙人掌:タカさんがマックスで危ないときにもいっしょにいたりもしましたしね。3、4日寝てないのも普通だったり、テーブルにアサヒのビールの空の缶がブーーーワーーーッと積んであって、灰皿もブーーワーーーッて山盛のタバコだったり。
BES:鼻地獄だったみたいっすよ。
仙人掌:ははははは。そういうダークな時期もありましたね。タカさんとラップしたり遊んでいるうちに謎の状況に巻き込まれていっしょにタクシーに乗って向かうと、「俺がいるべきじゃない場所にいるかもしれないぞ。ヤベえ……」ってこともありましたね(笑)。そういう意味でもホントにいろんな貴重な経験させてもらいましたよ。タカさんはそういう時期を経て、『REBUILD』(2008年)をリリースしていったんですよね。
BES:『REBUILD』を出したあともまた俺はいろいろ食らっちゃったけどね(笑)。
俺はタカさんやSEEDAくんにヒップホップ観を変えられたし、俺がラッパーに本気で怒られたのってタカさんとSEEDAくんぐらいなんですよ。だから俺はこのふたりを認めさせたいと思ってラップしていますよ、いまも。 (仙人掌)
SEEDA feat. BES, 仙人掌“FACT”
■『CONCRETE GREEN』と言えばいわゆる「ハスリング・ラップ」をシーンに認知させて、定着させたコンピでもありましたね。一方で、BACHLOGICがプロデュースした、BES、仙人掌、SEEDAの共作曲“FACT”(『CONCRETE GREEN.3』収録。2006年)も重要な曲ですよね。
BES:そのころの俺はもうファックドアップでしたね。金があるときとないときが激し過ぎて山あり谷ありで大変だった。子どももできて育てなくちゃならなかったですしね。“FACT”を作ってるときはまさにそういう時期ですね。あの曲は現実を目の前にして困惑する自分も出ている。
仙人掌:あの曲をI-DeAさんの家で録ってるときにちょうど子どもが産まれそうな時期でしたね。「(録音中に)嫁が産気づいちゃったらすみません」みたいなことをSEEDAくんに話してたのをおぼえてます。
BES:“FACT”は思い浮かぶリリックをそのまま書くっていうテーマがあった。『REBUILD』に入ってる仙人掌との“Get On The Mic”は、俺が「そろそろコレじゃダメだ。マイクとラップで生きていこう」という気持ちで作った曲でもありましたね。
仙人掌:だから実際、ハスリング・ラップがどうこうでもないと思うんですよ。SEEDAくんやタカさんやSCARSのラッパーの人たちの何が圧倒的にすごいかって、スピードなんですよ。何が正しい、何が間違っているではなくて、その瞬間をラップでパッケージするスピードなんです。リリックの言葉遣いに迷っていたり、そのころになるともう韻の数を数えてやっていたら……
BES:追っつかないよね。
仙人掌:そう、ぜんぜん追っつかないじゃないですか。そういうスピードが『CONCRETE GREEN』1枚1枚の、あのヴォリュームにもなってると思う。とにかくラップをビートに乗せて、ヤバい表現があって、それが作品なんだっていうラップとヒップホップの捉え方なんですよ。ホントにずーっとフリースタイルしてましたからね。それで作品も作っていく。そういう物事の捉え方とアウトプットとスピードが俺には衝撃的だった。
BES:しかも世に出す作品としてのクオリティが問われはじめるときだよね。
仙人掌:ホントにそうですね。俺はタカさんやSEEDAくんにヒップホップ観を変えられたし、俺がラッパーに本気で怒られたのってタカさんとSEEDAくんぐらいなんですよ。だから俺はこのふたりを認めさせたいと思ってラップしていますよ、いまも。もちろんこれからも。
BES:もう最初に会ったときにすでに認めてるけどね。
■“FACT”はI-DeAさんの自宅スタジオで録音したということですけど、当時のことをおぼえてますか?
I-DeA:俺が中目黒に住んでいたときの部屋に2時間おきとかにラッパーが来て録ってました。『CONCRETE GREEN』の1、2、3あたりのSCARS関連の録音は全部俺ですよ。アカペラをインストに乗せて、エディットして、別バージョンを作ったりしていた。でも、ぜんぜん金が入ってこなかった(笑)。「遊びましょうよ」って連絡があって『ウイニングイレブン』をやって、俺が負けたらタダでRECしてましたから(笑)。そうやってRECしていって気づいたら『CONCRETE GREEN』が出てた。『SEEDA'S 27 SEEDS』(2005年)なんかもまさにそうですね。
■ラッパーたちの録音の仕方とか、曲で印象に残っていることってありますか?
I-DeA:DNCやSD JUNKSTA周りのラッパーと一気に知り合って、彼らが入れ代わり立ち代わり俺の自宅スタジオに来てひたすら録音していったから、その記憶しかないんですよね。あと、ビートがかかるとみんなでずーっとフリースタイルしている光景は鮮明におぼえてる。俺はラップしないから、「うぜぇなあ」とか思いながら見てましたけど(笑)。でも、いま10年ぐらい経ってあらためて思うのは、お世辞抜きに『CONCRETE GREEN』に入ってるラッパーたちのクオリティやスキルが高かったことですね。関係も近くて当時はそのことにあんまり気づいてなかったけど、レベルが高かったんだなって。
■ちょっと前に田我流くんに『別冊カドカワ DIRECT』という雑誌の日本のラップ特集で取材させてもらったんですよ。仙人掌くんも同席してもらって。そこで田我流くんが、『CONCRETE GREEN』はひとつの「ムーヴメント」だったと言っていて、「いまの俺らがあるのは、『CONCRETE GREEN』の勢いがあったから。いままであのジェットコースターの勢いに乗ってやってきたと言っても過言じゃない」って強調してたのがすごく印象的でした。
BES:俺もそうっすね。それに乗っかった感じですよね。当時はずっとみんなと遊んでいたんですけど、生活が変わればサイクルも合わないし遊ぶ時間もなくなる。だから、いま会うのは〈bed〉ですよね。そういえば、当時、SCARS全員が俺らの下でワチャワチャ遊んでた高校生の卒業式のアフター・パーティみたいな会に呼ばれて行ったことがありましたね。親御さんもいて、「これでどうやっていつも通りライヴしろっていうの?」って雰囲気だった。案の定ライヴ後にシーンとなりますよね。親御さんが「いったい、これは何なの?」みたいな顔してたな(笑)。
一同:だははははっ。

辞書も引かなくなりましたね。わざわざ外人のあいだで流行ってるスラングを使う気にもならないし、それでも気になったら人に訊けばいいじゃないですか。それよりも自分が普段しゃべっている言葉でラップを作るほうがいいと考えましたね。 (BES)
JUSWANNA feat. BES & 仙人掌“Entrance”
■BESさんは、「勘繰り」や「バッド・トリップ」の複雑な精神状態をラップの表現に落とし込んで、それを他に類を見ないひとつのスタイルにまでしましたよね。
BES:それをやると絡まれるから誰もやらないんですよ(笑)。“かんぐり大作戦”を作って実際に3、4人に絡まれてますしね。
仙人掌:ヤバい(笑)。
BES:まあ、ハスってると勘繰りがたぶんすごいっす。みんなそうだと思います。
■勘繰りって物事の裏の裏まで読んでしまうことだと思うんですけど、本人が意図しないものも含めて、そのことによってラップの中にダブル・ミーニング、トリプル・ミーニングといくつもの意味が発生していってそれが独特のドープさになったのかなと思うんです。BESさんと同じ経験をしていなくても、聴く側はそのラップからいろんな想像力を喚起させられる余地を作るというか。
仙人掌:たしかに。それはまさにそうかもしれないですね。
■しかも、スラングはあったりしますけど、特別に難しい言葉や単語をそこまで使わないですよね。
BES:そうですね。国語辞典を引いたりしていたのは初期だけですね。パトワ語の辞典も引いてましたね。でも、辞書も引かなくなりましたね。わざわざ外人のあいだで流行ってるスラングを使う気にもならないし、それでも気になったら人に訊けばいいじゃないですか。それよりも自分が普段しゃべっている言葉でラップを作るほうがいいと考えましたね。
仙人掌:タカさんの表現はアメコミっぽい部分もあると思うんですよ。俺とメシアくんとタカさんで作った“Entrance”(JUSWANNA『BLACK BOX』収録。2009年)もそうですよね。現実をただありのままに描写しているんじゃなくて、自分たちが何かと格闘しているというある設定を頭のなかに描いてラップしたりしている。それで、あの曲の最後に「火のついたマイク飛ばす」って表現が出てくる。
■ああ、なるほど。
仙人掌:やっぱり人と違う言語感覚がありますよね。例えば、金色(キンイロ)をあえて金色(コンジキ)って発音することで言葉のハネやリズムを良くするとか、そういう感覚を当たり前につかんでるんですよね。仮にダサいラッパーが言葉として良い表現だからっていう理由だけでタカさんと同じ言葉を使ったとしても(言葉が)死ぬと思うんですよ。ただの言葉じゃなくて、倒置だったり、比喩だったり、リズムだったり、そういうのをすべて含めたタカさん独自の言語感覚があるし、ラップなんですよね。俺が最初観たときからそういうセンスや感覚がずば抜けていたんです。
BES:ありがとうございます(笑)。仙人掌も昔から生々しいラップをするし、自分の周りのことを歌っているのが聴いてすぐわかる。こっちもいままでそういう仙人掌のラップにずっとヤられてきたんで。俺がどんなに頭がおかしくなっても普通に付き合ってくれますしね。
仙人掌:ははは。それはホントに勘弁してくれって思いますけどね(笑)。
仮にダサいラッパーが言葉として良い表現だからっていう理由だけでタカさんと同じ言葉を使ったとしても(言葉が)死ぬと思うんですよ。ただの言葉じゃなくて、倒置だったり、比喩だったり、リズムだったり、そういうのをすべて含めたタカさん独自の言語感覚があるし、ラップなんですよね。 (仙人掌)
仙人掌も昔から生々しいラップをするし、自分の周りのことを歌っているのが聴いてすぐわかる。こっちもいままでそういう仙人掌のラップにずっとヤられてきたんで。俺がどんなに頭がおかしくなっても普通に付き合ってくれますしね。 (BES)
仙人掌 feat. ISSUGI & YUKSTA-ILL“STATE OF MIND”
■それぞれの最新作を聴いてお互いどんな感想を持ちましたか?
BES:仙人掌は選ぶトラックがやっぱりオシャレだなっていうのはありますよね。
仙人掌:タカさんの選ぶビートは俺にはつねに驚きがありますね。『THE KISS OF LIFE』もかなりヴァリエーションがあるっすよね。
BES:そうだね。作り始めたときは振れ幅があってまとまりのないアルバムにしようと思って。最終的には起承転結のついたアルバムとしてまとまっているけれど、まずはそこまで意識しないで曲作りをしようと思った。次に作る曲のことを考えながらいま作ってる曲をやらないようにした。まず、目の前にある曲に対して思ったことを書いて、完成したら次の曲を録る。そうやって作ったね。(I-DeAを見ながら)先生もそれを手伝ってくれましたね。昔からレコーディングのときに的確なアドバイスをいただいているんで。
仙人掌:B.T.REOくんのビートの曲(“ピキペキガリガリ”)、おもしろいっすよね。ディストーションがかかったようなミックスにしてますね。あれは自分のアイディアですか?
BES:あれは先生のアイディアでしたね。
I-DeA:あれはBESくんのアイディアじゃなかったでしたっけ? BESくんがそういう感じにしたいって言ってたと思う。
BES:もう忙し過ぎておぼえてないっすね(笑)。
一同:ははははは。
■MVもアップされている“Check Me Out Yo!! Listen!!”のRECはどうでしたか?
仙人掌:ビートが決まるのもRECも早かったですよね。ふたりでMalikのビートを聴いて「これだ!」って決めて、スタジオ行く前に駅前のマックで1時間ぐらいでリリックも書いた。即行作らないと緊張するんですよ。これまでタカさんと曲を作るとき俺のほうが待たせたこととか多いから。俺も無意識に力が入っちゃうんですよ。でも、俺、タカさんとやるときはラップ、キレてると思うっすね。
BES:たしかにキレキレですね。この曲のアナログも出しますよ。
仙人掌:だから、タカさんとやるときは「このフロウで食らわしてやろう」みたいな気持ちっすね。
■SHAKUもかっこいいですよね。
BES:かっこいいっすよね。JOMOさん(〈bed〉のマネージャー/ヒューマンビートボクサー/DJ)に「最近〈bed〉でいい若いラッパーいます?」って訊いたときに名前が挙がったのがSHAKUだったんですよ。自主でCDも出しててかっこいいんですよ。今日、持って来れば良かったな。
仙人掌:このアルバムもそうだし、『REBUILD』も『Bunks Marmalade』も何がヤバいって、ほとんどのメンツが〈bed〉で完結してるんですよ。そうやってフッドを上げることはヒップホップのなかでいちばんかっこいい行為だと思うんですよね。それは何にも代えがたい行為でもあるし、そういうタカさんを尊敬してますね、俺は。
BES:ラッパーとしてのノウハウをおぼえていろんな勉強をして、お世話になってきた場所が〈bed〉だからね。すべてのきっかけとなったのが、俺はあそこだから。俺のホームなんですよ。だから、リリパは〈bed〉でやるって決めてる。今日もこれから〈MONSTER BOX〉でライヴがあるしね。
仙人掌:今日あらためて、普通に、冷静に、タカさんとこうやって話せるの、自分的にヤバかったです。ありがとうございました。
仙人掌“Be Sure”
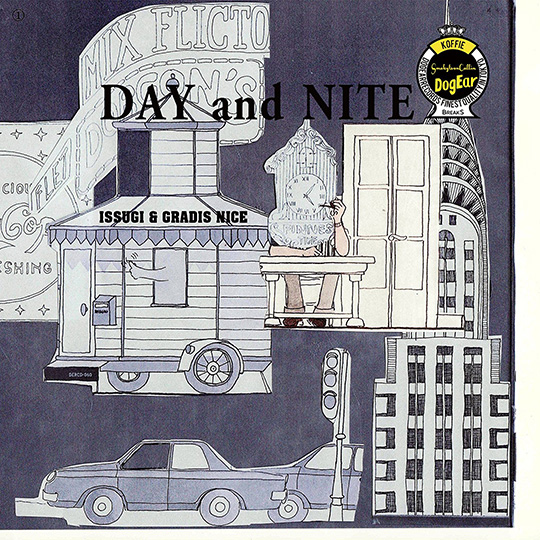 ISSUGI FROM MONJU - DAY and NITE
ISSUGI FROM MONJU - DAY and NITE

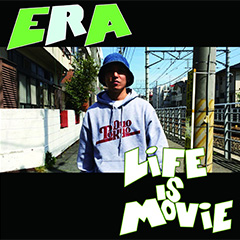


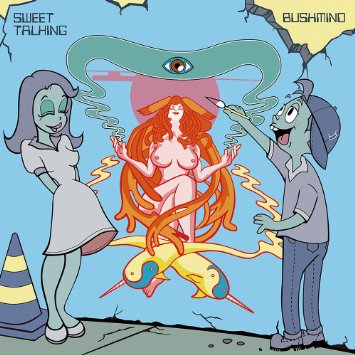

 〈オネスト・ジョンズ(正直者のジョン)〉は、ロンドンのレーベルであり、レコード店。ロンドン中心のやや西側、ポートベルロードで1974年にオープンしたレコード店(開店は1974年)にはじまっている。
〈オネスト・ジョンズ(正直者のジョン)〉は、ロンドンのレーベルであり、レコード店。ロンドン中心のやや西側、ポートベルロードで1974年にオープンしたレコード店(開店は1974年)にはじまっている。