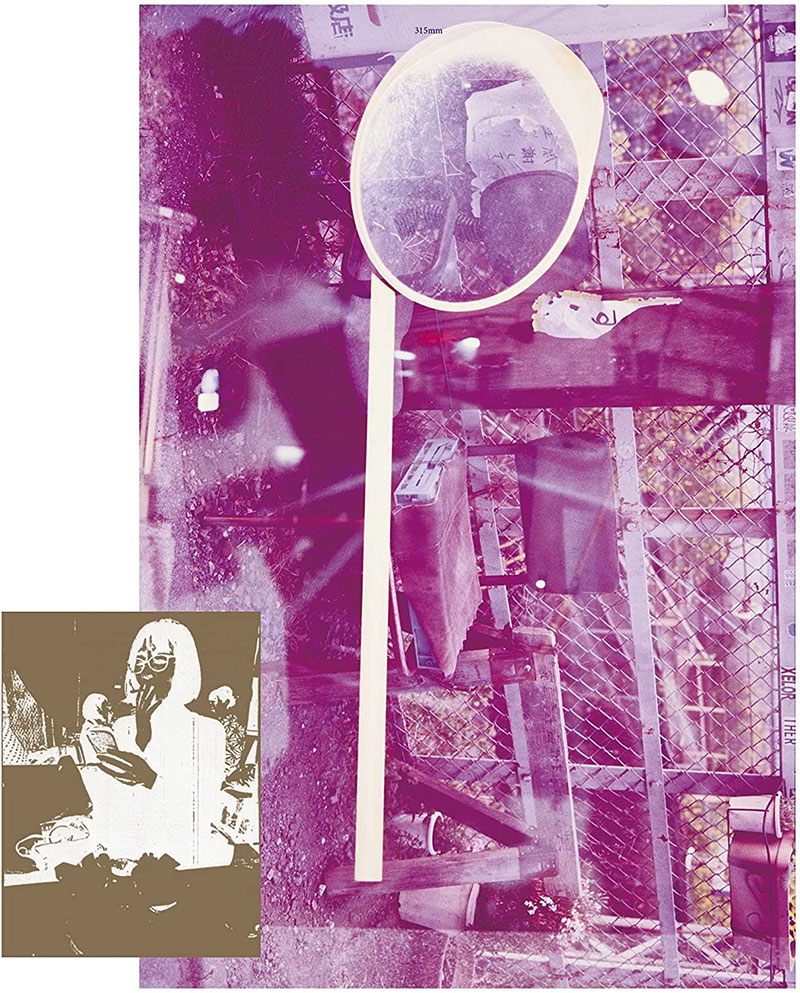いわゆるコロナ禍が一旦の終わりを迎えた2023年以降、ここ日本においてもナイト・ライフは復活を果たし、東京という手狭な都市には平日・休日を問わず多種多様なパーティが溢れかえっている。ただし、その姿形は2019年以前のものとは一変したようだ。
2020年──世界中のクラブ、ライヴ・ハウスが閉鎖され、ほとんどの人が自室に縛り付けられていた、パンデミックの時代。しかし、そんな苦況でもアンダーグラウンドの水面下では新たな動きが同時多発的に発生していた。それこそがいま、2020年代の新たなクラブ・シーンを形成した発端であり、抑圧されたユースの底知れないフラストレーションと真っ直ぐな音楽愛を熱源に燃え盛っている「クラブ・オルタナティヴ」ともいえるムーヴメントなのだ。
ラッパーが、DJが、バンドが、ひとつの空間上で交差し連帯する。シーン、ジャンル、界隈、リアル、フェイク、そんなしがらみはどうでもいい。とにかく、見たこともない景色と聴いたことのない音楽を浴びよう、場所がなければ作ろう、場所が失われることを食い止めよう。そうやって自然なクロスオーバーが各所で発生していった。そんな流れも2024年のいま、さらなる変容を遂げつつある気配がする。
吹けば飛びそうな小さな火種をアンダーグラウンドで守り続けた立役者は枚挙に暇がないが、今回はコロナ前夜にコレクティヴ〈XPEED〉を立ち上げ、現在は(こちらもコロナ禍に誕生した)新宿のクラブ・SPACEでスタッフを務めるDJ/オーガナイザーのAROW亜浪(CCCOLECTIVE)と、中国から日本に移り快活にサイケデリック・ワールドを探検するTEI TEI(電気菩薩)の2名を証言者として迎え、コロナ禍のこと、それ以前のこと、そして未来についてざっくばらんに語った。聞き手はNordOst名義で2021年にDJとしてのキャリアをスタートしたパンデミック世代の音楽ライター・松島です。
どんどん自分でヤバいパーティ作ってみよっかな~って! 見たことないパーティ作りたいよ。(TEI TEI)
■改めて振り返ると、TEI TEIちゃんは2021年のシークレット・パーティ「愛のテクノギャルズ」でデビューしてから大活躍ですね。
TEI TEI:2021年の6月ね!
■TEI TEIちゃんが主催してるパーティ〈電気菩薩〉をはじめたのはいつのこと?
TEI TEI:2022年の終わりごろぐらい。だからいま1年ぐらいやってきた感じになるかな。
亜浪:1年しか経ってないんだ! スピード感ヤバいね。
■サイケデリック・トランスから入って、いまはミニマル・テクノ的なアプローチになってるのもTEI TEIちゃんの面白いところで。
TEI TEI:でも、サイケから入って別の感じになっていったDJって多いと思うよ?
亜浪:その印象はあるかも。〈Liquid Drop Groove〉っていうレーベルをやってるYUTAさんのDJが好きなんだけど、インタヴューを読んでると「最初はトランスから入って、そのあとヒプノティック・テクノやミニマルに移ってった」って話をしてたし。
■なるほど、そうなんだ。「サイケデリック」って冠してないジャンルにサイケ感を見出して、そっちに行くようになるってことなのかな? よりトリッピーな音を求めて。
亜浪:ちょっと大人になって……みたいなね。
■2020年から今年で4年目になって、3年以上経ってるわけで。そうすると自然とみんな大人になってくだろうし、趣味も変わるしね。亜浪も、いまもう一度2020年11月に主催したシークレット・レイヴ〈PURE2000〉をやるのは難しいでしょ、初期衝動的なヴァイヴスのままだと(笑)。
亜浪:そうだね、絶対無理(笑)。
■やっぱりあのレイヴに自分はすごく影響されて、DJやってみようかなと思ったきっかけでもあったし。TEI TEIちゃんはその頃からもう日本にはいたんだっけ?
TEI TEI:私、けっこう日本に来てから長いよ。もう8年ぐらいかな。最初は全然音楽のことわからなくて、「愛のテクノギャルズ」に出る前もそんな感じで。ageHaのサイケのパーティとか、富士山の麓のレイヴとかでなにも知らないけど遊んでて、誘われたからDJやってみたの。もう、本当に運命だと思う、私と音楽って(笑)。
ジャンル問わず、アンダーグラウンドと呼ばれるシーンで連帯が生まれやすかったのがコロナ禍だったよね。バンドとかラップのフィールドで活動してる人もそうだし、同じようなことがダンス・ミュージックの場でも起きていたなっていう。(亜浪)
■コロナ禍で生まれた新しいクラブの動きを「ハイパー」みたいな言葉で総括することもあるけど、TEI TEIちゃんと電気菩薩はそういうシーンとは近くて遠い、よりアンダーグラウンドな場所にいたってことなのかな。僕らはあの時期、限られた遊び場を求めて自然と合流していった、というか。パンデミックがなければ、いまこうして3人で座談会をするなんて機会もなかったと思うし。具体的には2020年から2022年ぐらいまでかなと思う、シーンに点在してた人が一箇所に集まってた時期っていうのは。
亜浪:ジャンル問わず、アンダーグラウンドと呼ばれるシーンで連帯が生まれやすかったのがコロナ禍だったよね。それはライヴ・ミュージック、つまりバンドとかラップのフィールドで活動してる人もそうだし、同じようなことがダンス・ミュージックの場でも起きていたなっていう印象が強いかな。
■いまはもうみんな、古巣とか実家みたいなところに戻っちゃった印象もあるけどね。
亜浪:でも、一度できたつながりが完全に消えるっていうのは、やっぱありえないからさ。たとえばシーンは全然違うけど、バンドのAge FactoryとラッパーのJUBEEがAFJBってバンドをはじめたりとか。あれはコロナがなかったら実現されなかった動きだと思うし、そのタイミングでメンバーもDJやビートメイクをはじめたりしてて。ああいうタイプのバンドがここまでミクスチャー的に動いていく、っていうのはほぼなかったんじゃないかな? もちろん、その背景にはオカモトレイジ君の〈YAGI〉みたいなパーティが入口の役割を果たしてくれてる、っていうのもあるだろうけど。
■コロナ禍の時期ってとにかく表現の場が失われてみんな追い込まれてたから、既存のこだわりとか固定観念を超えた違う手段を見つける必要もあったしね。遊びに行く側も音の出る場所がなくて飢えてたところがあるし。亜浪が最初に〈XPEED〉を立ち上げたのは2019年ぐらい?
亜浪:うん、19年の10月ぐらい、コロナ前夜だね。幡ヶ谷のForestlimitからはじまって。
■幡ヶ谷Forestlimit、中野heavysick zeroとかの、ライヴ・ハウス性も持ったクラブではじまったんだよね。
亜浪:そうだね、でも次第にクラブのなかだけでやるのも違うな、って思って野外でやったのが2020年の〈PURE2000〉だった。
■〈PURE2000〉は、その前に同じ川崎のちどり公園でやってた〈SLICK〉の初回で体験したことに感化されて開いたレイヴだったんだよね。
亜浪:そう、〈SLICK〉の初回にめっちゃ感動して、「これを俺らでもやりたい!」って気持ちだけで動いてた(笑)。〈SLICK〉の7eさんたちに「どうやってここを借りたんですか?」とか、ゼロから質問させてもらったりして。本当に初期衝動的な感じ。
■だからこそ今年の5月に電気菩薩が川崎・ちどり公園でレイヴをやるっていうのは結構感慨深いものがあって……(笑)。
亜浪:たしかにね!
TEI TEI:ありがと(笑)。そろそろDJのブッキングもしようと思ってる。やるのは24時間!
■24時間やり続けるんだ!(笑)。
TEI TEI:フロアは2個ね。海側のエリアは使えないみたいなんだけど、見るだけの休憩スペースみたいにしようかな。まだ細かいことは決まってない、これからね。

2月、club asiaでおこなわれた〈電気菩薩〉のパーティ。提供:電気菩薩
2023年ごろからはベッドルームでDJソフトを触ってた子たちが集まる場としてのクラブ、っていう小さなパーティが急増した印象があって。「クラブの文脈を知らずに、フレッシュな感じでクラブを使って遊んでる」みたいなね。(亜浪)
■電気菩薩のメンバーってどうやって増えていったの? TEI TEIちゃんのほかにインドネシアから来たDIV☆ちゃんと日本人のzoe、ハイテックやダーク・サイケのDJをやってるMt.Chori君、あとはダウンテンポで渋めのプレイをするOwen君(Beenie Pimp)と、パーマネントなDJは5人ぐらいだけど。
TEI TEI:メンバーは……じつは私、めちゃくちゃ適当な人だから、最初は友だちの感じで誘ってた(笑)。DIV☆ちゃんとは最初そんなに喋ってなかったけど、私のパーティに毎回来てくれてたから。zoeちゃんは私のすっごい仲いい友だちで、Chori君とはめちゃ会うんだけど、実はいまでもそんなに喋ったことなくて。Owenは私が派手なルックの子が好きだから誘ったの!(笑)
■Owen君はドレッドで不良っぽいスタイルだけど選曲のセンスとかが激渋で、そういうギャップも込みでカッコいいよね。一周して、「派手さ」よりも「渋さ」をカッコいいと考えてそうな人もクラブには増えてきてる気がする。
亜浪:たしかに。新しいものは一旦拡がるところまで拡がったかな、って感じもあるし。ハイパーポップを飲み込んだ新しい音楽の流れにはまだ新しい余地はあるんだけど、もうすぐ天井が見えそうな雰囲気っていうかね。
■トラップやドリル以降、日本語ラップのシーンがものすごく大きくなったのとかも関係してそうだよね。草の根的なクラブ文化と交わらなくても独立して存在できちゃうから。
亜浪:あと、コロナが明けたと言われてからすごく感じたのが、クラブの健全なイメージがさらに色濃くなったな、ってこと。自分がちゃんと東京のシーンを観測できてるのはここ7、8年ぐらいのことだけど、最初ヘルシーな感じで遊びに行けてたのが〈CYK〉のパーティとか〈YAGI〉とかで、そのあたりが入口として機能してた印象。行ってなかったけど〈TREKKIE TRAX〉とかもそういう感じだったんじゃないかなと思う。で、2023年ごろからはベッドルームでDJソフトを触ってた子たちが集まる場としてのクラブ、っていう小さなパーティが急増した印象があって。「クラブの文脈を知らずに、フレッシュな感じでクラブを使って遊んでる」みたいなね。これはこれでめちゃくちゃ面白い状況だな、とも思うけど。
■一回コロナでそれまで続いてた流れが断絶したから、また新しい文脈がゼロからでき上がりはじめてるってことだよね、いまは。
亜浪:〈みんなのきもち〉とかにもそういう感じがあるかも。
■彼らには独特のテック美学みたいなものがあって、先にブレインダンス的な快楽性があってから身体性にアプローチしてくような感じが強いからね。
亜浪:歴史のなかで見ていくと、縦の流れから生まれたというよりは横のつながりから自然発生的に生まれたような動きだよね。
■ある種のデジタルな価値観って、いまのメインストリームな感覚になってってる気がする。だから逆にそうじゃないものを求めて、よりアンダーグラウンドで渋い感覚のあるところに向かっていくような動きもカウンター的に生まれてるのかな?
亜浪:まあ、パンデミックを経て明らかに絶対数も増えたからね。海外の人がまた入ってこられるようになってからは本当に爆発的な増え方をして、無数のパーティが毎週、毎日いろんな場所で開かれるようになったし。(コロナ期の)パーティへの飢餓感みたいなものは薄れたような気がするけどさ。
[[SplitPage]]

CCCOLECTIVE #7 AROW open to lastにおけるアニメーション作家/イラストレイターのZECINによるライヴ・ペインティング。提供:CCCOLECTIVE
私たちを支えてくれたのは、もちろん日本のみなさんもそうだけど、やっぱ中国の子たち。小紅書(RED)っていう中国のインスタグラムみたいなアプリにめちゃ載せてたら、中国には電気菩薩みたいなレベルのテクノ~トランスのパーティが全然ないみたいで、文化服装学院とか東京モード学園に来てる留学生がめっちゃ多くて。(TEI TEI)
■コロナ禍を経てTEI TEIちゃんとか僕とか、フレッシュな感じでクラブに面白さを見出していろいろとやってたら知らない間にDJになってたようなタイプも結構いるしね。まだ初心者マークが付いてるつもりだったけど、そうじゃなくなったのかも。単純にこの3人とも出演機会が増えたし。
TEI TEI:でも私、そんなにやってないよ。去年は66本ぐらい?
亜浪:いや、それも多い部類に入るんじゃない(笑)。
■TEI TEIちゃんはとくに、一回一回がすごく大規模だったりしそうだし。
TEI TEI:野外とか多いし、そうかも。
亜浪:1回の出演で2、3日とか拘束されるわけだし、自分の持ち時間とかも多いだろうしね。
■持ち時間でいうと、やっぱり東京のクラブの場合、文脈と一度切り離されたからこそショート・レングスのセット、40分以下みたいなスタイルが増えたっていうのはありそう。
亜浪:その辺の動きをSPACEのスタッフとして見てて思うのが、短いスパンでタイムテーブルを詰め込んでいくようなスタイルには課題もあるなってことで。もともとは箱ないしオーガナイザーからブッキングされて、フロアにいる人たちを楽しませて、お酒が出る雰囲気を作るような「職業としてのDJ像」があったと思うんだけど、ショート・レングスなパーティだとそこの部分が欠けてることもあるじゃん、ホームパーティ的なものの延長にあるコミュニティ的な動き方というか。コミュニティが大きくなるにつれて、それなりにしっかりした規模感のヴェニューでも通用するようになっていくと思うんだけど、そういうアプローチが通用する場っていうのはやっぱり限られるから、中の人たちのライフステージが変わっていくなかでプレイヤーの人口もまたグッと落ち込むんじゃないかな、って危惧してる。
■結局のところ、現状遊びに来てくれてる人たちが飽きてしまったら終わる動きではあるし、それはたしかに課題かもね。
亜浪:もちろん否定するわけじゃないんだけど、それで経営的に成り立っているヴェニューもいまは少なくないわけで、縦の歴史的な結びつきが希薄だといつか破綻しちゃうんじゃないか、っていうのが心配。だから、さっき言ってた「渋い」じゃないけど、職人的な感じの強度にもフォーカスしていって、どちらも横断できる感性を育める土壌が作れたらクラブの経済圏と一緒に発展していけるんじゃないかな、って思うんだけど。
■自分がまさに、最初期は過去育まれてきた文脈に一切目を向けないような感じだったからわかるなあ……いまは考え方を変えて、料理人とか職人みたいな気持ちでDJに臨むようになったけど。
亜浪:たとえばVENTなんかわかりやすいけど、あそこには下手なことができない空気感があるじゃん、出る側もやる側もテクノやダンスフロアの美学を尊重してるっていうか。撮影禁止だったり、一応ドレスコードがあることもあったり、と。雰囲気へのフィット感って、やっぱプレイヤー側はある程度意識すべき要素だよね。
■最初はしがらみにしか感じられなかったんだけど、1~2年ぐらい経ってやっとTPO的なものがいかに大事か気づいた、遅すぎたけど。遊びに行く側としても、やっぱりそういうこだわりとか美学みたいなものが強く伝わる場所にいたいなって思うし。電気菩薩はそこのこだわりがすごく強そう。
TEI TEI:最初は西麻布のTrafficぐらいの規模でやってて、けどもうひとつ違う道を歩きたいな、って思ってclub asiaやWOMBを貸してもらったりして。私たちを支えてくれたのは、もちろん日本のみなさんもそうだけど、やっぱ中国の子たち。小紅書(RED)っていう中国のインスタグラムみたいなアプリにめちゃ載せてたら、中国には電気菩薩みたいなレベルのテクノ~トランスのパーティが全然ないみたいで、文化服装学院とか東京モード学園に来てる留学生がめっちゃ多くて。その子たちの友だちもいまは旅行でめっちゃ日本に来てるから一緒に遊びに来てくれるし、メッセージもめっちゃ来るの、「最近おすすめのパーティはある?」って。小紅書の私のフォロワーはそんなに多くないんだけど、中国のクラバーの子たちはみんな電気菩薩を知ってくれてたの。先週上海のPLAYGROUNDってクラブが私を呼んでくれたりもしたし、アジアではフレッシュなものとして見られてるのかなあ。
■つまり、中国ではいま、まさにコロナ禍真っ只中の東京みたいな感じでみんな音に飢えてるような感じなのかな。熱気がすごそう!
TEI TEI:中国、実際いま電子音楽みたいなものがすごく流行ってると思う。ちょっと遅いけど、波が来てる感じ。中国で有名な『NYLON CHINA』って雑誌も、私たちのことをインタヴューしてくれたし。こういうことをやっている人は、まだ中国にはいないみたい。
亜浪:日本のDJも中国、台湾あたりにガンガン行ってるし、そういうアジアとの繋がりも今後強まっていけばいいね。
■もしかするとこれから、2年半前のTEI TEIちゃんみたいに電気菩薩とかのパーティに感化されて、新しくDJになったり、音楽を作ったりする人もどんどん増えそうかなと。ただ楽しく遊んでただけなのに、そうやって道ができていくっていうのは嬉しいことだし、希望ですね。
亜浪:そういう動きはいろんなところで起き続けてそう。音楽に限らず、東京って狭くて広い街だから。クラブ・シーンってひとくくりにするにはあまりに広大すぎるし。
■そのなかでも、よりアンダーグラウンドで音楽とクラブを本当に好きな人が集まってる場にやっぱり惹かれるよね。コロナ禍の異様な熱量ってやっぱり、現場への飢餓感があったからだと思うし、逆にいまは飽食の時代というか。これだけパーティが増えたのは素晴らしいことだけど、その分いろいろな場所を足で探さなくても自分にフィットする環境がすぐ見つかっちゃうから、広すぎるシーンの一角しか捉えられなくなっていくのかな、とか懸念があって。
亜浪:飽食の時代か(笑)。そういえば、自分の周りのクラバーは今年カウントダウン・イベントとかにも全然行かず思い思いに過ごしてたし、ある程度遊んできた我々世代はもうお腹いっぱいって感じなのかもね。
■今年を堺に次のタームに突入しそうだよね。好きなものに飽きてきたら自然と自分で作ったり、別の場所を探したりするようになると思うし、ここ数年のトレンドが肌に合わなかった人は流れを変えたいと思ってるはずだし。
TEI TEI:私も、ちょっと飽きてきた(笑)。でも飽きたから、どんどん自分でヤバいパーティ作ってみよっかな~って! 見たことないパーティ作りたいよ。
■そういえば、亜浪は新宿のSPACEで働いてどれぐらい経つんだっけ? 2021年のオープンから今年で3周年になるけど、新宿二丁目エリアに近くて繁華街と少し距離がある立地の感じとか、流れる音楽の多様性とか、ポップなデイ・パーティとディープなナイトタイムが共存してる感じとか、個人的には幡ヶ谷のforestlimitの次ぐらい好きな場所になりつつあるんだけど、そんなクラブでスタッフとして過ごしてみてどうだったかな。
亜浪:もうちょいで1年かな。感想か……疲れた!(笑)。単純に夜勤って体力的な消耗がヤバくて、遊びに行く感じとはまた違う話でさ。もちろんやりがいはあるけどね。あと、パーティを観るときの視点が良くも悪くも変わったかな。裏方の人の表情とかを観てその日がどういう雰囲気かを察せるようになったり、パーティの構成要素を隅から隅までチェックするようになったり。いままではタイムテーブルとかフライヤーの質感とかがパーティを構成する主要素だと思ってたけど、PAのオペレーションや箱の導線とか、いろんな物事が複雑に混ざりあってムードができてるんだな、ってことも知れた。
■オーガナイザーがこだわってる部分が人それぞれで異なるからこそ、同じクラブでも日によってまったく違う景色が広がってるっていうのはあるかも。もちろん統一感がある場も最高だけど、同じ空間でおこなわれる表現で空気が一新されるような場所ってやっぱ好きだな。電気菩薩はその点、世界観づくりにすごくこだわってる印象なんだけど、どうでしょう。
TEI TEI:電気菩薩は、もう本当に出てくれる人が自由にやりたいことをやってほしい感じ。私、すごく適当な人だよ(笑)。毎回いい空間ができてることにすごいびっくりしてるぐらいだし。前回はSMパフォーマンスのお姉さんが出てくれて、私はどんなパフォーマンスなのかあんまり知らなかったんだけど、ロウソクを垂らしたりとかしてて(笑)。でもなんか、それも電気菩薩っぽかった。不思議!

2月、club asiaでおこなわれた〈電気菩薩〉でのダンス・パフォーマンス。提供:電気菩薩
電気菩薩は、もう本当に出てくれる人が自由にやりたいことをやってほしい感じ。前回はSMパフォーマンスのお姉さんが出てくれて、ロウソクを垂らしたりとかしてて(笑)。(TEI TEI)
■電気菩薩に誘われた人たちが、無意識的にその空間に寄り添うようなパフォーマンスを寄せるでもなく自然体でやってくれてる、ってことなのかな。それってすごく理想的なパーティでカッコいい……。
TEI TEI:ね(笑)。いい空間が毎回ちゃんとできあがってくれて、ほんとにすごいなって思う。最初のころから出てくれてる友だちとかも、どんどんいい感じになってくれてるし。すっごい嬉しい!
■パンデミックが一応終息して思ったのが、配信イベントとかの時期を経てVJや映像みたいなヴィジュアル面での表現とか、音以外のクラブを構成する要素の地位が上がったかもな、ってことで。アーティストと音が絶対的、みたいな力関係が崩れたような気がするんだよね。
亜浪:それは良いことだったかもね。フライヤーデザインだったり、会場のポップアップとか展示だったり、いままでサブ扱いされてた要素とその作り手も出演者だよ、ってパーティは少しずつ増えてってるような気がする。というか、そもそもDJも裏方であって、空間それ自体をみんなで作り込んでく、っていうのがクラブ像として昔からあったわけだし、若い世代のシーンも徐々に然るべき形に洗練されてってるのかな、とも。
■尊重されるべきはフロアそのもの、というかね。自分含め、ライヴがなくなったからクラブに行きはじめたって感じのお客さんが多かった時期は、やっぱりDJもライヴ・アクトのような感じで観に行く人が多かったと思うんだけど、それだけじゃないっていうのは多くのユースが理解しはじめたのかな。
亜浪:いま(2023–2024)の感じがクラブ原体験になってる人たちが長く遊び続けてくれるかどうかの分かれ目って、自分の好きな物事以外の領域に、いかに興味を持ってもらえるかってことだなと思ってて。私がSPACEで毎月の最終水曜にやってる〈CCCOLECTIVE〉のブッキングは、とにかく人を見て決めてるところがあるんだよね。「この人とこの人がいたらこういうお客さんが楽しんでくれそうだな」っていうのをなんとなく予想して、そこと交わってないけど相性が良さそうなアーティストたちを違うフィールドからそれぞれ呼んでみて、出演者にもお客さんにも刺激を与えられたらいいな、って感じで。ただオルタナティヴな場所を目指すんじゃなくて、未来に繋がっていくようなパーティにしたい。

CCCOLECTIVE #7 AROW open to lastにおける空間演出。提供:CCCOLECTIVE
ただオルタナティヴな場所を目指すんじゃなくて、未来に繋がっていくようなパーティにしたい。(亜浪)
■本当の意味でハブになるような場所を作ってくれてるわけなんだ。
亜浪:うん、交わってなさそうで交わってなかったところを繋いでいきたい。
■いま各シーンで起きてることは、距離こそ近くても足がかりがないから今後ますます離れ小島みたいな感じになっていくんじゃないかな、ってちょっと心配してて。だから、そこに橋を架けてコミュニティ同士に連帯が生まれていけばいいな、と願うばかりです。音楽が好きで、クラブが好きなのはたぶんみんな同じだし、別に現場的な物事が好きじゃなくても、「ちょっといいかも」って思ってもらえたらいつかは合流できるはずだよね。
プロフィール
AROW 亜浪(CCCOLECTIVE)

DJ/オーガナイザー。新宿SPACEスタッフ。旧名Ken Truth時代にはSUPER SHANGHAI BAND、Usのフロントマンとして活動し、ロックとクラブ/レイヴ・カルチャーを横断するコレクティヴ〈XPEED〉を2019年に立ち上げ、2020年代の新たなオルタナティヴを創り上げた。2021年に改名し、現在はDJを主としたパフォーマンスを展開する。
2022年末に始動した〈CCCOLLECTIVE〉は、有機的な繋がりを持ったオープンな共同体を通じ、参加者に精神の自由をもたらすことを目標として掲げている、自由参加型のクリエイティヴ・プラットフォーム。これまで『Orgs』と題したパーティを昨年12月に下北沢SPREAD、今年4月には代官山SALOONにて開催。また、2023年8月からは毎月最終水曜日の深夜に新宿SPACEにて同名を冠したパーティを定期開催中。シーンを牽引するアーティストらを招き、実験と邂逅の場の構築を試みている。
https://www.instagram.com/917arow/
https://www.instagram.com/cccollective22/
TEI TEI(電気菩薩)

中国・北京より日本・東京にやってきたヒプノティック・サイケ・ギャルDJ。サイケデリクス表現を通過し、現在はテクノを主とした先鋭的でディープな音楽をジャンルレスにプレイ。母国文化や仏教的な美学など、汎アジア的な感覚をカオティックに表現するパーティ〈電気菩薩〉主宰。Re:birth、Brightness、EN Festival、ZIPANG Festival、和刻など全国各地の大規模野外レイヴに出演する傍ら、日々首都圏のディープなクラブ・シーンに硬質な華を咲かせている。
https://www.instagram.com/teitei08056/
https://www.instagram.com/denki.bodhisattva/