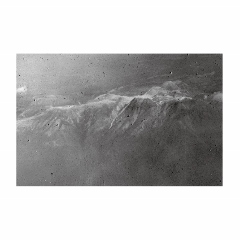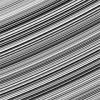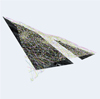MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- 橋元優歩
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 『成功したオタク』 -
- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
Home > Reviews > Album Reviews > Ord- W
ストーリーを覚えていない映画の記憶が、いや、そもそもまったく観たことすらない映画の記憶が、なぜかフラッシュ・バックのようによみがえる。映像すら霞むようなスクリーンの眩い光が瞬間、脳裏に再生する。しかし、その瞬間の映像には音はない。サイレント=イメージ。だが、それはその抽象性ゆえ、どこか音楽のようでもある......。
京都〈シュラインドットジェイピー〉の最新作ord『w』を聴きながら、そんな記憶が想起されていく。優しく牧歌的で、儚く幻想的で、そして澄んだ空気のように清潔な音。その質感が生み出す記憶。その記憶=音の向こうにある静寂。さまざまな音楽フォームを見事に昇華したポップで瀟洒なエレクトロニカ/エレクトロニクス・ミュージックでありながら、同時に、サイレンス/サイレントな世界を希求する音楽に思えたのだ。
そんな空想じみた結論らしきものへと先に急ぐ前に、アルバムについて簡単な説明をしておこう。ordは甲田達也とMihoyoのユニットだ。甲田は〈涼音堂茶舗〉から作品をリリースしていたheprcamの元メンバーである。彼らのアルバム『COHCOX』は涼音堂茶舗を知る人ならば記憶に残っているだろう。heprcamはドラマー/パーカッショニストの青木淳一とのデュオだが、ordはヴォーカリストMihoyoとのユニットである。ここにおいては「声」が、00年代以降のエレクトロニカのサウンド・フォームのなかで見事にエディットされている。たとえばプレフューズ73のヴォーカル・チョップとボーカロイドが00年代のエレクトロニクス・ミュージックにおける「声」の扱いという意味で、ふたつの解答を用意しているように、本作もまた声とエレクトロニクスの交錯を、とても繊細な手法で実現しているように思えたのだ(ちなみに、声とエレクトロニクスという意味ではATOM TMの最新作『HD』のエディットも重要であろう)。
とはいえ、ヴォーカル・トラックは主に3曲であり、全8曲のトラックはヴァリエーションに富んでいる。アルバム1曲め"Koko"は、レコードのスクラッチ・ノイズに、ミニマルなサティのようなピアノのフレーズとフランス語による会話(映画からのサンプリング?)が重なっていくトラックだ。この瀟洒なトラックにおいては、ピアノと言葉のミニマルな反復が時折、絶妙にグリッチし、まるで壊れた記憶のような音像が生み出されていく。2曲めはMihoyoによるボーカル曲"Eriel"だ。メロディに対してトラックは極めてミニマルである。だがそのミニマルなトラックの隙間から、鳴っていない弦の音が聴こえてくるような不思議な感覚を味わうことができる。続く1分20秒ほどのギターをメインとした"Moyo"を経て、テープ反転の音からノイズが鳴り響くエレクトロニカ・シューゲイズ"Kugeuka"に。アコースティックからノイズへの世界の反転=暗転。そして、クリッキーなビート、そこに突如クラシカルなピアノ、ジャズのブラシワークのようなリズムなどがエディット/交錯する"Irena"へ。シンセウェイブ的なアンビエント・トラック"2006"を経て、ヴォーカル/ヴォイストラックであり、本アルバムの代表曲といってもいい"Msimu"に行き着く。独特のリズムとMihoyoのボーカルとサウンドが微細にエディットされ、聴き手の聴覚を軽やかに刺激する見事なトラックに仕上がっている。ラスト"Lala"においては、ギターのミニマルなフレーズに、微かな環境音がレイヤーされ、00年代初頭のフォークトロニカ(例えば、2002年に〈カーパーク〉からリリースされたグレッグ・デイヴィス『アルボール』など)が現在の音響的精度で再生したような曲でアルバムは静かに幕を閉じる。同時にこのラスト・トラックの響きは、冒頭"KoKo"のピアノの響きへと繋がっていくだろう。
そう、あらゆる時間が円環するように、このアルバムもまた最初の時間へと円環するのだ。2000年代のエレクトロニカを最良の音楽性がいち枚の作品に内包されているかのようなアルバムである。だが、ゴッタ煮的な騒がしさは全くない。アルバムの音は、ひとつのトーンできちんと統一され、音楽は記憶の残像のように展開する(糸魚健一の丁寧なマスタリングも、作品の本質を引き出しているように思える)。
ここでアートワークを見てみよう。写真もまた甲田達也自身の作品だという。表面は、白地に宙を舞う鳥の瞬間を捉えており、対する裏面は黒のイメージ。ケースを開くと、青い空に強烈な光を放つ太陽の写真イメージ。「朝」と「夜」が、「昼」の瞬間の光を挟み込んでいるのだ。強烈な光の記憶。その記憶がもたらすサイレンスな朝と夜。その無音の記憶。その無音に向けての音楽。このアルバムは実にバリエーションに満ちた音楽を収録しながらも、ある種の静寂さのアトモスフィアを生成している。いわば本作は、エレクトロニクス/ポップによって、そんなサイレント/サイレンスの世界を繋いでいるように思えるのである。それはとても繊細な創作だと思う。
なぜ、人が不意に映画のワン・カットを想起するとき、そこには音はないのか。映像と音響の乖離。だが、その瞬間の記憶に音をつけることはできるだろう。本作は、エレクトロニクス/ポップによって、そんなサイレント/サイレンスの世界を繋いでいるように思えた。それはとても繊細な創作であり、また同時に「聴くこと」が「無音の記憶のトレース」であることをも想起できる仕事のようにも思える。
それにしても、〈シュラインドットジェイピー〉から相次いでリリースされる作品は、どれも日本の電子音楽の最先端を語る上で欠かせない重要な作品ばかりだ。近作A.N.R.i.『All Noises Regenerates Interaction』もエレクトロニカとミュージック・コンクレートを極めてポップな質感で実現した傑作であった。本作もまた、日本の電子音楽の最良のカタチを、密やかに、優雅に、セカイの耳に向けてプレゼンテーションしているように思えた。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE