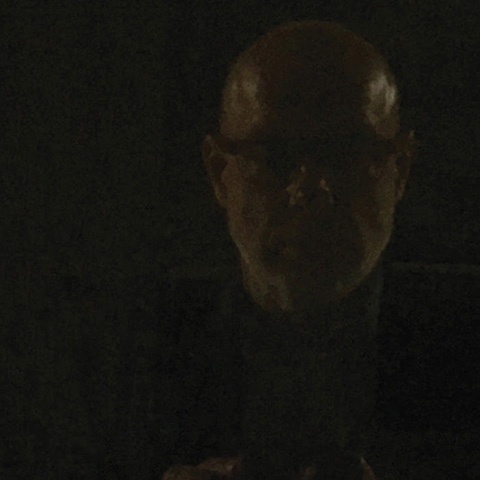MOST READ
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- 『ファルコン・レイク』 -
- レア盤落札・情報
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
Home > Reviews > Album Reviews > David Byrne- American Utopia
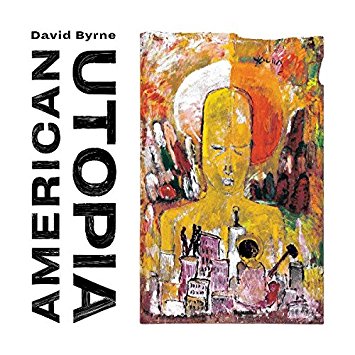
柴崎祐二
デヴィッド・バーンは、長い活動を通して、知的アメリカン・オルタナティヴの拠り所で有り続けた。
初期ニューヨーク・パンク・シーンにあってトーキング・ヘッズはテレヴィジョンと並び唯一無二の個性を湛えたバンドとして活動し、ロックンロールへ回帰類型化していくパック・ロックへのカリカチュアとも言えるような脱構築的ロックコンボとして名を上げ、アフリカン・リズムを導入やブライアン・イーノとのコラボレーションなどを経て、その存在感を確固たるものにしてきた。
その後もバーンはバンドの活動と並行して映画や舞台へも活動の場を広げながら、様々に先進的な作品を世に問い続けてきた。その表現活動は常に精緻な知的バランスに担保されたもので、時に理屈先行型のヘッド・ミュージック的(懐かしいワードだ)であると批判をされることもあったが、オルタナティヴの始祖のひとりとして、音楽界に限らず広く深いリスペクトを集め、いまや齢60代半ばにしてその評価は不動のものとなった感がある。
今作『アメリカン・ユートピア』は、ファットボーイ・スリム、セイント・ヴィンセントらとのコラボレーション作を挟んで、ソロ・アルバムとしては『グロウン・バックワーズ』以来14年ぶりの作品となる。
一聴してまず感じるのは、久々のソロ作と銘打つに足る盤石のデヴィッド・バーン・マナーの復活であろう。盟友イーノとの共作曲をはじめ、ロディ・マクドナルド (The xx、King Krule、Samphaなど)、ジャム・シティ、ジャック・ペニャーテ、トーマス・バートレットといった多彩なミュージシャンの参加に加えて、もっとも注目すべきはバーンと数曲を共作しているダニエル・ロパティン (Oneohtrix Point Never)の貢献だ。これまでもジャンル越境的なコラボレーションを重ねてきたバーンの活動ゆえ、この共演はまさに起こるべきして起こったものとも言えるだろう。ダニエルは一部曲で「テクスチャー」とクレジットされている通り、彼が本作に持ち込んだ質感は、これまでも絶えることなくバーンが志向してきた先端的でライブリーな音楽との交接という点において非常に大きな役割を演じていると言えるだろう。
しかし、ここで注目したいのは、そうした気鋭のミュージシャンと組んで、いかに新味をまぶした音色で彩っていても、結局はやはり「デヴィッド・バーン」という大きな屋号に吸収されていく、そのようなダイナミズムなのだ。
おそらくそれは先述の通り、バーン自身の知的バランス感に負うところが大きいだろう。様々な音楽要素を貪欲に取り込みながらも、その音楽要素自体が本来的に内蔵する土俗的・肉体的ダイナミズムに対して、ある種の透徹した視点を欠かさない。ラテン〜アフリカン・リズムを導入し、そのダイナミズムを深く理解しクリエイターとして血肉化しつつもなお、究明対象たる音楽自体に全身を預けるといったことはしない。常に、ひとりのアーティスト、いやプロデューサーとして、音楽的風景を睥睨し、設計図を理解し、システムを統括しているのだ。
このような創作姿勢が文化収奪的と批判するのは易しいが(現にそのように非難を受けることもあった)、ここに聴かれる音楽からは、所謂「作家的エゴ」のようなものが聴こえてこないのだ。これは、彼が旧来的な意味でのロック・バンド観や、作家主義的アーティスト像を常にカリカチュアの対象として扱ってきたことを考えれば理解は容易い。それゆえにいかに様々な音楽要素を「援用」しようとも、当のセルフィッシュな主体がそもそも存在していないのだ。これは例えばかつて椹木野衣がハウス・ミュージックについて述べたシミュレーショニズムとしての音楽観に親和的なものだろう。
さて、そういった視点であらためて本作を鑑賞してみよう。冒頭に置かれた“アイ・ダンス・ライク・ディス”は、クワイエットなピアノとボーカルに導かれたあと、攻撃的なビートが突如として現れ、リスナーの虚を突く。また続く“ガソリン・アンド・ダーティ・シーツ”や“エブリバディ・イズ・ア・ミラクル”では得意のラテン的狂騒とポップネスが理想的に融合し、フレッシュなトラックの音像とあいまって、この作品がソロ名義作として並々ならぬ自信を伴ったものであることを伺わせる。また、リードトラックとしてミュージック・ビデオも公開されている“エブリバディズ・カミング・トゥ・マイ・ハウス”はイーノとの共作曲で、キャッチーなトラックにバーンのハイトーン・ヴォーカルが乗り、まるで80年代初頭の綺羅星がごときトーキング・ヘッズ楽曲を思わせる楽曲だ。
しかし、アルバム全体を通して、そのように数多くの音楽要素の繚乱(物理的な音素数も相当に多い)に彩られながらも、これまでのバーン作品と同様、情念の表徴としてのパッショネイトな表現は周到に排除され、そのことによって逆説的に「主体の透明」な作家としてのデヴィッド・バーン像が前景化することになる。あくまで我々は、デヴィッド・バーンの体臭ではなく、デヴィッド・バーンの知性を味わうことになる。
また、今作のリリックで彼は、知的シニカリストとしての手腕を相変わらず縱橫に発揮しているが、現実状況それ自体がシニックをブルドーザーのようになぎ倒そうとしていくいま、ひとりのポエットとして苦い逡巡を滲ませることに思いの外素直だ。
苛立ち、不安、欲望が様々な形で現れているこの世界(それこそを彼は「アメリカン・ユートピア」と表現しているようだ)と、それに囚われる私達自信を、時に感傷的とさえ言えるほどの筆致をもって描き出す。「あなた」「わたし」という審級を超えて(“ドッグス・マインド”では私たちが犬の視点に引き据えられ、“バレット”では、拳銃から発射される弾丸の視点を取る)語られる物語もしくはその断片は、極めて悲観的な世界観であるようでいながら、どこかに慈しみが潜んでいる。
その点で、リリックにおいては、知性で組み上げられた精緻な建築に若干ながらエモーショナルで不確定な要素を持ち込んだと言っても良いのかもしれないが、このような時代だからこそ、社会と、そこで生きる自らも含めた人間のネガティブな面にジリジリと迫ることが出来るというのもまた、また知的な態度であると言えるだろし、同時に、人間の感情という不確定性を自らのアートの中に内在化することで作品自体が外的世界へ扉を開くことになる、ということも彼は知っているのかもしれない。
デヴィッド・バーンという人は徹頭徹尾、本来的な意味で「アーティスト」だ。その鋭敏な知性はいま、これまでに増してより鮮明に我々の目に映りつつある。
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE