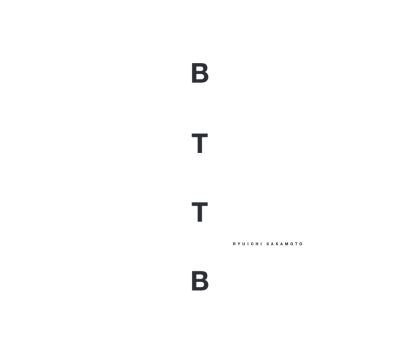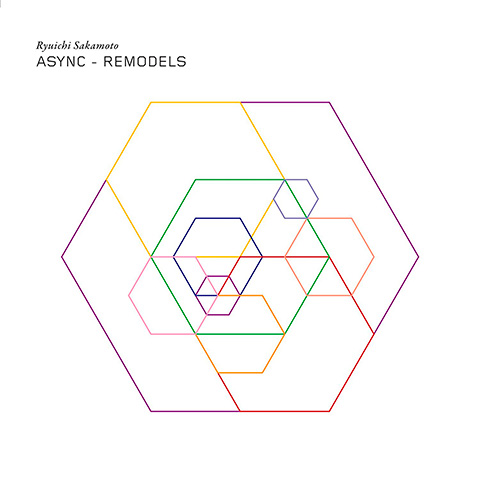MOST READ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- Beyoncé - Renaissance
Home > Reviews > Album Reviews > 坂本龍一- 12

デンシノオト
音を置く------。ひとつひとつ丁寧に、慈しみながら、繊細に、 音がノイズが、旋律が、音の庭に、そっと置かれていく。
坂本龍一の6年ぶりのアルバム『12』を聴いて、そんな印象を持った。坂本龍一が、ひとりでコツコツと、まるで毎日の大切な仕事のように、いうならば「音の庭師」のように、音を丁寧に、繊細に、置いていく光景が脳裏に浮かんだのだ。静かな庭に響く音たち。サイレント・ガーデンのような音楽とでもいうべきか。唐突だが、私は、どこか後期の武満徹の透明な響きを連想した。
同時に『12』は00年代以降の坂本龍一が追求していたアンビエント/クラシカルな音響作品の結晶体ではないかと思う。この20年ほどの坂本龍一の活動が、静謐な音響のなかにミニマムに、そして複雑に息づいている。
では、『12』は、これまでの坂本龍一のアルバムのなかでどのように位置付けにある作品だろうか。ひとことでいえばとてもパーソナルな作品だと思った。
サウンドのムードとしては『async』(2017)の後半、 “ff” や “garden” を継承する透明なアンビエンスを展開している。しかし『async』よりもさらにパーソナルな音だ。これまでのようにコンプセプトを立てたソロアルバムではなく、いわば「日記」のように制作された楽曲を収めたアルバムゆえ、より個人的な音に感じられるのは当然かもしれない。
スケッチのようなアンビエント/電子音楽を収めたアルバムというならば、2002年にリリースされた『COMICA』がある。『COMICA』は9.11から受けた衝撃を治癒するかのように内省的な電子音楽を展開していたという意味では、『12』との共通項を見出すことが可能だ(私見では『COMICA』があるからこそ2004年の『キャズム』があり、『キャズム』があるからこそ、2009年の『out of noise』が生まれ、あの傑作『async』に至ったと考えている)。しかし『COMICA』の楽曲は、ある程度は編集されていたようだが、この『12』の楽曲はほぼ無編集のまま収録されているという違いがある。
さらに、1曲目、5曲目、7曲目などで聴くことができるシンセサイザーの音色や響きについては、『愛の悪魔』(1999)や『デリダ』(2002)の内省的な電子音/電子音楽も思い出しもする。クリアな残響が美しいミニマルなピアノ曲という意味では、『トニー滝谷』(2007)などのミニマルなサウンドトラックも想起してしまう。とはいえ『愛の悪魔』『デリダ』『トニー滝谷』は、映画音楽である。映画作品あってこそ作られた音楽だ。一方、『12』は、まるで日記をつけるように演奏・録音された楽曲であり、作品の成立過程がまるで異なる(私見だが『トニー滝谷』クリスタルな残響に満ちた透明なピアノの音は、『out of noise』以降のソロアルバムの音に受け継がれているように思える)。
加えて坂本龍一のルーツがこれ以上ないほどに素直に表現されているパーソナルな作品という点では、ピアノ・ソロの『BTTB』(1999)系譜の作品と位置付けることもできるかもしれない。8曲目 “20220302 - sarabande” などは、普通のポップスではあまり使われない複雑な転調が自然に用いられ、より洗練・成熟した「20年後の『BTTB』」とでも称したい楽曲を収録している。だが、『BTTB』はピアノソロ・アルバムでもあり、電子音楽・電子音響的な要素はないという差異がある。
小節構造にとらわれない自由な演奏/音響の記録という意味では、クリスチャン・フェネスとの共作『Flumina』(2011)を思わせもする。加えて冷たく美しいシンセサイザーの響きという意味では、アルヴァ・ノトと共作したサウンドトラック『レヴェナント』(2015)の音響のようでもある。00年代以降、彼らとの共作が、坂本に与えた影響を大きいことに違いはないが、『12』のサウンドは、純度100%の坂本龍一の音楽である。
つまり、本作『12』は、2009年の『out of noise』、2017年の『async』のオリジナル・ソロ・アルバムで追求されたアンビエント音響、1999年の『愛の悪魔』、2002年の『デリダ』、2007年の『トニー滝谷』などのサウンドトラック・ワークで披露されたパーソナルなシンセやピアノの響き、アルヴァ・ノトやフェネスなどの電子音響アーティストとの共作による電子音とピアノの融合、1999年の『BTTB』で実現したバック・トゥー・ベーシックな坂本のピアノ楽曲など、坂本龍一の四つの系譜が交錯しつつ、しかしそのどれからも微かに逸脱している稀有なアルバムということにある。
しかし坂本ファンであれば、じつは、この『12』のような「完全なソロ」、つまりは彼の音の結晶を聴きたかったのではないかと想像してしまう。じじつ私がそうだ。『12』は、私にとって長年夢見ていたようなアルバムなのである。私はこのアルバムをすでに深く愛してしまっている。
このアルバムに満ちている美しさ、清潔さ、透明さ。それは意図されたものというより、ごく自然に坂本龍一の身体を通じて表出した結果ではないか。大病を患った坂本龍一が自身の心と体を癒すために、日々の感覚のままに、編み上げられたアルバムだからだろうか。
じっさい坂本龍一は、このアルバムをつくるきっかけについて、治療後、それまでは音楽を聴いたり、作ったりする体力がなかったが、ある日、シンセサイザーの音を浴びたくなり、何も決めずにただ演奏したことが始まりだったという。その曲が、本作の1曲目 “20210310” に収められている曲らしい。以降、日記を書くように徒然なるままに、音のスケッチを残していった。いわば音による治癒のようなものを感じつつ、編まれていった曲たちといえよう。つまり自身の体力と病、そして坂本の長年にわたる音楽の経験が交錯し、一種、身体に作用するような音楽・音響作品に仕上がっていったのではないか。
楽曲名から推測するに、2021年3月に2022年4月までに制作された12曲が収録されているが、坂本はこの「12」という数字に特別な意味は持たせていないと語っている(2023年1月1日・NHK FM放送・ラジオ特番「坂本龍一ニューイヤー・スペシャル」より)。
曲名も制作日がわかるような簡素な数字になっている(自分としてはこのシンプルなミニマムさに河原温のミニマルアートを思い出してしまった)。 ただ「12」という数字には坂本がこだわり続けてきた時間の概念を象徴しているとも『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』の最終回(「新潮」2023年2月号)でで語っている。たしかにこのアルバムを聴いていると「時」を意識する。
シンセサイザーのシャワーのような曲に始まり、やがてピアノと電子音、環境音が交錯する電子音響になり、再びシンセサイザーによるアンビエントを経て、より洗練された「作曲」を意識した曲に変化し、メタリックな、鈴のような金属音でアルバムは終わる。まるで時の円環のように私は、またアルバム冒頭に戻り、はじめからアルバムを聴いてしまう。くりかえし、くりかえし…。
音から音楽へ、そして音へ。私は、その曲すべてに、いや音のすべてに、音の一音、音の一粒を慈しむような感情を感じた。もちろん「美しい」という言葉は批評の放棄かもしれないが、しかしやはり「美しい」と私は何度もつぶやきたい。『12』はとても美しいアルバムだ。
加えて『12』の収録曲を繰り返し聴いていると、まるでピアノやシンセサイザーの音色を間近で感じるような距離の近さを感じてしまった。曲が生まれる瞬間を聴いているような感覚とでもいうべきか。では「距離の近さ」とは何だろうか。私は、坂本龍一の生の「呼吸」が音楽に反映しているからではないかとも思えたのだ。
その点から3曲目 “20220123” と4曲目 “20220123に注目したい。この2曲は、ピアノと環境音が、まるで森の中をゆっくりと歩くように交錯する瞑想的なトラックだ。そこに何か呼吸のような、もしくは環境音のような音が一定に反復されていく。私は勝手にこのスー、ハーという音を坂本の呼吸=リズムのように感じ取ってしまった。続く4曲目 “20220123” でも即興的なピアノに環境音がレイヤーされ、そこに呼吸音とも鳥の鳴き声ともいえる音が繰り返される。
この2曲のピアノは即興的であり、「呼吸」は少し浅く、苦しげである。しかしその呼吸もまた透明な音楽の中に次第に溶けていくかのように残響を響かせる。まるで音によって身体が治癒されていくように。なによりピアノの透明な響きと「間」が実に美しい。呼吸。残響。間。ここにあるのは「時間」というものの美しい提示だと思う。
音を置く。鳴らす。聴く。呼吸をする。すると持続と変化が起こる。ときに反復も逸脱ある。まるで「生きること」そのものように。生を治癒するように。そうして時間が無限に連なっていく。坂本龍一が「ぼくはあと何回、満月を見るだろう」最終回(「新潮」2023年2月号)でひいていた武満徹『時の園丁』の言葉を思い出した。
『12』のミニマルな音響のなかには、無限の時/音の螺旋階段がうごめいている。2023年から未来に託すような名盤として、これからも聴き継がれていくに違いない。(1月7日記)
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE