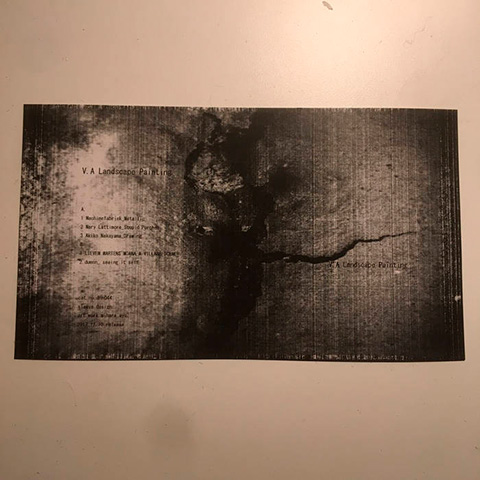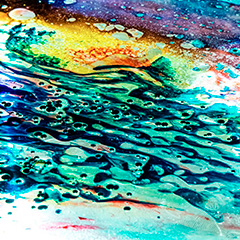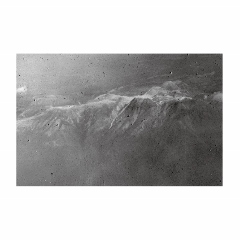MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Reviews > 合評 > duenn feat. Nyantora- duenn
素直に楽しめない作品では、あるが...... 文:竹内正太郎
いつかは君と本当の空を飛べたらなぁって、それだけさ
スーパーカー"CREAM SODA"(1997)
本当じゃない空を走る、真っ白なひこうき雲。成熟に対する拒絶と、未熟に対する拒絶を同時に抱えながら、反抗という社会性をなんら帯びなかったそのバンドの思春期は、シューゲイジーなギター・プロダクションと、倦怠をはらんだ歌唱、そして何より、言葉に落とし込まれた過敏な十代の感性によって、世の典型さや平凡さを斜めに断裁しながら、あっという間に過ぎていった。癖になった意味のないため息、うんざりするような馴れ合い、不必要に甲高い連中の笑い声、ありふれた虚栄、虚飾、駆け引き、出し抜き、気持ちの悪い上昇志向、そして、それらをシニカルに見つめる自分の凡庸さ。『スリーアウトチェンジ』(1998)は、およそ十代という罪深い幻の季節を、コンパクト・ディスクの許容値ぎりぎりまで使い、ギター・ロックのエチュードとして録音している。
1995年、青森県八戸市にて結成。どう考えても遅すぎる出会いだったが、私は彼らの解散がアナウンスされた後、初めてその車に乗った。従前のギター・プロダクションにエレクトロニクスが屈託のない表情で交わる『JUMP UP』(1999)は、作品のバランスという点で、彼らの早熟さをもっとも端的に捉えている。ウォーク・スローリー。しかし、この時期のシングルB面で、ドラムンベースの試験的導入や、憂鬱なダウナー・ポップを披露せずにはいられなかった彼らにとって、そうした思春期性はもはや足枷でしかなかったに違いない。ろくにトリートメントされていないようなロウなミックスで過去を一括清算した『OOYeah!!』『OOKeah!!』(1999)を経て、彼らはトランス・ロックの加速度でもってゼロ年代の始まりを一気に駆け抜ける。『Futurama』(2000)は、レイヴ・ミュージックへの憧憬を、ロックの文脈においてヴァーチャルに昇華させた意欲作だった。
ところで、良くも悪くも独りでは曲を作れないという点に、団体音楽の大きな魅力がある。密室で顕微鏡をのぞくような、省察が行き届いた孤独なベッドルーム・ミュージックにはない、共同体の中でのある種の運動(ときに競争原理)が働くことによって、バンドのポップ・ポテンシャルが大きく引き出される例を、私たちはよく知っている。『HIGHVISION』(2002)は、互いの方向性に違和を感じ始めた彼らにとって、ポップ・バンドとしては最後の結実だった。益子樹や砂原良徳らとの合流、テクノの跳躍力、電子音の煌めき。全反射するような"愛(I)"は光の伝送路で無限に増幅され、ひこうき雲が消えた本当じゃない夜空に、"Strobolights"を何本も突き刺す。終盤、勝井祐二のバイオリンが外界の光を閉じていくそのアルバムは、バッド・トリップ気味に暗い示唆をまき散らしながら終わっていく。
消えてしまったストーリー
出番を独り待っている
静かに 静かに ただ静かに 夢を見ている
スーパーカー"LAST SCENE"(2004)
そして、最後の妥協点を探るように作られた『ANSWER』(2004)は、ポップ・バンドとして結成された彼らが、かつて拒絶していた成熟(少なくとも高度化や洗練)を受け入れ、セミ・ポップの領域へと踏み出したことを如実に物語る。音の装飾よりも空間のニュアンスを重視した、メロウなプロダクション。散文的な歌詞。ミニマルな展開。その削ぎ落とされた妥協点は、逆説的に彼らの飽和でもあった。翌年、バンドは解散を選ぶ。これ以降の4人の物語と、私はなぜか一定の距離を保ってきた。個人的にもっとも親しみをもって追いかけたのは、リミックス・ワークを通じてTV・オン・ザ・レディオやデイダラスら海外のオルタナティブ、そしてボーカロイド文化とも前向きに交わってきたフルカワミキであるし、一般的にもっとも成功した存在として認知されているのは、ロック・バンドのプロデュースからK・ポップの作詞まで手掛ける、いしわたり淳治であろう。
中村弘二(以下、ナカコー)はといえば、アンダーグラウンドを好み、端的にはiLLを名乗ってレフトフィールドの開拓を試みてきた。テクノ、アンビエント、グリッチ、ドローン、ストーナー・フォーク、チェンバー・ポップ、ひと回りしてのロック、あるいはスーパーカーの再考、そしてLAMA。そうした変遷の先に、いつの間にか復活させたNYANTORA(ニャントラ)名義によって、ナカコーは相変わらずの実験趣味(と孤独趣味)を爆発させている。〈ダエン〉からのリリースとなった、レーベルの代表アーティストでもあるダエンとのコラボレーション『duenn feat nyantora』は、相当時間の無音部・微音部を含む、実に抽象的な作品となっている。カセット・テープなので、スキップもできずにとりあえずは黙って聴いているしかないわけだが、音も鳴らないし、あー、眠ってしまおうか、と、忘れたころに浮かび上がる音。かと思えば、あれ、いつから音、鳴ってないんだっけ、と、気付いたら霧散している音。鳥のさえずりもあれば、心地よいグリッチ、耳をかすめる程度のノイズもある。
正直にいえば、一応、遅れてきたスーパーカー世代である筆者としては、素直に楽しめない作品では、ある。私はまだ音楽に加速度を欲しているし、ポップのある意味での下品さを必要としている。とはいえ、狭く聴かれることと、広く聴かれないことを同時に望んできたナカコーの立場からすれば、本作は完全な匿名性をまとうことに成功した作品ではある(いま、無条件でカセット・テープを聴ける人はそう多くないはずだし、ネット上で聴くこともできない)。というか、不況だ、不況だと言われて久しい昨今の音楽業界にあって、内容的にも外装的にも、"あえて広がり過ぎない音楽"をアナログ・メディアでリリースすることを、私は贅沢なことのように思う。DIY文化のプライドか、LAMAとのバランスか。いずれにせよ、小さな承認を大仰に分け合う、繋がりすぎた私たちのネットワークを断ち切るように、聴き手の受動性を拒絶するアンダーグラウンドの精神は続く。
文:竹内正太郎
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE