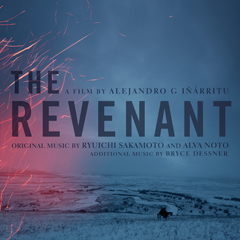MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル
- 『成功したオタク』 -
- Bobby Gillespie on CAN ──ボビー・ギレスピー、CANについて語る
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
- Claire Rousay - a softer focus | クレア・ラウジー
Home > Reviews > Album Reviews > Diamond Version- CI

現代アートは、メディアと人の関係を批評的にリ・プレゼンテーションする。ゆえにポップ・アートは大量に消費される複製品をネタにしてきた。そして消費社会特有の空虚な隙間から不意に表出する死を拡張させていく。空虚/死。そこにおいて美の価値判断は転倒し、結果として批評性が生まれる。その批評性ゆえ、作品の価値も生じる。価値はトレードされ、金銭を生む。
たとえば、アンディ・ウォーホル、リチャード・ハミルトン 、ロイ・リキテンスタイン、ゲルハルト・リヒター、リチャード・プリンスを思い出してみよう。彼らは消費社会のきらびやかな(もしくは捨てられた)空虚に、積極的にアジャスト/アディクトしてきたアーティストたちである。彼らは空虚なきらめきを、クールに模倣し、コピーし、ウィルスのように増殖させる。
そして2014年、ダイアモンド・ヴァージョンは、彼らの方法論を意図的に借用する。そう、広告やマーケティングに塗れた世界に「反撃」を加えるために。
ダイアモンド・ヴァージョンはカールステン・ニコライとオラフ・ベンダーによる音響エレクトロ/インダストリアル・ミュージック・ユニットだ。
カールステン・ニコライは、ドイツの電子音響レーベル〈ラスター・ノートン〉を主宰するドイツ出身のアーティストである。彼はアルヴァ・ノト名義で多くの電子音楽作品を発表してきた。また、池田亮司とのユニットcyclo.や坂本龍一とのコラボレーションも知られており、まさに現代電子音響シーンの最重要人物といえる。さらに本人名義で多くのインスタレーション作品を制作しており、高い評価を得ている。
オラフ・ベンダーも同じくドイツ出身のアーティストだ。〈ラスター・ノートン〉からバイトーン名義で音楽作品をリリースしている。彼は、1996年にフランク・ブレットシュナイダーとともに〈ラスター・ミュージック〉を設立した。後にカールステン・ニコライの〈ノートン〉と合併し、〈ラスター・ノートン〉が生まれたというわけだ。いわばドイツ電子音響シーンの中心人物というべき人物である。その作風はエレガンスと攻撃性が同居したメカニカル・エレクトロニクス・ミュージックといえる。
2012年、この2人がダイアモンド・ヴァージョンというユニットを組んだという報は、彼らの音楽を追いつづけてきたリスナーに瞬く間に広まった。 ダイアモンド・ヴァージョンは、アナログ盤でのEPシリーズをリリースし、勢力的なライヴ活動を世界各地で行う。2013年には日本にも訪れた。EPシリーズには、映像作品(PV)も同時制作され、ユニット/トラックのテーマを増幅させる役割を担っている。
カールステンとオラフの生み出すトラックは、これまでの電子音響テイストから最先端のデジタル・ジャーマン・エレクトロ(インダストリアル)へと変貌した。だがその変化は、近年の2人のサウンドからするとさほど意外ではない。たとえば、2011年にリリースされたアルヴァ・ノト『Univrs』、バイトーン『Symeta』の音響エレクトロなサウンドの系列に繋がる音ともいえる。また、ノトとブリクサ・バーゲルトのannbも重要だ。さらには〈ラスター・ノートン〉自体も、近年、エレクトロ、インダストリアル化しつつあり、00年代初頭のクリック/グリッチな音とは一線を画する音楽作品をリリースしているのだ(ちなみにダイアモンド・ヴァージョンのリリースは〈ラスター・ノートン〉ではなく、老舗〈ミュート〉から)。
そして本作『CI』は、リリースまで時間をかけてこともあってか、とにかくクオリティが高いアルバムに仕上がっている。ビートもノイズもすべてが磨き挙げられ、まさにダイアモンドのようなきらめきを放っているのだ。
だが真に重要なことは彼らが、あるクリティカルな意識で、自らの「ポップ」化に向かい合っている点でもある。本作『CI』は、オフィシャルのアナウンスにも書かれているとおり「ブランドスローガンの派手な広告、そして狡猾なPRなどのマーケティング合戦の時代への反撃」として制作されたという。CIとはコーポレイトアイデンティティの略であるのはいうまでもない(「企業ロゴ」をテーマとしたアルヴァ・ノト『Univrs』にも通じるテーマだろう)。
ふたりは、ある戦略的な方法論をユニット/アルバム・コンセプトに導入したように思える。自ら「ポップ」になることで通俗的なポップを打つとでもいうべきか。ここで私なりにダイアモンド・ヴァージョンの「4つのポップ/アート戦略」を提示してみる。
●ポップ/アート戦略1「ミュージック/コンテクスト」
クラフトワークなどジャーマン・エレクトロニクス・ミュージックの伝統と現在形/型である。エレクトロなビートを導入し、同時に80年代中期のキャバレー・ヴォルテールのような流行のインダストリアル/テクノへも接近している。また、ペットショップ・ボーイズのニール・テナント、元祖スーパーモデル・詩人のレスリー・ウィナー、オプトロンを駆る伊東篤宏 、〈ラスター・ノートン〉からアルバムをリリースしたばかりのKyokaなど、多彩かつ個性的なゲストの参加によって、 音楽のコンテクストの複雑化と錯乱を実現している。また、声の導入も重要なポイントといえよう。
●ポップ/アート戦略2「アート/クリティック」
末期資本主義社会(=グローバリズム社会)において「流通するイメージ批判=ポップ・アート」としてのデジタル・ミュージックを成立させている。世界に溢れる広告的なイメージをPVの映像などに引用することで、その本来の機能を停止し、ダイアモンド・ヴァージョンなりの新しいクール/ポップへと変換。EPシリーズのPVのみならず、アルバムのアートワークにも引き継がれているコンセプトである。そのPVはデイヴィッド・ブレア『WAX』を想起してしまう。
●ポップ/アート戦略3「サウンド/アディクト」
その磨き上げられた音響と音圧がアディクトを促す。このアルバムのミックス/マスタリングは精密かつ端正である。また、全体にマイナーコードのトラックが多く、そこに硬質なダイアモンドのようなビート、ベース、ノイズがストロボのように点滅しているのだ(ロック的な、ともいえる)。高音と低音の見事なコントラスト、そこはかとないダークさ。この音の良さが聴覚へのアディクトを生む。ゆえに、あの異物感に満ちたkyoka参加のトラックが際立つ。
●ポップ/アート戦略4「ポップ/イコン」
その3つのポップ戦略から本作の存在意義が見えてくる。それは「ポップ/イコン」化である。メディア批判を内包しつつも、それ自体がクールで現代的なポップ/イコン足りえること。真のポスト・モダンの実現。ゆえにアルバム・タイトルが『CI』なのだともいえる。彼ら自身がデジタル・ポップ・アートなのである。
「コンテクスト」「クリティック」「アディクト」「イコン」。この4つポップ戦略によって、ダイアモンド・ヴァージョンは自らをポップ/イコン化する。彼らはサウンドによって流通する広告イメージを意図的に模倣する。そして、その模倣によって、ウィルスのように社会に浸透する広告イメージの効用を停止させてしまうのだ。
ポップ・アートの伝統とでもいうべき方法論である。それゆえ、このユニットの音楽やヴィジュアルには、微かなノスタルジー(いわゆる90年代初頭のビデオアート的な?)を感じてしまうのだが、何より重要な点は、この研ぎすまされたデジタル・サウンド/ビジュアルによって、現在でもポスト・モダン/ポップ・アートが成立してしまう点にある。私は、そこに時代のモード(の本質)を感じてしまう。世界、メディア、飽和、危機、模倣、反撃。そのような身振りが、いままた、とてもクールなのだ。
クール・ビューティなダイアモンド・ヴァージョンのトラックを耳に注入すること。それは「世界」へのアジャストであり、同時にアゲインストだ。この疾走する両義性こそ、ダイアモンド・ヴァージョン、最大の魅力でもある。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE