MOST READ
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- Reggae Bloodlines ——ルーツ時代のジャマイカ/レゲエを捉えた歴史的な写真展、入場無料で開催
- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50
- DJ Narciso - Dentro De Mim | DJナルシゾ
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定
- DJ Python and Physical Therapy ──〈C.E〉からDJパイソンとフィジカル・セラピーによるB2B音源が登場
- aus - Eau | アウス
- interview with Ami Taf Ra 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ | アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio
- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先
- interview with Shintaro Sakamoto 坂本慎太郎、新作『物語のように』について語る
- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門
- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ
- Ikonika - SAD | アイコニカ
Home > Interviews > 菊地成孔×大谷能生 ジョン・コルトレーンを語る - ──パオロ・パリージ『コルトレーン』日本版を読みながら
簡単に言うと、また神格化が起こっているんだよ。(菊地)
菊地:それからこの本がele-king booksから出てくるってこと。もう死語だけど「クラバー」と呼ばれているひとたちがさ、やっとジャズをネクスト・レベルのものとして捉えるようになり、クラブジャズはハードバップのダンス・ミュージック形だということも知っちゃったいま、ピース系やフリー、スピリチュアルなものを聴いて高揚感を得ることがクラブの効用で、その源流にコルトレーンがあることから、この漫画が出たことは……
大谷:そうね。『スイングジャーナル』がないからあれだけど。もうジャズ・メディア最後の宝ですよね(笑)。
菊地:簡単に言うと、また神格化が起こっているんだよ。アリス・マクロードとくっつくのは必然的だから難しいけど。
大谷:一応ね、われわれの啓蒙活動もあり、ポリリズムの話もわりと通用するようになったじゃないですか? コルトレーンはアコースティック・サウンドで、ベースがあって、4ビートでいっしょだから、リズム構造がわからない状態で聴いているひとが多いでしょう? たくさんの作品があるんですけど、それぞれけっこう違う。いちばんアラブに寄っているものとか、けっこうめちゃくちゃになっているのとか(笑)。『ライヴ・イン・ジャパン』を聴いていて思うのは、混乱したまま進んでいるときと、スカッとやっているときがあったりとか。
菊地:メンターがほしいひとっていうのは、いつまでたっても弟子でいたいわけなので、言葉はあれだけど、ファザコンな娘さんがいつまでも小娘でいたいっていうかさ。比較的幼稚なことをコルトレーンがしているのを、昭和のコルトレーン聴きのひとは絶対に認めないっていうか(笑)。コルトレーンが“チム・チム・チェリー”にまで手を出していたことを見て見ぬふりをするっていうか。
大谷:「これはなかったことに」ってのがコルトレーンは多いんだよね。
菊地:「なかったことにする」っていう人間の心的営為はね、年々重要度を増していると思うんだよね(笑)。SNSが発達したりとか、過去のテキストを読んだりっていうときにね、見たくないものをなかったものにする。チャーハンのなかのネギやグリーンピースは取っちゃうみたいなさ(笑)。大人買いに対する子ども食いっていうかさ(笑)。
あと、有名な話で、『ブルー・トレイン』のジャケットのコルトレーンはじつは飴を舐めていたっていう。これ、作者は気づいて書いてる?
有名な話で、『ブルー・トレイン』のジャケットのコルトレーンはじつは飴を舐めていたっていう。これ、作者は気づいて書いてる? (菊地)

大谷:これはね、気がついてないですね。描き方がそう。
菊地:あれは亡くなった中山康樹先生の卓見っていうかね。
大谷:あれは棒付きのキャンディを舐めているんじゃないかという説があって、その目で見ると随分と印象が変わって見える。実際に棒がちゃんと写っているんですよ。
菊地:哲学的な思慮深いジャケットってことになっているし、あと『ブルー・トレイン』っていうくらいだから、青いフィルターを通しちゃっているから見にくいけど、じつは飴食ってんじゃないかと(笑)。
大谷:そう思うと、この本の絵は目が点になってますけどね。
菊地:この漫画は作画上、全員の目が点になっていて、すべてのメガネが白になっている。で、ブラック・パンサーだけ黒いんだよね。俺は漫画評論なんかやるわけじゃないけれど、ひとつのフォーマットを置いてますよね。あと筆者自身があとがきで書いていますが、当たり前のことだけど、これは伝記としておもしろくするために多少のフィクションは自覚していると。たいしたことじゃないんだけどね。ボブ・シールの着任を1年ズラして書いているから、クリード・テイラーに〈インパルス〉へ引っ張られたというのが抜けるんだよね。マイルスにおけるテオ・マセロとは言わないけれど、ボブ・シールは大変なパートナーになっていくわけで、そこを史実よりも1年早く書いている。それを含めて、これはフィクションとして読んでほしいと。そんなこと言われても相当伝記なんだけどね(笑)。
コルトレーンが意外と早く亡くなっていることと、その負荷になった理由は、昔麻薬をやっていたから体が弱かった、というだけではすまない。やっぱりストレスは大きい要素だからね。早婚の妻を捨てて、自分のメンターであるアリス・コルトレーンに向かったっていう。俺はアリス・コルトレーンが好きだけど、アリスをオノ・ヨーコさん扱いするひとがいるんだよね。オノ・ヨーコさんも俺は好きだよ(笑)。要するに、インテリでスピリチュアルな女性を、子どもっぽいアーティストが奥さんとしてメンターにしていくことの典型例というかね。それに対して、何度も言うけど、昭和マッチョのジャズ聴きたちは、あんまり問題にしていなかったというか。子ども聴きでそのことは抑えちゃう。でもこの本は、そこを丁寧に描いていて、それはさすがイタリアっていうかさ。
大谷:うん。恋人の影響は大事だよって。奥さんをメンターにするというか、アーティストにはそういうひとが多いですからね。マネージャーが嫁とか。
やっぱり、デザイン的にうちらはもっと知っているなと思うんだよね。〈ブルー・ノート〉や〈プレスティージ〉のトリミングの仕方とかね。タッチはいいとして、これを描くんだったら〈インパルス〉のデザインでやれよって思うところもあるわけ。(大谷)
菊地:でもアリス・コルトレーンとオノ・ヨーコさんはそれどころじゃないからね(笑)。ジョン・レノンとジョン・コルトレーンというふたりのジョンの人生を変えているわけで。ジャズはすごくホモ・ソーシャルな世界で、そこをまだぬけていない。ヒップホップですら現在柔らかくなってきたんだけどね。
大谷:付き合っている女で人間が変わるということを認めたがらないバンカラな感じだね。あと、漫画を読んでいて逆説的に気づいたのは、渋谷系はコンテンポラリー・プロダクションのデザインのパワーがすごくイメージ作りに大きくて、たとえば昔のレコード・ジャケットの名作をリアレンジしてカヴァー・イメージを作ったりしたじゃないですか。それがやはり秀逸だったんだなと。この漫画を見ると、基本的にコマはレコード・サイズで全面的にやってるんだけど、その二次創作具合が甘いっていうか、デザイン的には日本の方が全然進んでるなって。〈ブルー・ノート〉や〈プレスティージ〉のトリミングの仕方とかね。タッチはいいとして、これを描くんだったら〈インパルス〉のデザインでやれよとかって思うところもあるわけ。字をどこに置くかでも印象は変わってくるじゃない? でも残念ながら、イタリアには渋谷系はなかった(笑)。信藤三雄さんがいなかったから、そういうデザイン感覚がないのかなーとかね。キャラ化も含めて、日本の二次創作ってすごいじゃない? 日本で漫画化したら、コルトレーンもキャラ化しそう。そういう意味で日本は特殊なんだなと思いました。
菊地:さっき言ったけど、クラブへ行ったひとが、EDMは空虚だって思ったときに、何か空虚じゃないものを求める。俺はEDM好きだけど、たぶんそこで求められるのは、コルトレーンの精神性と同じものなんだよね(笑)。宗教的でもあり政治的でもあるということから、EDMとは違った、内実のある音楽としてコルトレーンを拝めていくということなのかなと。この作者は80年生まれでしょう? 95年に15歳だから、クラブ全盛期世代なわけだよね。日本だと野田努さんとかもさ、俺たちが東大に呼んでよせばいいのにジャズの話をした(笑)。「おれはジャズのことなんか何にもわからない」って言ってた(笑)。さらに、イギリスのクラバーにとってジャズなんか、ブラック・ミュージックのフィクションなんだってハッキリ言った人間が、いまはもうカマシ・ワシントンみたいなものにどっぷりっていうかさ(笑)。やっぱり人間、子どもができるとそうなるもんですか、みたいな。
大谷:野田さん、スタイル・カウンシルならわかるんだけど、って言ってたじゃないですか、とか。
菊地:一生デトロイト・テクノでいいって言ってたのにね(笑)。セオ・パリッシュが新譜を出したのはいいんですか? まぁ、俺が『ele-king』読んでないだけで、何か言ってるんだろうけど。
大谷:まぁ、ヨーロッパ経由のジャズっていうイメージがよっぽど変わるよね。
「私は聖者になりたい」は、真に受けるものではないっていうさ(笑)。
菊地:逆にアメリカだけにこれがないっていうか。アメリカの外側に広がる、クラブでジャズを聴くってひとたちに対して、いちばんストイックでいちばんスピリチュアルな役回りを負わされていて、本人も実際に負わされていたところがあるんだよね。だから、やっぱり負荷がかかっているよね。
大谷:みんなにそう言われたら、コルトレーンだったらそう答えるよね。
菊地:答えるだろうね。それに、このひとはモンクとやっているときがいちばんのびのびしてるんだよ。モンクがメンターだから。マイルスとやっているときもすごいんだ。あと、メンターじゃないんだけど、エリック・ドルフィーが隣にいてくれたときも相当心強かったと思うよ。『アフリカ/ブラス』もそうだし『オレ!』もそうだし。ところが先に死んじゃうからさ。モンクも頭がおかしくなってしまいますし。マイルスとはつかず離れずだったけどね。だから、自分の体質に合わないパブリック・イメージを背負わされ続けると、すごく負荷になる。自覚される誤解によって苦しむことは、逃げ出せるからそんなに負荷じゃないんだけど、コルトレーンはそれを自分で背負ってしまって、自分の体に向いていないことを、神輿に乗せられてやっちゃうっていうのがコルトレーンの最晩年だよね。だって4、5年ズレていたら公民権運動もこうなってはなかったし、第3世界の音楽がアメリカにとってどうのこうのってふうにもなってなかった。
大谷:あと4、5年生きていれば……たとえばチック・コリアが「永劫回帰(リターン・トゥ・フォーエバー)」とかって言い出すし、ショーターも入信するわけでしょう? その時代に突入していたら意外と大丈夫だったかもね。
菊地:あと藤岡靖洋先生がやたらと、自著やいろんなところで言いたがる、コルトレーンが来日会見で言った「私は聖者になりたい」は、真に受けるものではないっていうさ(笑)。「もう悪いことはやめます」って言っているだけだっていうさ。
大谷:あれは後ろに「(笑)」をつけるのがちょうどいいんだっていう。「私は聖者になりたい(笑)」。
菊地:そのことも漫画のなかには何もないよね。大谷君がキャンディ話とその話をあとがきで指摘しているけど。ただ、伝説を信じたいひとは、それを破壊されるのが怖いから、伝説破壊的な言説をすると、袋叩きに遭うじゃない? だからコルトレーンがメンターが欲しかった体質だったっていう、よく見ると誰でもわかる現実なのに、それを言うだけで特定のひとに嫌がられると思うんだよね。だからわざわざ嫌がられることをウェブに載せたり、スペース・シャワーTVで話してもね……(笑)。
大谷:だんだんそうなっちゃいますよね。最後に組んでいるドラマーなんてラシッド・アリだよ(笑)。みんなわかってんの(笑)?
マイルスはクールにモードになっていって、コルトレーンはホットにモードになっていった。それがフリー・ジャズと直結しちゃった。さらにはギャラクティック・ソウルというか、銀河に想いを馳せるてしまうというね。(菊地)
菊地:俺なんて2005年の時点で鈴に気をつけろってあんなに言ったのに、この漫画のはじまりはドラだからね(笑)。(※編集部注 ラシッド・アリとのデュオによる『インターステラー・スペース』では曲の冒頭に鈴の音が入る)
大谷:コルトレーンはドラは叩いてない。鈴まではいったけど(笑)。演奏の最後にドラをバーンって叩いたら面白いけどね(笑)。
菊地:そういうバンドは他にはいっぱいあったからね。
大谷:ディープ・パープルとかレッド・ツェッペリンと間違えてんじゃない(笑)? プログレ・バンドのドラマーのうしろにはなんでドラがあるんですかね。コルトレーンのバンドがやったら面白いけど。
菊地:ドラを叩きそうな勢いだったけどね。最後はバタドラムといっしょにやってるし(笑)。民族楽器を使ってワールドへ行くところだったんだよね。普通にエチオピアン・ジャズみたいなさ、「コルトレーンの影響なんて知らねえよ」って感じのファンクに毛が生えたみたいなアフリカのジャズって、いっぱいあんのよ。「エチオピアン・ジャズ コンピ160」とかさ(笑)。
大谷:しかもほとんど60年代後半でコルトレーンと同世代。
菊地:あんな感じでアフリカだって言いながらサックスを吹いていたら、もうちょっといけただろうね。
大谷:写真を見ればわかるわけで、コルトレーンはアルトも吹いていたからね。なのに意外とみんな子ども食い、子ども聴きしてしまう。どう考えてもジャケットにはアルトを吹いている姿が映っているでしょっていう。コルトレーンは「ヤマハからもらったアルトをずっと吹いていました」って言っているし。
菊地:来日ライヴね。もらってうれしかったんだね(笑)。
大谷:もらってうれしくて、その晩に使っちゃうっていうのも子どもっぽいね。コルトレーンを聴くときは、そういうところも確認してほしいんですよね(笑)。この写真なんて、「はい、先生」みたいな感じじゃないですか。はっきりと師匠と弟子の関係ができている。
菊地:この段階で学生みたいな顔ができるっていうね(笑)。あとは、ビーバップに対するモーダルみたいなものを、独力で身につけたでしょう? マイルスと手に手を取ってと言ってもいいんだけど。モードについて説明をすると、ものすごく時間がかかるからね。ジョージ・ラッセルやマイルスを含むモーダリストっていうかさ。バップを超えてモードへ行くっていうことの月と太陽っていうか。マイルスはクールにモードになっていって、コルトレーンはホットにモードになっていった。それがフリー・ジャズと直結しちゃった。さらにはギャラクティック・ソウルというか、銀河に想いを馳せるてしまうというね。
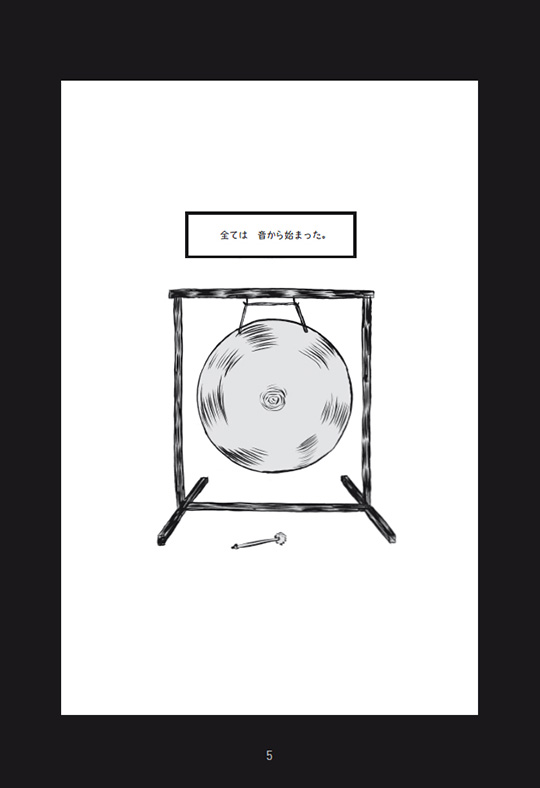
コルトレーンは宇宙船に乗らなかったことで、神話性が消えてないっていう。(大谷)
大谷:サックスの奏法の話でいうと、コルトレーンはダブルリップで、上を巻くじゃないですか? 歯が悪かったのかもしれませんね。この漫画ではそこは意識しているように見える。あとモードのサックスのタンギングをするのに、シングルじゃなくてダブルタンギングで切っていくやり方。マニアックな話ですが(笑)。
菊地:バップはハーフタンギングだからね。
大谷:昨日けっこう音源を聴き返していたんだけど、58年の時点でずいぶんとフレージングが違うなと。
菊地:元祖ワールド・ミュージックだよね。『カインド・オブ・ブルー』なんてまだまだジャズっぽいだろうと油断して聴くと、あの段階でエチオピア民謡みたいになっているからさ。相当モードだよね。
大谷:マイケル・ブレッカーの『ドント・トライ・ディス・アット・ホーム』の一曲めってさ、スコットランド民謡みたいなやつじゃん? EWI使って。ああいう方向もあったんだろうなっていうね。変なワールド・ミュージックという意味でいうと、ブレッカーはコルトレーンを受け継いでいるっていうか。
菊地:サキソフォンって楽器が新しいからね。いろんな奏法ができるから。擬似民族楽器としても使える。
大谷:アラブの笛や、ティンホイッスルみたいな、あんまりタンギングしないでも使えるっていうか。このあたり吉田隆一氏が詳しいですけど。
菊地:両巻きはチャルメラの吹き方と同じだからね。
大谷:そういう要素がサックスのなかに混ざっているので、けっこうやり散らしているなと。
菊地:早い段階から民族音楽的ではあったと思う。それはモードだから。パーカーはぜんぜんモードじゃないからね。そこからモードのやり方に向かっていく時点で、時限爆弾は仕掛けられていたというか。最後の方にやり散らかしのレリジョン・ミックス、もしくはエスニズム・ミックスみたいになっているというね。
大谷:簡単に言うと『スター・トレック』というかさ(笑)。「宇宙にはなんでもあるんだぞ?」っていう状態になっていく過程で、亡くなったようなところがあったもんね。
菊地:ミクスチャーされた状態を、なんとなく宇宙ってことでいいんじゃないかっていうふうに、コルトレーンはできなかったんだよ。リアルなので。その点では殉教の感じがあるし、リスペクトせざるをえないっていう。ギャラクティックな方向へ行っちゃうと、「お気の毒」っていう気持ちから「面白い」って気持ちになっちゃうからね(笑)。たとえば、サン・ラやジョージ・クリントンにはコルトレーンみたいなリスペクトは抱けない。違うリスペクトなら抱けるんだけどね。
大谷:コルトレーンは宇宙船に乗らなかったことで、神話性が消えてないっていうね。
コルトレーンは宇宙船が救いにこなかった。だからシリアスなんだよ。宇宙船がきちゃったら笑えるから。笑えるってことは素晴らしい癒しであり、赦しであるわけで。(菊地)
菊地:もうちょっと体調がよかったらコルトレーンが宇宙船に乗ったかどうか、誰にもわからないね。だけど、コルトレーンのすぐ後のひとたちは、宇宙船にも乗ったしね。アルバート・アイラーみたいにすぐに死んじゃったひともいるけど。アイラーなんてチャーリー・パーカーと同じで34歳で死んでいるんだから。現役8年間。コルトレーン以後のブラック・ミュージックが、アメリカ国内で迎えたレリジョン、エスニズムとポリティクスの混乱を、音楽家という本来は快楽的でバカなひとたちがなんとかまとめようとしたときに、宇宙にしてしまう(笑)。サン・ラの『サン・ソング』っていうさ、ハーマン・ブラントがサン・ラに変わった瞬間のアルバムとね、カール・グスタフ・ユングの絶筆『空飛ぶ円盤』って本が1年違いで出てるの。もうちょっとくっついていたら、ユングはおそらく臨床例として、サン・ラを挙げていたかもしれない。自分のことを土星人だと思っているんだから(笑)。『空飛ぶ円盤』は翻訳で読めるんだけど、やっぱ運命の糸を感じざるをえない(笑)。野田くんの『ブラック・マシン・ミュージック』(2001年、河出書房新社)の大きなテーマになっていくギャラクティカという問題はさ、レイヴから繋がっているじゃん? 要するに、大麻だとか、ドラッグを使って飛ぶのだと。それで山のなかで音楽を聴いて、クサを食って宇宙へ行った気がして現生から逃げるという欲望がさ、白人や黄色人種どころじゃなかったでしょうな、というね。
大谷:宇宙に行きかけたひととしてのコルトレーンだね。
菊地:鈴も鳴らしたし、お寺まで行ったからもう一歩だったんだけどね(笑)。ただ、コルトレーンの場合は宇宙船が迎えに来なかった(笑)。
大谷:これは死んだ後に出たやつだからな(「インターステラ・スペース」)。よく見るとここらへんに宇宙船が写っていたりして(笑)。
菊地:それは矢追純一イズムでしょう(笑)。写っていないものが見えてくる。……結論としてはコルトレーンは宇宙船が救いにこなかった。だからシリアスなんだよ。宇宙船がきちゃったら笑えるから。笑えるってことは素晴らしい癒しであり、許しであるわけで、ジョージ・クリントンがあんな格好をしてるよとか、サン・ラっていう土星人は泣けるよねっていうのは赦しがあるんだけど、コルトレーンは赦されなかった。
大谷:サン・ラとかアルバート・アイラーみたいな格好をして出てくればよかったのにね。それにも間に合わなかった。
宇宙まではあと一歩。(大谷)
菊地:アリスがしてあげればよかったのに、惜しいところだったよね。全部を一気にアウフヘーベンして、しかもギャラクティックではなく、ストリートなまま政治や宗教の混乱の負荷を受けてしまって、一種の殉教者みたいになって。いつまでたってもコルトレーンを神格化するひとがいる原因はそこにある。音楽のなかからそれが読み取れるなら、コルトレーンにとってはそれがいちばん幸せなんだけど、音楽の構造分析的には読み取れないんだよね。聴いた感覚ではわかるんだけど。そりゃ、1曲1時間もやったら誰でも飛ぶよ(笑)。
大谷:だからリキッドで立って聴くのがいいんだよ(笑)。
菊地:ジャズ・クラブで座って1時間聴いていたらたまったもんじゃないよね。産経ホールはやばかったでしょう。あの知的な相倉先生だとか、あらゆる知将たちがコルトレーンが聖人だって物語には乗っているからね。悪いというわけじゃなくて、ヒップなひともいたと思うの。コルトレーンの最後は若気の至りで、〈ブルー・ノート〉時代がいちばんよかったよなってひともいっぱいいたと思う。いまそうじゃなくて、円盤が迎えに来なかった殉教者としてのコルトレーンがクラバーにもてはやされているのが現状っていう。
大谷:もてはやされるといいな。
菊地:ははは(笑)。
大谷:まだ予断は許されない。この一瞬で消え去るかもよ。
菊地:でもみんなコルトレーンは聴かないんだよ。甥っ子であるフライング・ロータスを聴く。コルトレーンの血脈がラヴィまで含めていまのクラブ・シーンに繋がっているけど、それは全部ぶっ飛ぶ音楽だから、そういう意味で先駆だよね。
大谷:フラローのおかげでロスまでは来てるから、宇宙まではあと一歩。カルフォルニアには(UFOが)よく来ているからね(笑)。
対談:菊地成孔、大谷能生(2016年7月22日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー
- interview with Rafael Toral - いま、美しさを取り戻すとき ——ラファエル・トラル、来日直前インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE
