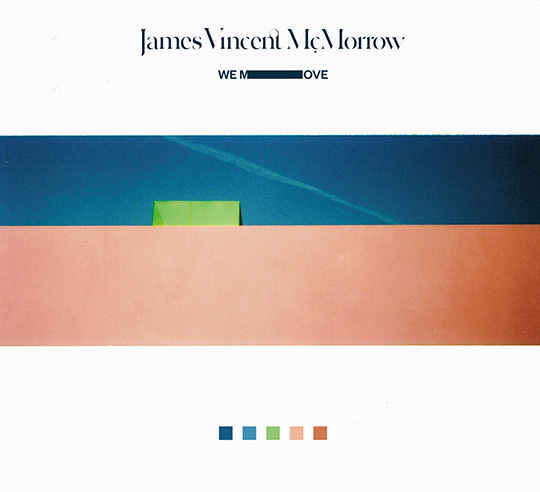音楽でメッセージを伝える方法。
そのひとつは言うまでもなく、リリック。言葉。言いたいこと、伝えたいこと。言葉は、同じ言語(ラング)世界内において不特定多数の相手に意味を運び、時に意味そのものとも同化して扱われる、高効率の意味伝達手段である。
もうひとつは、リリック以外の構成素たる「音」。それは言葉と違って狭義の記号性を保持しがたいがゆえ、それ自体でメッセージ作用を孕むことは一般的に難しいという前提で議論とされることが多い。(「音そのものには政治性は無い」といったように)しかし我々はこれまでも、例えばジェリー・リー・ルイスがピアノを叩きつけるときに生まれる三連符や、ジョニー・ラモーンが性急なダウンストロークで鳴らすパワーコード、または空間を埋め尽くすように咆哮するジョン・コルトレーンによるテナーサックスの音、そういった音々に、尋常ならざる意味やメッセージを読み取ろうとしてきた。
そもそも西洋クラシック音楽史上においても、ソナタ形式が洗練を重ねながらどのような「意味」を付与されてきたのかといったことを読み解く行為は、伝統的な音楽教養主義の中核を形作るものでもあったし、短調は「悲しげ」、長調は「楽しげ」だとする、現代では広く共有される認識も、長い歴史の中で徐々に獲得されていった「印象」であり「意味」である。今日共有される「音の意味」は、度重なる創作と鑑賞・批評の相互干渉がもたらした混合物であるのだ。(もちろん文化相対主義的視点からは、上記のようなクラシック音楽における記号論・意味論が西欧社会ローカルでの議論であり、世界では様々な音が様々なコミュニティで様々に意味付与されているということも強調しておきたい)
さて、あらためて考えてみるに、そういった音そのものと意味の対応関係の醸成過程というのは、実はまさに「言葉」が辿った道筋と近似であるということが分かるだろう。いうまでもなく、言葉ははじめ「音」であり、他の音との峻別や使用される場面、文脈、あるいは話者は誰か、そういった様々な場面で段階的鍛錬を経ることで「意味」を獲得していったのだった。
そう、歴史性ということに着眼して記号論的視点を敷衍するならば、決して「言葉」と「音」というものは隔絶した概念ではなく、むしろ近似のものであると言えるだろう。だから、「音」だけでメッセージを伝えることだって可能なはずである。かつて、リンク・レイによるロックンロール名曲「ランブル」を、青少年の非行を励行するおそれがあるとして、インスト曲にも関わらず放送禁止指定した人たちは、おそらくそのことを十分すぎるほどよく知っていたのだろう。
セラミック・ドッグはマーク・リーボウが近年最も力を入れて取り組んでいるバンドである。(あくまでプロジェクトではなく「バンド」であると彼は主張する)。キャリア初期からジャズとロックの垣根を取り壊すギター・プレイを披露し、「偽キューバ人たち」なる、アルセニオ・ロドリゲスらキューバ音楽のレジェンドへのリスペクトを捧げつつもバンド名通りどこかいかがわしい(しかしすごくフィジカルな)グループを組んだり、エルヴィス・コステロやトム・ウェイツといったロックの巨人たちのセッションで、あまりに記名性の高い独特の演奏を提供したりと、様々なフィールドでカメレオン的と呼ぶべき活動してきた彼が、このセラミック・ドッグにおいては、かなり直裁的に、というか素直にロック・ミュージックへの志向を見せていた。自身の激烈なエレクトリック・ギター・プレイに加え、腕っこきのチェス・スミス(ドラムス)、シャザード・スマイリー(ベース)というメンバーを従え、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスやブルー・チアー、遠藤賢司バンドといった燦然と輝く轟音ロック・トリオを彷彿とさせるその演奏は、前作『ユア・ターン』でひとつの頂点を極めていたとも言えるだろう。
しかしこの3作目『ホワイ・アー・ユー・スティル・ヒア』において彼らは、そうしたパワー・ロック・トリオ的表現から、より汎世界音楽的な視点を持ち込もうとしている。それは、これまでのマーク・リーボウの活動を知るものとしては当然の旋回に思えるかもしれないが、そうした音楽的偏移とともに、バンド発足当初より強く発散してきた太い基軸としての「怒り」を、トランプ政権下で進行しつつある移民政策の歪みなど様々な不条理へ反抗的に咆哮することで、一層具体化・先鋭化させることとなった。様々に織り込まれたレベル・ミュージックから得られる「意味」をガソリンとして。
ドラムスのキックが騒々しく八分音を刻み、マークのけたたましいボーカルが駆け巡る“Personal Nancy”は、その曲名の通り、シド・ヴィシャスによるあの支離滅裂なソロ・アルバムにあったパンクとしか言いようのない混沌を思わせるし、続く“Pennsylvania 6 6666”ではキューバン・ミュージックのストリートな肌触りを借用しながら、ドクター・ジョンによる、あの恐ろしげなファースト・アルバム『グリ・グリ』のブードゥー的世界を蘇らせる。「Agnes」では、まるであの『ナゲッツ』や『ペブルス』シリーズに収録されていても違和感が無さそうなアングリー・ヤングマン風情のガレージ・パンクと、プライマス的(懐かしい……)ミクスチャーロックを強引に接合する。
“Oral Sidney With A U”はインストゥルメンタルだが、かつてマーク自身が在籍したラウンジ・リザーズを思わせるアナーキックで脱臼的ジャズが奏でられ、しかも途中にはマザーズ・オブ・インヴェンションの「ハングリー・フリークス・ダディー」のフレーズが挿入されるのだった。ビリンバウのヒプノティックな響きを交えたジャム“YRU Still Here”では、初期アシュ・ラ・テンペルがごとき不穏さが覆い、一見穏やかめかしたマークのボーカルがかえって静かな怒りを抑えつけているようで、異様な緊張感が漲る。
“Muslim Jewish Resistance”では、その曲名通り各宗教コミュニティを鼓舞し、彼らを不当に扱うものへ抵抗せよ! と呼びかける。ポストパンク的シリアスを湛えた演奏に導かれながら、フリーなサックスが咆哮する中、マークが初期ビースティー・ボーイズやパブリック・エネミーが如き極めてテンションの高いラップを繰り出していく。意味深長なタイトルを持った“Shut That Kid Up”では、90年台初頭のグランジ的熱狂を思わせる3人のプレイが圧巻。ここでいう“That Kid”とは……? それは、いうまでもなくトランプ大統領のことを指しているのだろうが、インスト曲にこの曲名を持ってくる辺り、却って並々ならぬバンドの憤怒を知らしめているようだ。
そして、アルバム中もっとも直接的で反抗的歌詞をもった“Fuck La Migra”。“Migra”とは、米国移民税関捜査局の俗称で、現在の移民行政を推進する組織と、その体制、そしてその体制を支持する価値観を徹底的に攻撃する。
「俺の兄弟に指一本触れたら、お前はまた震え上がることになるだろう/トラブルは起こしたくないし仕事もある、俺は穏やかな男さ/だけどさらに言うならば、共和党員が一人減ることになるだろう」という剣呑なリリックが載るのは、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンを思わせる演奏で、しかもコーラス部では80年代UKのOiパンクが如きシンガロング・スタイルで「くたばれミグラ!」を連呼する。続く“Orthodoxy”は「正統性」(ギリシャ正教、ユダヤ教正統も意味する)という曲名にも関わらず、シタールが導く南アジア的世界を表出させ、「正統」を撹乱する。
“Freak Freak Freak On The Peripherique”はESGやリキッド・リキッドといった80年代ニューヨークのノーウェイブ~ポストパンク・アクトを思わせる性急且つステディーなビートがストリート的焦燥を騒がしく掻き立てる。そしてクローザー曲“Rawhide”は、映画『ブルース・ブラザース』で南部白人の保守性の象徴としてコミカルに使われていた有名な同名曲をギターリックで喚起させつつも、クラフトワーク的に変質した声色が駆け巡りながらブロークンなパンク・ジャズを奏で、まるでレジデンツか!? というべき奇異世界を作り出す。
数多の音楽要素がゴツゴツと荒っぽく閉じ込めれた本作、なによりもマーク・リーボウ自身の憤怒と焦燥が聴くものの胸に強く蟠る。それは、ここに収められた曲が、リリックもさることながら、なんといっても音そのものに「反抗性」を色濃く付与された音楽遺産からの引用に溢れているということに拠るところが大きいだろう。これまで各曲を聴きながら述べてきたとおり、ポピュラー音楽史上に数々現れた「レベル・ミュージック」の断片を、記号論・意味論的に用い、極めてトピカルなリリックとの融合物として、それらに付与されてきた反抗性を鮮やかな手際で蘇生してみせる。その意味でこれは、幅広い含蓄を楽しむべき一種のレベル・ミュージック賛歌集であるとも言えるかもしれない。
怒るべきことに対して、直情的なリリックで強く怒りを表明しつつも、音楽表現の手法として記号論的観点をも用いるというしたたかで強靭な知性を持つアーティスト。鳴らされている音楽は激烈だけれど、思慮と分別も内蔵している。マーク・リーボウという人は、新たな時代における「怒り」のイデオローグとして、最前線にいるのかもしれない。実にカッコいいではないか。