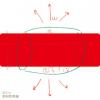MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Shuichi Mabe - さらばメタ、ようこそ王道
 集団行動 - 充分未来 CONNECTONE / ビクターエンタテインメント |
相対性理論――この文字列を目にしセックスの理論と勘違いする者はよもやおるまいが、しかしノーベル賞を授かったかの名高き物理学者よりも、2006年に結成されたかの軽妙なるポップ・バンドのほうを思い浮かべる者はそれなりに多くいるだろう。さほど彼らが00年代末期に残した衝撃は大きかったわけだが、それは彼らが意識的に「ポストYouTube」や「ソフトウェア」といった惹句を掲げ、「メタ」や「フラット」といった言葉が盛んに飛び交っていた同時代の潮流とリンクする活動をコンセプチュアルに展開していたこととも無縁ではあるまい。
その相対性理論を脱退した真部脩一が、同じく相対性理論の一員だったドラマーの西浦謙助と、新たにオーディションで出会ったヴォーカリスト・齋藤里菜とともに起ち上げたプロジェクトが集団行動である。昨年1月より活動を開始し、6月にはファースト・アルバム『集団行動』を発表、年が明けてこの2月には早くもセカンド・アルバム『充分未来』をリリースしている。
この集団行動なるいささかかぶいたバンド名を耳にすると、くだんの相対の性理論もとい相対性の理論と同じく、その背後には入念に練られたコンセプトが横たわっているのではないかと勘繰ってしまうが、どうやら今回はそういうわけではないらしい。むしろ現在の真部はわかりやすさをこそ索めているという。「どこかで聴いたことのある感じってポップスの条件だと思うんです」――そう語る彼は、「メタ」や「フラット」といったタームによって彩られた今世紀初頭の文化的喧噪を、それこそ相対化しようと目論んでいるのかもしれない。いままっすぐにポップ・ミュージックの王道を歩まんと試みる彼に、その心境の変化やバンドの成り立ち、新作の勘所について伺った。

「こんなのバンドじゃねえ」と言っている感じです。「ただの集団行動だろ」っていう(笑)。
■まず何よりバンド名が印象的ですが、これには何かコンセプトがあるのでしょうか?
真部脩一(以下、真部):いや、今回はコンセプトは皆無ですね。とにかく「バンドをやろう」というところから始まっています。相対性理論のときは「曲ができたから人を集めよう」という形でスタートしたんですが、集団行動は「バンドを組むために曲を書こう」というところから始まっているグループなんですよ。
■相対性理論脱退後は、ハナエさんやタルトタタンさんをプロデュースされたりVampilliaに加入されたりしていましたが、いままたご自身のバンドをやろうと思ったのはなぜですか?
真部:心境の変化というか、フリーランスになってプロデュースという作業に関わらせてもらうようになって、それはけっこう自分に向いているし得意だと思ったんですけど、でもそれを続けていくうちに、僕はひとりのリスナーとしてはプレイヤーの音楽が好きというか、構築された音楽よりも演奏された音楽のほうが好きだということに気づいたんです。小さい頃からジャズが好きだったというのもあって、このまま音楽にプレイヤーとして参入できなくなるのは心残りだなと。
■相対性理論のときはあまりそういう感覚はなかったのでしょうか?
真部:相対性理論に関しては、主体性を持って取り組むようなバンドではなくて、むしろそういうものを排除していこうというか、そう見えないようにしていこうというバンドだったので、主体的に音楽に関わるきっかけがあるとしたらいまかなと思ったんですよね(笑)。
■相対性理論はやはり時代性みたいなものを意識していたのでしょうか?
真部:相対性理論ってウェブを利用して仕掛けたバンドだと思われているんですけど、べつにそんなことはなくて、たんにウェブで扱われやすかったバンドだと思うんですよね。「ポストYouTube時代のポップ・マエストロ」と銘打っていたんですが、当時はいろいろなコンテンツがフラットになっていって、事件性やメッセージ性のようなものが暑苦しく感じられるようになっていって、僕もそういう暑苦しいものが好きではなかったので、自分の好みと時代性がちょうど合ったところでやっていたバンドなんです。だからけっこう意識的に当事者性を排除していた部分があって。
■当事者性というと?
真部:当時「相対性理論はソフトウェアである」と謳っていたんですけど、要するに相対性理論は「発信者」ではなくて「どこかの第三者が作り上げたソフト」である、というふうに打ち出していたんですよね。
■初音ミクのような感じですか?
真部:そうですね。ただそうなるとけっこう寿命が短かったというか。結局そのあとにSNSが出てきて、タイムラインという概念が登場して、また事件性みたいなものがフィーチャーされるようになってきた。それでちょっとバカバカしくなったというか、自分の得意としていたメタな部分に少し飽きちゃったんです。だったらひとりのプレイヤーとして一生懸命音楽を作りたいと思ったんですね。
■なるほど。でもやっぱり「集団行動」というネーミングはだいぶコンセプチュアルですよ。
真部:そう見えますよね。でもたんに「バンド」という概念を目指しているだけなんです(笑)。じつはまだぜんぜんバンド的じゃないんですよ。バンドマンが「こんなのロックじゃねえ」って言うのと同じように、「こんなのバンドじゃねえ」と言っている感じです。「ただの集団行動だろ」っていう(笑)。まだバンドになっていない、ということですね。
■メンバーもまだぜんぜん足りていないというようなことを仰っていましたよね。
真部:始まった時点でリズム・セクションすら揃っていなかったという(笑)。ギター、ドラム、ヴォーカルの3人でスタートしたので、ほとんどのパートを僕が演奏せざるをえない状態でした。だからこそバンドであることに意識的になったというか。
■ベースは真部さんが弾いているのですか?
真部:前作まではそうですね。ファースト・アルバムはギター、ベース、キーボードを僕がやって、そこにドラムとヴォーカルが加わる形でした。ただ今回のセカンド・アルバムではサポート・メンバーに入ってもらっているんです。そうすると自然にバンド感が出てくるんですよね(笑)。ゴダールの『ワン・プラス・ワン』という映画の、ぜんぜんレコーディングがうまくいかなくて、1週間くらい試行錯誤して、ひとりパーカショニストを呼んでみたらなんかうまくいっちゃった、みたいな感じに近くて(笑)。やっぱりロック・バンドはちょっと他力本願だなと(笑)。いまはその状況を楽しんでいますね。

誰にでもできるところまで削ぎ落とされたもののなかに、その人じゃないと成り立たない要素がふと浮き上がってくる音楽がすごく好きなんですよ。
■真部さんのリリックは、情景を想起させたり物語を紡いだりすることよりも、韻の踏み方だったり子音と母音の組み合わせだったり、音としての効果のほうに重きを置いているような印象を受けました。
真部:そう言っていただけて本当にありがたいんですが、自分としてはすごく薄味を目指しながらも、結局はドラマ性や意味性みたいなものを捨てられずにいたという感じなんです。以前東浩紀さんにお会いしたときに「君はPerfumeみたいな意味性のないものは書けないのか」と言われて(笑)。そこは自分の未熟な部分でもあって。言葉って並べてしまった時点でどうしてもドラマや意味が発生しちゃうんで、その扱い方に長けていなかった。それにそもそも、単純にドラマティックなものが好きなんですよね。なのでドラマ性や意味性を保ったなかでなるべく軽く軽く洒脱に、ということをやってきたんですが、最近はそれってちょっとわかりにくいのかなと思い始めていて。いまは、ベイ・シティ・ローラーズのようなもっとわかりやすいものを求めていますね。たとえばマドンナのファーストは、感情移入の懐が広くて、言葉もすごく平易なのに奥行があるんですよ。そういうものに挑戦したいと思っていて。
■いわゆる「ナンセンス」みたいなものを目指しているのかなとも思ったのですが。
真部:僕は私的なことを歌詞にしているわけではないので、どうしてもストーリーテリングが平坦になってしまう。それを異化するための工夫として、ナンセンスが必要だったんです。でも、いまとなってはちょっと回りくどいかなと。今作は単純に、作詞家としてもう少し自分を軽量化する必要があるんじゃないかと思っていたんですよね。
■ちなみに水曜日のカンパネラについてはどう見ていますか?
真部:ケンモチ(ヒデフミ)さんとは仲が良いんですよ。相対性理論を抜けて2、3年した頃かな、Vampilliaのメンバーとして知り合ったんですよね。(水カンの)“一休さん”という曲が出たときに、ケンモチさんから「真部くんさあ!」って電話がかかってきて(笑)。「YouTubeのコメント欄で相対性理論のパクリだってすごい叩かれてるんだけど、聴いてみたらたしかにそう思わせる部分あったわ!」って(笑)。
■そう言われて実際に似ている部分はあると思いました?
真部:「そうですかねえ?」という感じです(笑)。そもそも僕だったらコムアイちゃんみたいなポップ・アイコンをきちんとコントロールできないと思いますし。ただ楽曲のクオリティとか、ケンモチさんはひとりの職人としてすごく達者な方なので、素直にリスペクトしていますね。
取材・文:小林拓音(2018年2月26日)
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE