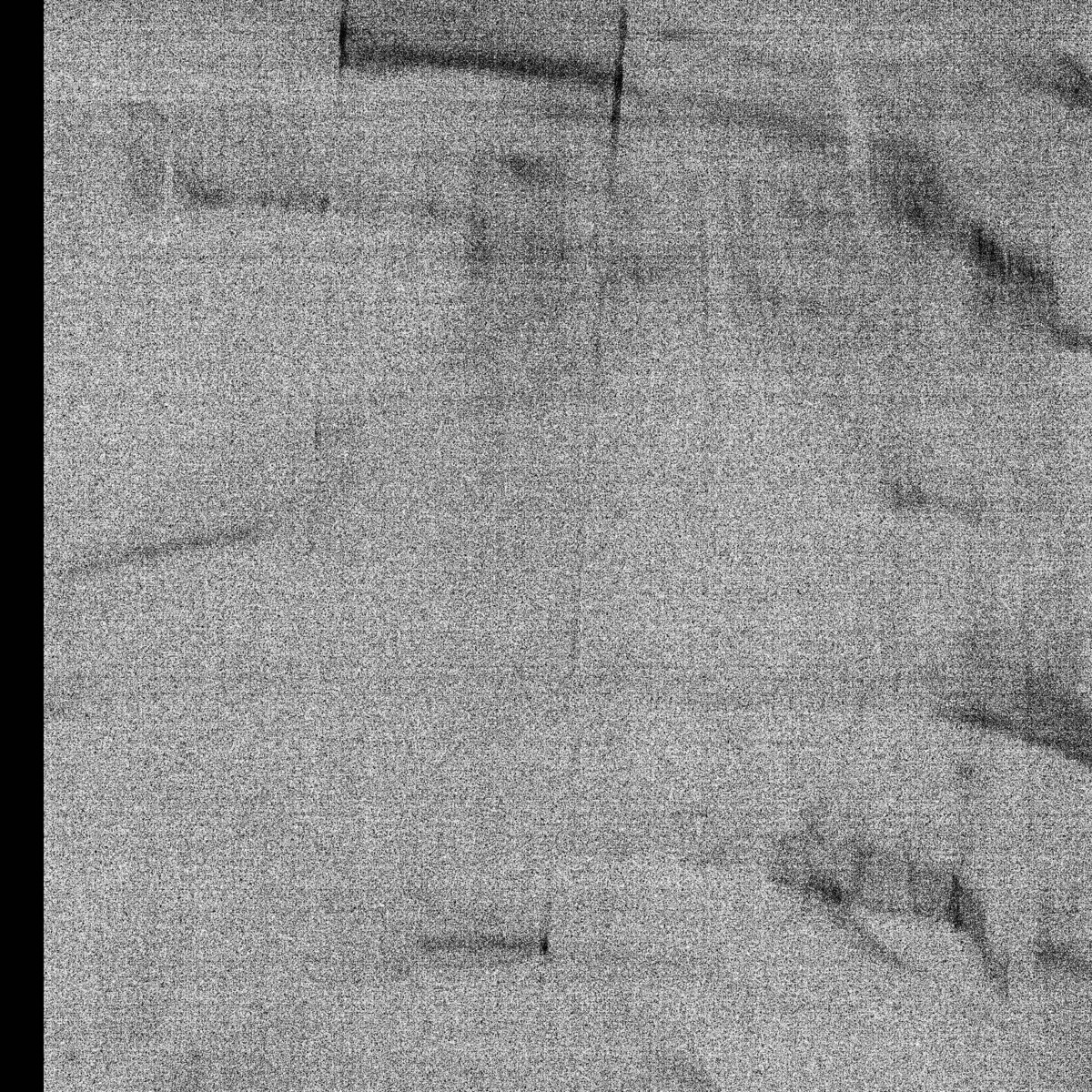MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Natalie Beridze- Of Which One Knows

90年代に野田努が「トランスは享楽的で、テクノは快楽的」と評した時、なるほどな~と思った。それは当たってるな~と。享楽的な音楽も快楽的な音楽もどっちも好きだった僕は、そして、もう少しそのことについて考えた。享楽的な音楽はその瞬間だけが面白く、長持ちしない音楽で、快楽的な音楽は繰り返し何度も聴ける音楽。だけど、初めから快楽的なものしか選ばないと決めてかかるとそれも堅苦しい。10年か20年ぐらい経ってから享楽的な音楽をもう一度聴くと独特の身体性がよみがえり、それはそれで別種の面白さがあるとも。要はどれだけ夢中になったかということで、その経験があれば享楽的でも快楽的でもどっちでもいいかなというのが最終的な結論である。快楽的だと感じた音楽にも時間の経過の中でますます強度を増していくものもあれば価値が薄れていくものもある。逆に享楽的でも快楽的でもなく、ただ自分がその良さを分かりたくて何度でもトライする音楽も「課題」として抱えていると、その音楽が理解できた時の喜びはまた別次元のものだし、わかったつもりでいた音楽がまったく違うものに聞こえた瞬間はさらにたまらないものがある。音楽を聴いていて、いつも思うことは、だから、時間がいくらあっても足りないということ。地球をしばらく止めてくれ、僕はゆっくり音楽を聴きたい(寺谷修司のパクリでした)。
デヴィッド・ムーアによるビング&ルース名義『Tomorrow Was The Golden Age』を初めて聴いた時、これはモダン・クラシカルを享楽的なモードで聴かせる試みだと僕は思った。それなりに話題になった作品だけれど、僕はそれこそ1~2回は面白いけれど、何度もは聴かないなと。あれから8年が経っているので、久しぶりに聴いてみたところ、記憶と同じ音楽がそこにはあり、これを1時間近くも聴き続けるのは面倒くさいなという身体性もぶり返した。2003年にトーマス・ブリンクマンのレーベルからTba名義でデビューしたナタリー・ベリツェも本名だけを使い始めた頃からモダン・クラシカルに作風を寄せ始め、多種多様なアプローチを試みてきた人なのでどことなく捉えどころがなかったのだけれど、〈ルーム40〉からは初となる『Of Which One Knows』で、実に快楽的なモードと絡ませることとなった。モダン・クラシカルはインダストリアル・ミュージックが変成したものだという認識が僕にはあるので、そういう意味ではビング&ルースもナタリー・ベルツェも苦行モードから大いなる価値観の転換を図っているという意味で同じ方向性を示すものであり、ベリツェだけに快楽性を感じるというのはどういうことなのか、にわかには自分でもよくわからない。
ベリツェにとって12作目となる『Of Which One Knows』は、実際には2007~12年にかけて録音されていたトラックにレーベル・ボスのローレンス・イングリッシュがポスト・プロダクションを加えたものである。没トラックだったということなのだろうか。それとも彼女のメイン・レーベルであるグトルン・グートの〈モニカ・エンタープライジズ〉とは価値観が合わなかった曲を集めたということなのだろうか。昨年リリースされた『Mapping Debris』には似たようなタイプの曲もあったので、それを聴いたイングリッシュが独自に方向性をオファーしたということも考えられる。オープニングがT・S・エリオットの詩をつぶやくように歌う“Ash Wednesday”。オーケストラを丸ごとスクリュードさせたような曲調は、続く“Sio”にも引き継がれ、そのままスモーカーズ・デライトなモダン・クラシカルという異形のサウンドスケープが一貫して最後まで響き渡る。これまでのアルバムのように急に目先を変えるような曲が差し挟まることはなく、“Forensic Of The Thread”で少しばかり棘のある雰囲気を醸し出す以外、全体としては延々と快楽的なヴィジョンがリヴァーブの海を漂い続ける。甘ったるくもあり、虚心になったり、感傷的になるなど、表現にグラデーションが備わっていてとても素敵なアルバムである。
どうやらこのアルバムに描かれたイメージは彼女の幼少期の記憶と結びついているらしく、このところアレキサンドラ・スペンスやマドレーヌ・ココラスなど個人の記憶とアンビエント・ミュージックを結びつけたアルバムを多発する〈ルーム40〉としては同傾向のプレゼンテーションになっているのではないかと(意識的かどうかはわからない)。そういった等身大のサンプリングなどからアンビエント・ミュージックを構築した最初の例は、僕は、コージー・ファニ・トゥッティがスロッビン・グリッスル『D.o.A. 』に寄せた“Hometime(下校時間)”が最初だったのではないかと思うのだけれど、どうだろう? ジャン~クロード・エロワやエリアル・カルマ、あるいはブライアン・イーノやポーリン・オリヴェロスが壮大なテーマに取りんでいた一方で、パンク以降のDIY精神がアンビエント・ミュージックに反映された例として“Hometime”は稀有な例であり、意外とその系譜は途切れていたのではないかと。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE