MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > 赤痢- 赤痢
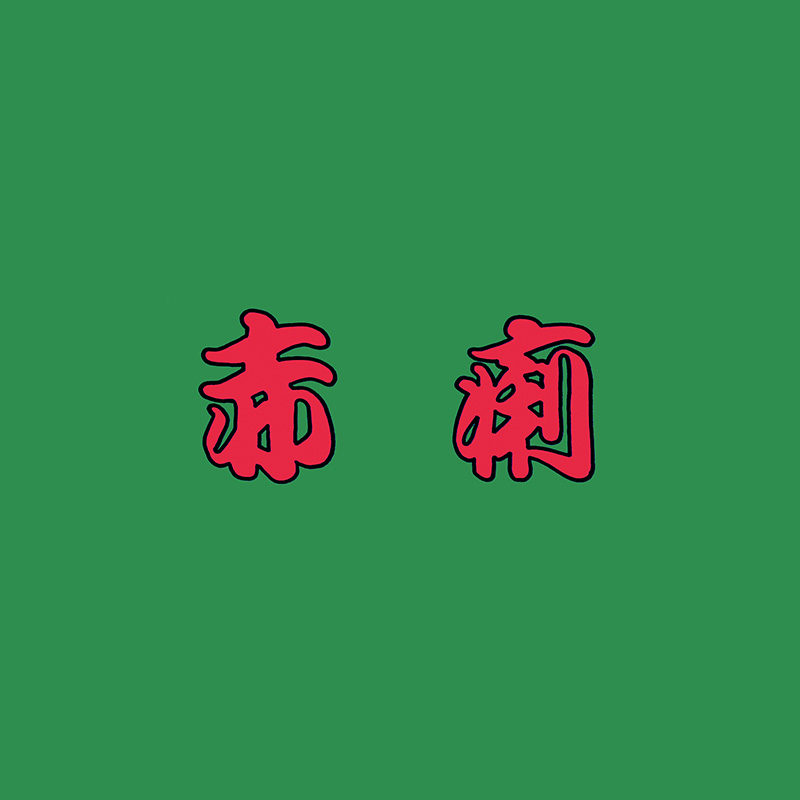


文:水越真紀
久しぶりに赤痢を聴いて思うのは、なんと楽しいバンドなのかということだ。ドラムとベースの、乗るものを決してうらぎらないおもったい確かさの上で好きなように不機嫌になり、照れ、言葉を駆使し、頭を痺れさせる赤痢の楽しさったらない。赤痢が何度も何度も発売され続けるのは、このリズム隊の心地よさと歌詞の古びなさのためだろう。
ユーモアと切なさに満ちた歌詞はほとんど1分から2分という短い一曲でも同じフレーズの繰り返しが多い。つまり言葉を尽くして、言葉を駆使してストーリーや心情を語ったり、描写をするのではなく、ときには、あるいは多くは、メロディやサウンドに呼び覚まされたたとえば「死体こぼれ死体こぼれ」(“ベリー・グウ”)のような唐突な、「音」優先のフレーズは、それでも何かのイメージを映しながら、身体と心を揺さぶる。
「うまいよこれほら食べてみて 愛してやまない理由がある 笑えない口で、はい、どーぞ 生きてりゃなんでも欲しくなる サバ、サバ、サバビアーン」(“サバビアン”)、「ひとつ食べたらばら色 ふたつ食べたらばば色 希望なんてないんだって チョッコレートブルース 欲望だけがあるんだって チョッコレートブルース」(“チョコレートブルース”)などが日常の些細なできごとのつぶやきなら、「にぎる万札 もらう給料 おきゅうりよ カツカツの生活にボーナスもらって夢見たことはお金返してすぐまた借りて まーた借りて」(“かつかつROCK”)も「ラリって吸ってラリって吸う もいちど教えてもいちど教えて はあほうらナッシングを抱く」(“デスマッチ”)、「頭をぶらぶら手足をぶら 体をスウィング 寄せては返すあなたの波 信じこむバカ」(“エンドレス”)もそうで、「ゆるんだネジをぐるぐる回して いやな時代ももうすぐ終わる」(“青春”)といった年齢に似合わないような、いや10代だからこそのニヒリズムも青春の日常のひとこまだ。と30年来のデフレ経済を生きてきた現代人は思うだろう。しかしこれが作られたのはデフレ世代が「夢見る」バブル経済期のことだと思い出せば、感じることは変わってくるのではないか。
改めて「赤痢」というバンド名さえ新鮮に思える。たとえば赤痢が結成された時代とはスターリンがいて、アレルギーがいた日本だったと同時に、というより、ロンドンにザ・スリッツがいて、ベルリンにマラリア!がいた世界だった。「赤痢」が “夢見るオマンコ” を歌ってなんの不思議があったろうか。むしろ自然な流れではないか、ということが体験としてわかるコロナ禍後の世界だ。
振り返られるときは赤痢結成前、つまり40年以上前ということになるが1981年辺り。西ベルリンのポスト・パンク・シーンではマラリア!という女性だけのポスト・パンク・バンドが活動していた。電子楽器を使ったサウンドは、初期衝動で発する新人バンドとは違っても、ふたつのバンドの野太く気だるい女性ヴォーカルを重ねてみたくなる。マラリアと赤痢──感染症の名前をバンド名につけることの不謹慎さと禍々しさ、それから細菌やウィルスという、我と世界の境界線で生き死にに関わる生命体、感染者への差別的視線などの数多くのイメージが、コロナ・パンデミックを過ごした直後の私たちには喚起される。そのマラリア!の少し前、ロンドン・パンク・シーンで女性性のモチーフを使い尽くしたバンド、ザ・スリッツも同時に思い出している。もちろん、赤痢のメンバーが高校時代にリリースしたデビュー・シングルに収録された “夢見るオマンコ” からのつながりでだ。
かつてなら、その存在自体が悲劇性を帯びた憂い顔の女性歌手に、性的に際どい歌詞を歌わせて、そこに男にとっての夢のような寛容さや包容力を想定し、〈菩薩〉と崇めるやり方があった。ポスト・パンクの80年前後以降の、日本もまだ含まれていたはずだった「世界の変化」は、女性表現者が社会の男性性による有言無言有償無償の要請からいかに離れて、コントロールの主体を奪うことだった(たとえば1980年の山口百恵の結婚への、当時の同世代の女たちの失望感は、阿木耀子との共作で山口百恵がそれを成しうるかと思った矢先の、なんだか元の木阿弥のような決断に対してだった)。
80年代といえばまだ「菩薩」的女性像や「女は子宮で考える」といった非科学的なファンタジーを男性中心のメディアが無邪気に広めていた頃で、京都のバンド赤痢が “夢見るオマンコ” をリリースした翌年、やはり京都の女子短大助教授だった上野千鶴子が『女遊び』(学陽書房)の巻頭に「おまんこがいっぱい」というエッセイを収録したことには、いまとなっては時代の曲がり角が見える気もする。が、当時実際には高校生バンドのデビュー・シングルとフェミニズムの第一人者となる学者のエッセイは無関係に、対象も意味も少し違うところに放たれた。
20世紀の女性解放運動の後、ウーマンリブ(フェミニズム)が主流男性社会から疎んじられ、女性たち自身にさえ距離を取られてしばらく経った頃、上野千鶴子が『女遊び』の中でまだ衝撃を持って取り上げていたAV女優黒木香の脇毛を見せた演技など、露悪的で挑発的で爆発的な「女自身による」と限りなく思える程度の、女性身体の相対化が試みられていた。女の身体または身体性を売るとすれば、それはあくまでも女性自身であり、その表現が誰の期待に応えていなくても、というか、応えていなければいないほど、それは観客ともなる女性自身も含めた社会の要請に応えているということにもなった。これもひとつのマーケティングだとしても、そのことをもう現代の経済システムでは逃れられなくても、ひとりの人生を超えて、ずいぶんマシなことだと思う。しかしその試みは歴史を振り返れば、それほどうまく進まなかったように思う。特に日本社会での女性性や女性身体の表層にまつわる問題は、ただ「表現の自由」といったリバタリアニズムに乗っ取られているように思えるからだ。
ところで私が赤痢を知ったのはファースト・アルバム『私を赤痢に連れてって』がリリースされた後だった(当アルバムは当時だけで5000枚以上の大ヒットになったという)。まず、あっけにとられたのは、アルバム・タイトルの大胆さとデザインのかわいらしさだった。これがいかに “でたらめさ感” (野蛮さ、大胆さ、不敵さといってもいい)を醸し出していたかについては、40年後のいまでは伝わりにくいものになっているかもしれない。言わずと知れた87年公開の日本映画『私をスキーに連れてって』のあまりにもシンプルなもじりを、公開数ヶ月後というこの速度でここまでベタにペーストした、そのあっけらかんとしたセンスにはいきなりクラクラした。当該映画はまさにバブル・カルチャー最盛期の、“映画” というよりCMに近く、すでにマーケティング重視で楽曲を作っていると公言していた松任谷由実による主題歌・挿入歌を含めて、完全なる広告代理店製のトレンディ・デート・ムーヴィーだった。その後、広告代理店文化がサブカルチャーの行き場をせっせと掠め取り、「作る部分」ではなく「売る部分」だけを国策化して中間マージン・ビジネスを確立してゆくハシリとなった。
赤痢はそういう作品(言葉)を、逆張りや奇を衒ったふうでもなく、(おしゃれでもパンクでもない)素朴で可愛らしいデザインとともに世に出した。まるで本家の、スマートでポジティヴで快楽的で資本主義的な、大人や男といったすでにより権力を持っている人たちが引いた社会デザインそのものを、上空から見下ろすような視点が最高にサイコーだ。しかも、彼女たちが見下ろしていたのはそれだけではなくて、女性性や女性の身体性が当事者から切り離されて金儲けシステムの棚に載せられてしまうことと、同じシステムが最もコストパフォーマンスがいいと判断した若さや姿形、軽妙さやコミュニケーション手法が同じようにジャッジされ、「プロデュース」されるという社会システム上の同じ問題をも眼下の視野に入れていたことは、これを40年後のいまに持ってきてもなお刺激的だ。
ともかく、高校生の赤痢のデビュー・シングルはそういう時代にリリースされた。「夢見るオマンコ」という単語の組み合わせのなんと愛らしいことか。ティーンエイジャーの性や性行為への距離感の、リアリティのある幸福さが現れている。しかし親しみやすくポップなメロディに乗せられた実際のこの歌の歌詞はさらにリアルだ。「恋した彼氏がおもしろくないから 一発やらして 一発孕んで 一発産み落とす あんなに夢見たオマンコも どうしてこんなにつまらない」「恋した彼氏があきらめられないから 一発おとして 一緒にホテルで 連発やりまくる」(“夢見るオマンコ”)と、これは恋するときの幸福をよく描いている。この「夢見る(オマンコ=性交)」と男たちの「菩薩女」へのファンタジーは同じように上野千鶴子が先のエッセイで指摘した「中産階級の子女の性的無知は、絵に描いたような近代のブルジョア性道徳の体現である」と指摘してみる。けれども同時に当時の私だって十分にその体現者だった。そりゃあもう、どんな強いこと言っても、その辺についてはブルジョアな道徳の体現者以外のものではなかった。思い出したのは高校生の頃に読んだ女性運動の本だ。「手鏡で自分の性器を見る」ことについて読み、「なるほど、“今度” やってみよう」と、私は本を閉じたことがあった。赤痢がデビューしたのは、じっさいそんな時代のすぐ先だった。私に何をえらそうなことが言えよう。妹たちのような年齢の彼女たちに、私は2、3枚の鱗を目から剥がしてもらったわけだった。
そのことが楽しい。いつだってそのドラムは裏切らない。私の体のあちこちを硬くしている、なんとまあ半世紀かけても落ちていない鱗を何度もはがし、それでいて残酷に床に叩き落としたりしないという意味でだ。轟くビートは私の重くなっていく足を、また跳ばせてくれる。
(8月10日記す)
水越真紀、清家咲乃
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE

