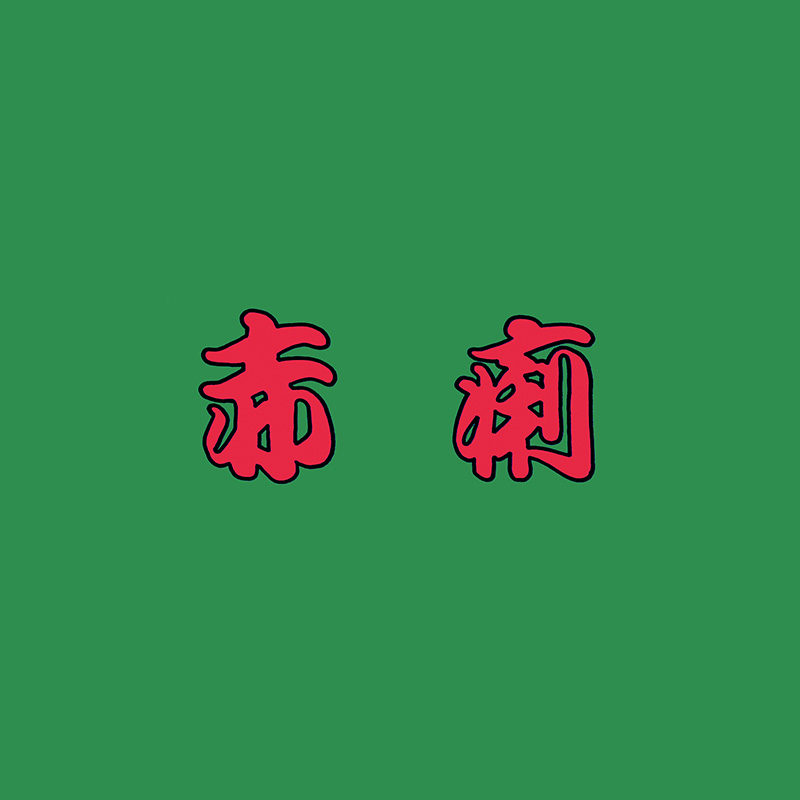MOST READ
- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース
- KMRU - Kin | カマル
- Deadletter - Existence is Bliss | デッドレター
- Squarepusher ──スクエアプッシャーのニュー・アルバムがリリース
- Free Soul × P-VINE ──コンピレーション・シリーズ「Free Soul」とPヴァイン創立50周年を記念したコラボレーション企画、全50種の新作Tシャツ
- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯
- Loraine James ──ロレイン・ジェイムズがニュー・アルバムをリリース
- Cardinals - Masquerade | カーディナルズ
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Laraaji × Oneohtrix Point Never ──ララージがワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの来日公演に出演
- Columns 内田裕也さんへ──その功績と悲劇と
- xiexie - zzz | シエシエ
- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her | アマンダ・ホワイティング
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Columns The TIMERS『35周年祝賀記念品』に寄せて
- Cindytalk - Sunset and Forever | シンディトーク
Home > Reviews > Album Reviews > 赤痢- 赤痢
文:清家咲乃
「こんなのって、つまらない」と感じながら日々を過ごしている人は、一体どれくらいいるのだろう。きっとほとんどが心の中でそう唱えながら生きているんじゃないだろうか。充実して見える人たちも、つまらない状態に陥らないために自転車操業的に輝きを補充してるんじゃあないか。反対に、完全な諦めの境地に浸かるのもまた難しい。あと一歩で悟りを開けるところまで来てしまっていることになるし。そう考えれば、つまらなさの打開へ至る破壊的衝動というものは何時の誰にでもリンク可能である。80年代に生まれていなくても、女性でなくても、それはとくに関係ない。
赤痢は80年代前半から90年代中盤にかけて活動していたパンク・バンドである。細かな活動経歴や実状、ソニック・ユースのサーストン・ムーアがファンであることを公言していたとか、彼女たちの出身地である京都にてリアル病(やまい)の赤痢が一時物理的に流行ったことに由来するバンド名らしいとか、そうしたことは当時を知る世代の方が既に記しているはずなので、そちらに任せたい。いや、本レヴューを書くにあたってざっと調べたところネット上では思いのほか情報が少なかったので、改めて語っていただけるなら是非にそうしてほしい。
現在の耳で聴きつつ過去をたぐり寄せていくなかで不思議なほどすんなり入ってきたのは、赤痢がデビュー作以降〈アルケミーレコード〉に在籍していたという部分だった。非常階段の中心人物・JOJO広重が主宰するレーベルだ。私が彼を知ったきっかけはおそらく高校時代にBiS階段を聴いたことだったっけと思い返して、ピンときたのだろう。アイドル界のタブーを破り尽くすBiSというグループと、言わずと知れたアンダーグラウンドの主による異色のタッグ。リアルタイム世代が綴る赤痢の第一印象と、赤痢の活動停止以降に生を受けたわれわれ世代がBiSにおぼえた高揚とも嫌悪感ともつかぬ衝撃が重なった気がした。痛いところをかばっているように不安定な演奏/歌唱。若い女性が忌避して然るべき(と思われている)猥語をためらいなくうたい叫ぶことによる威嚇。なりふり構わないパフォーマンスをしたかと思えば、自室に貼ってあるポスターを見られてしまった思春期の少女のような照れが顔を出すこともある。同じく非常階段が過去にコラボレーションを果たしたアイドル・グループ、ゆるめるモ!にも上記の特徴はかなりの割合で共通していると気づく。そしてもうひとつ。赤痢にもBiSにもゆるめるモ!にも、女性ファンは多くついている。赤痢は「ガールズ・パンクの先駆け」と評されていることからして、当時の客層は元々シーンにいた男性が主なのかと思いきや、『LIVE and VACATION』収録のライヴ映像に映るオーディエンスはほとんどがメンバーと同年代の女性だ。2010年代にヴィレッジヴァンガードに出入りしていたサブカルチャーを嗜む女の子たちが、尖った地下アイドルをロールモデルに選んだ現象に近いものが80年代にも起きていたのだと考えれば合点がいく。したがって、インターネット登場前夜、デジタル録音普及前の音楽が有している──そしていまとなっては完全に失われた──アウラとでも言うべきなにかを抜きにすれば、赤痢に隔世の感を感ずることはあまりない。これが表示されているデバイスと地続きである。
前段では女性を軸に語ってしまったが、冒頭で述べたとおり、そこは特段焦点をあてるべき部分ではない。つまらねえのを如何にかしたい気持ちはみな同じなのだ、と知らしめることにこそ彼女たちの目的があると思う。“夢見るオマンコ” を筆頭に女性性を開陳する楽曲が多い赤痢だが、それは自らが聖域化されないための破壊活動だ。こわれものだと目されてきた領域を内側から足蹴にしてみせる。みなさまがいやに丁重に扱っているこれは、真実この程度のものなんだ、というように。少女に夢見ていたのはどちらだったのか。わたしに夢見る他者が、わたしが夢を見るように仕向けていたのではないか。
作品を重ねるにしたがって不可抗力的に向上した演奏技術は赤痢をよりフラットに、いちバンドとして見せるための添え木となって補強されていく。『PUSH PUSH BABY』ではクシャクシャとブリキのおもちゃのように跳ねていて、いかにもガレージ・バンドというギリギリのバランスでまとまりを保っていたのが、1stアルバム『私を赤痢に連れてって』までのわずかな時間でグッと強度を増している。各楽器の鍔迫りあいだったものがアンサンブルと呼べる形になり、本筋以外の音をSE的に盛り込んだ “カメレオン” からはメンバーが遊び心を具現化する方法を仕入れたことがうかがえる。各所で指摘されている「気だるさ」が前面に出てきたのもここからだ。続く『LOVE STAR』で今度はメロディ・ラインが魅力を増し、旋回しながら攪乱するような演奏とのバランスで不可思議なポップネスを提示。もはや「10代の少女がショッキングな楽曲を演っているバンド」のみでは説明不足になるほど音楽的な面白みがあらわれており、万人のための退屈破壊装置としての機能を獲得している。
スリッパで踏みならす家の床もカーテンの向こう側もどうしようもなくつまらなく感じるとき、そういうときがきたらこの作品を手に取ってみてほしい。そろそろ春も終わるが、それでも「いやな時代ももうすぐ変わる」と信じながら。
(5月25日記す)
水越真紀、清家咲乃
ALBUM REVIEWS
- Milledenials - Youth, Romance, Shame
- KMRU - Kin
- Deadletter - Existence is Bliss
- Cardinals - Masquerade
- Jill Scott - To Whom This May Concern
- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her
- xiexie - zzz
- Cindytalk - Sunset and Forever
- CoH & Wladimir Schall - COVERS
- KEIHIN - Chaos and Order
- DIIV - Boiled Alive (Live)
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- aus - Eau
- 見汐麻衣 - Turn Around
- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations


 DOMMUNE
DOMMUNE