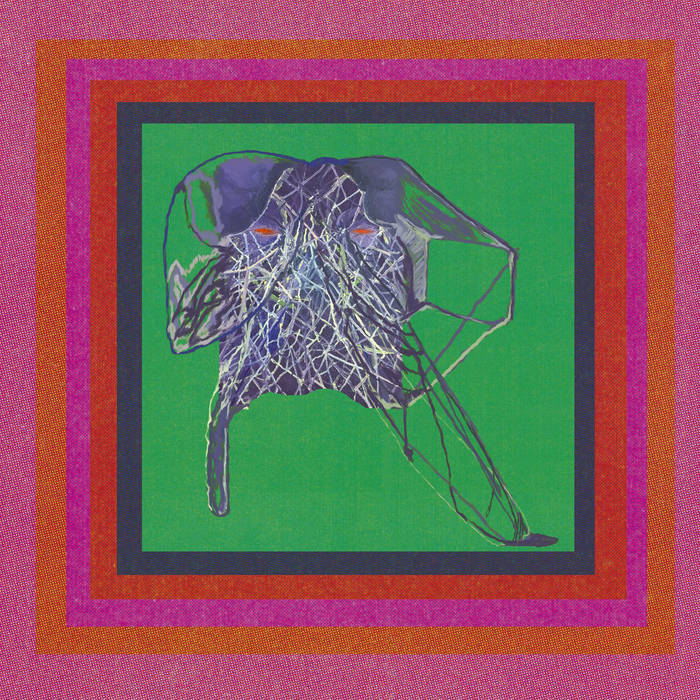MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Jlin- Akoma
フットワークのすごいところは、この音楽がダンスのためにあり、ダンスという行為から自発的に生まれる創造性に対応すべく進化した点にある。踊っている側が、バトルのためにより複雑な動きを必要とし、音楽がそれに応えたのだ。つまり、あの平均値80bpmのハーフタイムのリズムと160bpmのオフビートでのクラップとハットの高速反復、初期のそれにはいかがわしいヴォーカル・サンプルも追加されるという(その点ではヴェイパーウェイヴとの並列関係にあった)、ああしたフットワークのスタイルは、アートを目指して生まれたものではない。踊るために機能するサウンドとして生まれ、磨かれたということだ。RPブーもDJラシャドもDJスピンも、みんな元々はダンサーである。いや、その源流にあたるゲットー・ハウスの王様、DJファンクだってダンスからはじまっている。「ファック・アート、レッツ・ダンス」とは初期レイヴの有名なスローガンだが、シカゴはそれを一時期の流行ではなく、世界がシカゴに注目しなくなった90年代後半においてもずっと継続していたのだった(デトロイトのゲットーテックとともに、ダンス・ミュージックにおけるダーティな側面の追求)。きっと、いまでもそうなんだと思う。
ジェイリンは、シカゴのフットワークをインターネットを通じて知ったその外部者のひとりで、インディアナ州ゲイリーを拠点としている。現場とは直接関わっていなかったがゆえにダンサーたちの要求に応える必要もなく、自由な発想ができる立場にいた彼女は、それでも最初は現場の手ほどきを受け、そして自分のアイデアを加えてフットワークを拡張した。そのみごとな成果は、すでに『Dark Energy』や『Black Origami』といった作品として知られている。とくに後者はオウテカの領域にも近づいており、その4次元的なリズム宇宙とテックライフ系のフロアとの架け橋をしているようなアルバムだった。もっともジェイリンのシカゴの現場へのリスペクトにはたいへんなものがあって、彼女はフットワークのAFXにはならないし、彼女の音楽から「レッツ・ダンス」の要素はなくならない。それは今回のアルバムにおいてもっとも話題となったフィリップ・グラスとの共作“The Precision Of Infinity”も証明している。
この曲で驚くべきは彼女のリズム・トラックだ。もちろん、いままでもそうだったように、単純な反復ではない。フットワークにおけるハーフタイムの構造を活かし、曲は複数回にわたって別のリズムへと展開する。複雑な構造だが、複雑には聴こえないし、ゲットー・ハウスに聴こえる瞬間すらある。ダンス・ミュージックにおけるもっともダーティな側面(からの進化形)とグラスが、どんな経緯があろうとも結果、共鳴しあっているかと思うと、ぼくはついつい微笑んでしまうのだが、良い曲だと思う。クロノス・クァルテットとの共作“Sodalite”も、同じように彼らの旋律の変化に合わせてリズムも変わる。ちなみにジェイリンは、バージニア・ウルフの小説を下地にした映画『めぐりあう時間たち』のサウンドトラックでグラスを好きになったという話だ。
ビョークとの共作は、ジェイリンがすでにホーリー・ハーンドンとの共作を出していることを思えば驚くに値しない。その曲“Borealis”も、グラスとの共作同様にシームレスなリズムの変化が魅力で、これまでの作風がどちらかと言えばヴァーティカル(垂直的)な傾向(つまり、いつどこで聴いてもその曲の魅力はわかる構造)にあったことを思えば、今回はそこにリズムの展開を加えること(つまり、最初から通しで聴いた方がその魅力がわかる構造)が大きなコンセプトになっていると言えそうだ。それから、まあこれは以前からもあった要素だが、“Challenge ”や“Eye Am”など、パーカッシヴな響きの多彩な見せ方も今作の特徴になっている。野心作としてはほかにも、ヴァイオリンやチェロなどの弦楽器の音をパーカッシヴに使った、抽象的だがリズミックな“Summon”があるが、この実験においてもフットワークの影響が残っている。そう、だから、シカゴではアートではないからこそアートになりえるという逆説が成り立っていると、ジェイリンはそのことをよく理解していた。フットワークとはリズムの音楽で、その可能性/横断性は限りない。というわけで、さあ、レッツ・アート、レッツ・ダンス!
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE