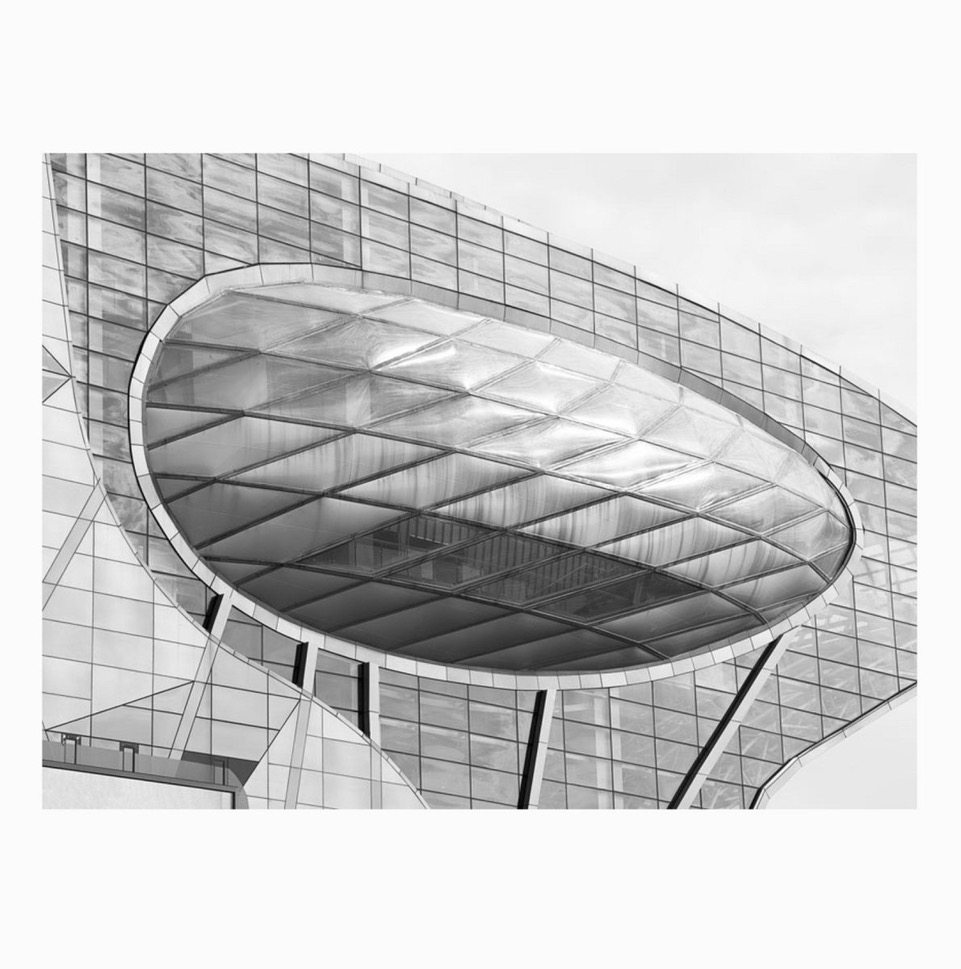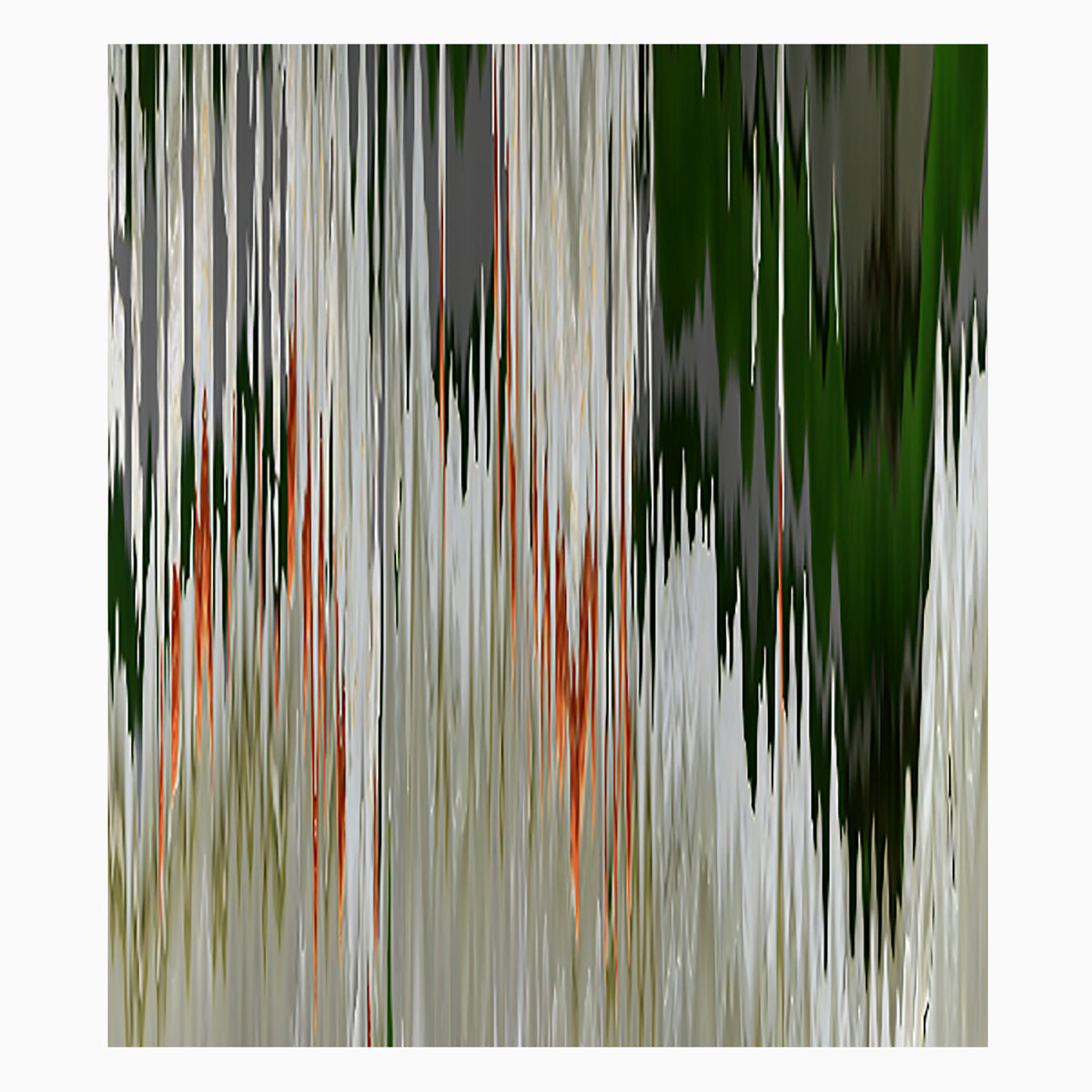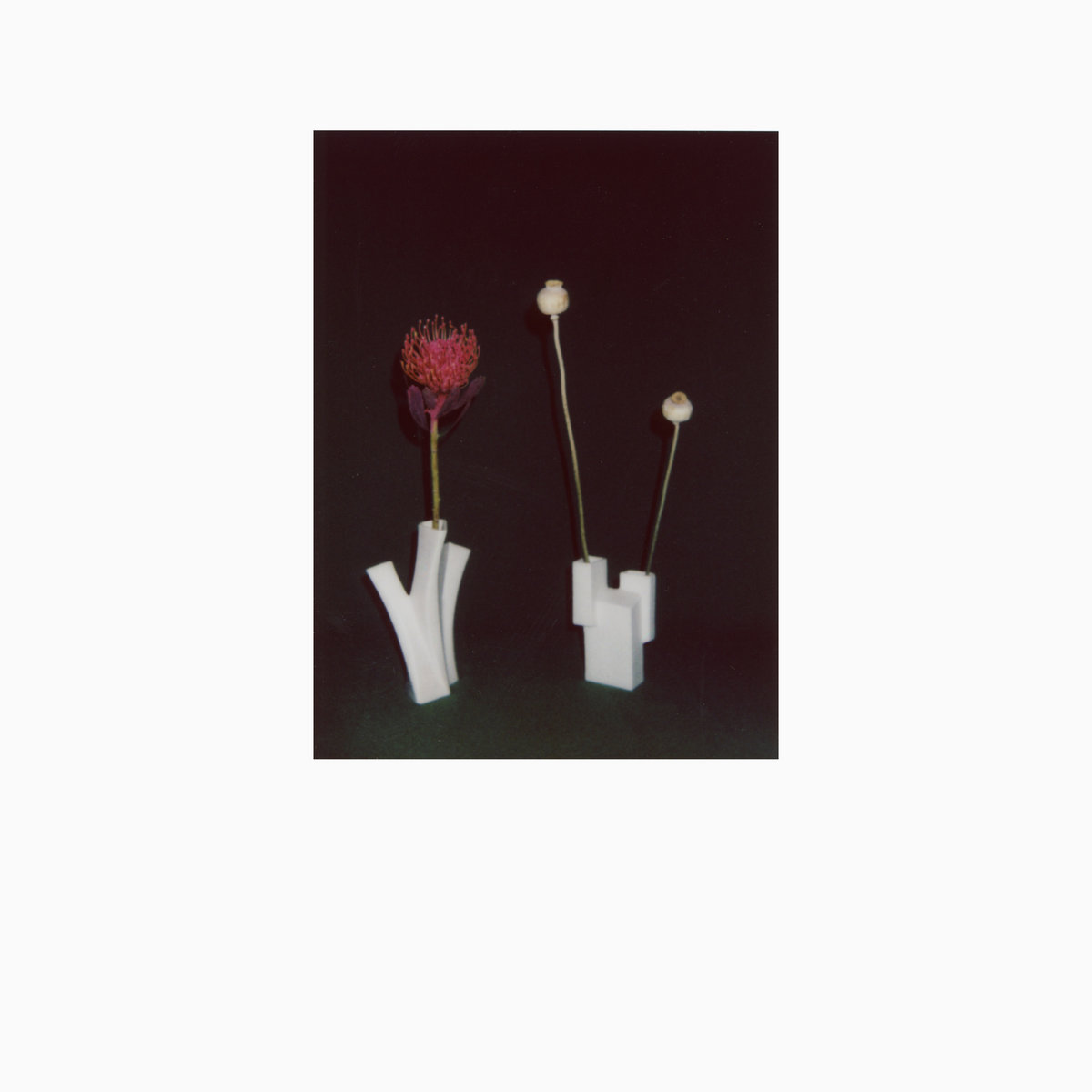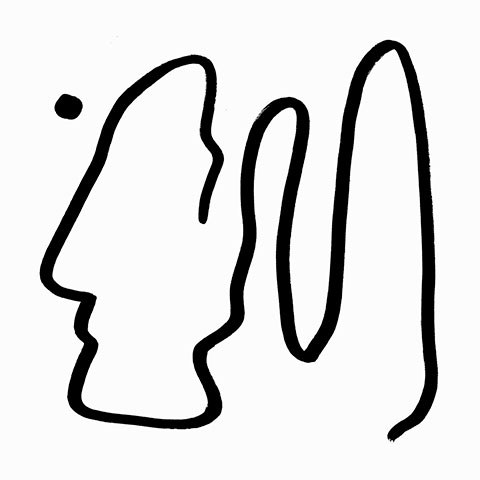MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > James Hoff- Shadows Lifted from Invisible Ha…

ニューヨークのアーティスト、ジェイムス・ホフ(1975年生まれ)の新譜『Shadows Lifted from Invisible Hands』がフランスの実験音楽レーベル〈Shelter Press〉からリリースされた。アルバムとしては2014年にドイツのエクスペリメンタル・ミュージック・レーベル〈PAN〉から発表された『Blaster』以来なので実に10年ぶりにということになる。
もっとも2022年にEP『Inverted Birds And Other Sirens』を〈PAN〉よりデジタルリリースしているので、ホフのサウンドアーティストとしての音源発表は2年ぶりなのだが、そもそも2022年のEPリリースもそれなりに驚きだったのだ。だいいちこの時点で8年ぶりだ。
というのもホフは現代アートの画家としても活動をしているし、さらには60年代以降の知られざる現在美術を発掘する独立系出版社「Primary Information」(https://primaryinformation.org)の共同設立者でありディレクターでもあるのだ。つまり現代アート/美術方面での活動がメインと言ってもよいかもしれない(ちなみに『Shadows Lifted from Invisible Hands』のアートワークは米国の画家・彫刻家のジャック・ウィッテン(Jack Whitten)の1979年作品「Mother's Day 1979 For Mom, 1979」)。だからもうサウンド・アーティストとしての音源はリリースされないのではないかと勝手に思っていた。ゆえに2022年の『Inverted Birds And Other Sirens』は驚きだったし、今回の『Shadows Lifted from Invisible Hands』も同様である。次のリリースまで10年近い月日が必要だったのだろう。
テン年代エクスペリメンタルミュージックのリスナーにとって、〈PAN〉からリリースされたジェイムズ・ホフの『How Wheeling Feels When The Ground Walks Away』(2011)と『Blaster』(2014)は忘れ難いアルバムだった。新しいノイズ・ミュージックを提示する10年代前半の〈PAN〉とのノイズとポップの領域を拡張するような作品をリリースし始める10年代後半以降の〈PAN〉との「はざま」にあるような作品/アルバムだったからである。ノイズとポップ、実験とポップの領域を拡張するような作風だったというべきか。
特に『Blaster』はダンス・ミュージック的な躍動感と強烈な電子ノイズが同居する躍動的なアルバムであり、コンピューターウイルスに感染させたサウンドファイルを用いるなどコンセプチュアルなアルバムでもあったのだ。あえていえばマーク・フェル直系のグリッチ/テクノ・サウンドだった。
だが本作『Shadows Lifted from Invisible Hands』はやや趣が異なる。理由は3点ある。まずリリースが〈PAN〉からではなく、フランスの〈Shelter Press〉ということ。そしてピアノやドローンを用いたクラシカルなサウンドということ。加えてマシニックかつ無機的な『Blaster』と比べるとエモーショナルなこと。この3点である。
むろんノーコンセプトというわけではない。「ここ数年頭から離れないポップソング(ブロンディ、マドンナ、ルー・リード、デイヴィッド・ボウイ)の断片と、何十年も経験してきた耳鳴りの周波数から作られた」という。だが同時にこれは「自伝的」ともホフが語っている。つまり「このアルバムは主に、現代の音響状況の中で、個人的、感情的、そしてもちろん批判的な新しいものを作ることをめざした自己肖像です」というのだ。
ここで興味深いのは、この明晰な「コンセプト」が、そのまま自伝的な意味合いを帯びている点である。それが結果として静謐でエモーショナルなクラシカル/アンビエントになったことが自分には興味深い。この作風は確かにストリート・エクスペリメンタルな作風の〈PAN〉というより、室内楽的な音響作品を主とする〈Shelter Press〉的だ。
アルバムは30分ほどの収録時間で全4曲収録している。先に書いたようにピアノ、シンセサイザーによるアンビエント調の楽曲だが、どこか中心点な曖昧で、音がゆっくりと崩壊していくようなムードがある。そこに微かなエモーションが息づいているという不思議な音楽だ。マシンからエモーショナルへ? ともあれ確かに現代はエモ・アンビエント(クレア・ラウジー)の時代なのかもしれない。
1曲目“Eulogy for a Dead Jerk”は低音のシンセサイザーによる短い持続音から始まり、やがてそれが弾け飛ぶような音と共に本格的に幕を開ける。その一撃から音楽性は一変し、点描的なピアノと弦学風のシンセサイザーによるアンサンブルになる。やがて高音の電子音も絡みつく。実に見事な電子音のアンサンブルだ。
2曲目“Everything You Want Less Time”はクラシカルなピアノから始まり、透明なシンセサイザーのフレーズが折り重なる短い楽曲だ。3曲目“The Lowest Form of Getting High”は1曲目“Eulogy for a Dead Jerk”のような高音の電子音にクラシカルなフレーズがレイヤーされるトラックで、その旋律はやがて誰もが耳にしたことがあるだろうメロディへと変化していく。4曲目“Half-After Life”は以前のホフ的な強烈なノイズからは始まり、すぐさま弦の音とピアノの音が絡み合うサウンドへ変化する。それがやがて美麗なシンセサイザーと加工された声や電子ノイズが応答するようなサウンドスケープを形成する。何より霞んだピアノの響きが美しい。
このアルバムに自伝的な要素があるとすれば、先にあげたポップソングの引用だろう。しかしそれらの楽曲の音は徹底的に加工され、原型は消失し、もはやほぼ判別ができない。だから重要なのは「記憶」が溶け合っていく、そして「消失」してしまう、その感覚の表現にこそあるように思える。記憶、生成、消失。その音楽/音響化を、例えばザ・ケアテイカーとは異なる手法で実現したアルバムが、本作『Shadows Lifted from Invisible Hands』ではないかと思う。20年代のアンビエンスがここにある。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE