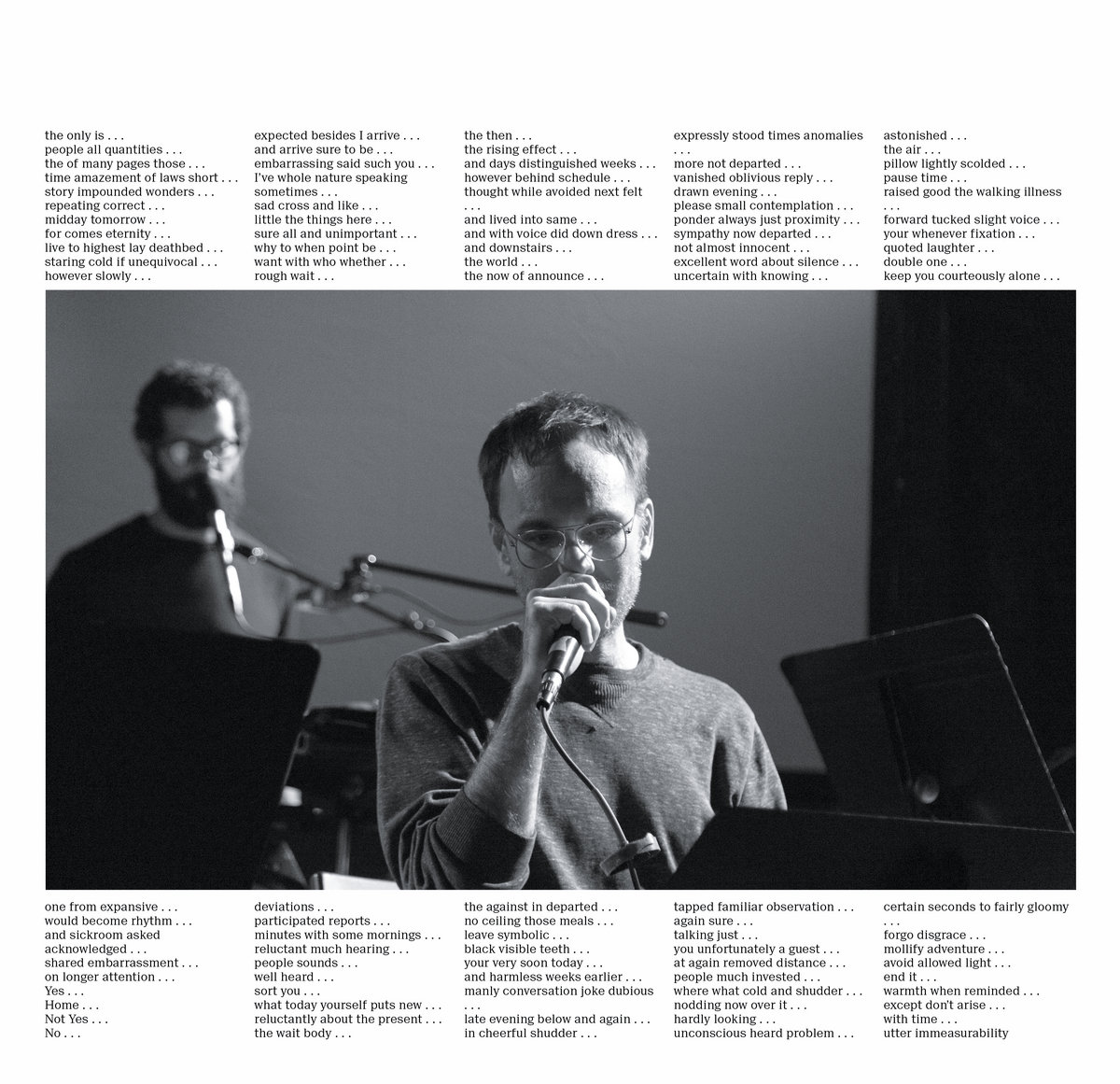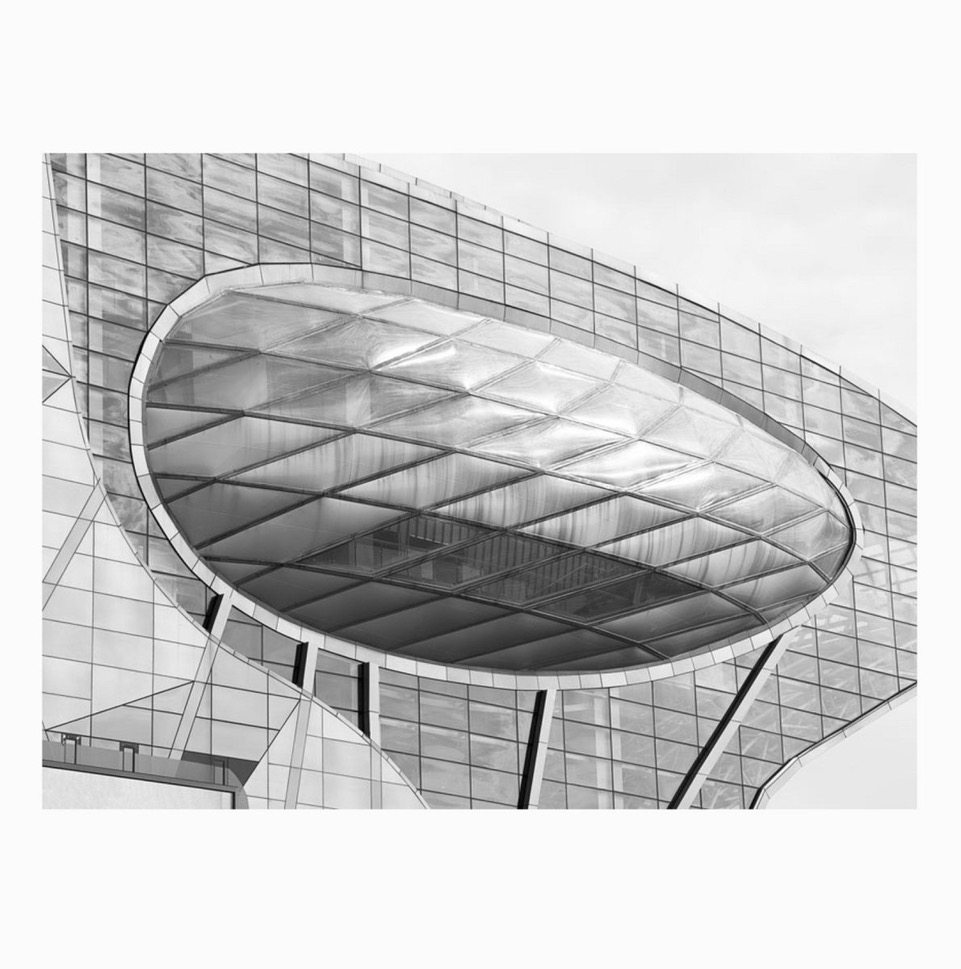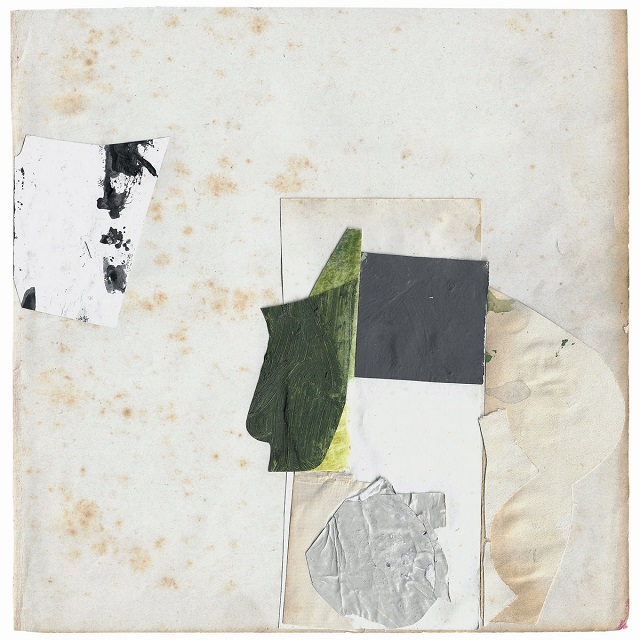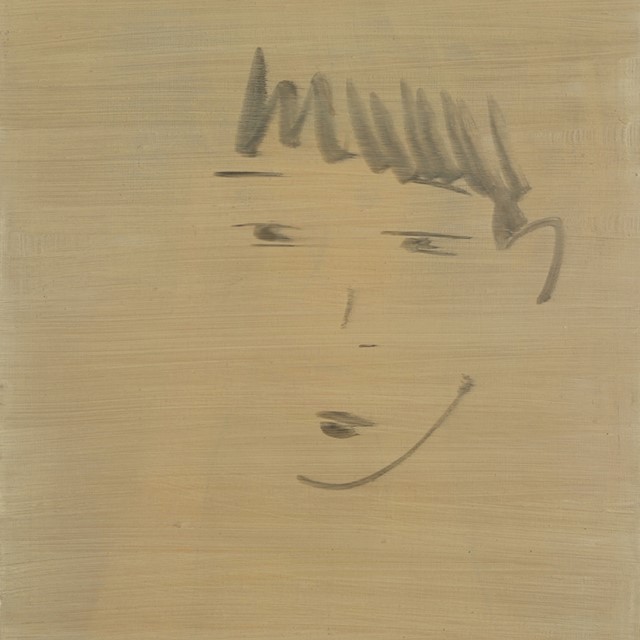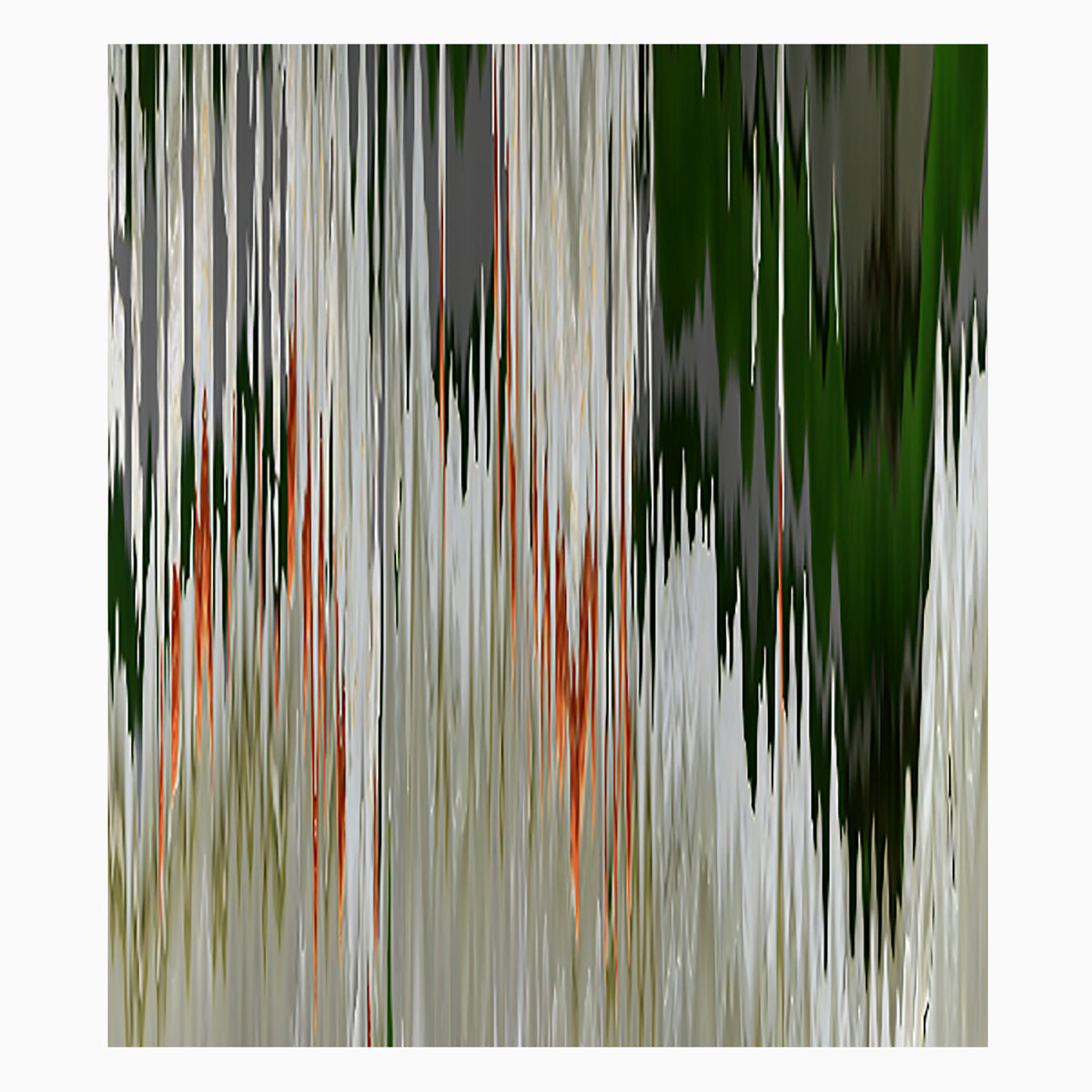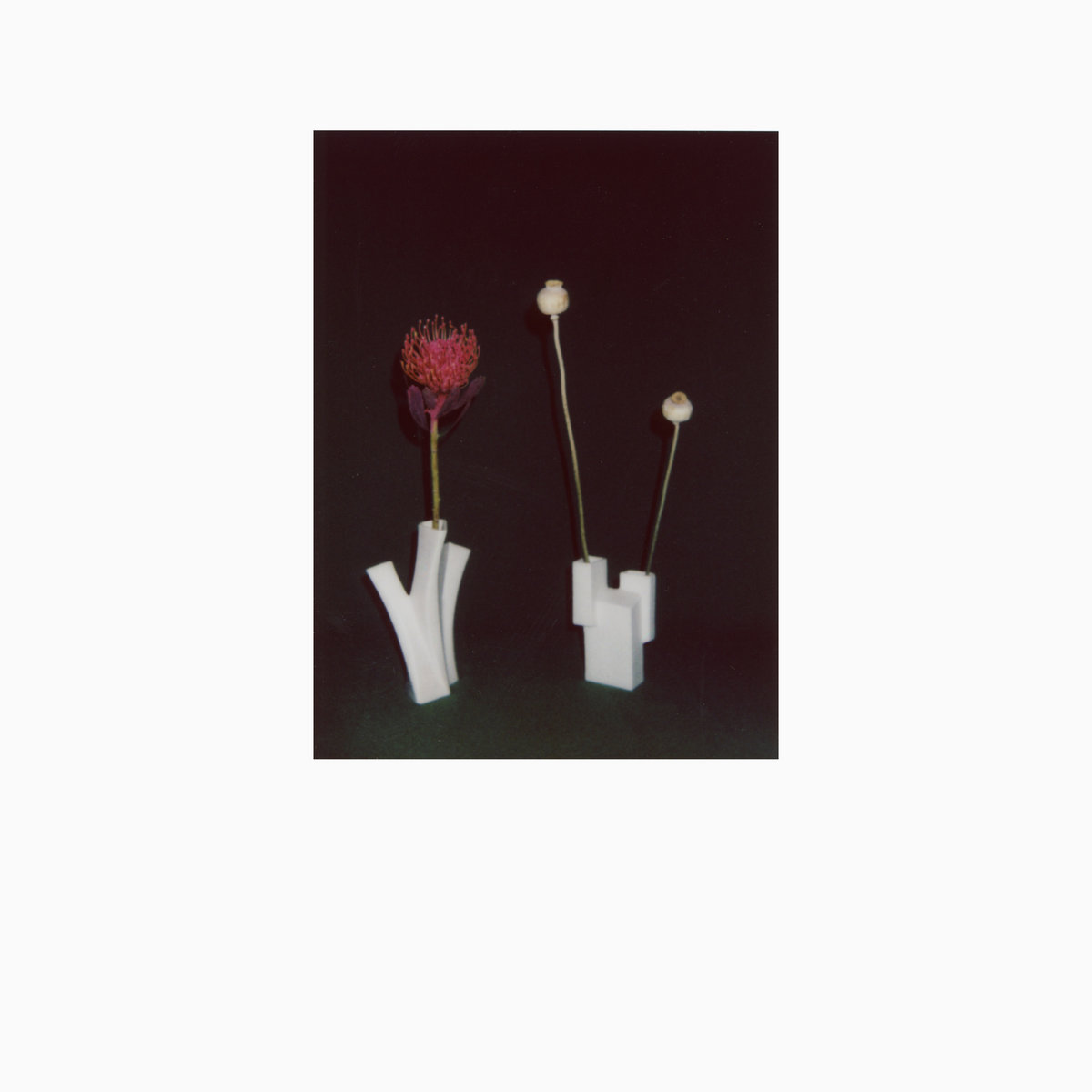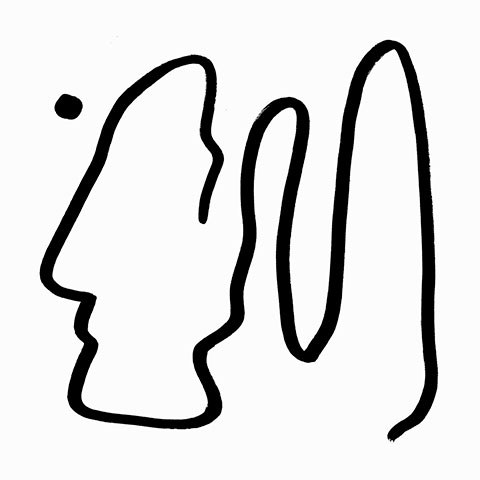MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Jules Reidy- Trances
ジュールス・レイディの新作『Trances』は、まるで完璧な工芸品のように美麗に構築された音楽・音響作品である。同時に卓抜した技法で演奏されるギター作品でもある。幻想的なムードを放つエクスペリメンタルなフォークといえる。まさに音楽・音響の複合体とでもいうべきか。これは相当なアルバムである。
ベルリンを拠点として活動を展開するレイディは、加工されたギターを用いてエレクトロ・アコースティックな作品を創作してきた才能に満ちた音楽家だ。これまでジュールス・レイディは〈Room40〉、〈Black Truffle〉、〈Editions Mego〉など、錚々たるレーベルから独自のエクスペリメンタル・ミュージック・アルバムをリリースしてきた人物である。
どのアルバムも特殊なギターとミニマルな電子音、深い残響、ときに微かな加工された声が交錯する見事なサウンドを構築している。あえていえば、「ギター・エレクトロニカ」+「電子音響」といった趣のアルバムと称するべきだろうか。理知的な印象の楽曲だが、しかし、どの楽曲もサイケデリックな音響を展開している点も重要だ。聴き込んでいると意識が飛ばされてしまう。
これまでリリースしたどのアルバムも良いのだが、なかでも実験音楽家/ギター奏者のオーレン・アンバーチが主宰する〈Black Truffle〉から2022年にリリースされた『World In World』は、ジュールス・レイディのこれまでの技法と音響が見事に結晶化された傑作であった。
フランスのエクスペリメンタル・レーベル〈Shelter Press〉からリリースされた本作『Trances』は、その『World In World』の「続編」と称されている作品である(2019年に同レーベルからリリースされた『In Real Life』も『World In World』『Trances』へと続く系譜の作品に思える)。あえていえば「悪いはずがない」というほどの作品だ。私見だが『Trances』は、今後、ジュールス・レイディの「代表作」と称されるようになるのではないか。
『Trances』は、純正律にチューニングされたヘキサフォニック・ギターを用いているという。純正律とはウィキペディアによれば「周波数の比が整数比である純正音程のみを用いて規定される音律」のこと。つまり、純正律ではより純粋な(綺麗な)和音の響きを実現することができるということだろう。ジュールス・レイディは響きの純粋さを追求したかったのではないか。じっさい『Trances』の響きはどれも澄んでいて美しい。
この『Trances』は、12のフラグメンツがシームレスにつながる構成となっている。いくつものフレーズ、音響が交錯し、大きな流れとなっているのだ。純粋な響きを放つギターの放つ残響と、電子音響によるアンビエンスが溶け合い、光のようなサウンドを生成する。
まるでギターとエレクトロニクスよる交響曲のようである。例えるならば、ジム・オルークとスティーヴ・ライシュとシャルルマーニュ・パレスタインとアルヴァ・ノト(カールステン・ニコライ)とクリスチャン・フェネスのサウンドが交錯するような音響空間とでもいうべきか。
加えてジュールス・レイディの「声」も重要だ。その「声」がまるで霧のカーテンのように音響空間にまぐれ混んでいくように鳴りはじめることで、フォーク・ミュージック的な要素も加わることにある。ギター・エレクトロニカ+電子音響作品の要素に加え、エクスペリメンタル・フォークのエレメントも重要な要素になっているのだ。
アルバム冒頭からラストまでミニマルでありなかまら拡張的な音響は一瞬たりとも緩むことなく、見事な演奏とサウンドを展開している。アルバム冒頭から、ミニマムなギターのアンサンブル、透明な電子音響、霧のような声が次第に展開され、アルバムの全体像を惜しげもなく提示する。
アルバム全体は一種の変奏曲のように構成されているが、単調さはまったく皆無だ。変わりゆくギターと音響の美を心ゆくまで満喫することができる。個人的には冒頭の “I” や最終曲の “V” に惹かれた。この二曲を聴き比べるとアルバムにおける変奏やパターン、音響の変化をよく理解できる。
もちろん、このような要素はジュールス・レイディのこれまでのアルバムでも共通する要素である。だが『World In World』を経て、この『Trances』では、さらにアルバムの音響と構成力に磨きがかかったように思えたのだ。
即興と作曲・構築のバランスがよりいちだんと高いレベルになったとでもいうべきか。断片がつながり、より大きな音楽・音響が構成されている。ギターの変奏、声のレイヤー、電子音響の変化と拡張。12のフラグメンツが違いに呼応するように音響/音楽が変化していく。
『Trances』を聴くということは、この音響/音楽の「生成と変化」のありようを体験する時間でもある。まさに繰り返し聴くに値する素晴らしい音響作品であり、音楽作品であり、ギター・ミュージックでもあり、電子音楽であり、電子音響でもあり、アンビエント・ミュージックでもあり、誰が聴いても美しいエクスペリメンタルなフォークでもある。高度でありながら難解ではない音楽性に圧倒される。
ミニマルなギターのアルペジオと電子音。ふたつのアルペジオが少しだけずれながら重なりあうことで、モアレ状のサイケデリックなパターンが生成されていく。そこに光のように煌めく音響が折り重なり、美しい残響が交錯する。音楽のズレとパターンの交錯という意味では、どこかコーネリアスの音楽性にもリンクしていきそうである。例えば、ジュールス・レイディがリミックスしたコーネリアスの楽曲なんてものも聴いてみたくなる。共演なども聴いてみたいものだ。まさに実験音楽マニアのみならず、広く音楽ファンに聴いてほしいアルバムといえる。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE