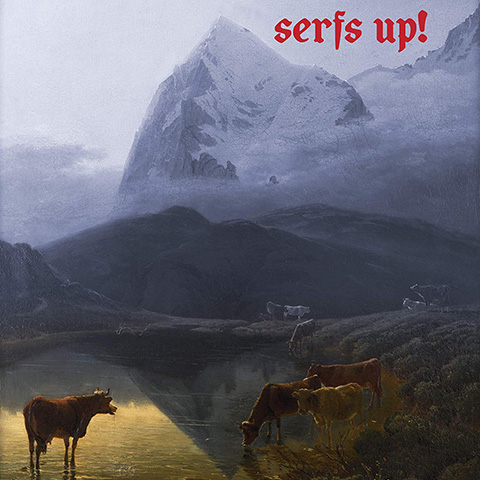MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。
ロックの本質をラディカルなものだと捉えているバンドマンは絶滅種に近い、とまでは思わない。日本からUKを見た場合、リアス・サウディやスリーフォード・モッズのような人たちはすぐに思い浮かぶけれど、まだ紹介されていないだけで、じつはほかにもいる。だから、UKロックがいよいよファッショナブルな装飾品になった、というのは早計だ。が、こんにちのロック界がラディカルなものを求めているのかどうか……ぼくにはわからない。
ジョン・ライドンやジョー・ストラマー、あるいはポスト・パンク世代たちのインタヴューが面白かったのは、彼ら彼女らが、自分が言いたくても言えなかったことを言っていたから、という気持ちだけの話ではない。彼ら彼女らの発言には、たとえ平易な言葉であっても社会学や哲学、政治の話を聴いているかのような、知性に訴えるものもあった。リアス・サウディのインタヴューは、あの時代のUKインディ・ロックの濃密な実験が完全に消失されていなかったことを証明している。意識高い系へのウィットに富んだ反論という点では宮藤官九郎の「不適切にもほどがある」と微妙にリンクしているかも……いやいや、ファット・ホワイト・ファミリーのリスナーの大部分は昭和など知らない、ずっと若い世代です。
とまれ、ファット・ホワイト・ファミリーが5年ぶりの4枚目のアルバムをリリースするまでのあいだ、バンドの評判が母国において上がっているとしたら、ベストセラーとなった共著『1万の謝罪』の効果もあろう。が、音楽シーンにおける難民となっている彼らだから見えている光景を、人はもうこれ以上、目を逸らすことができなくなってきているという状況があるとぼくはにらんでいる。この、いかんともしがたいダークな事態が続くなか、風穴をあけんとジタバタし、破れかぶれにもなり、じつを言えばなんとしてでもロックンロールを終わらせたくない男=リアス・サウディへの共感は、スマートではないからこそさらに熱を帯びることだろう。彼にはいま、作家としての道も開けているそうだが、ぼくとしては、ひとりでも多くの日本人がファット・ホワイト・ファミリーの音楽を聴いてくれることを願うばかりだ。

中央にいるのが、取材に応えてくれたリアス・サウンディ
テイラー・スウィフトを聴く方が、あの手のバンドを聴くよりも「侮辱された」って気にならないだろうな。例の「ポスト・ポスト・ポスト・ポスト・パンク」バンドの手合いね。生真面目で、時機に即した正義感あふれる歌詞、たとえば「自分たちはどれだけ移民を愛してるか」だの、ジェンダー問題云々、まあなんであれ、そのときそのときでホットな話題を取りあげる連中。
■素晴らしい新作だと思いました。
Lias Saoudi(LS):オーケイ。
■この時代のムード、とくにやるせなさや空しさをひしひしと感じました。
LS:うん。
■最初にアルバムを通して聴いたとき、いちばん心にひっかかったのは、“Religion For One”でした。ぼくは英語の聞き取りのできない日本人なので、頼りはサウンドだけです。その次が“Today You Become Man”で、これが気になったのはサウンドと曲名です。ほかの曲も好きですが、この2曲から感じた、恐怖、混乱、倒錯的な快楽、目眩、空しさ、これらはこのアルバムのなかで重要な意味をなしているように思いました。この感想についての感想をお願いします。
LS:ああ、だから一種の、想像力およびアクションの麻痺、みたいなことなんだろうな。ある種……それが注意力を引きつけるのは当然のことだ、というか。だって、それ以外に何も起きてないわけだから。
通訳:それは、現在の世界では何も起きていない、ということでしょうか?
LS:そう。いまやこう、ぞっとするくらいの停滞状態、というポイントにまで到達したと思うし。だから一種の、この……アポカリプスか何かの一歩手前、って状態が恒久的に続いている、みたいな? つまり、そうなる寸前の段階で時間が凍りついて止まってる感じ。だから逆に、いっそ物事が崩れ落ちてくれる方がむしろ救いになるんじゃないか、と。それってだから、永遠に変わらない型/枠組みが存在する、波頭が砕けることはない、ということだし。とにかく、そういう……まじりっけなしの不安感がある、と。で、思うにそれがおそらく、「これ」と明確にわかるやり方で、ではないにせよ、おれが伝えようとしてることなんじゃないのかな。とは言っても〝Today You Become Man〟、あの曲は、おれの兄の体験した割礼のお話で。
通訳:えぇっ? そ、そうなんですか!
LS:(苦笑)うん、彼は子供の頃に割礼を受けて……おれたちは半分アルジェリア人の血が混じってるんだ。だから兄は父方の故郷で、北アフリカの山々で割礼を受けた、と。
通訳:なるほど。かなり残忍な儀式、という印象ですが。
LS:ああ、かなりむごい。兄は麻酔も受けずにカットされたし……
通訳:ぐわぁ〜っ、聞いてるだけで痛そうで、きついなあ。
LS:フハハハハッ! でも、だからなんだよ、あの曲がかなりナーヴァスなものに響くのは。
■音だけだと、あの曲はフィリップ・K・ディックの小説で描かれる悪夢みたいで、強烈に惹きつけられました。
LS:なるほど。一種、そうかもね。ハッハッハッハッ!(※ディックは「陰茎」を意味する言葉でもある)
通訳:たしかに……(苦笑)。
LS:でも、あのとき兄は5歳くらいだったはずで。だからあの曲では、兄があの思い出を語るときにやるおれたちの父親の物真似、それをおれが真似てるっていう。あの曲で起きてるのは、そういうことだよ。
このグループのなかに、アルバート・アイラー的な面はあるよね。思うに……おれ自身は、フリー・ジャズに造詣が深いとは言えないだろうな。ただ、誰もが色々でっちあげたというか、アルバム作りのあの時点で、みんな、思いつくままクソをあれこれと壁に投げつけて、何がこびりつくか見てみよう、と。
■フリー・ジャズは聴くんですか? “Today You Become Man”にその影響がありますが、もしそうなら、とくに好きな作品/アーティストは?
LS:まあ、このグループのなかに、アルバート・アイラー的な面はあるよね。思うに……おれ自身は、フリー・ジャズに造詣が深いとは言えないだろうな。ただ、誰もが色々でっちあげたというか、アルバム作りのあの時点で、みんな、思いつくままクソをあれこれと壁に投げつけて、何がこびりつくか見てみよう、と。
通訳:(笑)
LS:あの曲は実は、9人で演奏した、20分近いジャムみたいなものだったんだ。だからアルバムに収録したのは、そこからカットした短い部分。
通訳:ジャムから編集してアルバム向けの尺にした、と?
LS:っていうか、あの曲のヴォーカルにとって「これだ」と完璧に納得できる、その箇所だけ使った。
■FWFの10年の歩みを綴った、アデル・ストライプとあなたの共著『Ten Thousand Apologies: Fat White Family and the Miracle of Failure(1万の謝罪:ファット・ホワイト・ファミリーと失敗の奇跡)』(2022)はいつか読みたい本です。レヴューを読む限りでは、FWFの歴史においての、おもにドラッグ常用者の手記みたいなものらしいですが、合ってます?
LS:ああ……。
通訳:もちろんドラッグ体験ばかりではなく、バンド・ヒストリーも追っているのでしょうが。
LS:まあ、本の多くは、おれとおれの弟(Nathan Saoudi)の生い立ちについて、だね。アルジェリア半分/英国半分の子供で、北アイルランド、そしてスコットランドで育ち……ということで、まあ、とにかくちょっとばかし奇妙なお膳立てだったわけ。で、続いて20年くらい前のロンドン音楽シーンの話になり、みすぼらしい生活、一時的なスクウォット暮らし等々……不潔さ、カオス、ドラッグが山ほど出てくるよ、うん。でも、どうなんだろ? たぶん、これくらい早い時点でああいう本を書くのは、ちょっと妙なんだろうな。ただ、パンデミック期だったし、おかげでほかに何もやることがなかったし、だったらまあ、ここでひとつ過去を吟味してもいいだろう、と。当時は音楽活動をまったくやってなかったし。
■この本を書こうと思った動機について聞きたいのですが、たしかに「バンドの伝記」はちょっと早いですよね。いまおっしゃったように、コロナがきっかけだった? それともいつか書きたいと思っていた?
LS:いいや、たぶんアデル・ストライプは、どっちにせよこのバンドのバイオグラフィを書くつもりだったんだと思う。彼女はパンデミックの前から、おれに協力を要請していたからね。パンデミックが世界的に爆発したまさにその頃に、おれたちは日本・中国・台湾・香港etcを回ってるはずだったんだよ(※2020年3月に予定されていたがキャンセルになったツアー)。だから本来は、おれがロード生活の合間に彼女にいくつかのパラグラフをメールする予定だったわけ。ところが何もかも一時停止し、バンド全員が家にこもっていたし、ほんと、こりゃ執筆には完璧なタイミングだな、と。うん、あれはまあ、一種のセラピー的なプロセスだったというか。どうかな? とにかく、もっと過去に起きた、とんでもなくカオスな出来事の数々を自分なりに理解するのに役立った。ほんの少しだけど、それらからなにがしかの理解を引き出せた。
■書名を『Apologies(謝罪)』としたのはなぜ? 単純な話、まわりに迷惑をかけたからでしょうか?
LS:んー、おれが思ったのはそれよりももっとこう、このバンド内には常に、非常に悪意に満ちた、有害な対人関係の力学が存在してきたわけ。おかげでその歴史は丸ごと、絶え間ない川の流れのような無意味な謝罪の連続、みたいな。つまり、あれは一種の内輪ジョークというか。ほとんどもう、いちいち相手に謝るのすら面倒くさいというのに近い。どうせまた険悪になるんだし、だったら中身のない謝罪ってことだから(苦笑)。
通訳:なるほど。バンド内のテンションや個人間の葛藤もありつつ、それでも仲直りし再出発するものの、でもまた誰かがおじゃんにする、の繰り返しで続いてきた、と。
LS:まあ、悲惨なのは、この……「仕事」というのか何というのか、そのいちばん魅力的な面というか、本当はたぶんそうするべきじゃないのに、でも続けたくなってしまう、その理由って、パフォーマンスをやることと、そしてそれにまつわる経験すべてのもたらすハイなんだよね。だから、おれたちの間で起きた口論の数々は、みんなの生きてる自然界での当たり前の人間関係だったら、たぶん完全な仲違い・絶交に繫がっていただろう、そういう類いのものだったわけ。普通なら、自然死していたはずだ。でも、おれはこの、いわば痛みを感じにくい生命維持装置めいたものをまとい続けていたし、それって風呂に浸かったまま生きるようなもんで、だから毎晩のようにマジにエクストリームなことをやっていた、と。ところがいったんライヴが終わるや、一気に罪悪感が出てきて、全員がハイな状態のままで「ごめんな」「悪かった」とか、謝り合うわけ。すると急に、「何もかも滅茶苦茶だけど、それでもオーライ!」って信じることができるっていう。それってある意味……勝手な思い込み・妄想なんだろうな。一種、毛布をひっかぶってイヤなものは遮断する、そういう幻想っていうかさ。そうやってひたすら目をつぶって邁進し続け、でも状況はどんどん悪化し、恨みや憤りもどんどん積み重なっていく、と。うん、そんなとこ。
序文・質問:野田努(2024年4月25日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE