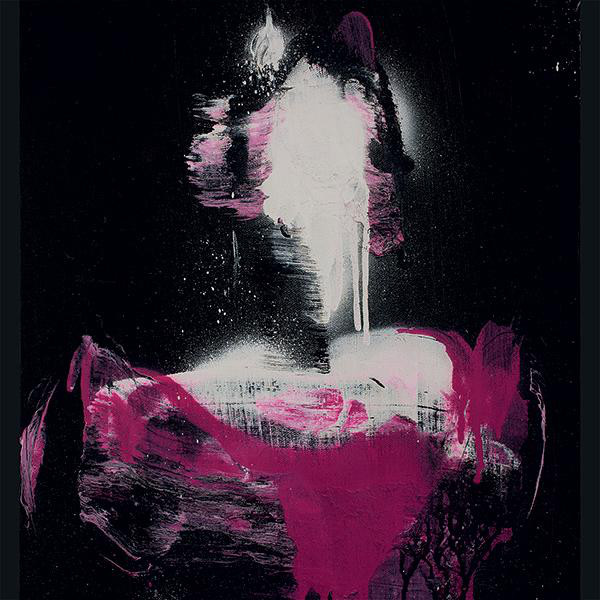MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
interview with Keiji Haino
灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
ドアーズを初めて聴いたのが中3で、その後の2~3年で、すごいスピードでいろんな音楽を吸収した。レコードやラジオで。そして、ハードなもの、他にないもの、この二つが自分は好きなんだとわかった。
灰野敬二さん(以下、敬称略)の伝記本執筆のためにおこなってきたインタヴューの中から、編集前の対話を紹介するシリーズの2回目。今回は、高校時代からロスト・アラーフ参加までの1969~70年頃のエピソードを2本ピックアップする。ロック・シンガー灰野敬二の揺籃期である。
ちなみに本稿がネットにアップされる頃、灰野は今年2度目のヨーロッパ公演(イタリア、ベルギー、フランス)へと旅立っているはずだ。
■ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン
■灰野さんが高校時代からドアーズやブルー・チアの熱心なファンだったことは有名ですが、当時、特に好きだったミュージシャンとしては他にはどういう人たちがいたんですか?
灰野敬二(以下、灰野):高校の学園祭では “サティスファクション” などを歌ったんだよ。先輩たちのバンドのシンガーとして。学園祭のためだけの即席バンドね。3年生のギタリストはジェフ・ベックに似ていた。その他にも、ビートルズやナインティーンテン・フルーツガム・カンパニー(1910 Fruitgum Company)の “サイモン・セッズ Simon Says” とか歌った。当時流行っていたロックやポップスの曲ばかり。先輩から声をかけられて参加したバンドだし、曲も先輩たちが決めていたからね。でも、“テル・ミー” と “サティスファクション” を10分ぐらいずつやった時は、普通の演奏をバックに、ドアーズ “When The Music's Over” を意識したストーリーテリング的ヴォーカルにしたんだ。あと、俺はテイスト(Taste)の「シュガー・ママ Sugar Mama」(69年のデビュー・アルバム『Taste』に収録)をやりたいと言ったの。でも、誰も知らなかった。俺は『Taste』の米盤を持ってて、特にロリー・ギャラガーのギターが大好きだったから。
ギターに関しては、もちろん最初はエリック・クラプトンやジミ・ヘンドリクスなどを熱心に聴いていたけど、ロリー・ギャラガーはそういったブルース・ロック・ギタリストとはどこか違うと感じていた。変だなと。曲の作りが、ロックでもブルースでもカントリーでもない。リフも他のギタリストとは全然違う。理論ではなく直感としてそう思った。たとえば、ジミヘンやクラプトンの音楽が五つの要素から成っているとすると、ギャラガーは七つの要素で成っている。だから、飽きない。バロック音楽的要素も感じたりして。で、当時の自分の中でギャラガーは最高のギタリストになった。ちょっと後、渋谷ジァン・ジァンなどに日本のバンドのライヴを観に行くとみんなでクラプトン大会とかやってて、フーンと思っていた。当時から日本のロック・シーンはそんな感じだったんだ。
Taste “Sugar Mama”
今の若い世代は音像ではなく音響に関心を向けがちだけど、そのあたりは世代格差を感じる。センスという言葉で音の加工を重視するけど、俺はそういうのは好きじゃない。ロックを感じない。
■17才でロリー・ギャラガーの特異性をしっかり感じ取れたってのはすごいですね。
灰野:とにかくいつも “違うもの” を探し求めていたから。ドアーズを初めて聴いたのが中3で、その後の2~3年で、すごいスピードでいろんな音楽を吸収した。レコードやラジオで。そして、ハードなもの、他にないもの、この二つが自分は好きなんだとわかった。ジミヘンもクラプトンもカッコいいけど、彼らはやはりロックの優等生なの。ギャラガーだってもちろん優等生だけど、そこにとどまらない、更に何か違うものがある。
■アイリッシュという属性も関係してたんでしょうね。
灰野:そうそう。彼の表現の根底には反イギリスの感覚がある。ヤマトの人間が持ちえないセンスをアイヌや沖縄の音楽家が持っているように。俺はお前たちとは違うぞ、俺たちにも目を向けろ、という意志を感じる。彼の音楽の中にあるカントリー・テイストも、ルーツはアイリッシュ・フォークだし。
■ロリー・ギャラガーの他には?
灰野:デビュー時のレッド・ツェッペリン。高校1年の冬だったと思うけど、パック・イン・ミュージックの火曜日、福田一郎さんが、日本盤はまだ出てなかったツェッペリンの1st『Led Zeppelin』(欧米では1969年1月リリース)の “You Shook Me” をかけたのを聴いてショックを受け、翌日か翌々日、日本の発売元だと思われる日本グラモフォンに電話した。「ツェッペリンのファン・クラブを作ってくれ」と。それぐらいこのデビュー・アルバムにはずっと、ものすごい愛情を持ってきた。“You Shook Me” の最後の部分のギターとヴォーカルの掛け合い、俺はあれでヴォーカリゼイションに目覚めたの。ブルー・チアのグルーヴ感とロバート・プラントのヴォーカルが、ミュージシャンとしての自分のスタート地点になったと思う。ドアーズの演劇的表現は別にして。
Led Zeppelin “You Shook Me”
とにかく “You Shook Me” はショックで、パック・イン・ミュージックを聴いた後、寝られなくなった。当時はまだ高校を辞めてなかった頃で、翌日学校から戻るとすぐにお金を握りしめて渋谷ヤマハに駆け込んだ。当時あそこは6時15分が閉店で、学校から帰宅してから急いで行くとだいたい6時ちょい前ぐらいに着く。だから、試聴している時間などない。幸い、盤はあり、それを大事に抱えて帰宅したのを憶えている。米盤で、3000円近くした。当時は英盤はなかなか入ってこなかった。
日本の発売元が日本グラモフォンだとどうやってわかったのか……はっきり憶えてないけど……当時の日本ではいいバンドの発売元はだいたいグラモフォンだったから、勘で電話したんだと思う。でも、電話に出た人はツェッペリンのことを知らず、話がまったく通じなかった。もしわかっている人が出ていたら、俺は日本のツェッペリン・ファン・クラブ会長になっていたかもしれない。だいたい、当時はヤードバーズやキンクスだって、日本ではあまり知られてなかったからね。
ツェッペリンは今でも1stが一番好きだね。というか、2作目以降は関心がなくなった。1stはアヴァンギャルドでしょう。今の若い世代は音像ではなく音響に関心を向けがちだけど、そのあたりは世代格差を感じる。センスという言葉で音の加工を重視するけど、俺はそういうのは好きじゃない。ロックを感じない。
“You Shook Me” を聴いて、音楽や歌や声に対する概念が自分の中で変わったと思う。ああいうことをしてもいいんだ、なんでもありなんだ、と。あと、ロックじゃないけど、ヴォーカリゼイションのヒントということだと、パティ・ウォーターズも大きかった。今はもうロバート・プラントは嫌いだよ。歌がヘタだから。声を出すことと歌うことは違う。「歌」ではなく「ヴォイス」と呼ばれることを俺が嫌いなのは、ヴォイスの人たちは歌がヘタだから。歌は、ずっと歌い続けていかないと上手くはならないんだ。
取材・写真・文:松山晋也(2024年4月16日)
| 12 |
Profile
 松山晋也/Shinya Matsuyama
松山晋也/Shinya Matsuyama1958年鹿児島市生まれ。音楽評論家。著書『ピエール・バルーとサラヴァの時代』、『めかくしプレイ:Blind Jukebox』、編・共著『カン大全~永遠の未来派』、『プログレのパースペクティヴ』。その他、音楽関係のガイドブックやムック類多数。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE