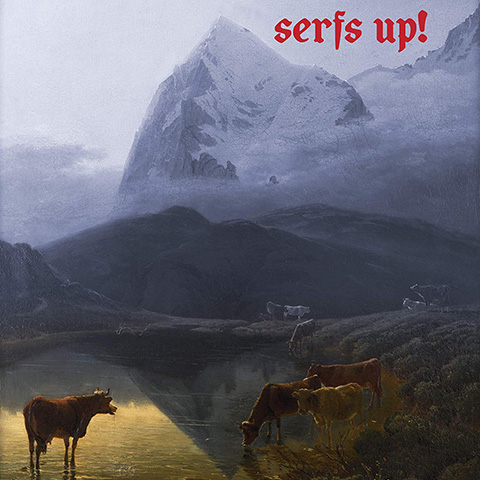MOST READ
- Sisso - Singeli Ya Maajabu | シッソ
- R.I.P. Steve Albini 追悼:スティーヴ・アルビニ
- interview with I.JORDAN ポスト・パンデミック時代の恍惚 | 7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- seekersinternational & juwanstockton - KINTSUGI SOUL STEPPERS | シーカーズインターナショナル&ジュワンストックトン
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
- Claire Rousay - Sentiment | クレア・ラウジー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- interview with Anatole Muster アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 | アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Cornelius いかにして革命的ポップ・レコードは生まれたか
- 角銅真実 - Contact
- There are many many alternatives. 道なら腐るほどある 第11回 町外れの幽霊たち
- Overmono ──オーヴァーモノによる単独来日公演、東京と大阪で開催
- interview with Yui Togashi (downt) 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド | 富樫ユイを突き動かすものとは
- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Columns Kamasi Washington 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 | ──カマシ・ワシントンの発言から紐解く、新作『Fearless Movement』の魅力
- interview with Sofia Kourtesis ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 | ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- Loraine James / Whatever The Weather ──ロレイン・ジェイムズの再来日が決定、東京2公演をausと蓮沼執太がサポート
- great area - light decline | グレート・エリア
Home > Interviews > interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。
そもそもこのバンドは常に、なかばダダイスト的な、社会実験みたいなものだったからね。だから、ヒットを出して大きく当てる、みたいなことはハナから意図してなかった。
■“Religion For One”には不思議なパワーを感じます。負の感情が横溢していますが、この曲には陶酔感もありますよね。曲ができた経緯を教えてください。
LS:えーと、あの曲を書いたのはいつだったっけ? フーム……ああ、パンデミックが起こる直前に、おれは曲を書き始めて、それとフィンガー・ピッキングのギター奏法も勉強し始めたんだ。フィンガー・ピッキングでギターを弾きたいとずっと思ってきたし、ここでもまたパンデミックが、アコギで指弾きをやるのを習得する格好のタイミングになった、と。で、おれはちょっとした曲を作り始めたし、それらは、そうねえ……「えせレナード・コーエン」調とでもいうか? 単に自分で浸って書いていたし、あとまあ、〝Suzannne〟をギターで弾こうとえんえん練習してたから、というのもある。で、そのプロセスのなかからこの曲が浮上してきた、みたいな。たしかあの頃は、ルーマニア人の悲観主義作家/思想家のE・M・シオラン(Emil Mihai Cioran)をよく読んでたな。
通訳:ほう。
LS:彼の文章はまあ、「宇宙的にブラックな笑い」、みたいな? で、あのときのおれが向かおうとしていたのも、そのノリだったわけ。というわけで、そうだな……(小声でつぶやく)さて、あの曲を書いたのはいつだったかな、はっきり思い出せない……まあともかく、いまからずいぶん前の話だよ。おれが、いわゆる「タートルネックを着た、真面目なフォーク吟遊詩人」になろうとしていた間に書いた曲だ。
通訳:(笑)ボブ・ディランみたいな?
LS:そう、ボブ・ディランか何かみたいな(笑)
■FWFのなかは、ロックにおける成功とはいったいなんなのか?という、カート・コベイン的なヒニリスティックな疑問があるのでしょうか? たとえば、大衆受けする曲を書いて、こうして取材を受けて、売れて、儲かるという、それらすべてのポイントってなんなんだ? みたいな。
LS:いや、おれは複数のバンドを掛け持ちしようとしてるし、執筆活動もやる。だから、9時5時の普通の仕事をせずに食いつなぐためには、色んなことをやらなくちゃいけないわけ。だからおれからすれば、自分が標準的な職に就くのを回避できたら、それは漠然とした「成功」と捉えていいだろう、と。もっとも、公正を期すために言うと、今のこの仕事(=バンド〜アーティスト活動)だって、ある意味、普通の仕事と同じくらい嫌いなんだけどね。普通の仕事をやってる方が、たぶんもっと経済的に楽だろうし。ってことは、自分はそこすら勘違いしてたんだろうな、つまり自分なりの「成功」の定義のレベルですら、あまりうまくいかなかった、と。いやだから、以前のおれは、ステージに登場しただけで、バンドがまだ何も始めてないのに観客が拍手喝采する、そうなったら成功だろうと思ってたんだよ。ほら、人気を確立したバンドのライブだと、彼らがステージに上がった途端に、もうお客は拍手するわけじゃない? そうなったら、たぶん自分はそれだけで満足だな、昔はそう思っていたわけ。でも、満足するってことはなかった。それ以外にも、求めることはいろいろあるっていう。ただ、近頃じゃ……スポティファイ等々の権力を持つ側が基本的に、「お前にはなんの価値もない」と決めてしまったわけでね。だからおれたちも、「ロックンロールのサクセスとは何か」の定義/尺度を格下げしなくちゃならなかった、と。その公式見解に足並みをそろえるのは可能だし、そうすればもうちょっとバンドも長続きするかもしれないけど、そもそもこのバンドは常に、なかばダダイスト的な、社会実験みたいなものだったからね。だから、ヒットを出して大きく当てる、みたいなことはハナから意図してなかった、という。まあ、いわゆる「インディ・ロック」と呼ばれる類いの音楽で実際に成功してるもの、それらの実に多くはマジに、もっとも憂鬱にさせられるような戯言だしね。あれを聴くくらいなら、おれはむしろ……いや、実際にテイラー・スウィフトを聴いたことはないけど、たとえば彼女の類いの音楽を聴く方が、あの手のバンドを聴くよりも「侮辱された」って気にならないだろうな、と。つまり、例の「ポスト・ポスト・ポスト・ポスト・パンク」バンドの手合いね。生真面目で、時機に即した正義感あふれる歌詞、たとえば「自分たちはどれだけ移民を愛してるか」だの、ジェンダー問題云々、まあなんであれ、そのときそのときでホットな話題を取りあげる連中。それこそもう、「いま熱い」トピックを次々に繰り出す糸車みたいだし、しかもそのすべてに歯を食いしばるようなひたむきさが備わってて。だから、ユーモアにもセックスにも欠けるし、ただひたすらこう、「乾いてる」という。そういうのには、おれはとにかく、一切興味が持てない。
通訳:カート・コベインについてはどう思いますか? ニルヴァーナは90年代でもっとも成功したロック・バンドのひとつになり、彼はその重圧に苦しみました。で、大ヒット作のパート2ではない『In Utero』を作ったのは一種の「自己サボタージュ」だったと思います。『In Utero』はいまではクラシック・アルバムとされていますが、当時はニルヴァーナのキャリアを棒に振ると言われた問題作でしたし――実際、彼は自らの命を絶ってしまいました。彼のそういう厭世的なところは、理解/共感できたりしますか?
LS:そうだな、今日の……おれたちが生きてる時代の音楽の歴史って、実際面での再編成に影響されてるんじゃないかな。つまり、音楽をやってもちっとも金にならない、と。その点は本当に、とにかく何もかもの力学を丸ごと変えたと思う。不可能だ、と。だからもう、そうしたことをやる権限はないわけ。おれが見渡す限り、そういうタイプのスター、あるいはならず者的な存在は見当たらないし、うん、少なくともロックンロールの世界では、そうした人物は過去の遺物だね。まあ、もしかしたらカニエが、ラップ界でその旗を振ってるのかもしれないけど(苦笑)?
通訳:(笑)たしかに。
LS:(笑)「マジにファッキン狂った男」をやってて、危ない奴だ、と手かせ足かせで拘束されるっていう。一方でロックンロールはいまや、ブルジョワ階級の道楽めいたものになってる。こけおどしの儀式/祭典みたいなもんだし、これといった文化的な生命力は、そこにはもはやない。とにかく都会暮らしの中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だし、要するに、そこには鋭い切れ味がすっかり欠けている、と。だから、いま言われたような「成功を拒絶する」型の声明を打ち出すのは、もう、どんどんどんどん、むずかしくなる一方なわけ。ってのも、メンバー全員が完全に頭がおかしくなり、あっという間に爆発してしまうことなしにバンド活動を続け、作品を出しツアーに出続けるのは、もう不可能だから。いまバンドをやってる連中は、そこにこもってODできるような私邸すら持ってない。三回離婚しても慰謝料を払えるほど稼いでもいないし、個人的なメルトダウンを起こしたら逃げ込める私有牧場も持ってない。コカインは高過ぎて買えないから、それより安いスピードに切り替えるしかないし、ヘロインの代わりにフェンタニル(※合成オピオイドの鎮痛剤)を使う……みたいな感じで、とにかくあらゆる基準において、何もかもが格下げされてきた。もちろんほかのすべて、生活基準etcもグレードが落ちてるけど、音楽におけるそれは、とりわけひどい。音楽がいかにシェアされるか、という意味でね。それこそもう、基準なんて存在しない、というのに近い。少し前に――これまた一種の「ロックンロールの自殺者」と呼んでいいだろうけど――デイヴィッド・バーマンに関する記事を読んで。
通訳:ああ、シルヴァー・ジュウズの(※1989年結成のUSバンド。2005年にラスト・アルバムを発表し09年に解散、フロントパーソンのバーマンは2019年に新プロジェクトをデビューさせたものの程なくして自殺)。
LS:うん。デイヴ・バーマンについて読んでたんだ、彼が自ら命を絶つ少し前にリリースした、最期のアルバムがとても好きだから。
通訳:『Purple Mountains』ですね。
LS:そう。あれはほんと……今世紀のもっとも美しいレコードのひとつ、というか。それくらい、本当にあのアルバムが好きで。でまあ、それで彼に関する記事を読んでたんだけど、そこに「彼はナッシュヴィルに家を買った」みたいな記述があって。90年代のレコード売上げ等々で彼には家を買えた、と。それを読みながら、おれは……いやだから、シルヴァー・ジュウズを聴くと、そのいくつかはとんでもない内容で(苦笑)。
通訳:(笑)
LS:それこそ、もっとも商業性のないオールドスクールなフォーク・ロックみたいなノリだし、歌詞にしてもへんてこで脱線気味。どう考えても「ヒット曲満載」ってもんじゃないし、支離滅裂で。だから「えぇっ、デイヴ・バーマンはあれでも家を買えたんだ!」と驚いた。「一体どうやって?」と思った。でも、ああそうか、90年代だったからか、と納得したっていう。
通訳:時代もありますし、あの頃のナッシュヴィルでも、郊外ならまだなんとかなったんじゃないですか?
LS:ん〜〜、たしかに。それはそうだな。ナッシュヴィルの不動産価格をきちんと調べた上でじゃないと、これに関して早合点はできないかもしれない。
通訳:(笑)。いまは、たとえばナッシュヴィルで腕を磨いたテイラー・スウィフトの成功で再び新世代のカントリー・シーンが盛り上がり、状況も違うんでしょうが。
LS:だけど、カントリーは常にかなり人気があるジャンルだと思うけど? それって、アメリカ国外のおれたちみたいな連中には認識できない、そういうもののひとつだと思う。ただ実際には、カントリーはアメリカでいちばん人気のある音楽と言っていいくらいポピュラーで。ヘタしたらヒップホップよりビッグかもしれないし、産業としてもめちゃめちゃ巨大だろうし。で、その再重要地点がナッシュヴィル、みたいな。だから、いまはもちろん90年代ですら、家の価格はかなり高かったんじゃないかと思うな……。ちょっと話が逸れたけども。

メンバー全員が完全に頭がおかしくなり、あっという間に爆発してしまうことなしにバンド活動を続け、作品を出しツアーに出続けるのは、もう不可能だから。いまバンドをやってる連中は三回離婚しても慰謝料を払えるほど稼いでもいないし……みたいな感じで。
■たしかに。質問に戻りますが、先ほど「音楽にヴァイタリティがなくなってしまった」とおっしゃっていましたが、文化全般についてはいかがですか? 60年代末のカウンターカルチャー、パンク〜レイヴ・カルチャーの時代に比べて、文化の力が弱まったという意見がありますよね。あなたもそう思いますか? もしそういう自覚があるようだったら、その苛立ちというのはFWFに通底していると言えるのでしょうか?
LS:まあ、基本的にインターネットがそうした物事のすべて、君がいま挙げたようなサブカルチャーetcのポテンシャルを一掃してしまったんだと思う。それらはみんな、「ポスト・インターネット時代」においては認知不可能なものになってしまった、と。人びとの頭のなかに入り込んでしまう、この、奇妙な均質化と関連してね。つまり、インターネットの本質に不可欠なのは、可能な限り誰もがほかのみんなと似たり寄ったりになる、ということだし、そうすればマシンもより円滑に機能するわけで。思うに、かつて特定のファッションなり、音楽やサウンドなり、とある地域なりの周辺に集まって融合したエネルギーというのはすべて……そのエネルギーはきっと、何かに対する反抗だったり、あるいは単に、抑圧された表現の奔出だったんだろうけども――それらは全部、この「オンライン空間」みたいなものにパワーを集中し直したんじゃないかと。というわけで、意地の悪いケチな争い合いの数々に、色んなヴァイラル/TikTokのバズの堆積物の山だの……要するに君は、エンドレスに連続する、減少していく一方の無数の「無」を前にしてる、みたいな。フィジカルな世界で有機的に成長していくことのできる、真の意味での焦点/中心点ではなくてね。何もかもからそれが剥ぎ取られてしまい、そうした過去のサブカルetcに対するノスタルジアがそれに取って代わった感じ。おかげで、安っぽいイミテーションだのパロディが絶え間なく出て来るし、いまやもう「パロディのパロディの、そのまたパロディ」みたいな地点にまで達してる。でも、たとえばUKを例にとってみても――もちろん、音楽はいまだに英国有数の大産業だし、もっとも稼ぐ輸出産業のひとつなんだよ。ただ、そんな国なのに、全国各地で小規模のライヴ・ハウスやクラブ会場が消えつつあって、その存在は風前の灯。代わりに、新たなアリーナ会場が作られてる。
通訳:ああ、そうですよね。
LS:アリーナ公演のチケット代が天井知らずで上がる一方で、200〜300人規模のヴェニューは店じまいしてるわけ。だからなんというか、ギー・ドゥボール的な「スペクタクルの社会」になってる、というか? そこにはプラスチックでにせの「神」的存在が次々担ぎ出され、古風なロックンローラー、それこそテイラー・スウィフトでもいいし、ポール・マッカートニーでもいいけど、その手の重々しい「巨人たち」が登場する、と。ただ、そんな見世物はどう考えてもこっちも即応できる反応的なものじゃないし、観客が参加することも、何か加えることもできない。そこでは何もかも司令部からのお達しに従っているし、すべては大企業型の、こちらを疎外するような中央集権的なノリ。でも、そこが変化するとは、おれは思わないな。というのも、60年代等々の、文化がまだ重要だった時代から遠ざかれば遠ざかるほど、それに対するノスタルジアは強まる一方だろうから。人びとは20世紀半ば以降の半世紀を振り返って、あの頃は文化的に最高な時期だったと思うんだろうし、とくに、ポップやロックンロールといったタイプの音楽に関してはそうだろうね。ただ、あれらは本当にその時代特有の、かつ、当時の社会経済およびテクノロジー状況に固有の音楽であって。つまり、あの頃にはまだ第二次大戦後復興期の若々しい元気さがあったし、ある種のナイーヴさもあったわけで。新たに生まれた各種テクノロジーに対する、子供のあどけなさに近いものもあったし、そうやってラジオやロックンロールのパワーをコントロールしていった若者たちに、まだ企業/体制側も追いついていなかった、と。うん、いまの時代に、それはまったく不可能な話だと思う。
■新作には、ダンサブルな曲がいくつかあります。“What’s That You Say”や“Bullet Of Dignity”のことですが、こうしたエレクトロ・ディスコな曲をやった経緯について教えてください。つまり、あなたはダンス・ミュージックにどんな可能性を見ているのか。
LS:いや、っていうか、おれはDecius(ディーシアス)って名前のダンス・ミュージックのプロジェクトもやってるんだ、パラノイド・ロンドンの奴らと一緒にね。そこではクラシックなハウス〜テクノ系の音楽をやってるよ。でもまあ、ダンス・ミュージックへの傾倒は以前からあったし、何年もの間に自然に、徐々にそっちに向かっていたんだと思う。だから、とくに深く考えてのことじゃないね。たまたまそういう流れだった、と。おれたち、ドナ・サマーのファンだし。
通訳:(笑)彼女は最高です! とにかく『Forgiveness Is Yours』は時代のムードに合っている作品でとても気に入っています。どうも、ありがとうございました。
LS:ありがとう。バイバイ!
序文・質問:野田努(2024年4月25日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン


 DOMMUNE
DOMMUNE