MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー
自分の作品ではあるんですけど、自分という範疇を超えてるものでもあるので。映画って、コントロールできない部分がすごく大きいと思うんですよ。
胸にずしんと響く映画だ。
ママチャリに乗って愉快に声をかけあう若者たち。楽器を背負った彼らは海の見える坂道を駆けのぼっていく。舞台は明石。それまで味気ない日々を送っていた主人公のコウ(富田健太郎)は、強烈な個性を放つバンドマン、ヒー兄(森山未來)と出会ってから、その弟キラ(堀家一希)たちとともに自身でもバンドをはじめていたのだった。そしてそれはいつしかコウの居場所のようものになってもいた。一般常識に縛られないヒー兄の存在はそんなコウたちに刺戟を与えつつも、なにかと目立つその行動は種々の問題を引き起こしていくことにもなる──
かつてどこかで起こったのかもしれない出来事。あるいはもしかしたらいまも列島のいずこかで繰り広げられているのかもしれない光景。何度も登場する「赤」のモティーフが象徴するように、青春映画でありながら幻想的な演出やメタ的な挿入を退けない『i ai』は、現代を舞台にしたおとぎ話のようにも映る。
バンド GEZAN はもちろんのこと、小説の執筆や入場フリー/投げ銭制の大胆なフェス《全感覚祭》の開催、反戦集会の決行など多面的な活躍を見せ、ここ10年ほどで日本のオルタナティヴな音楽シーンを担うひとりとなったマヒトゥ・ザ・ピーポー。今度は、映画だ。初監督作『i ai』は、たとえば「汚い」ものや「危ない」ものが排除されるクリーン志向の今日、もしくは人びとが電子上のコミュニケーションによってホルマリン漬けにされているような現代日本にあって、見過ごせないヒントを多く含んでいる。あるいはこう訴えかけているとも言えるだろう。株式会社に就職したり起業したり、逆に引きこもってモニターを眺めつづけたりすることだけが人生ではないのだ、と。
これまでのマヒトゥ・ザ・ピーポーを知るひとはむろんのこと、いろんなことに悩んでいる20代の方たちにこそ、『i ai』はぜひ観てもらいたい映画だ。(小林)
なんの映画なのかってカテゴライズするのはけっこう難しいかもしれない。ただ、アートの映画にはしたくなかったんですよ。
■もういろんなところで喋っているとは思うのですが、まず、そもそもなぜ映画を撮ろうと思ったのでしょうか?
●小説や音楽はひとりでもやろうと思えばできるけど、映画は予算も人員も規模がまったく異なるよね。
マヒトゥ:まあ、映画の神様に肩を叩かれた、みたいな。
●神秘主義者だよね、マヒトゥ・ザ・ピーポーは(笑)。
マヒトゥ:冗談です(笑)。全感覚祭をやったりして、もうBPM250くらいの勢いでエンジンがかかった状態だったときに、ちょうどコロナのタイミングになってしまって。ライヴも映画館も止まっちゃってなにもできないし、ひとにも会えない状態が続いてくなかで、エネルギーの出し方を探さなきゃエンジンが焼き切れると思ったのがはじまりです。全感覚祭は祭りですが、そのとき祭りにいちばん近いと思ったのが映画だったんですよね。個人の力だけではなく、役者も裏方も、関わるいろいろなひとのエネルギーが立体的に集まってひとつのかたちになっていく点で、映画と祭りは似ているな、と。
●全感覚祭をとおして得た集団作業の経験が大きかったんだ。
マヒトゥ:やっぱり大きいですね。ぜんぶ自分の作品ではあるんですけど、自分という範疇を超えてるものでもあるので。映画って、コントロールできない部分がすごく大きいと思うんですよ。たとえばフィクションだと、その日の天候だったり役者が背負ってきた歴史だったりが反映されるわけじゃないですか。逆にノンフィクションでも、音楽をつけたり都合の悪いシーンをカットしたり演出が入るから、フィクションの要素があるし。その境界って曖昧だと思っていて。そういうふうにコントロールできないもの、自分が自分の外側に広がっていくことに興味があったからかな。
●もともと映画自体を観るのは好きだった?
マヒトゥ:そうですね。総合芸術としてのパワーがありますよね。もちろん音楽もですけど。
●とはいえ映画って気軽に撮れるものではないじゃない?
マヒトゥ:だから、俺けっこう映像作家の友だちとかに嫌われてますよ。普通は、たとえばMVをいっぱい撮ったり、助監督とかでいろいろ経験を積んでから初監督、って流れですけど、スキップしちゃっているから。正面からウザいって言われましたよ(笑)。
●愛情表現じゃないの(笑)。
マヒトゥ:いや、目が笑ってなかった(笑)。
●経験がないからこそできる表現っていうのもあるから。そういう意味でいうと、『i ai』は音楽家っぽいやり方だなと。
マヒトゥ:フリーインプロの衝突を記録するという意味ではそうなんですかね。音楽でも、やっぱファースト・アルバムを出したころには戻れない。経験を積んで知識が増えると成長っていわれがちだけど、それが意外と制限になったりもするじゃないですか。だから映画も、この先絶対ここには戻れなくなるだろうなって思って、ルールでがんじがらめにするようなチームではやらずに、最初はバンド・メンバーや〈十三月〉のチームではじめていった。撮影の佐内正史さん含め、「映画とはこう撮るものだ」っていうルールを持たないひとたちとつくろう、っていうのはありましたね。

ホームレスもスケーターも街の観察者で、ほんとうはそういういろんな視点があることは豊かさなのに、対話に自分のエネルギーを割くのを省いて、楽に自分の欲しい情報だけをいかに早く手に入れるか、みたいな状況が加速している。
●この映画が具現化される、最初の一歩はどこだったんですか?
マヒトゥ:最初にヴィジュアルを撮りました。この(ポスターやチラシに掲載されている)炎のやつ。クラウド・ファンディング用に佐内さんが撮ってくれて。そのあと1か月後くらいに佐内さんから電話がかかってきて「ぼくがムーヴィーまわそうかな」って。その唐突な電話が映画のはじまりです。
●映画を撮るのにどれくらいの期間をかけたんですか?
マヒトゥ:どうだったかな。1年かな。脚本の書き方とか映画監督がなにをやるのかとかは一応わかっていたけど、現場はほぼ見たことがなかったので。豊田利晃監督の『破壊の日』(2020年)って映画に出演したときに現場を見たのが初めてだった。豊田組の「ヨーイ、はい!」の怒号の出し方みたいなのだけはっきり影響受けてます。細胞を起こすための怒号。
■さきほど祭りの延長という話がありましたけど、じっさいに映画をつくってみて、フェスや音楽との違いや新しい発見はありましたか?
マヒトゥ:世に出る速度がぜんぜん違いますよね。ラッパーとかって有事のときの反応がすごく早いよな、って震災のときに思いました。そういうふうに思ったことにすぐリアクションできるのが音楽なんですけど、この映画は公開までに3年ぐらいかかってます。そもそも映画って時代をとらえるような感覚より、もっとプリミティヴな題材に合ってるんだろうなと思ってて。もちろんそれにも時代の空気感とかは含まれるんですけど、『i ai』をつくるときはコロナがいつ明けるかもわからないタイミングだった。だから、もうちょっとそういうものに接近した題材にするっていう手もあったのかもしれないけど、時代の最先端のものって一瞬で過去になって、タイムラインで流されていくじゃないですか。そういうことよりも、永遠に古くならないもののほうがたぶん映画の持ってる資質のなかで重要なんじゃないかな、と。
■ちなみに舞台を兵庫県の明石市にした理由は?
マヒトゥ:俺というより俺らが音楽をはじめるときにいろいろな影響をくれたひと、ヒー兄のモデルになったひとがいた場所だから。自分たちにとっては今回こういうかたちになったけど、それぞれの場所で挑戦してるひとってだれかしらいると思うんですよ。ライターさんでも、自分の前を走ってるひと、かつて見上げてたひとっているだろうし。だからやっぱ、はじめるならこの原風景からかな、っていうので明石に。
●これはもう、下津(光史)君の青春を描いているものとばかり……
マヒトゥ:いや、違う(笑)! それ言うのは野田さんだけ。
●はははは。観ていてすごくメッセージを感じた。要所要所でどちらかといえば映像よりもマヒトくんの言いたいことが前に出てるんじゃないか、ぐらいに思ったんだけど、それはここで繰り広げられているライフスタイルや人間像みたいなものが、現代に対する批評にもなっているからじゃないかな、とぼくは思ったんだよね。さっき「時代性をとらえることはできない」と言ってたけど、ひょっとしたら地方都市のどこかにいまでもああいうやつらがいるかもしれない。
マヒトゥ:いるでしょ。
●ね。そういうライフスタイルって表に出てこないけど、ああいうところにいるんだと。『i ai』には不器用な、世の中とうまく折り合いをつけられないひとたちに対する愛情をすごく感じたんだよね。
マヒトゥ:そこを奪い取られたら、もう自分の軸がわからなくなりますよね。世の中でいう成功とされるものだとか、あるいは逆に自殺しちゃうとかもそうで、「あの人は負けた」「人生だめだった」って烙印を押されることがあると思うんですけど、それでいえばみんな最後は死ぬし、ひとが何人集まったとかCDが何枚売れたとかで数字が積み上がったところで、いったいなんなんだろう? って疑問はつねにありますよ。なんて言ったらいいんだろ……生産性のあるものには価値があって、なにかを生み出せないものには価値がない、みたいな。けど、ヒー兄のモデルになったひとは、自分たちに映画を撮らせるところまでいかせて、いまだに影響を与えていて。それってやっぱ力があるってことだと思うし、数字でいえばただの「一」、たったひとり動かしただけなんだけど、その「一」が横の広がりだけじゃなくて縦の深いところにまで潜っていく。そういうことってメディアに載るときはないものにされてる気がするんですよ。ひとりのひとが感動したっていうことは一万人が感動したことより数は小さいかもしれないけど、ひとりの深度はたしかに存在していて。それは電子の海には乗らない、まだ翻訳しきれないものだと思ってて。それはひとが生きる上での営みにとってはすごく重要で、もちろんAIでは代替できないことだと思う。その愛おしさは、けっして器用・不器用の軸では測れない。そういうものが無価値なものだ、っていう行為を俺は全身全霊で軽蔑します。
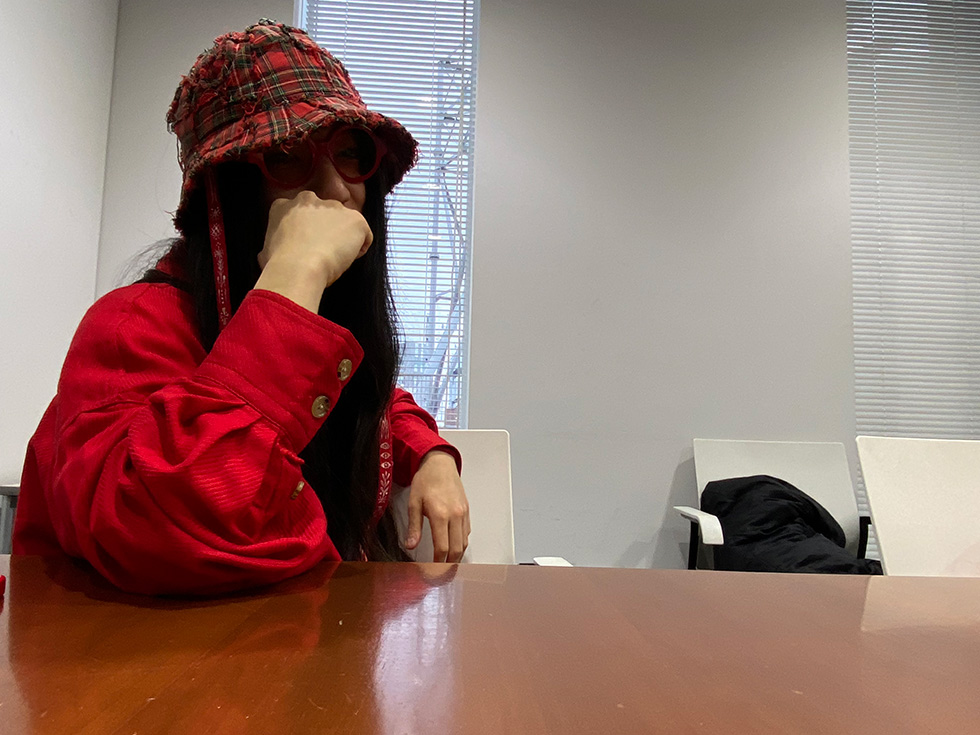
きれいなモデルを見て「わたしもキレイになって、自分に自信を持たなくちゃ」って服を買って真似をして、でもその主導権は事務所側にある。自分がそこにいることを否定させて、資本主義と結びつけてよりお金を生み出すような流れだと思うんですよ。
■印象に残っているシーンのひとつに、ヒー兄がるり姉とつきあうきっかけになった回想の場面があります。ヒー兄は初めて出会ったるり姉を前にして、ケータイもお金も海に投げ捨てる。いまの数字とか価値の話につうじるというか、型にはまらない生き方の体現ですよね。ヒー兄のモデルになった方にも、そういうところがあったんでしょうか。
マヒトゥ:ありましたよ、イーグルから聞いた話ですけど六甲山っていう山があって、心霊スポットなんですけど、そこで夜遊んでて石を持って帰ってきたんです。三日後ぐらいにそのひとと歩いてたら、ぜんぜん知らないおじさんにポンと肩を叩かれて、「石、返せよ」って言われてて。だれもいない真っ暗ななかで遊んでたのに。ヒー兄の説明にはならないけど、そういう引き寄せがたくさんあったひとでしたね。
●ぼくはこの映画を一種のゲットー・ファンタジーだと思ったのね。もちろんリアリズムもありつつ、全体としてはある種のおとぎ話としてもつくられているんじゃないかなと。
マヒトゥ:なんの映画なのかってカテゴライズするのはけっこう難しいかもしれない。ただ、アートの映画にはしたくなかったんですよ。佐内さんとも最初に話したんですけど、「俺らはただ普通に撮ってもねじれるから、まっすぐつくろう」って。みんな奇をてらって、新しいカメラの技法とかいろいろトライしてると思うんですけど、そういうのは他人に任せて、自分たちは気配を撮ろうよ、と。
●役者さんたちもすごくよかったです。みんな素晴らしくて、とくにK-BOMB(笑)。あの演技力!
マヒトゥ:野田さん、K-BOMB好きっすね(笑)。
●(笑)いや、K-BOMBが映画デビューしたってだけでもすごいよ。
マヒトゥ:でも、森山未來さんもすごくて、「あのひとは何者なんだ……」みたいな感じで。俺はああいう「たゆたっている」ようなひとが街にとってすごく重要だと思ってて。たとえばグラフィティもただ街になにか描けばいいわけじゃなくて、あれは視点のゲームなんですよ。「こいつ、こんなところにいたんだ」っていう、「was here」のゲーム。でもグラフィティやってる友だちは最近むなしいわ、って言ってて。みんな携帯ばかり見てて街を見てない。たとえば俺の家の前にもホームレスのおじさんがいるんですけど、街の経過をずっと見てるのってそういうおじさんか、あとはカラスとかネコとかしかいないんですよ。いまはみんなノイズキャンセリングのイヤホンつけて音楽聴いて、移動中もみんな携帯を見てる。その一方で、街の観察者であり定住しない「たゆたう」存在が異なる世界へのレイヤーをまたげることは実体験としてある。だからあの役はK-BOMBさんにやってほしいなと。ただ、たまにクレームがあって、「セリフが地鳴りのように低すぎてなに言ってるか全然聞きとれない」って(笑)。俺はK-BOMBさんの声に耳が慣れすぎてるから全然聞こえるんですけど。
■その話に通じるんですが、ぼくがこの映画でいちばん印象に残っているのが、商店街の入口にある道でヒー兄がおかしくなってふらふらしているときに、カップルが通りかかるところです。女性のほうが心配そうに声をかけようとしたら、男性のほうが「こいつヤバいから」みたいな感じで止める。それに対してヒー兄が「コミュニケーションとろうや」って繰り返す。そういうふうに現代では「普通」から外れた相手とのコミュニケーションを避ける状況がある一方で、逆に現代はものすごくコミュニケーションにあふれた時代だとも思うんですよ。固定電話の時代や手紙を書いて送っていた時代と違って、ケータイや電子メールがあって、さらにスマホが出てきてからはSNSがありソシャゲがありストリーマーもいて、だれもがスマホをいじっていて、コミュニケーションが多すぎる。あのヒー兄のセリフには、そういうコミュニケーションのいろんな層が重なっているように感じたんですよね。
マヒトゥ:ちなみにこの男のほうは神戸薔薇尻っていう、小林勝行というラッパーです。おもしろいひとですよ。コミュニケーションが多いっていうのはそのとおりだと思うんですけど、SNSなんかに溢れてるのは対話ではないと思ってて。対話っておなじ線上で話すことだと思うんですが、いまあふれているコミュニケーションは無数の飛び交う一方通行。俺はどちらかというと、ノイズに感じますね。SNSなんかは顕著ですけど、みんな自分が対話すべき相手のテリトリーみたいなものに自覚的で、線を引いているようなのが多い気がする。対話ってわかりあえないところからはじまるのに、カルチャーの趣味とか政治的な方向性とかでバイアスがあって、自分に都合のいいシーンがつくれる。そういうものに警鐘を鳴らす存在として、以前は街の異端がいたと思うんですけどね。絶対にわかりあえないひとがちゃんといること。政治的に押さえこめるわけではない感じのひとがいること。(『i ai』に)ヤーさんが出てくるのもそういう風景のひとつなんですけど、いまはそういうものが均一に慣らされてる感じを整頓と呼んでる。ホームレスもスケーターも街の観察者で、ほんとうはそういういろんな視点があることは豊かさなのに、対話に自分のエネルギーを割くのを省いて、楽に自分の欲しい情報だけをいかに早く手に入れるか、みたいな状況が加速している。やっぱりみんな疲れてるんだろうな。ある程度はそれでもいいとは思うんですけど、いちばん手放しちゃいけない叫びとか、人間が持ってる存在の揺らぎとか、そこまで省いていっちゃうと人間がデータになっちゃう。それらへの反逆は『i ai』に限らず、俺の全部の表現にあって。
●むちゃくちゃ詰まっているよね。それをちゃんとフィクションで伝えようとしていることはすばらしいと思う。メッセージではなく、物語で伝えようとすることが。
マヒトゥ:壁にぶつかっていくというか、俺はカウンター側じゃないですか。もしかしたらもっと説明的に、もっときれいに筋を立てられるひとがいたらまた違ったのかもしれないけど、そこはべつにいいっすね。
●不完全であることの生々しさもあるよね。
マヒトゥ:そうですね。いまってほんとうにみんなキレイになりすぎてて。写真とかもレタッチが施されてるし。雑誌とかでも、ここのホクロはとるけどこっちは残すとか(笑)。たとえば、すごくきれいなモデルを見て「わたしもキレイになって、自分に自信を持たなくちゃ」って服を買って真似をして、でもその主導権は事務所側にある。自分がそこにいることを否定させて、資本主義と結びつけてよりお金を生み出すような流れだと思うんですよ。でも俺は表現の目的って、そのひとがそこにいることがすべてで、それを肯定することだと思ってて。不完全な気持ちを持っていていいし、不完全であることが許されるような。それが映画や音楽、フロアに求めることでもあるし、自分がそういうものに救われてきたから、完璧を達成することにはあまり興味がないんですよね。広告っぽい映画とか広告っぽい音楽は、だれか他の広告っぽいひとがやればいい。バンドも、俺は隙が残ってる音のほうが好きですね。「こうすべきだ」っていう軸に寄せれば寄せるほど、機械がつくったものと変わらなくなるというか。「生産性だけじゃないんだ」って言ってるやつの音が嘘をついてることもよくあるじゃないですか。そういうのは俺はわかんないです。
●やっぱり現代への批評性があるよ。
マヒトゥ:ムカついてるだけですよ(笑)。
●だからこそ『i ai』は観てほしい映画ですよ。とくにいまの20代には観てほしい。こういう生き方も全然やっていいんだよ、アリなんだよ、ってことを言っている映画じゃないですか。しかも武骨なパンク・バンドが。あと、みんなママチャリで移動するところもいい(笑)。
マヒトゥ:あれはもう、ほんとにイーグル・タカが中学のころから使ってるママチャリで。東京にまで持ってきて使ってるやつをまた向こうに戻して使って。すごい執着があるんですよ。GEZANにはママチャリしかダメってルールがあって。バンドのルールはそれだけで、ほかはなんでもいいんですけど、チャリはカッコいいのに乗っちゃダメっていう(笑)。タイヤ太いのとかも。2ケツできるのが重要なんじゃないですか、ママチャリって。
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE

