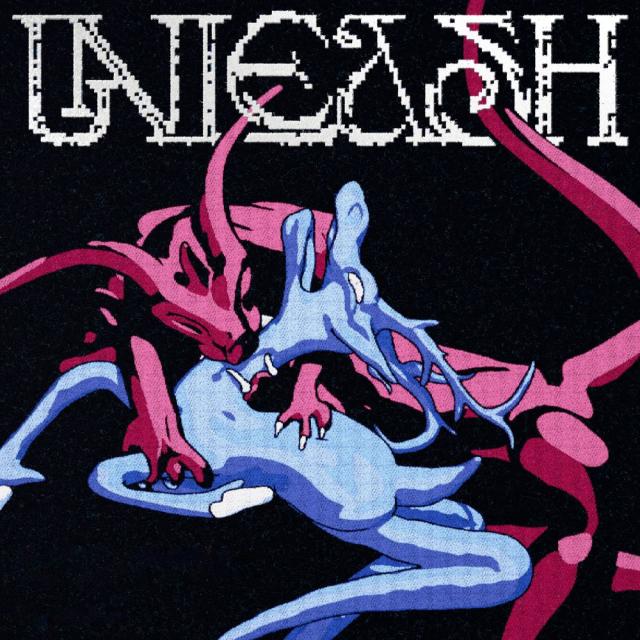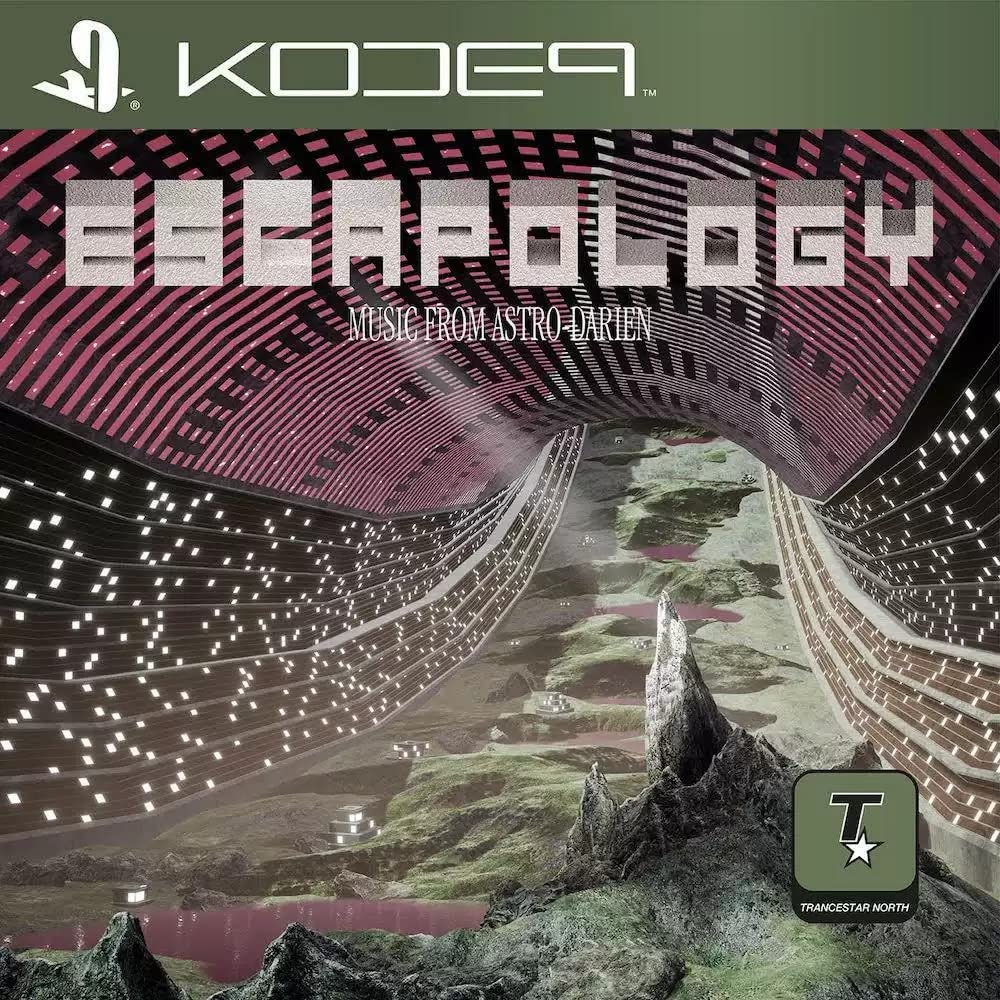MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年
以前はロンドンがベース・ミュージックのセンターだったけど、いまは違っていて、いろいろなところからそれが出てきている。ロンドンはあくまでネットワークのひとつという存在になってきているかな。
最新型の尖ったエレクトロニック・ミュージック、とりわけダンス~ベース寄りのそれを知りたいとき、UKには今日でもチェックすべきインディペンデント・レーベルが無数にある。そのなかでも長きにわたって活動をつづけ、日本における知名度も高いレーベルに〈Hyperdub〉がある。90年代末、当初オンライン・マガジンとしてはじまった〈Hyperdub〉がレーベルとして動き出したのは2004年。今年でちょうど20周年を迎える。
主宰者コード9自身のレコードを発表すべく始動した同レーベルは、すぐさまベリアルというレイヴ・カルチャー=すでに終わってしまったものの幽霊とも呼ぶべき音楽を送り出すことになるわけだけれど、ほかにもアイコニカ、ゾンビー、ダークスターといったおおむね「ダブステップ/ポスト・ダブステップ」なるタームでくくりうる音楽──あるいは90年代から活躍していたケヴィン・マーティンによるさまざまなプロジェクト──のリリースをとおして、10年代頭ころまでにひとつのレーベル・カラーを築きあげていた。
大きな転機となったのはシカゴのフットワーク・プロデューサー、DJラシャドのアルバム『Double Cup』(2013)だったという。ただ他方ではそれと前後し、直截的にダンス・ミュージックというわけではないディーン・ブラント&インガ・コープランドやローレル・ヘイローのような実験的なエレクトロニック・ミュージックの名作を送り出したりもしている。注目すべきアーティストの列が途絶えたことはなく、ジェシー・ランザ、ファティマ・アル・カディリ、リー・ギャンブル、クライン、日本との関連でいえばチップチューンのクオルタ330、独自視点で編まれたゲーム音楽のコンピ、近年の食品まつりなども忘れがたい。なかでもここ数年のレーベルの勢いをもっともよく体現しているのはロレイン・ジェイムズに、そしてアヤだろう。それら一級のカタログはもちろん、アンダーグラウンドな音楽にたいするコード9の鋭い嗅覚によって裏打ちされてきたものだ(かつて南アフリカのゴムを世界じゅうに広めたのも彼である)。
そんな感じでスタイルの幅を広げていった〈Hyperdub〉の姿勢にはしかし、どこか一本太い芯が通っているようにも感じられる。やはりレーベルの根底にダンス・ミュージックが横たわっているからなのだろう、どれほどエクスペリメンタルな作品をリリースしようとも〈Hyperdub〉のディスコグラフィがハイブロウに振り切れることはない。尖りながら大衆に開かれてもいるその絶妙なバランスは、フットワークやジャングル、アフロ・ダンス・サウンドが入り乱れる先月の O-EAST でのコード9のプレイにもよくあらわれていたように思う。とりわけ印象に残っているのは高速化されたDJロランドの “Knights of the Jaguar” だ。いや、あれはほんとにかっこよかった。まるでゲットー・ハウスかフットワークのごとく生まれ変わったそれはヘスク(Hesk)なるDJによるエディットだという。すごいのはコード9なのかロランドなのかヘスクなのかわからない──ダンス・カルチャーにおける反スター主義の好例といえよう。
さらにいえば、そうしたサウンド上の冒険だけに終始しているわけではないところもまた〈Hyperdub〉の魅力だ。以下でも語られているとおり、アヤのようなコンセプチュアルな要素を含む音楽のリリースを考える際には、友人である思想家、故マーク・フィッシャーもきっと気に入ったにちがいないと想像を働かせてみるそうだし、サブレーベルの〈Flatlines〉ではオーディオ・エッセイにとりくんでもいる。ダンス・ミュージックとともに、ものを考えること──まさにそれを追求してきたのが〈Hyperdub〉であり、だからこそ彼らはいまなお最重要レーベルのひとつでありつづけることができているのではないか。
そんな〈Hyperdub〉のボスは現在、ダンス・ミュージックの状況をどのように見ているのだろう。

DJラシャド。あのレコードは人びとに大きな影響を与えたし、DJとしての自分を大きく変えてくれたものでもあった。以降10年間の、自分のDJの方向性を定めてくれたものだった。
■日本はひさびさですよね。何年ぶりですか。
Kode9:2019年の12月以来。そのときは〈Hyperdub〉の15周年で、場所は渋谷WWW だったかな。あと(その翌週に)渋谷ストリームホールでやった《MUTEK》も。
■この5年間でどんどん大きなビルが立ったり、渋谷の街並みはだいぶ変わりました。ひさしぶりに訪れてみてどんな印象を受けましたか?
Kode9:ビルは増えたよね。でも Contact のようなクラブはクローズしてしまったね。代官山 UNIT はどちらかといえばライヴ・ハウスのような感覚が強まった印象だし。東京のクラブ・シーンは少し変わってしまったのかな。
■ロンドンも頻繁に再開発されているんでしょうか。
Kode9:ロンドンのクラブ・シーンは悪くないよ。パンデミック後に若いDJやアーティストがたくさん出てこられるようになって活発だ。すばらしいとまではいえないけれど、ロンドンのクラブ・シーンではつねになにかが起きているような感覚がある。ただ、自分も歳をとってきたから、仕事以外ではあまり出かけなくなってしまったんだけど(笑)。
■あなたは最新のベース・ミュージックにすごく敏感な方だと思うのですが、いまのロンドンで新たな音楽のムーヴメントのようなものは起こっていますか?
Kode9:UKガラージやジャングルのリヴァイヴァルは起こっているね。あと、新しい流れでいうとアフロ・ハウスやアマピアノ、ゴムのようなアフリカのダンス・ミュージックから影響を受けたものが出てきているように思う。UKにとってそれが新しいものかどうかはわからないけれど、少なくとも10年前、15年前よりは色濃くなっていて、それは大きな違いかな。以前はロンドンがベース・ミュージックのセンターだったけど、いまは違っていて、いろいろなところからそれが出てきている。ロンドンはあくまでネットワークのひとつという存在になってきているかな。
それとUKドリルが盛んになっている印象が強くて、それはシカゴ・ドリルのUKヴァージョンではあるんだけど、そういうUKスタイルの音楽が世界的に影響を与えているような気がする。ビートだったり、ベースラインだったり、ラップのスタイルだったり。ほかの都市のローカルな音楽にUKからの影響が見られるものが出てきたと思う。自分にとってもその影響は大きくて、ここ2、3年の動きは2000年代初頭のグライムやダブステップのMCを思い出させるね。自分がDJでかける音楽もいまあげたすべてのものから影響を受けているんだけど、とくにジューク/フットワークだったり、ジャングル、アマピアノとかを自分のまわりのDJグループもジャンルレスにミックスしていて、そうしたものの影響は大きいんじゃないかなと思う。
■O-EASTでのDJセットを体験して、まさにいまおっしゃっていたようなサウンドが印象に残りました。スクリーンに映し出されたヴィジュアルも記憶に残っているのですが、視覚上のテーマもあったのでしょうか?
Kode9:じつは、来日するまでライヴ・プレイをやってほしいと思われていることを知らなかったんだよね(笑)。だからぜんぜんプランがなくて、どうやってオーディオ・ヴィジュアルのショウをやろうかギリギリまで考えたんだ。2日間くらいで。あの演出はヴィジュアル・アーティストの JACKSON kaki と自分との即興に近くて、彼がぼくのDJセットの世界観に合わせたゲーム・アヴァターのようなヴィジュアルをつくってくれたんだ。
■序盤にDJロランドの “Knight of the Jaguar” のテンポを上げて、ゲットー・ハウスのようにかけていたのが強烈でした。
Kode9:あれはDJヘスク(Hesk)のフットワーク・エディットだね。テクノ・ファンなら絶対にわかるトラックだと思ったから、イントロをループで伸ばして盛り上げようかな、と。よく気づいたね(笑)。
取材:小林拓音(2024年2月20日)
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE