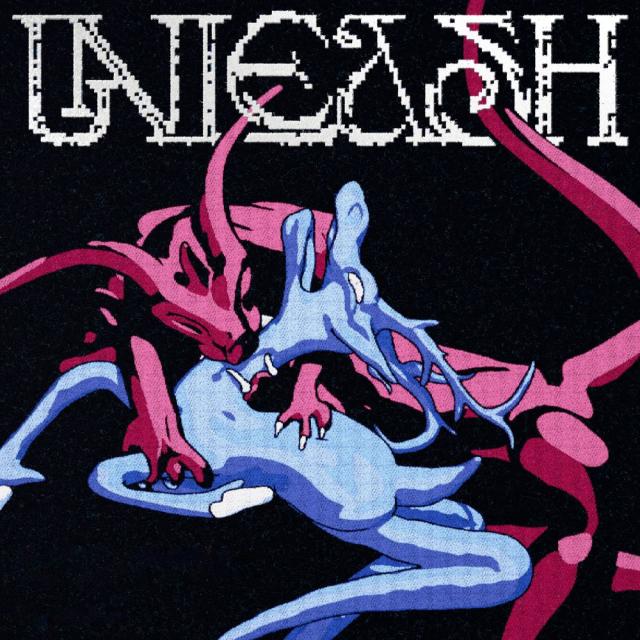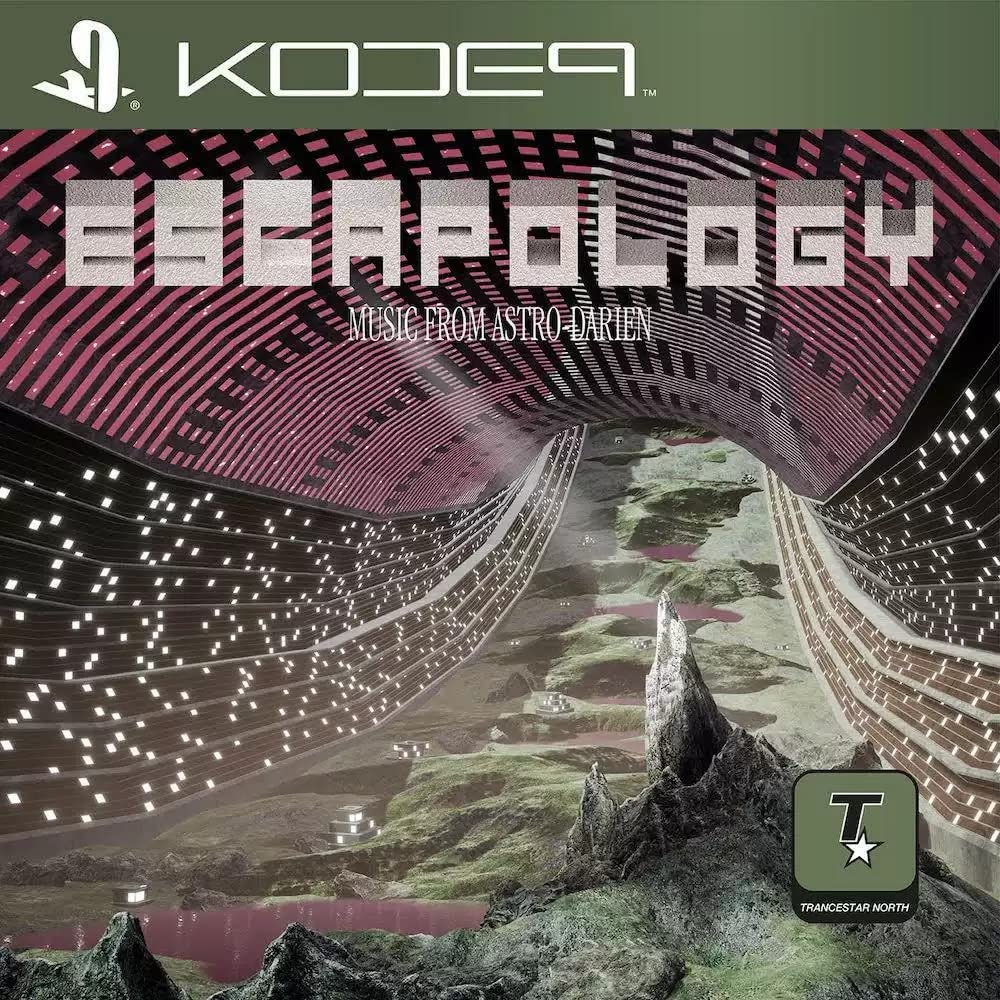MOST READ
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50
- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催
- aus - Eau | アウス
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース
- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio
- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース
- Geese - Getting Killed | ギース
- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門
- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート
- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー
- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜
- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス
Home > Interviews > interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年
いまイギリスでは、音楽雑誌をあまり信用できなくなっていることが問題になっている。メディアの貧困化でジャーナリストたちも稼ぐことができないから、ライティングの質も低下しているんだ。
■今年で〈Hyperdub〉は設立20周年を迎えます。当初はウェブ・マガジンとして発足して、のちにレーベルになっていったわけですが、2004年当時の意気込みと、現在の状況との違いについてお聞かせください。
Kode9:すごく変わったと思う。もともとの目的は自分の音楽をリリースすることだったんだけど、いまは時間がなくてできていないんだ。自分のリリースがないことがまず大きな違いだよね。レーベルをスタートしたあとは自分だけじゃなくベリアルやザ・バグだったり、ダブステップやグライム、UKファンキーなどの作品をリリースするようになって、2009年ごろまではUKが主だったけど、日本のアーティストとも契約するようになってだんだん国際的になっていった。2011年ごろからはダンス・ミュージック以外のローレル・ヘイローだったり(近年の)ロレイン・ジェイムズだったり、ジェシー・ランザのようなポップスにIDM、エクスペリメンタルなアーティストのリリースも増えたし、2012年からはシカゴのフットワークも扱うようになって、ダンス・ミュージックだけでもなく、イギリスだけでもなく、どんどん拡がっていったのが大きな変化かな。
■いちばん大きな転機となったリリースはなんでしたか? できればベリアル以外で。
Kode9:DJラシャド。あのレコードは人びとに大きな影響を与えたし、DJとしての自分を大きく変えてくれたものでもあった。以降10年間の、自分のDJの方向性を定めてくれたものだったし、そこからフットワークやジュークに影響を受けた音楽をプレイしはじめたから、あのリリースがいちばん大きかったかな。そう自分では思ってるよ。
■最近のリリースだと、やはりロレイン・ジェイムズの存在がもっとも大きいのではないかと考えています。彼女の最大の魅力はどこにあると思いますか?
Kode9:彼女の音楽はすごくパーソナルで、親密なものだと思う。内向的なところがいいね。彼女の外向的ではない点はある意味ベリアルとも似ているけれど、やっぱり違っている。ベリアルは姿を見せないけど、彼女はシャイでありながら前に出ていて。そこに人を惹きつける魅力があるのかな。ぼくはシャイなアーティストが好きなんだ。内面を表現しながら成功している人たち。シャイっていうのは音楽の内容にかんして、っていう意味で、彼女は音楽業界のなかでも真摯に、名声なんか関係なく真剣に音楽をつくりつづけている。そこがすばらしいんだ。彼女はシャイでありながらSNSの使い方もうまくて、SNS上でファンとのつながりをもっている点もおもしろいね。みんなをパーソナルな世界に招いて立ち入らせてくれるところはファンも感謝していると思うし、そこですばらしいつながりが築きあげられているんじゃないかな。
■去年出たアルバムでもうひとつ大きかったのはジェシー・ランザかなと思うのですが、彼女は〈Hyperdub〉のなかではポップな路線を担っているアーティストですよね。そこで、あなた個人のポップ・ミュージックの趣味が気になりました。どういうポップ・ミュージックが好きですか?
Kode9:ポップ・ミュージックからは学ぶことが多いんだ。すごく皮肉なことに、ポップスのほうがエクスペリメンタル・ミュージックよりもつくるのが難しいしね。だから、ぼくはKポップやアメリカのR&B、ヒップホップも聴くんだけど、自分にとってポップ・ミュージックは学校みたいなもので、聴くとほんとうに感銘を受けるし、楽しむためというより学ぶために聴いているね。ぼくは音楽教育をいっさい受けてないし楽器も弾けないから、ぜんぶ耳で聴いて楽しむんだけど、ああいったベーシックなハーモニーやキャッチーさを聴いただけで「ワオ!」と感心してしまう。自分にとってそれはすごく新しいものなんだ。
■ele-kingは〈Hyperdub〉のアーティストだと aya にすごく関心があるのですが、次のアルバムは進んでいますか?
Kode9:願わくは、今年じゅうにリリースしたいと思ってるよ。aya は天才だ。コンセプト的にも音楽的にもすばらしいと思うし、パフォーマンスのレヴェルも違う。歌も歌えてラップもできて、ロック・スター的な雰囲気がありつつパンク的なところもあって、アティテュードにあふれているよね。シャイなところとは正反対な感じが彼女の魅力だと思う。
■〈Hyperdub〉はアルバムより尺の短いEPをたくさんリリースしていて、その姿勢からは信念が感じられます。90年代はダンス・ミュージックが12インチをリリースの中心にすることで、アルバム主義を解体しました。〈Hyperdub〉のリリースもその延長線上にあるのではないかとele-kingの編集長は考えているのですが、シングル/EP単位でリリースすることの意義について教えてください。
Kode9:すごく難しいところだけど、まず、レコードのセールスが厳しくなったからデジタルEPをリリースするようになったんだ。ヴァイナルはパンデミック以降つくるのが大変で時間もかかるようになってしまったんだけど、これからはもっとアルバムをしっかり出していきたいと思っているよ。アルバムというのはアーティストの世界観を表現できるフォーマットだけど、EPはそれよりも早くつくれるから、アーティストのそのときのムードや音楽シーンの動向を捉えてリリースできるところが長所だよね。アルバムは制作に時間がかかるからこそ、ステイトメントのようなものを示すのに向いていると思う。逆にEPのスピード感は、レーベルの勢いや現在を捉えてみんなに見せていけるものだね。
マーク・フィッシャーの影響は強く〈Hyperdub〉にも〈Flatlines〉にも残っている。ベリアルや aya のような好きなアーティストたちをリリースするときも、「彼も同じように100%好きだろうな」というイメージのもとで考えるんだ。
■次の質問も編集長から預かってきたものです。90年代に東京で暮らしていたとき、UKのアンダーグラウンドなダンス・ミュージックを知る方法は12インチのシングルを聴くことでした。それらは安価に入手できました。今日ではネットが擡頭し、情報が氾濫してすごくフラットな状況になっています。当時は12インチのヴァイナルが日本とイギリスのアンダーグラウンドにパスのようなものを形成していたのですが、いまはそれが途絶えてしまっているように思えます。どうすれば生き生きとした良質なUKダンス・ミュージックにアクセスできるのでしょうか? その方法があれば教えていただきたいです。
Kode9:まず、いまはそれをやること自体が難しくなってしまったよね。シンプルなものからなにかを得ようとするのは時代的に不可能に近い。すごく複雑化していて、いくらでもリリースの仕方やつくり方がある。バンドキャンプを利用したセルフリリースもあるし、ある種のフィルターやクオリティ・コントロールなしに音楽がどんどん出まわる時代になったわけだよね。インターネットが擡頭してから変わってしまったんだ。昔ならジャングルやドラムンベース、ダブステップだったり、それぞれひとつのシーンがあったけど、いまはシーンというものが中心にドンとあるというよりも、焦点がぼやけて、小さなシーンがほんとうにたくさん存在していると思うんだ。ベッドルームとインターネットが直結しているから、あいだになにも入らない。総数が膨大になったがゆえについていくのが大変になったし、つくり手もみんな(シーンや音楽が)ありすぎて大変なんだ。だから、ほんとうに信頼できるレーベルやウェブ、雑誌を自分なりに決めて、そこに絞るしかないのかなと思う。
いまイギリスでは、音楽雑誌をあまり信用できなくなっていることが問題になっている。メディアの貧困化でジャーナリストたちも稼ぐことができないから、ライティングの質も低下しているんだ。20年前はライターたちがちゃんとフィルタリングして良質な情報を発信していたけれど、いまの音楽業界自体やプレスなども含めて、とにかく情報があふれているから厳しい状況だね。だから、ジャーナリスト側はニュースレターを書くようになった。雑誌に寄稿するのではなく。いまは転換期だと思う。ポッドキャストや配信の場もできているし、書く側も情報を与える側も、これからは自分たち自身で情報を発信できる場をつくっていくことになるかもしれない。信用できる情報は、自分たちで絞っていかなければいけないんだ。
■わたしたちはマーク・フィッシャーの著作を3冊出版しているんですが、彼はあなたについても書いていますよね。あなたはマーク・フィッシャーの文章のどんなところが好きですか?
Kode9:マークとは一緒にPh.D.(博士号)をとった仲で、1996年から2000年にかけて一緒に勉強してきたんだ。ちょうど2、3日前が命日だったな……。彼の影響はものすごく大きくて、たとえば彼は、現代資本主義のように、嫌いなものがはっきりしていた。それへの批判を力強いことばで表現するのが特徴的だった。それは好きな音楽についてもそうで、社会的・政治的に音楽がどう広がっているのかも的確に表現していた。
〈Hyperdub〉のサブレーベルにオーディオ・エッセイやソニック・フィクションをリリースする〈Flatlines〉というのがあるんだけど、そこから2019年にジャスティン・バートンとマークのコラボレイション作品『On Vanishing Land』をリリースしている。その作品は、マークが映画や本について書いた『奇妙なものとぞっとするもの(The Weird and the Eerie)』(原著2016)のアイディアをもとに、(音で)実践したものなんだ。レーベルの〈Flatlines〉の名前もマークが90年代に書いた論文のタイトル「Gothic Flatlines」から来ている。それくらい彼の影響は強く〈Hyperdub〉にも〈Flatlines〉にも残っている。ベリアルや aya のような好きなアーティストたちをリリースするときも、「彼も同じように100%好きだろうな」というイメージのもとで考えるんだ。たとえば、aya はノース・イングランドの出身なんだけど、マークはロンドンの外にある音楽シーンに関心を抱いていたし、彼がつくりあげてきた世界観にフィットするようなアーティストをピックアップすることはいまも意識している。ちなみにオーディオ・エッセイというのは、哲学やフィクション、ラジオ・ドキュメンタリー、ラジオ・ドラマ、エクスペリメンタル・ミュージックのミックスだね。
それと、アーバノミック(Urbanomic)という出版社のエディターであるロビン・マッカイと『ソニック・ファクション(Sonic Faction)』というオーディオ・エッセイについての本を編集したんだけれど、それを数か月後には出す予定だ(https://www.urbanomic.com/book/sonic-faction/)。「ファクション」というのはフィクション(fiction)とファクト(fact)を組み合わせたもの。だから、理論を書いてはそれを音にして、また理論に戻って、また音の作品に落としこんで……というサイクルを繰り返しているね。
■〈Hyperdub〉の2024年はどんな一年になりそうですか? 直近で控えているリリースも含め教えてください。
Kode9:「サヴァイヴァル」だね。20周年を迎えるというのは信じられない(笑)。アルバムをたくさんリリースしたいと考えている。20周年記念のショウケースの予定もたくさんあって、バルセロナのプリマヴェーラ・フェスティヴァルやロンドンのファブリック、オーストラリアのエレヴェイト・フェスティヴァル、フランスのニュイ・ソノール。祝福する場はたくさんあるんだけど、いま小さなレーベルを運営することはすごく複雑で大変なことなんだ。さっき話したようにストリーミングも増えたし、音楽業界自体やジャーナリズムも変わってきているし、それがすべてレーベル運営に影響する。だから、小さいレーベルとしてはサヴァイヴァルになっていくんじゃないかな。生き残りが大変なんだ。ひとりならまだしも、スタッフを3、4名抱えているしね。3月にはシカゴのヘヴィ(Heavee)がDJラシャドの『Double Cup』のようなムードを持ったアルバムをリリースするよ。ロレイン(・ジェイムズ)の前の前のアルバム(『Reflection』)や aya のアルバムにヴォーカルで客演していたアイスボーイ・ヴァイオレットというマンチェスターのラッパー[※UKでは2~3年前から注目されている、アンダーグラウンドで評価の高いMC]のアルバムもリリースする予定。もしできるなら、aya とナザール(Nazar)、DJハラム(Haram)、ティム・リーパー(Tim Reaper)……ぜんぶ出せたらいいな。少なくともヘヴィとアイスボーイ・ヴァイオレットは確実に出すことが決まっているね。
※なお、今回の取材でベリアルの新作が〈XL〉から出たことについて尋ねなかったのは、取材日(1月15日)がその情報が流れるよりも前だったからです。
取材:小林拓音(2024年2月20日)
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー
- interview with Rafael Toral - いま、美しさを取り戻すとき ——ラファエル・トラル、来日直前インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE