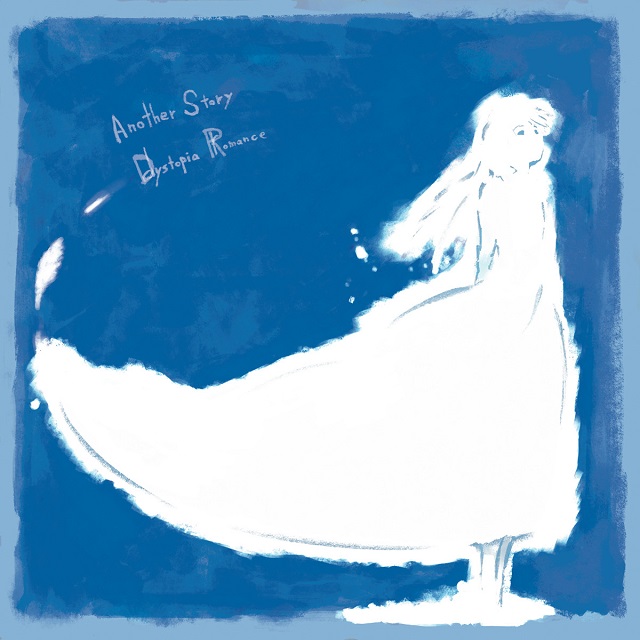MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > 壊れかけのテープレコーダーズ- 楽園から遠く離れて
宇多田ヒカルがシミュレーション仮説に言及したり、コーネリアスこと小山田圭吾がループ量子重力理論的な思考を歌に込めたり、最近、サイエンス・フィクションにかなり近づいた哲学や物理学がポップ・ミュージックの歌詞にも影響するようになっている。それらは、現実の危うさ、不確かさ、頼りなさを積極的に肯定することで、「現実の現実感」や「現実の現実性」を忘却させ、それらに疲弊した存在を慰撫し、そこから逃避させ、この複雑怪奇な現実を生きる者の気持ちをすこし楽にさせる処方箋みたいになっているところがなくもない。「戦争の始まりを知らせる放送も/アクティヴィストの足音も届かない/この部屋にいたい もう少し」(宇多田ヒカル “あなた”)。すべては胡蝶の夢。時間は不連続であり、存在しない。そんなふうに思えたら、どんなに楽だろうか。ブルー・ピルを飲みたい者も、科学や資本主義の糖衣にくるまれたレッド・ピルを選びとりたい者も、結局、そう変わりはないように見える。そういう思考のゲーム的な傾向は現代における一種のブームのようなものにも思えるし、20世紀後半から21世紀という時代における流行だったと22世紀や23世紀の人間は──もしまだ人類という種が、この星を使いつくさずに生きながらえていたら──言うかもしれない。
同時に、まったく無意味な対比であることはわかっていながら、こうも思う。現実の重さや確かさが増してきているのも、また事実だと。現実に起こっている戦争や殺戮は、シミュレーションでもヴァーチャルなものでもない。もちろん、戦争や殺戮だけ/こそがなにか重いものなのだと言いたいわけでもないけれど、そういうものの抗いがたい重みや確実性に打ちひしがれ、押しつぶされそうになりながら歌われる言葉も、一方で存在している。壊れかけのテープレコーダーズの『楽園から遠く離れて』は、まさにそういうことを歌っているレコードだと思う。
壊れかけのテープレコーダーズは、リーダーの小森清貴(ヴォーカル/ギター)を中心に、遊佐春菜(ヴォーカル/オルガン)、shino(ベース)、高橋豚汁(ドラムス)からなるカルテットで、2016年、ドラマーの44Oが脱退したのちに現在のラインナップになった。小森は、大森靖子 & THEピンクトカレフ(2015年に解散)や元昆虫キッズの冷牟田敬のバンドなどでギターを弾いており、ソロ・アーティストとしても活動している。また、遊佐は、Have a Nice Day!の一員としても知られているだろう。ソロでは、〈MY BEST!〉からのインディ・ポップ的な『Spring Has Sprung』(2015年)、〈KiliKiliVilla〉からのエレクトロニックな『Another Story of Dystopia Romance』(2020年)という優れた作品をものにしており、2023年10月にもEP「夏の雫」を上梓したばかりだ。
彼らが〈ハヤシライスレコード〉からリリースした最初のアルバム『聴こえる』(2009年)は、バンド名のとおりのローファイで荒削りなサイケデリック・ロックないしガレージ・ロック・レコードで、1960年代や1970年代の同様の音楽を、あるいは1980年代や1990年代のアンダーグラウンドでインディペンデントなそれを直接的に想起させるものだった。当時、〈ハヤシライス〉は三輪二郎や前野健太の作品も発表しており、いわゆる「東京インディ」のバンド群も現れつつある時期だったが、東高円寺のU.F.O CLUBのムードにぴったりと重なった(この形容が正しいかどうかはわからない)壊れかけのテープレコーダーズの音は、先行世代や同世代の音楽家たちとの狭間で、不思議と遊離したものに聴こえていた。
バンドは、その頃から変わっていないといえば変わっていないし、大きく変わったといえば変わった。前作にあたる6作めのアルバム『End of the Innocent Age』は、不運にも新型コロナウイルス禍のとば口だった2020年5月に発表されていて、なおかつ、これまでになくポップや親しみやすさへの志向性が開花していた作品だった。高橋の加入も影響したのだろう、ファンクやディスコ的な16thフィールの活用など、リズムへのアプローチがまったく異なっていたのも特徴だ。
『楽園から遠く離れて』は、それから4年ぶり、古巣の〈MY BEST!〉を離れて自主レーベルから発表した新作である。端的に言って、これは、彼らのキャリアの中でもっとも素晴らしいレコードだと思う。前作は若干、過度に、無理にポップへ向かっているように聴こえたが、4人は今回、そこでの試みやとりくみを引き継いで反映させつつも、バンドの根っこにある原像を改めて捉えかえして、さらにかき混ぜ、「壊れかけのテープレコーダーズらしい」としか言いようがないロックとして吐きだしている。痛快で、シリアスでありながらも聴き手を突き放さず、軽やかで、かわいらしくて、あたたかくて、どこかかなしげで、人間味にあふれている。
プレス・リリースには、「コロナ禍、相次ぐ戦争、気候変動、、、未曽有の禍が現前する2020年代という時代の中で生まれた全8曲。この現実と向き合いながら生きていくことへの問いと意志を、信じるロック音楽へと込め、鳴らす」とある。4年間の出来事、いままさに起こっていることを直視したリリックは、とはいえ、小森らしく宗教的な言葉や終末的なイメージを挿しこみながら、個人的な視点や具体性よりも、シンボリックで示唆的な面がやはり強調されている。アクチュアルでありながらも、特定の時代性は嗅ぎとれない。失楽園と救済。過去と未来の併置。「映されたノスタルジア/進歩に潜むアイロニー」(“ノスタルジア”)。それでも、このひとつの現実の中で時間は単線的に進み、私たちは未来へと否応なしに押し流されていく。冷めつつも希望をかすかに透かして見るような現状認識は、ceroの髙城晶平が『e o』(2023年)で歌っていたことに重ならなくもない。そして、それらの言葉は、まさに、「死と再生のメロディー」(“梢”)にのせて歌われる。
壊れかけのテープレコーダーズは、「原ロックを求め続ける」という言葉を掲げている。その意味するところを、私はよく理解できていない。ただ、たしかなのは、彼らの音楽が聴く者の深いところに眠っている原初的な記憶や感覚にアクセスしようとすることだ。彼らの歌や演奏には、どこか童謡のような簡潔さや虚飾のなさ、直接性があり、同時になんとも未完成で不器用でもあり、その率直さや純粋さは時におそろしくもある。このアルバムは、その性向が特に強く、だからこそ彼らの最高傑作たりえている。
『楽園から遠く離れて』は、小学生時代の音楽の時間を思いおこさせる。音程の高低差が少ない簡素なメロディ、小森と遊佐のシンプルなユニゾンの歌唱、輪唱、叩きつけるようなあまりにも単純な拍子……。目的の音にめがけてストレートに向かう小森の歌唱も、遊佐のかすれた声も、私にはクラスメイトの歌や有孔ボードが一面に貼られた音楽室の景色を思いださせる。演奏楽器に「オルガン」とわざわざ明記されている遊佐のプレイは、もちろん、サイケデリック・ロックの伝統に連なるものであるのと同時に、オルガンという楽器が明治以降、近代日本における音楽教育で果たしてきた役割の大きさをもう一度意識させるものでもある。あるいは、小森の歌詞とあいまって、当然、キリスト教の世界観も強く喚起させるだろう。
強調しておきたいのは、こういった壊れかけのテープレコーダーズの音楽は、専門的なレッスンによって鍛えられた見事なヴォーカリゼーション(ミックス・ヴォイスやらエッジ・ヴォイスやら)、せわしない転調、複雑な和音の多用、ペンタトニック・スケール、奇妙な構成や変拍子などを好んでつかうことによって特異性を増す一途をたどっているJ-POPの、ちょうど反対項に存在するものである、ということ。
小森は以前、ある小学生の子どもがライヴに来るようになり、最前列で拳をあげて演奏を見ている、と語っていた。このアルバムこそは、そのことを見事に物語っているのではないだろうか。
インタヴューは8年前のものなので、その小学生は下手したら成人しているかもしれない。もっと言うと、壊れかけのテープレコーダーズのライヴにはもう来なくなっているかもしれない。それでも、『楽園から遠く離れて』は、彼/彼女の奥底にあるなにかに語りかけるものをどこかに内包しているはずだ。それに、ここでたびたび歌われている「未来」というものは、疲労感と諦念を浮かべた表情が日常的に貼りついてしまった私たちのためというよりも、むしろ、彼や彼女のためにあるのだから。
天野龍太郎
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE