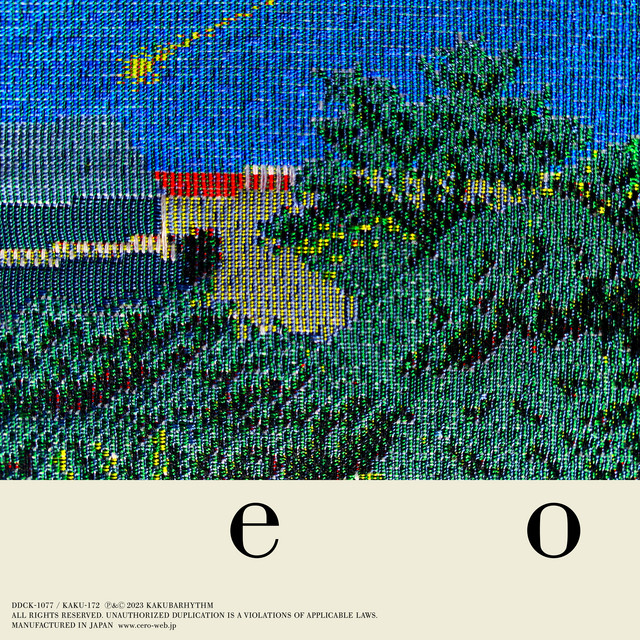MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > cero- e o
過去の真のイメージは、さっとかすめて過ぎてゆく。過去はそれが認識可能となる瞬間にだけひらめいて、もう二度と姿を現すことがない。そのようなイメージとしてしか、確保できないのだ。
歴史とは構成[構造体形成]の対象である。その構成の場は、均質で空虚な時間ではなく、今の時に充ちている時間である。
──ヴァルター・ベンヤミン「歴史の概念について」
小さいようで、大きいアルバムだ。それと同時に、大きいようでいて、なんだか小さいアルバムでもある。
いくつかのインタヴューで語られているとおり、この『e o』が以前の『Obscure Ride』(2015年)や『POLY LIFE MULTI SOUL』(2018年)と大きく異なる点は、プロダクションとその方法にある。制作にあたって、橋本翼が住んでいた吉祥寺のマンションを作業部屋にし、橋本と髙城晶平、荒内佑はそこに集まって、デモを制作していった。そして、後半は、カクバリズムの事務所の一室で同様のことをおこなったという。荒内は「3人とも宅録出身なんで、自然なやり方に戻った感じがしています」と、髙城は「高校生の頃はこんな感じで曲を作ったりしていたな」と振り返っている。
ceroの3人はここで、プレイヤーたちの身体的・肉体的な感覚をレコードに刻みつけるよりも、ホーム・レコーディングとプログラミングを中心にすることを選び、プリプロダクションからポストプロダクションまでをある程度シームレスにつなぐことでアルバムを織りあげた。いかにもバンド然とした演奏は後退して希薄化し、それらとエレクトロニクスとの有機的な接合が試みられており、髙城のヴォーカリゼーションもかなり抑制的だ(「ご近所に迷惑にならないようなレンジで歌う、っていう宅録でのスタンスが引き継がれ」たという)。『e o』を聴けば、原点回帰とも揺り戻しともとれるその小さな場所での小さな制作は、サウンドにおける内的宇宙の見事な伸長と拡大に結実していることがよくわかる。
3人は、このアルバムにコンセプトがなかったことも強調している。だから、断片的な作品だという印象も受ける。かといって、統一感がないわけでもない。ソロ・ワークの寄せ集めといった趣は皆無だし(3人は2020年以降、それぞれソロ活動とアルバム制作をおこなった)、むしろ、一定のクールなムードや空気、あるいは香りのようなものが充満しており、各曲の独立性とアルバムとしての統一性、その両方がある。“Fdf”、“Nemesis”、“Cupola”、“Fuha” という2020年から2022年にかけて断続的に発表されたシングルが収められてもいるが、それらはアルバムという置き場所を得たことで、リリースされたそのときには謎めいていたそれぞれの表情にひとつの解が与えられたような、不思議な座りのよさが感じられる。
なにかとなにかのあわいにあるような、むずがゆくてはっきりとしない、半醒半睡の、半酔の、靄がかかったような、中間的な領域をずっと漂っているような音。そうであるからこそ、「プラネタリーな規模と心の次元が結びついて織り合わさってるような」、マクロとミクロとを瞬時に行き来することができるような、自由に飛び跳ねる音。
髙城のリリックも、こういった変化にそのまま対応している。再びインタヴューの発言を引くと、『e o』で歌われているのは、これまでのように叙事性や物語性を志向したものではなく、「リニアに時間が展開していくよりも、意味を切断していくような『詩』らしい広がり方を」を持った、「香水のような」歌詞である。
極端なジャンプカットの連続のような、紙芝居のような、スナップショットの束のような、「ひどく粗いゲーム画面」(“Epigraph”)か「絡み合うタペストリー」(“Nemesis”)のような、跳躍を続ける言葉、そしてそれらが描く(少々 sci-fi な)イメージ。かといって、抽象的だったり、心象的だったりするばかりではない。「素粒子の精霊は観測者を待つ」(“Epigraph”)。「人新世の霊と 枯れた花のゲート」(“Fuha”)。「兵隊たちにインタビュー/乱れる映像」(“Evening News”)。『e o』で髙城は、まちがいなく私たちがいま生きているこの世界のことを、奇妙な手触りをもった言葉で歌っている。
髙城の断片的な詞は、その形式においても内容においても、圧縮され凝固された時間のようだ。注目すべきは、imdkm も指摘するように、アルバムのクローザーである“Angelus Novus”があきらかにヴァルター・ベンヤミンの「歴史の概念について」へのオマージュになっていること。この曲は、オープナーの “Epigraph” とともに、ベンヤミンの歴史や時間についての思惟と少なからぬ共振を見せている。
ベンヤミンは1940年、ナチスに追われて滞在中のパリから脱出し、スペインに逃れようと試みるが、9月にピレネー山中でモルヒネで自死している。「歴史の概念について」は、彼が最期まで手を加えていたという、十数のテーゼからなる原稿だ。そこでベンヤミンは、因果関係によって歴史を書く「歴史主義」や進歩史観を強く批判しながら、彼なりの史的唯物論を展開している。それは、平たく言えば、「今の時に充ちている時間」のポテンシャルにかけるような思考だ。抑圧された過去が現在と不意に出会い、星座的な布置をなし、現在を突然に変容させてしまう──ベンヤミンは「歴史の連続体を爆砕して過去を取りだす」という言い方もしているが、それが「今の時に充ちている時間」という(革命的な)チャンスである。
叙事的な語りや連続的な歴史観を捨ててそこから飛び出すことは、上で引いたとおり、『e o』における髙城の詞作の方法と相似形を描いている。「真新しいものがなくなり/ようやく静けさの中ページが開く」(“Epigraph”)というラインは、ベンヤミン的な歴史や時間に対する態度の一端を言い表しているかのようだ。
それは、音楽的にもそうである。『e o』は、『Obscure Ride』におけるネオ・ソウルや『POLY LIFE MULTI SOUL』におけるリズムの実験といった、わかりやすい参照点を持っていない。ここにある音楽は、溝にハマって離れることのないグルーヴ、あるいはリズムの交差が生み出す興奮ではなく、楽音や電子音などの多彩な要素が絡まりあい、冷静に構成された、一瞬の閃きや煌めきからなる複雑な織物である。
「歴史の概念について」は、ベンヤミンが執筆当時に置かれた状況を考えてもわかるとおり、けっしてオプティミスティックなものではない。それでも、そこには、私たちの中に潜性している「かすかなメシア的な力」にかける意志がある。「嵐がくる/楽園から吹きつける/透明な未来」(“Angelus Novus”)と歌って終わる『e o』には私たちが押し流されていく先にある未来へわずかに期待をかけるような、小さく冷静なオプティミズムが感じられる。未来は真っ白なブランクでしかないが、絵に描いたような未来に向かって単線的に進んでいくのではないかたちで、それをのぞみ求める、というような。
41分9秒というランニング・タイムは、cero のアルバム・ディスコグラフィの中でもっとも短い。けれども、その時間には、これまででもっとも濃密で、豊かで、深遠で、複層的な音と詞が封じ込められている。だから、奇妙なルールに支配された分厚いゲーム・ブックで遊ぶように、たくさん折り重なった襞の中に分け入っていくように、薄明かりが射し込む部屋に散らばったなにかを手探りするように、私は今日もまた『e o』に耳を傾けている。
■引用・参考文献
ヴァルター・ベンヤミン『[新訳・評注]歴史の概念について』鹿島徹訳・評注、未來社、2015年。
天野龍太郎
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE