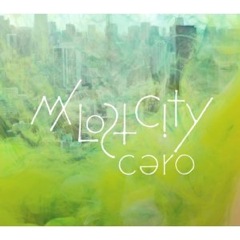MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Cero- My Lost City
街中がひっくり返ったような、東北地方の変わり果てた港町。その破壊のイメージが未だに私を離さない。比喩でもなんでもない、街は失われてしまった......と同時に、その街の記憶を持つ人びともまた、あるいは失われてしまったのだと思うと、奇妙な戦慄があった。完結してしまった喪失というものは、語り手を持たないものなのだと。
私たちが放り込まれた「以後」の世界は、完結していない喪失が進行と回復を繰り返しているようなややこしい場所だ。もちろん、死や別れは最初から私たちの人生のオプションだし、その意味では何も変わっていないという言い方もできるだろう。だが、やはり、多くの人が見る世界の在り方が大きく書き換えられたのは間違いないと思う。
その点、セロもたしかに、変わった。少なくとも、この新作『My Lost City』は、東京をもう以前とは違う(あるいは失われた)街と呼ぶことで生まれている。だが、ここには喪失を直視したことによって生じ得る重苦しさの類は、いっさいない。彼らは祝祭を継続する道を選んだのだ。いわば、現実に対する非服従としてのポップ・ミュージックを奏でている。喪失と、祝祭を、同時に引き受けることによって、それは高らかに鳴っている。
"大停電の夜に"が持った奇妙な予見性、そして、『WORLD RECORD』(2011)がそれと同時に持った同時代的な切迫感との乖離。そのギャップが彼らを苦しめていたことを、私は知らなかった。「でも、その時、村上春樹が『海辺のカフカ』で「想像の世界においても、人は責任を負わなければならない」というようなことを書いていたなって、頭をよぎったんです。(http://www.kakubarhythm.com/special/mylostcity/)」――そう、セロは、より強力な物語を立ち上げることで、虚構の作り手としての責任を引き受けたのだろう。
より大きな現実には、より大きな虚構を。"水平線のバラード"のア・カペラで導入され、以降、賑やかに、カラフルに、48分が目まぐるしく展開していく。何かヘヴィなものを振り切るように、ある種の切実さを持って、『My Lost City』は明確に祝祭性を志向する。現実からもっともっと遠く離れて。悲観や感傷ではなく、さらに大きな、情熱的なファンファーレで、「以後」の世界に生きる人びとを迎え入れている。
音楽としてのスケールも遥かに大きくなっているように思う。はっぴいえんど、鈴木恵一、ジャズ、ファンク、合唱、テクノ、キューバ音楽......打楽器にしても、金管にしても、鍵盤打楽器にしても、1曲のなかでも目まぐるしくシャッフルされ、特に演劇仕立てのプログレッシブ・ポップな展開を見せる"船上パーティー"は中盤のハイライトとなる。
また、セロ a.k.a. Contemporary Exotica Rock Orchestraというネーミングは実に的確で、チェンバー・フォーク的な緻密さと、ストリート・バンド的な豪快さを兼ね備えたムードがあり、何より、『My Lost City』からはたくさんの人の気配がする。スティールパンやトランペットで参加しているMC.sirafu、ドラムス、サックスで参加しているあだち麗三郎らは事実上のバンド・メンバーのようで、演奏のクレジットは賑やかなことになっている。
そう、音楽を作ることがあまりにも簡単になったこの時代に、数分のポップ・ソングのために数十人が集まっている。その光景を想像するだけでも感動的である。ルー・リードのクラシック"A Walk on the Wild Side"(1972)をトロピカル・サイケ・ポップにリアレンジしたような"cloud nine"、合唱に包まれながら、幽霊船に乗って暗闇の中を突き進む"Contemporary Tokyo Cruise"、そしてアルバム本編の実質的なエンディングを飾る"さん!"の底なしの多幸感には、私は小沢健二を感じた。
しかし『My Lost City』は、そこで終わらない(終わっていれば、いわゆる出来過ぎた「名盤」である)。"わたしのすがた"で、物語の主人公は現実の東京に戻っている。虚構の旅を終え、CDと文庫本でぐちゃぐちゃになった狭い部屋で、現実に思いを馳せる彼は、『My Lost City』を聴き終えたあなたそのものだ。そこで何を思う? 音楽で盛り上がったところで、「この街」は変わらない。そうした無力感とも取れる感情を吐き出し、『My Lost City』は、エレクトロニックな閉塞感とともに、ある意味では汚い終わり方をする。
ポップ・ミュージックが多くの人を熱狂的にアップリフトさせる時代は終わったし、その不可能性に逆に陶酔するというシニシズムの時代も終わったのだと思うが、それを自覚した上で、個人以上/社会未満としての都市(シティー)の気分や気配を、そのまま音楽にしてしまうことを、セロは諦めていない。それでも、"わたしのすがた"が生まれなくてはならなかった(あるいは録音されなければならなかった)理由を考えると、なんともアンビヴァレントな気持ちになる、、、。
少し話を変えよう。『My Lost City』が持つ意味について。筆者は昨年、「スモール・ミュージック」という言葉でこの国のあまり売れていない(だが素晴らしいと思える)音楽を形容したけれども、これは、かつて本誌編集長がロバート・クリストガウを引用する形で紹介した「セミ・ポップ」という概念とは少し違う。細分化に対して下位層に潜るのではなく、そこがどれほど狭い場所であれ、堂々とポップの可能性にベットする音楽――『ピッチフォーク』の表記に倣えばスモール・ポップ――の時代は、欧米ではアーケード・ファイアの『Funeral』(2004)で始まっているが、『My Lost City』はつまり、この国のインディ・ポップにおける始まりのはじまりである。
また、地球儀を軽くスピンするようなその豊かな音楽性を踏まえれば、『Illinois』(2005)前後のスフィアン・スティーヴンスに対する「風街」からの回答とも言えるし、あるいは、90年代に『LIFE』があったのなら、私たちの時代にはこれがある、『My Lost City』はそういう作品だ。奇跡のようなポップの現象はもう、このさき生まれ得ないのだろう。だが、奇跡をともに願える仲間を、セロは見つけたようだ。それもまた、小さな奇跡なのではないだろうか。「いかないで、光よ/わたしたちはここにいます」("Contemporary Tokyo Cruise")――この祝祭は、きっと徒花ではないし、ひとりの天才が作り上げた孤城でもない。枯死していく風景の中に浮かび上がる、輝かしい宴の虚像。この時代を笑顔で生きようとする人びとに捧げられた、巨大な祈りとしての音楽が、ここにある。
竹内正太郎
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE