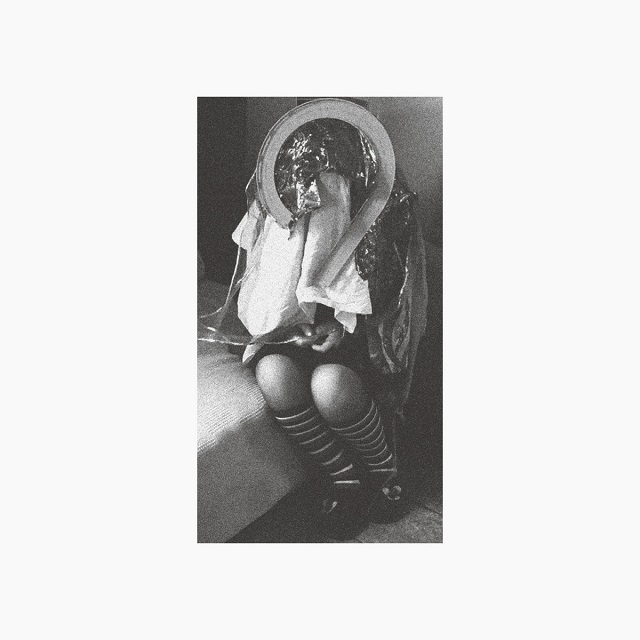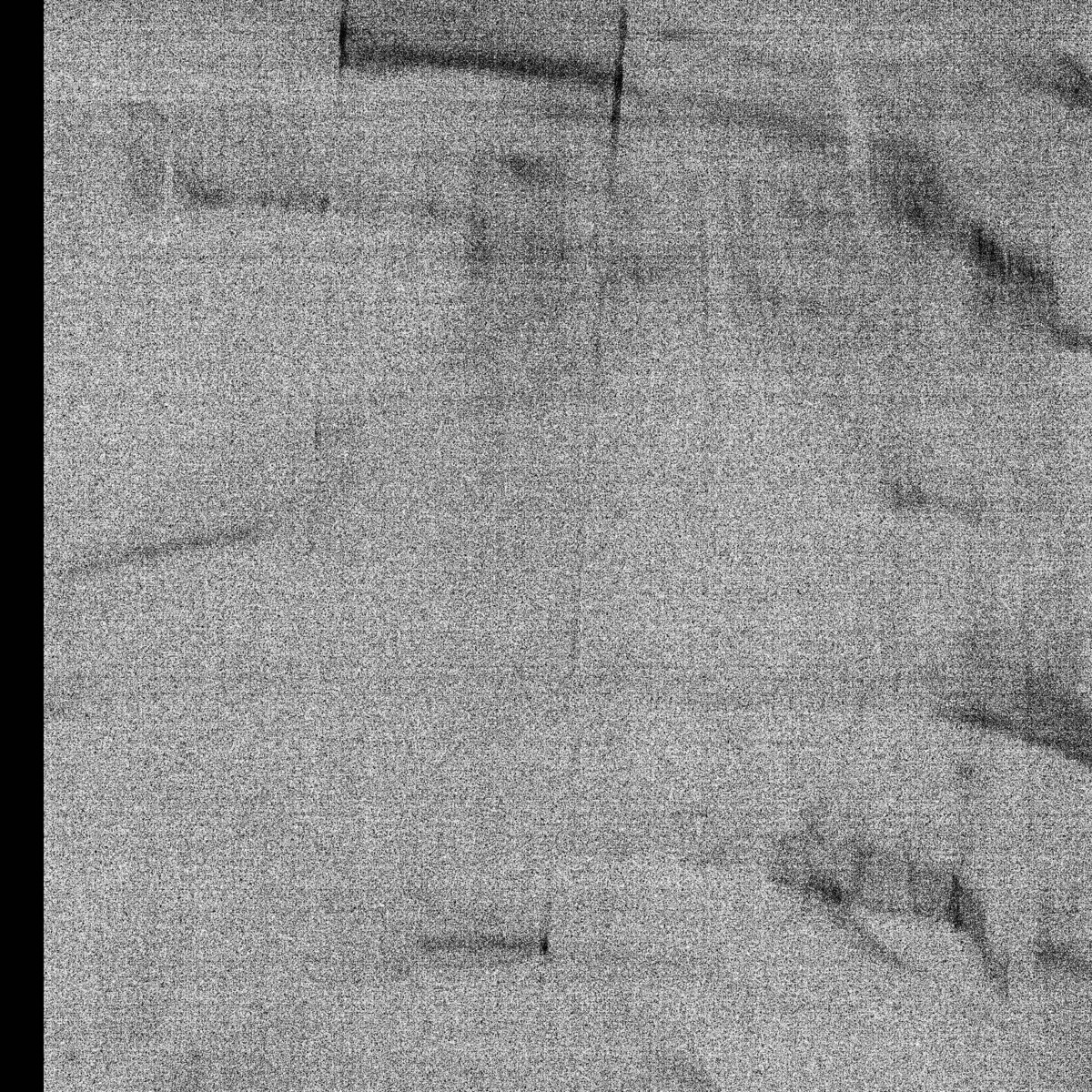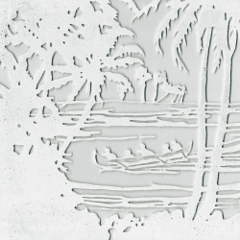MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Natalie Beridze- If We Could Hear
ジョージアはトビリシのナタリー・ベリツェはエレクトロニック・ミュージックのクリエイターであり、エレクトロニカ・アーティストであり、アンビエント・アーティストであり、サウンド・アーティストでもあり、モダン・クラシカルな音楽の作曲家でもある。その活動と楽曲は横断的であり、坂本龍一とのコラボレーションでも知られている。まさにジョージアのエレクトロニック・ミュージックのパイオニアといってもよいだろう。
00年代のナタリー・ベリツェは、トーマス・ブリンクマンが主宰するレーベル〈Max Ernst〉などからミニマル/グリッチなエレクトロニカを奏でる TBA としてアルバムをリリースもしていた。00年代末期以降は、一転として、ナタリー・ベリツェ名義でモダン・クラシカルで、アンビエントで、エクスペリメンタルな音楽を生み出していく。
とはいえこの名義自体は流動的のようで、TBA Empty 名義でのリリースもあるし、TBA 末期の頃はナタリー・ベリツェと両名表記になっていた。そもそもバンドキャンプでは TBA 名義時代のアルバムもまとめて配信されている。ナタリー・ベリツェ名義は、2016年にベルリンのレーベル〈Monika Enterprise〉からのアルバム『Guliagava』からだろうか。
近年のナタリー・ベリツェの重要なアルバムは、何といっても2022年にローレンス・イングリッシュが主宰する〈Room40〉からリリースされた『Of Which One Knows』だろう。この『Of Which One Knows』を発表したことで、現代のエクスペリメンタル・ミュージック・シーンに見事に切り込んだように思える。実験的な電子音と現代音楽風の弦楽の交錯は、まさにモダン・クラシカルの先端といえよう。
本作『If We Could Hear』は、基本的には『Of Which One Knows』と同系統の作風である。クラシカルなムードと実験的で不安定な音響がアルバムの中に混在しているサウンドスケープだ。なによりその「声」を中心にサウンドを構成している点が重要だ。
以前の『Of Which One Knows』と同様に本作『If We Could Hear』でもローレンス・イングリッシュが「ポスト・プロダクション」として参加しており、サウンド面ではイングリッシュとの「共作」という側面も強いのかもしれない。
しかし自分がこの『If We Could Hear』で注目したい点は、ナタリー・ベリツェの「作曲家」としての力量がこれまでの作品以上に発揮されていることにある。あえて例えるなら2009年に TBA _ Natalie Beridze 名義でリリースされた『Pending』収録曲 “Iced Turns End” (名曲です)などで聴かれた哀愁に満ちたエレクトロニカ楽曲をモダン・クラシカルな編成・アレンジで表現し切ったとでもいうべきだろうか。
特に2曲め “Who hugs terrain of comets” と3曲め “Who wakes the dawn” には驚いた。どこかレクイエムのような美しい旋律と和声が筆舌に尽くしがたい美しさを放ってた。決して大袈裟にならずに、繊細な音程の変化と移動は、このアーティストの知られざる音楽家としても才能をより表面化しているといえよう。
アルバム1曲め “Who hears it all” では不安定なノイズと声が提示され、不穏なアルバムのトーンを印象付けるが、続く2曲め “Who hugs terrain of comets” と3曲め “Who wakes the dawn” でクラシカルな作曲家としての力量を見せつけることで、アルバムの世界を押し広げていく、そんな印象を強く持ったのだ。
とはいえ現代のレクイエムのような微かな悲哀に満ちた音楽は、2曲め “Who hugs terrain of comets” と3曲め “Who wakes the dawn” がメインである。以降も曲は、エクスペリメンタルなサウドへと回帰しつつ、そこにうっすらと旋律の断片や声のカーテンのような響きがレイヤーされていくようになる。なかでも4曲め “Who whispers to hysteria” は、本作の過激な面を象徴するような曲である。「叫び」のような声のレイヤーをリズミックに繰り返す楽曲を展開している。
全7曲を聴き終えると、このアルバムは組曲構成のように思えた。じっさい「Who」という言葉で冒頭についた曲名が5曲続くことからも、連続性のようなものを意識しているのではないか。以降の2曲も、「Who〜」組曲(?)で展開された音響・音楽の要素を、まるで落ち葉拾いのように展開している。
特に最終曲 “And it’s countless expressions” に注目したい。本作の重要な音響的な要素である霧のようなノイズ、声の透明なレイヤー、夢と現実のあわいに溶け合ってしまうような不穏な響きが交錯する曲・音響となっているのだ。まさにアルバムのラストを飾るにふさわしい象徴的な音楽といえる。
全編、不安定な音響・ノイズと透明感に満ちた音楽・音響が交錯している。無調音楽と調性音楽の間を行き来するような音楽性とでもいうべきか。現在という時代においては、ただ不安定なだけでは希望がないし、逆にただ整合性のある響きだけでも物足りない。この「ふたつ」が必要なのだ。 この『If We Could Hear』は、まさにそんなアルバムなのだ。ノイズのうごめきと、レクイエムのような透明な響きが「同時に」交錯している。この『If We Could Hear』は、いまの「世界」そのもののように不安と不穏と希望の間で揺れているのである。
坂本龍一とも共演歴のあるナタリー・ベリツェだが、坂本龍一が存命で、もしも本作『If We Could Hear』を聴いたら、とても評価したのではないかと妄想してしまう。それほどまでに『If We Could Hear』では、ナタリー・ベリツェの音楽家としての力量、そして風格が増しているのだ。じつに記念すべき、そして充実した内容を誇るモダン・クラシカル/エクスペリメンタルなアルバムなのである。
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE