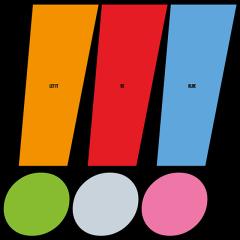DJイベントでもなんでも、そこにコンピューマの名前を見つける確率は、彼が仲間たちと精力的にライヴ活動をしていた90年代よりも、ゼロ年代以降、いや、テン年代以降のほうが高いだろう。年を追うごとにブッキングの数が増えることは、近年のアンダーグラウンドにおいては決して珍しい話ではない。シカゴのRP Booやデトロイトのデラーノ・スミスやリック・ウィルハイトのように、大器晩成型というか、年を重ねてから作品を発表する人も少なくなかったりする。ことにDJの世界は、ミックスの技術やセンスもさることながら、やはり音楽作品に関する知識量も重要だ。ゆえにコンピューマのDJの場が彼の年齢に比例して多くなることは、シリアスに音楽を捉えているシーンが日本にはあるという証左にもなる。
とはいえ、そうした文化をサポートするシステムや人たちが大勢いる欧米と違って、この国でアンダーグラウンドな活動を長いあいだ続けることはそれなりにタフであって、だからコンピューマのようなDJはいままさにその道を切り拓いているひとりでもあるのだ。先日、アルバム『A View』を発表した松永耕一に、まあせっかくだし、これまでの活動を思い切り振り返ってもらった。
当時はそれを世に出すなんてことはとてもじゃないですが考えたことなかったです。「チェック・ユア・マイク」にはバイト仲間の友だちと一緒に応募しましたが、テープの段階で見事に落ちてました(笑)。
■音楽活動をはじめてからいま何年目ですか?
松永:音楽活動は、バンド/グループのメンバーとして参加したのはADS(Asteroid Desert Songs)が初めてです。1994年末にADSイベントをはじめて、作品を出したのが確か1995〜6年にEPミニ・アルバムを出してますので、その頃から音楽活動をはじめたということになるのではないかと思います。
■ADS( Asteroid Desert Songs)がきっかけだった?
松永:バンドやグループに入って、自分自身が何か楽器を演奏して音を奏でるっていうことは、それまではあまり考えたことがなかったんです。どうにもリスナー気質で、DJはやりたいと思っていましたが。そう、だから聴くの専門で、ただ高校時代ダンス・ミュージックのメガミックスが流行ったり、メジャーの音楽でもホール&オーツでのアーサー・ベイカーのリミックスなどを知ってからは、自宅でラジカセでカセットテープを切り貼りしてみて、下手くそながら連打エディットにトライしてみたり、強引にカットイン繋いだりしてみたり、もちろん遊びの延長で全然上手くできないんですが、雰囲気や気持ちだけは(笑)。
その後上京して、コールドカットや「Lesson 3」などヒップホップ的メガミックスを知ってから、学生時代に4トラックMTRを使ってトラック作りの真似事やコラージュミックスなどを下手っぴで作ったりしたことはありましたけど、当時はそれを世に出すなんてことはとてもじゃないですが考えたことなかったです。〈チェック・ユア・マイク〉(※90年代初頭にはじまったECD主催のヒップホップのコンテスト)にはバイト仲間の友だちと一緒に応募しましたが、テープの段階で見事に落ちてました(笑)。
そういうこともオタクDJの延長でやってました。なので、まさか自分がバンド/グループに関わって何か作品を出すことになるなんてことは思ってもいませんでした。
■ヒップホップが大きかったんですか?
松永:リスナーの延長線上でも身近に音として戯れられるというか、こういう音の組み合わせにしたら何か新たな発見や楽しみ方ができたりワクワクしたのはあの時代に出会ったヒップホップ的ミックス感覚でした。大好きで影響を受けたのは、いとうせいこう/ヤン富田/DUB MATER X『MESS/AGE』、KLF『Chill Out』に『Space』、デ・ラ・ソウルの1stと2nd、ジャングル・ブラザース、パブリック・エネミー、そしてジ・オーブも。グレイス・ジョーンズ『Slave to the Rhythm』、マルコム・マクラレン『Duck Rock』などもあらためて……こういった作品やアーティストのセンスとユーモア、コラージュ感覚にとても惹かれました。クリスチャン・マークレイの存在もこの時期に知ってさらに世界が広がりました。あとは細野晴臣さん責任編集の季刊音楽誌『H2』の存在も大きいです。
■KLFの『Chill Out』と『Space』が出てきたのは、その後のコンピューマの作風を考えてると腑に落ちますね。
松永:大胆なコラージュ感覚とか、惹かれました。アート・オブ・ノイズも大好きでした。
■本当にサウンド・コラージュが好きだったんだね。
松永:いま訊かれて気付いたんですけど(笑)。そういう組み合わせの心地よさを無意識に感じていたんでしょうね。学生時代の音楽仲間と、いろんなジャンルのレコードのビートレスの曲のみでノンビートに近いDJミックスを作ったりしていたことも思い出しました。
■10代のころ好きだったレコードを挙げるとしたら?
松永:PiL「Public Image」『Metal Box』『This Is What You Want…』、アート・オブ・ノイズ『Who’s Afraid Of The Art Of Noise』『Moment In Love』、プロパガンダ、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドまで〈ZTT〉ものが好きでした。
■東京出てきてからの方が音楽にハマった感じ?
松永:インターネットもまだなかったですし、当時の同じ地方出身者同様に、熊本での限られた情報のなかで雑誌やラジオ、テレビを聴いたり見たりしながら、ラジオ短波でエアチェックしていた大貫憲章さんの全英トップ20だったり、NHKサウンドストリートだったり、音楽雑誌で紹介されてるアルバムを聴いていました。ただ、小遣いも限りがあるし、いわゆる田舎の普通の高校生の趣味の範疇での世界で、情熱はありつつも、そこまで深追いはできてなかったのではないかと思います。
思いだすのは、高校入学してすぐに仲良くなった音楽に詳しかった同級生から、彼の寮の部屋でペンギン・カフェ・オーケストラやブライアン・イーノを教えてもらったりして、衝撃を受けたりしてました。環境音楽? アンビエント? こんな音楽もあるんだとか。ヒップホップも、好きだったPiL経由で“World Destruction”を知って、アフリカ・バンバータの存在を認識しました。で、ジャケットがカッコよかった「Renegade Of Funk」の12インチを買ったり……。コールドカットのようなメガミックスものをちゃんと知るのは80年代後半に東京に出てきてからです。そこからまた新たな音楽世界を知っていくことが日々楽しくて楽しくて、友だちとレコード屋行きまくって、もちろん一人でも。当時は試聴もできなかったからレコードのジャケの雰囲気や裏面、見れたら盤面クレジットを舐めるように見て妄想して買ってみて、当たることもあれば、まったく予想と違っていたり、外したり……。ただ、そのときには聴いてよくわからなくても何とかわかろうとする気持ちというか、何度も聴いてみて、そこから新たな発見したりしなかったり……。買ったあろにあーだこうだと語り合ったり、お金もあまりないからレア盤はなかなか買えないし、とにかく安いレコードを買いまくって、そこから新たなグルーヴやあえてビートのない部分でかっこいいパートを探したりもしてました。コラージュするために(笑)。
■面白いですね(笑)。
松永:とにかく安く中古レコードを売っているお店に行って、ネタが見つかったらすかさず報告しあう。みたいなことをやってました(笑)。
■バイトは?
松永:当時、埼玉県の川越にあった〈G7〉っていうローカルなレンタル・レコード屋さんです。国内盤だけじゃなくて、輸入盤のCDやLP、12"、日本のインディも扱ってました。ヴィデオ・レンタルもやっていたり、なかなかマニアックなものが揃っていましたと思います。そこでの経験や出会った先輩や同僚、みなさんからの影響が大きかったです。
■ADSは〈WAVE〉(※80年代から90年代まであって西武資本の大型輸入盤店、当時は影響力があった)で働くようになってから?
松永:そうですね、〈WAVE〉に入ってからですね。ただ、ADSのイベントの初期では、〈G7〉時代の友だちにも手伝ってもらったりしてました。
■〈WAVE〉で働くきっかけは?
松永:就職活動の時期、1990年に『ミュージック・マガジン』に〈WAVE〉の社員募集の広告が出ていたんです。〈WAVE〉には当時憧れていたし、よく通ってもいたので応募して、面接も何度かあったりしました。社員入社して……、ちょうどその頃、ヒップホップやダンス・ミュージックを経た新しいタイプの音楽がどんどん登場するような時代だったので。なんとなくですが、自分もそういう新しい音楽をいろいろ紹介できるといいな、という夢を漠然とではありましたが、何となく描いていました。
■担当はどこだったでんすか?
松永:入社してすぐは〈WAVE〉の店舗ではなく〈ディスクポート〉という百貨店のなかにあるいわゆるレコード屋コーナーの店舗に配属されて、そのときの上司にお願いしまくって入社2年目にようやく渋谷のLOFTの1階の路面にあった渋谷〈LOFT WAVE〉に何とか移動できたんです。そこで、レジやアシスタント業務をしながら若手の一員としてワイワイと働いていたんですが、『RE/SERCH』誌の「Incredible Strange Music」特集号の出る前、その後のモンド・ミュージック前夜、『サバービア・スイート』が流行りはじめる頃に、そのサバービア関連アイテムを紹介できる小さなスペースをいただいて、本で紹介されていたムード/ラウンジ・ミュージック、エキゾチック・サウンズやオルガン・ジャズ、サントラ、ムーグものなどジャンル分けが難しいような作品やアーチストのCDになっている盤をセレクトして、それにプラス自分の勝手な妄想盤、サン・ラやジョー・ミーク、それに宇川直宏さんが作っていたハナタラシのライヴ音源にボーナス音源でついていたストレンジなムーグものやエキゾチック・ヴードゥーものセレクションCDをどさくさでサバービア関連と一緒に置いてみたりして……。そういえば当時、この売り場を見た橋本徹さんに「これはサバービアでない」と冗談まじりに怒られたり、とにかく無理矢理そういうコーナーをやらせてもらったんです。いま思うとホント勝手な奴で……若気の至りとはいえ、いろいろ反省してます。
[[SplitPage]]とにかく安いレコードを買いまくって、そこから新たなグルーヴやあえてビートのない部分でかっこいいパートを探したりもしてました。コラージュするために(笑)。
■音楽制作をやるきっかけは、村松誉啓くん(マジアレ太カヒRAW )との出会い?
松永:もちろんです。それまで、先ほど少しお話ししたように、学生時代にコンテストへ応募したりもしてみましたが、本格的に音楽制作をやるきっかけは、村松さん、高井(康生)さんと出会ってADSをはじめてからです。
■どうやって出会ったの?
松永:ヤン富田さんがプロデューしていたハバナ・エキゾチカ経由でバッファロー・ドーターも好きになって、サバービア橋本徹さんからの紹介でムーグ山本さんと出会いました。当時バッファロー・ドーターが渋谷のエレクトリックカフェでライヴをやるというので、それを見に行って、ライヴ終了後にムーグさんから村松さんを紹介していただいたんです。村松さんは当時、『i-D Japan』という雑誌の編集を手伝っていて、同誌の「オタクDJの冒険」というコーナーを担当していました。だからぼくのほうは勝手ながら村松さんのことを、あのコーナーを担当したあの人だ! と知っていたんです。
出会った頃の村松さんは、灰野敬二さんのような髪型していて、とんでもなくお洒落で……。当時の界隈ではなかなか存在感のある目立ってた人だったのではないかと思います。高井(康生)さんもそこで紹介されて、全員がヤン富田さんが大好きということで、いろいろ盛り上がって話しているうちに、みんなでDJイベントをやろうと意気投合して。高井さん、村松さんはそれぞれ楽器もできるというので、いろんなアイデアからDJと演奏との実験的セッションみたいなことをDJイベントとしてやってみようと、それがADSのはじまりでした。1994年だったと思います。青春ですね。ムードマン〈M.O.O.D.〉からEPを出してもらう前のことです。
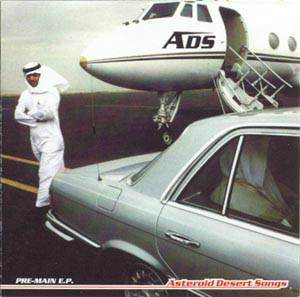
Asteroid Desert Songs
Pre-Main E.P.
M.O.O.D.(1996)
〈WAVE〉繋がりもあって仲良くしてもらっていた、ちょうどその頃にオープンした〈LOS APSON?〉の 山辺(圭司)さんにもDJをお願いしたり、〈LOS APSON?〉経由で知り合った宇川(直宏)さんにVJをお願いしました。その後、佐々木(敦)さんから四谷P3でのイベント「Unknown Mix」でのライヴに誘われて、村松さんドラム、高井さんがギターを担当するという、バンド演奏に初めてトライしてみました。ベースは当時、村松さんがDMBQのベース龍一君と3人でUltra Freak Overeatというバンドをやっていたんですが、そのベースだった(高橋)アキラ君(アキラ・ザ・マインド)を誘いました。で、ターンテーブルが自分という。消防士のヘルメットをレンタルしてコスプレして、ビーチ・ボーイズの“Fire”をカヴァーしました。ヘルメットで、ヘッドホン・モニターがめちゃくちゃやりずらかったことを思い出します(笑)。
■ADSといえば、村松君の機材で変調させた子供声も評判でしたが、あれも最初から?
松永:最初からですね。エレクトロ愛から。チップマンクスはもちろんバットホール・サーファーズもちらり(笑)。
■エレクトロ愛が高まったのは、ADSを組んでから?
松永:より高まりました! とにかく、エレクトロ愛は、村松さんと出会ってさらに加速したっていうのはあると思います。
■村松くんはもうエレクトロ?
松永:ビリビリにバリバリでした! 自分もそれに感化されながら、日々エレクトロ愛を邁進してました。それと同時に、お互い当時リリースされる数多くの新譜もかなりチェックしてました。
■あの時代は新譜が常に最高だったからね。
松永:毎週火曜日でしたっけ? CISCOの壁一面にその週のイチオシのものがバーン! と並んで、全員それを買うみたいな、そういう時代ですもんね。
■ADSは2年ぐらいで終わってしまって、すぐにスマーフ男組になるじゃないですか。あれは?
松永:自然の流れというか。もっとエレクトロに絞った活動をやりたくなって、それで、スマーフ男組になったという感じです。
■松永くんはまだ〈WAVE〉で働いていたんですか?
松永:渋谷の〈LOFT WAVE〉から関西へ異動を命じられたんですね。非常に悩んだんですが、ADSをはじめてすぐの頃だったんで、どうしてもそのときは東京にいたかった。それで泣く泣く〈WAVE〉を退社して……。その後、タワーレコード渋谷店へ何とか再就職できたという流れになります。
■それでいきなり、いまや伝説となったいわゆる「松永コーナー」を作ったんだ?
松永:1995年当時、タワーレコード渋谷店が現在の場所に移転したタイミングでした。6階がクラシックの売り場で、現代音楽の売り場もその階にもあったんです。ただ5階のニューエイジの売り場の隅にも現代音楽の一部も扱いつつ、アヴァンギャルドやその狭間みたいな、ジャンルは何?的な、売り場ではなかなか取り扱いが難しく扱いしづらいアーティストや作品を置けるような……当時は音楽産業絶好調で、しかも大型店だからできたと思うんですが……、余白を扱えるスペースとして機能できそうな売り場を作ることができたんだと思います。
タワーレコード渋谷店が現在の場所に移転した年で、ぼくはその5Fのニューエイジの売り場へ配属になって、上司や同僚と試行錯誤しながら、お客様やアーティストたちと併走するような形で学ばせてもらい、その売り場を形作ろうとしたように思います。クラシック現代音楽のコーナーにあるようなコンテンポラリー・ミニマルなアーティスト作品から電子音楽、ニューエイジ、アヴァンギャルド、アンビエント、民族音楽、フィールド・レコーディング、効果音、そしてこの時代ならではでのジャンル分けの難しい、規定のジャンルやコーナーでは取り扱いの難しいアーティストや作品を紹介できるような売り場になっていったんです。最初は売り場に名前をつけようがないのでとくに付けてなかったのですが、どうしてもコーナー・サインとして何かしらのジャンル名を付けなくてはならなくなって、ホント難しくて、悩みに悩んで“その他”(OTHERS)コーナーと付けたように思います(笑)。
■あのコーナーはホントに面白かったですよ。サン・ラー、ジョン・ケージ、ジョー・ミークやアンビエントまで、ジャンルの枠組みを超えたDJカルチャー的なセンスで展開していました。
松永:そういう時代だったんでしょうね。
■赤塚不二夫まで置いてあったよ(笑)。
松永:アニメーション作家レジェンド久里洋二先生の廃盤だったVHS作品をタワレコ渋谷店のみで限定再発とか(笑)。ESGのライヴ・アルバムなんかは、卸業者さんを通じて直接メンバーに連絡してもらい、残っていたCD在庫200枚をすべて卸てもらったり、上司の高見さんがイタリア〈Cramps Records〉のジョン・ケージやデヴィッド・チューダー、アルヴィン・ルシエ、『|Musica Futurista 』(※ルイジ・ルッソロなど、未来派の音楽の編集盤)などの電子音楽の古典的名作アルバムの数々をいち早く独占CD化したり、思い出すといろいろ懐かしいです。
デヴィッド・トゥープの影響も大きかったです。1996年に『Ocean of Sound』のCDも出たし、あのリリースには勇気づけられましたね。あのコンピレーションがメジャーレーベルからオフィシャル・リリースされたことで、ジャンルを横断的に楽しむってことは、もう普通になりつつあるんだなってことをあらためて感じて。そういう時代が来たんだなと。あれは嬉しかったです。実際、売り場でもものすごく売れました。
幅広いけど音楽への深い愛情と信念、ユーモア、その音楽を自分自身へと浸透させる力、そこへの気持ち、自分の言葉として語ること、宿る気持ち。村松さんはその説得力と音楽愛は半端じゃなかったです。
■松永くんはそういう自分のレコ屋のバイヤーとしての仕事をやりつつ、音楽活動もやってきている。だからあの時代のクラブの感じやレコード文化の感じの両方わかっているよね。ところで、スマーフ男組という名前は、村松くんが付けたの?
松永:ふたりでつけたんですよね。ADS(Asteroid Desert Songs)のネーミングからの反動もあって(笑)。エレクトロでは“スマーフもの”っていうスマーフをテーマにしたりタイトルに付けたクラシックがけっこうあって、ブレイク・ダンスの型にも“スマーフ”っていうスタイルがあったり、1980年代、エレクトロとアニメのスマーフがわりと繋がっていたところがあった。スマーフのキャラもかわいいし、村松さんも自分もフィギュアやグッズも集めてたんです(笑)。それとPファンクやヒップホップのように、何とかクルーとか何とかプロダクションとか、次々と入れ替わり立ち替わりメンバーを迎え入れる不定型の集まりでいるような、そういうものにもどこか憧れていたので、それで男組になったんです(笑)。とはいえ、結局のところは村松さんとアキラくんと自分、ほぼこの3人での活動でしたが(笑)。
■スマーフ男組の最初の音源は?
松永:〈P-Vine〉から出たマイアミベースのコンピ(『Killed By Bass』1997年)だった気がします。そのあとに〈File〉からの『Ill-Centrik Funk Vol. 1』(1998年)。〈Transonic〉からの『衝撃のUFO 衝撃のREMIX』(1998年)への参加だったと思います。

Various
Ill-Centrik Funk Vol. 1 (Chapter 2)
File Records(1998)
■松永くんから見て村松くんはどういう人だったの?
松永:天才ですね。ADS、スマーフ男組と一緒に活動させてもらっていましたが、ある意味では、自分も村松さんのファンで、村松さんの才能やすごさを世に伝えたいっていう気持ちがずっとあったように思います。
■彼の海賊盤のミックスCDを聴くと、フリー・ジャズからポップスまで、選曲が本当に自由じゃないですか。あのセンスはずっとそうだったんですか?
松永:ずっとそうですね。幅広いけど音楽への深い愛情と信念、ユーモア、その音楽を自分自身へと浸透させる力、そこへの気持ち、自分の言葉として語ること、宿る気持ち。その説得力と音楽愛は半端じゃなかったです。掘り下げ方、レコードやCDクレジット、ジャケットや盤面への思い、愛情と向かい合い方、情熱、気持ち。姿勢、本当にオールタイムで学ばせてもらったというか。
■ぼくはこういう仕事してるから音楽好きに会うんですけど、でもその「好き」の度合いが、けっこう軽かったりする人も少なくないんです。でも村松くんの「音楽が好き」っていうときの「好き」は、すごいものがあったよね。
松永:ホントそうですよね。そして、どこかカリスマ的なユニークなスター性もあったというか。

スマーフ男組
スマーフ男組の個性と発展
Lastrum(2007)

Smurphies' Fearless Bunch* And Space MCee’z
Wukovah Sessions Vol. 1
Wukovah(2007)
■『スマーフ男組の個性と発展』は、本当はもう少し早く出すはずだったんだよね?
松永:『Ill-Centrik Funk』が98年なんで、本当はその後すぐに出ていてもおかしくなかったんですよね。でも、そこから10年くらいかかってしまいました(笑)。ただその分、なんとも味わい深いアルバムができたと思うんですが、ADSからスマーフになって、その勢いがある時期でのリリースは完全に逃してしまいました。(笑)。
このデビューアルバムをリリースした後に下北沢〈Slits〉スタッフだった酒井(雅之)さんに声をかけてもらって、 酒井さんのレーベル〈 Wukovah〉からSpace MCee'z(ロボ宙とZen-La-Rock)とのJohn Peelセッションばりのスタジオ・セッション・アルバム(『Wukovah Sessions Vol. 1』2007年)をリリースしたんです。このプロジェクトを経て、スマーフ男組のライヴ・バンドとしての新しい可能性も感じて、メンバー3人ともすごくフレッシュな気持ちでそこへ向かい合っていました。その頃はたくさんライヴもやったんですよ。
■音楽活動とレコ屋での仕事とのバランスはどういうふうに考えてました?
松永:もう両方やってくしか生活できないっていう、ただそれだけです(笑)。
[[SplitPage]]悪魔の沼を10年以上まだ続けられて、現在もオファーをいただけて3人でプレイできているというのはホントにありがたい限りで、はじめた頃のイメージからすると信じられないありがたさです。
■ DJはもうスマーフになってからはやってました?
松永:DJはADSをはじめる前、〈WAVE〉に入った頃に六本木〈WAVE〉にいた同期入社だった井上薫君や現kong tong福田さんに誘ってもらって西麻布にあった〈M〉(マティステ)でやらせてもらうようになって、そこからADSイベントにもつながっていくのですが、スマーフ以降2000年代以降の大きな経験ということであれば、(東高円寺のDJバー)グラスルーツの存在が大きいです。店主であるQくんにDJ誘っていただいて、あの場所でいろいろと鍛えられました。タワーレコード渋谷を離れた頃、2004年、毎月水曜平日の夜中に「コンピューマのモーレツ独り会」っていう一人DJ会を1年間、全12回をやらせてもらったり。翌年には「二人会」シリーズ「ふらり途中下車」になって、これ以降、グラスルーツを拠点にDJとしての活動が本格化したように思います。
■自分のレーベル〈Something About〉もはじめますよね? 最初は自分のミックスCDだったね?
松永:そうなんです。『Something In The Air』という自分のミックスCDでした。ちょうどそのときもリリース後にele-kingのwebサイトで野田さんに取材(Something In The Air)していただきました。2012年なんで、もはや10年前なんですよね。時間が経つのが早すぎます。
■はははは。
松永:このミックスCDをリリースする2010〜11年頃は、個人的にもプレイスタイルの過渡期で、自分のDJスタイルを見つめ直していた時期でした。引っ越しもあったりして、あらためてレコードやCDのダンボールを整理したりしつつ、タワレコ渋谷5F時代に紹介した電子音楽や実験音楽などのCDをあらためて聴き直したりして、自分なりにDJミックスの表現の可能性を追求してました。東日本震災も大きいかもしれません。そんな中で生まれたのが『Something In The Air』でした。
■あれはまさにサウンド・コラージュ作品だったよね。
松永:この作品を制作するにあたって、密かに大きかったのが、2000年代初頭、永澤陽一さんのパリコレのファッションショーの音楽を担当する機会をいただいて、テーマや意向を詳しく教えてもらって、それをイマジナリーに音や音楽に変換してみて、その候補になりそうな音源サンプルを打ち合わせの際にたくさん持っていって、それらをひとつひとつ聴いていただいて、そのなかからじょじょに絞っていきながら、最終的に絞り込まれた厳選音楽素材、それらの音源を組み合わせてショーの音楽を構築していきました。10〜15分ほどの短いショーの時間内で、その音世界としてどのように起承転結を作ってくかというときに、自分の技術力の問題や選ぶ音楽の傾向や種類も関係したかもしれませんが、ビートが強くある曲を選ぶと、どうしてもBPMで繋いでいかなきゃいけなくなったり、カットアップ&カットインのポイントやタイミングの難しさや違和感にも繋がるから、なるべく柔らかに変容していくようにするために、どうしてもビートのあまり強くないものやノンビートのものを意識して選んでミックスしていたんです。その頃の経験が、その後『Something In The Air』でミックスしているようなことに繋がっていったように思います。
■どんな感じだったんですか?
松永:拙い英語力なので、コミュニケーションもままならないなか、現地スタッフさんと一緒にルーブル美術館の地下のフロアでひとり冷や汗かきながらMDプレイヤー数台とラック式CDプレーヤーを数台積んで。PA卓でショーのリアルタイムでプレイをトライしてました。モデルさんの出るタイミングやシーンの雰囲気の変わるタイミングを察しながら、舞台監督からの指示をもう片方の耳でモニターしながらでのプレイでもあるので、もうそれが半端じゃない尋常じゃない緊張感というか、絶対にミスれないので、めちゃくちゃドキドキで、かなり鍛えられた気がします。その経験を4〜5年やらせていただいたように思います。でもそのときの思い出として、ショーを無事に終えれてフィナーレのタイミングで拍手をもらったときの嬉しさやホッとする安堵感はいまでもたまに思い出します。貴重な経験させてもらいました。

Something In The Air
mixed by COMPUMA
2012
■『Something In The Air』はエディットなしのライヴミキシング?
松永:基本そうですね。
■それはじつに興味深いですね。で、『Something In The Air』は当時すごい反響があった。
松永:うーん。どうなんでしょうか。やっぱりアンダーグラウンド・リリースですし。でもあの作品をリリースしたことは自分にとってとても大きかったように思います。
■コンピューマ作品のひとつの原点になったよね。
松永:それは本当そうですね。ありがとうございます。
■松永くん個人史のなかで、人生の節目というのはいつだったと思いますか?
松永:そうですね。ソロ名義のアルバムをリリースしたいまのタイミングも大きそうな気がしますし、まだまだこれから先も続いていく、続いていってほしいとも思ってます。なので、これから先にもまだまだそのようなタイミングがいくつかあるかもしれませんが、これまでということで考えてみると、さっきとも重複してしまいますが、やはり震災を経て2012年初頭『Something In The Air』、あの作品をあのタイミングでリリースしたことは大きいかもしれません。自分のなかですごく楽になったというか、励みになりました。こういう世界観やプレイスタイルもDJ ミックスとしてトライしていいんだっていう、自信とまではいかないですけど、もっとやっていいんだ、ということに繋がったと思います。それと2017年に浅沼優子さんの尽力のおかげもあって、ドイツ〈Berlin Atonal〉へ出演できたこと、そこでDJ経験できたことも大きいと思います。何か景色が変わった気がします。
■いっぽうで悪魔の沼もはじめます。
松永:下北の〈MORE〉、厳密にいうと〈MORE〉店長だった宮さんがその前にやっていた同じく下北沢ROOM”Heaven&Earth”ではじまったイベントだったんです。メンバーのAWANOくんから「沼」をテーマにイベントをやるので一緒にやりませんかと、そして、何かいいタイトルないですかと相談されて、そのときに「沼」と聞いて、瞬間的にトビー・フーパーの映画『悪魔の沼』のポスターの絵、大鎌を振り回すオッサンのあの絵が頭にパッーと浮かんだんです。それで冗談まじりに『悪魔の沼』」はどうですか? と(笑)。で、AWANO君から「誰か一緒にやりたい人いますか?」と尋ねられて、その頃自分は勘違いスクリュー的なプレイを盛り上がってよくやってた頃で、コズミック(イタロ・ディスコ)が再評価された後の時期でもあったので、西村(公輝)さんは面識はあったのですが、それまではDJご一緒したこともほぼなかったんです。AWANO君と西村さんは学生時代から縁もあって、それもあって西村さんとご一緒できたらと思って声をかけていただきました。悪魔の沼イベント初期は全編ホラー映画のサントラのみでトライしてみたり(笑)。初期は一人30分交代だったので一晩で3〜4セットをプレイするという、皆レコード中心だったので準備だけでもなかなか大変で、かなりしごかれました(笑)。オリジナルメンバーとしては二見裕志さんも参加されてました。一時期、1Drink石黒君も参加していたこともありました。そんなこんなを経て、現在の3人になりました。その頃に、ミヤさんに「3人でback to backでやってみたら」とアドバイスもらい、試しにそれをやってみたことがきっかけで現在のスタイルに繋がってます。
〈MORE〉時代の沼イベントは、およそ季節ごとの開催でした。フリーゆで卵とか、フリーわかめとか、幻や沼汁というドリンクあったり(笑)、毎回ゲストを迎えながら、ダンス・ミュージックながら自由に沼を探ってました。
■これだけ長く続いているのは、やっぱ楽しいから?
松永:自分的には、ADS、スマーフ男組を経て、そしてDJの延長線上でもあったし、沼がテーマでしたし(笑)、なんだかとても気持ちが楽だったんです。季節ごとにやる趣味の会合や寄り合いくらいの感覚だったというか、なので、10年以上まだ続けられて、現在もオファーをいただけて3人でプレイできているというのはホントにありがたい限りで、はじめた頃のイメージからすると信じられないありがたさです。西村さん、AWANO君との共同プレイで、ヒリッとした刺激はもちろん、毎回の化かし合い含めて切磋琢磨し続けられているのはホントにありがたいなと思ってます。
■松永くんはDJをやめようと思ったことってないの?
松永:いまのところ意識的にはないですね。ただ、いつまでこういうことを現場でやっていけるのか。やっていいのか。やり続けていいのか。ということはここ最近何となく思うこともあります。コロナ禍以降、最近は、より若い世代や幅広いジャンルの素敵なDJやアーチストさん、バンドとご一緒する現場も多くて、幅広い世代の皆さんと一緒に音を奏でられることにも大きな喜びを感じてます。それと長年サポートしてくれている友人と家族には感謝の気持ちでいっぱいです。
[[SplitPage]]もう本当にそれはありがたい限りでして。一緒に遊ばせてもらってるっていうか、彼らと話していると、たまに、「お父さんと(お母さんと)同い年です。コンピューマさんの方が年上です。」とか話してくれたり(笑)。
■それで、今回のアルバム(『A View』)が、これだけ長いキャリアを持ちながら、初めて自分の名前(COMPUMA)で出したアルバムになるんですよね。
松永:はい。
■元々は演劇のために作ったものを再構築したっていう話なんですけど、作り方の点でいままでと変わったところってあります?
松永:僕はミュージシャンではないので、できることがかなり限られてるんです。だから、ある意味で音楽を作る場合は、諦めからはじまるともいいますか。今回の作り方も基本的にはそういう意味では一緒なんですが、ここ近年での制作は、今作も含めて、Urban Volcano Sounds/Deavid Soulのhacchiさんの存在はすごく大きいです。
■ダブでやミニマルであったり、松永くんのDJミキシングのサウンドコラージュ的に作っていたものとはまた違うところにいったように思いました。
松永:今回は、北九州の演劇グループ〈ブルーエゴナク〉さんからオファーいただいた演劇『眺め』のための音楽が基になってます。 2021年春頃に〈Black Smoker〉からリリースした『Innervisions』というミックスCDがありまして、その内容がかなり抽象的な電子音のコラージュが中心で、ダンス・ミュージックと電子音楽の狭間を探求するような、わりと内省的な内容だったんですけど、ブルーエゴナク代表の穴迫さんがこのミックスCDを購入していただいたようで、そこからオファーをいただきました。自分的には当初『Innervisions』の感じの抽象的なものだったら何とかできるかもしれないと思って、リクエストもそんなような感じの内容だったんで、それであればいけるかもということでお受けしたんですが、具体的に進行させたところ、実際にはかなり場面展開もあって、抽象的な音がダラッと流れるだけじゃどう考えても成立しないということがわかって、しかも九つの場面用の音楽が必要ということで、実のところかなり焦りました(笑)。
そこからBPM90でミニマル・ミュージックというお題をいただいたり、台本から音のイメージにつながる言葉をいくつもいただいて、それらの言葉をイマジナリー音に変換していって、それらをパズルのように組み合わせて試して構築していきながら制作を進めました。
■『眺め』という言葉を松永くん的に音で翻訳してたと思うんですけど、どんなふうに解釈してどんなふうに捉えていったんですか?
松永:演劇タイトル「眺め」から当初感じていたのは、何となく、どこか遠くからというか、俯瞰してるような感覚でした。ただ、制作を進めていく中で、これは俯瞰だけではなくミクロでマクロな世界観も含めての「眺め」なんだと再認識しました。
■穴迫信一さんさんのライナーノーツにすごくいいことが書いてありました。希望が見えない時代のなかで、いかにして希望を見つけていけばいいんだろうみたいな、それを音に託したというような話があって。
松永:本当に恐縮で素敵なライナーノーツをいただきました。そして何より演劇の音楽を担当するという貴重な機会をいただいて心から感謝してます。
■松永くんの関わってきた音楽作品はダークサイドには行かない、それは意識していることなんですか?
松永:そうですか。そういうイメージなんですね。そこは無意識でした。ダークサイドに行っているか行ってないかどうかは自分ではわかりませんが、今作に関しては、演劇のための音楽でしたので、舞台と装置、照明や映像、お芝居もそこに入ってくるので、そういう意味では、今まで作った作品以上に、どこか余白の部分が残ることを意識した音、イメージとして何か少し足りないくらいの音にすることは意識しました。あとは、何と言いますか、何でもない、聴き疲れしまい音を目指すと言いますか、、
■それはなぜ?
松永:最初は自分の持っているシンセなどで用意した個性的な音を合わせたりしたみたんですが、どうにも今回は、なんだかイメージが合わなかったんです。それとミニマル・ミュージックというテーマもいただいていたので、そこも意識しながら発展させてみました。何も起こらない感覚といいいますか、インド古典音楽ラーガ的メディテーショナルな世界も頭のなかに浮かびつつ。
■いまでもレコードは買っていますか?
松永:新譜も中古もレコードもCDも買います。カセットテープもたまに。データで買うものもあります。全部のフォーマットで買ってますね。笑
■いま関心があるジャンルとかあります?
松永:オールジャンル気になった新譜をサブスクで軽く聴いたり、そこから気に入ったものはCDやレコードでも買ったりするんですが、サブスクって、ふと思ったのですが、便利なので活用しますが、何と言いますか、聴いてるけど何となく聴いた気にだけなっているというか、しっかりと自分の中に沁み込んでこないというか。年寄りだからなのかもしれませんが、レコードCDで購入する音源への思い入れが強すぎるのかもしれませんが、長年の習慣での癖が抜けきらないんですかね。購入したものでないとなんだかしっかりと頭に記憶されないというか(笑)。DJプレイに関わるものはまた別ですが、リスニングするものは幅広くオールジャンルに話題作、旧譜もチェックしてます。これも年のせいなのか、より耳疲れしないような音楽と音量や距離感を求めているようにも思います。
■最近はどのぐらいの頻度でDJやってるんですか?
松永:DJは平均すると週1〜2回くらいでしょうか。その時々によって差があるかもしれません。
■コロナのときは大変だったよね。
松永:DJほとんどやってなかったんで家にずっといて、街も静かだったじゃないですか。いろんなことを考えさせられました。東京も、こんなに静かなんだとも思って。
■なんかこう将来に対する不安とかある?
松永:それはもうずっとあります(笑)。凹んだり落ち込むようなことが多い世のなかですけど、少しでもいいところや心地いいところ面白いところを探していけたらと努めてます。息子達の世代が、少しでも未来に希望を持てるようなことを伝えられたり作っていってあげたいなというのが正直な気持ちとしてもあります。現実には、いろいろとなかなかハードなところだらけじゃないですか。だから、何かちょっとでも明るい未来を感じられるような気持ちと視点でありたいなという願望かもしれません。
■松永くんからみて90年代ってどういう時代だったと思います?
松永:自分の勝手な解釈なんで違うかもしれませんが、90年代といまが違うとしたら、妄想力の違いでしょうか。当時はまだインターネットがなかったから、海外のマニアックな音楽や文化に関しては、勘違い含めて、皆が妄想力でも追求して熱量で挑んでいたと思うんですね。DJ的センスが良くも悪くもいろいろな場面で浸透しつつあって、その感覚でいろんな視点から色々な時代いろんな音楽を面白がる感覚がより世間的にも広がっていくような感覚が90年代に誕生したんではないかとも勝手ながら思います。インターネット以降、とくに最近は、やはりその知り得る情報の正確さ、速さが90年代とでは圧倒的に違うと思うんです。勘違いの積み重ねや妄想の重ね方の度合いは90年代の方が圧倒的に高かったと思うんですよね。翻訳機能のレベルも高くなりましたし、ただ、SNS含めて情報量がとにかく多すぎるので、本当に自分のとって必要な情報を選ぶことが大変な時代になっているような気もしてます。それはそれでなかなかに大変ですよね。自分でも何か検索すると同じような情報がたくさん出過ぎて、どれを読めばいいのか、ホントに知りたい正しい情報まで逆に辿り着けなくて、それだけで疲れてしまうことも多々あったりしますし。
とは言ってもインターネットは便利ですし、音楽制作においてもDJにおいても素材集め含めてとんでもなく早く集められるし、それを活かせる環境があるから、90年代と比べると洗練された上手いDJプレイをできると思うんですよね。ただ、一概に比較は難しいのですが、どっちが好みかというのはまたちょっと比べられないですよね。どっちにもカッコよさもありますし、かっこよすぎてかっこよさ慣れしてしまう感覚もありますよね。
■松永くんは世代を超えて、若い世代のイベントにも出演しているわけだけど。
松永:いや、もう本当にそれはありがたい限りでして。一緒に遊ばせてもらってるっていうか、彼らと話していると、たまに、「お父さんと(お母さんと)同い年です。コンピューマさんの方が年上です。」とか話してくれたり(笑)。
■(笑)でも、DJの世界は、音楽をどれだけ知っているかが重要だから、ベテランだからこそできることっていうのがあるわけなので。
松永:ここ最近「沼」のメンバーとは会うたびに、こんなおっさんたちが、果たしていつまでこういう現場にいていいものかどうなのかっていう話にはいつもなります(笑)。
■はははは。でも、続けてくださいよ、本当(笑)。最後に、〈Something About〉をどうしていきたいとか夢はありますか?
松永:今回もいろいろな皆さんの協力のもと、自主リリースでソロ名義で初めてのアルバムをリリースすることができて本当にありがたい限りなのですが、このCDリリースをきっかけにして、ここから新たないろんな可能性を探求できたらと思ってます。できることなら海外の方にも届けられたらとも思いますし、デジタルやアナログ・リリースも視野に目指してみたいです。自分なりのペースにはなりますが、これからもオヤジ節ながらトライしていきたいと思います(笑)。精進します。どうぞよろしくおねがいいたします。
それと9/30金に、渋谷WWWにてリリース・イベントを開催させていただくことになりました。最高に素敵な皆さんに出演していただくことになりました。よろしければ是非ともです。よろしくお願いいたします。
■COMPUMA 『A View』 Release Party
■出演 :
COMPUMA
パードン木村
エマーソン北村
DJ:Akie
音響:内田直之
映像:住吉清隆
■日時:2022年9月30日(金曜日)開場/開演 18:30/19:30
■会場:渋谷WWW
■前売券(2022年8月19日(金曜日)12:00発売):
一般 : 3,000円/U25 : 2,000円(税込・1ドリンク代別/全自由 ※一部座席あり)
■当日券 : 3,500円(税込・1ドリンク代別/全自由 ※一部座席あり)
■前売券取扱箇所:イープラス<https://eplus.jp/compuma0930/>
■問い合わせ先:WWW 03-5458-7685 https://www-shibuya.jp/
※U25チケットは25歳以下のお客様がご購入可能なチケットです。
ご入場時に年齢確認のため顔写真付き身分証明書の提示が必要となります。
ご持参がない場合、一般チケットとの差額をお支払いいただきます。