〈Brainfeeder〉があらたなアーティストを迎え入れた。モロッコ出身、現在はロサンゼルス拠点で活動するアーティスト、アミ・タフ・ラ。モロッコの伝統音楽であるグナワとジャズ、ゴスペルを融合させた独自のトライバル・サウンドを得意としているようだ。
アミ・タフ・ラは〈Brainfeeder〉との契約にともない、かねてからツアーに参加するなどして親交のあるカマシ・ワシントンのプロデュースによるシングル“Speak To Us (Outro)”を公開中。タイトルに(Outro)とあるように、これはアルバムのリリースにも期待したいところ。以下、詳細です。

Artist : Ami Taf Ra
Title : Speak To Us (Outro)
Label : Brainfeeder / Beat Records
Release Date : Out Now
Format : Digital
Stream : https://amitafra.lnk.to/stu-outro
今回新たに〈Brainfeeder〉との契約が発表されたアミ・タフ・ラは、北アフリカのモロッコ出身でロサンゼルスを拠点に活動するシンガーソングライターで、モロッコのグナワ音楽などアラブの伝統音楽をジャズやゴスペルと融合させ、高く評価されている。
アミ・タフ・ラが契約発表にあわせて、長年のコラボレーターである伝説的サックス奏者カマシ・ワシントンがプロデュースを手がけた新曲「Speak To Us (Outro)」をクリオン・アレイが監督したミュージックビデオと共にリリースした。
この曲は、“悟り”を求める旅が一生涯続くものであり、終わるのではなく、人生の光が強くなるにつれて深まっていくことを思い出させてくれる。〈Brainfeeder〉ファミリーの一員になれて本当にワクワクしているし、彼らがこれまで世に送り出してきた偉大なアーティストたちの系譜に加われることを光栄に思う。 ──Ami Taf Ra
音楽を通じて文化の融合を探求し続けているアミ・タフ・ラは、自身のルーツを大切にしながら、さまざまな言語や国籍から新たな影響を取り入れ、独自のサウンドを築いている。文化の垣根を越えた融合と、アブドゥル・ハリム・ハーフェズ、ウンム・クルスーム、ワルダ、アスマハーン、ファイルーズといったアラブの伝説的ボーカリストたちの豊かな伝統に根ざしており、カマシ・ワシントンの影響により、スピリチュアル・ジャズ、アフロセントリックと呼ばれるアフリカ中心性理論、オーケストラの壮大さも融合している。
キャリアを通じてアミ・タフ・ラは、デンマーク、トルコ、モロッコ、ベルギー、レバノン、ヨルダンなど世界中のステージで観客を魅了してきた。また、カマシ・ワシントンとのツアーにも参加しており、ハリウッド・ボウル・ジャズ・フェスティバルなどの全米の名高い会場やフェスティバルで共演を果たしている。他にも、トロンボーン奏者ライアン・ポーター、サックス奏者リッキー・ワシントン、パーカッショニストのカリル・カミングス、ベーシストのベン・ウィリアムス、ドラマーのジョナサン・ピンソン、ピアニストのジャメール・ディーンといった多彩なミュージシャンと共演してきた。この秋、アミ・タフ・ラは北米ヘッドラインツアーを開始し、9月22日にニューヨークのブルーノート公演で幕を開ける。
アミ・タフ・ラは、音楽を通じた「つながり」と「癒し」の力に深い信念を持ち、ステージを超えて紛争や避難の影響を受けた地域社会とも関わってきた。オランダ人ミュージシャンのグループと協力し、子どもたちに向けた音楽と絵画のワークショップを開催した。その活動は子どもたちとミュージシャン、そしてアミ・タフ・ラが共演する2014年のアンマン・ジャズ・フェスティバルのオープニング・パフォーマンスとして結実した。







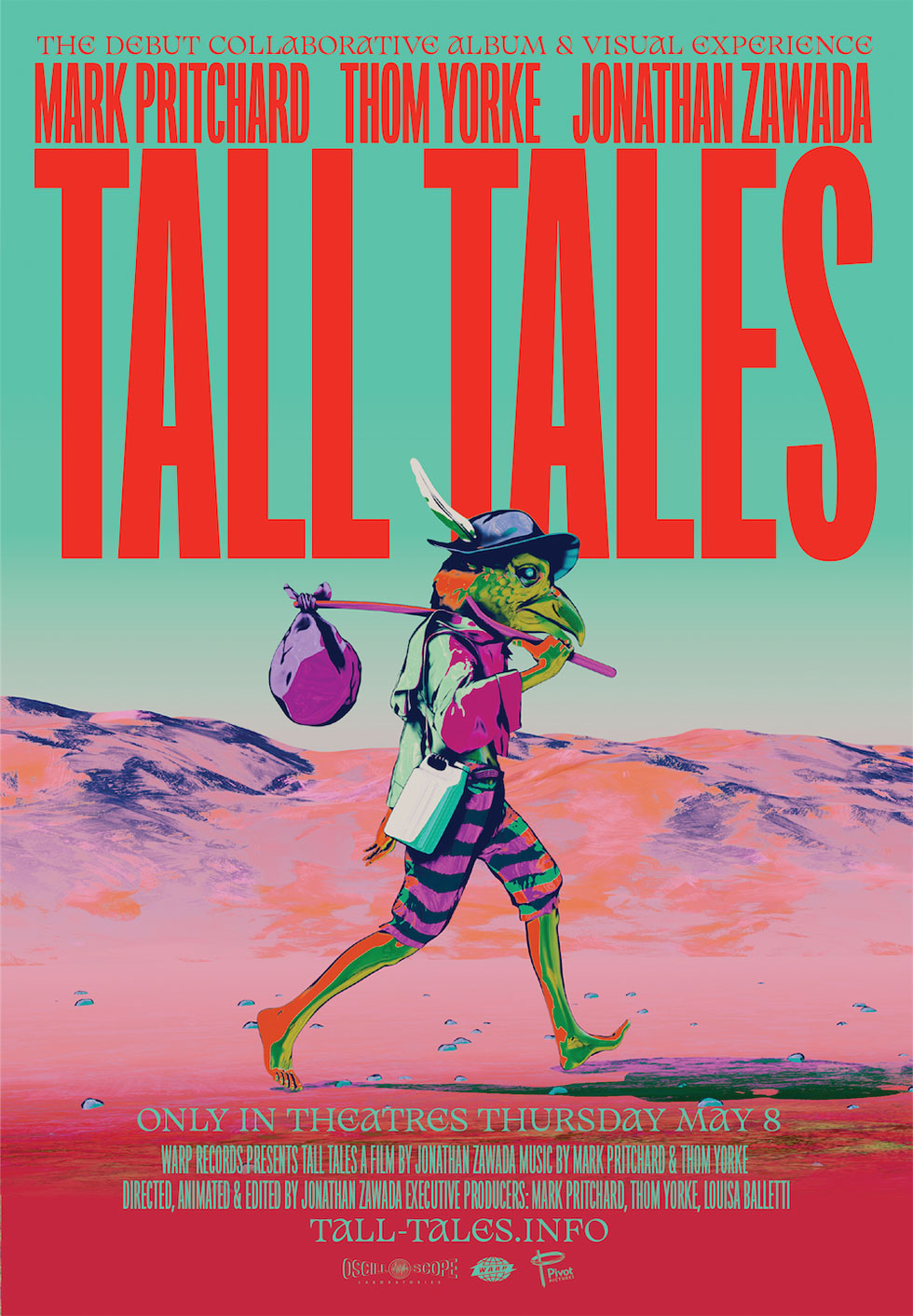



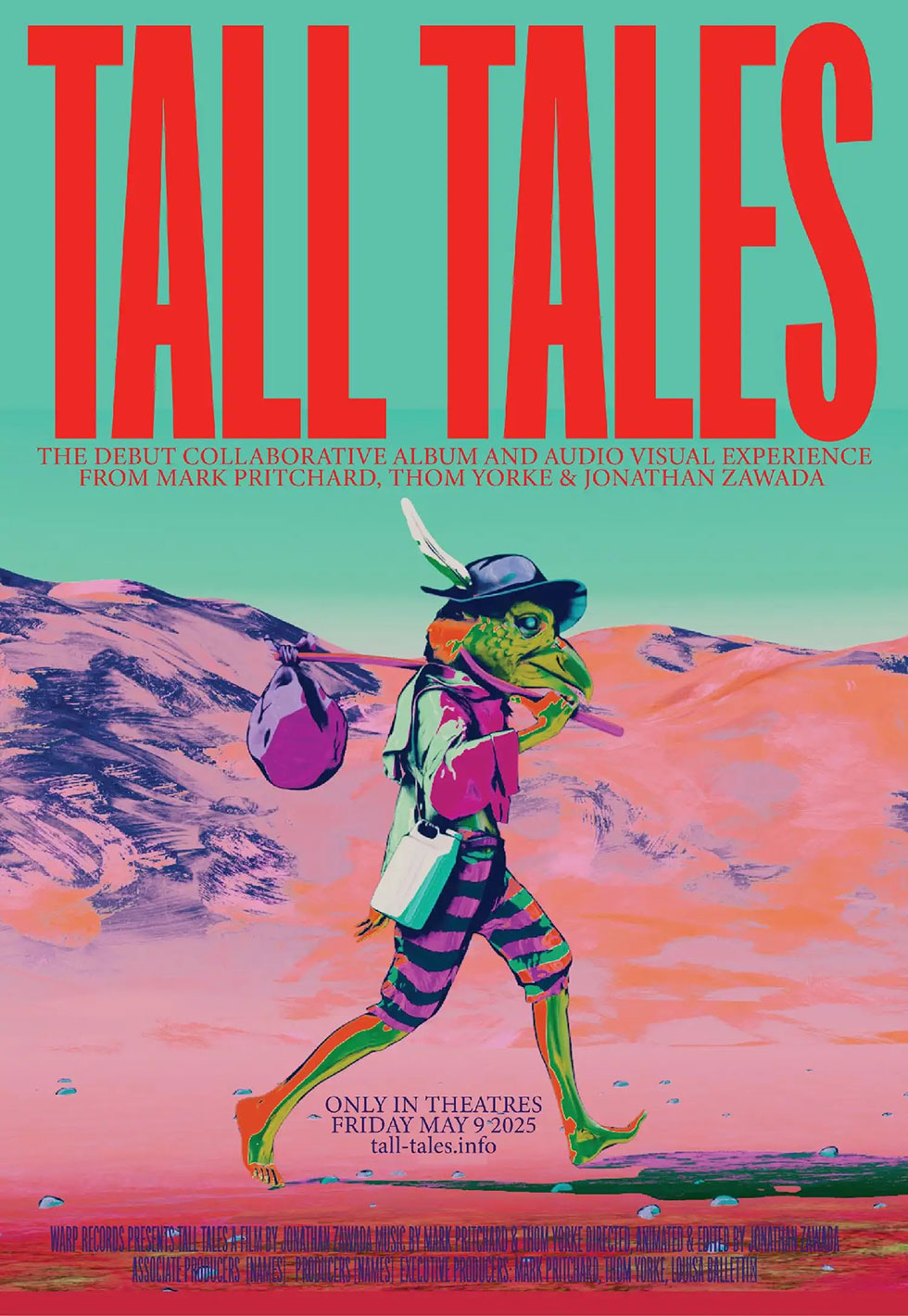
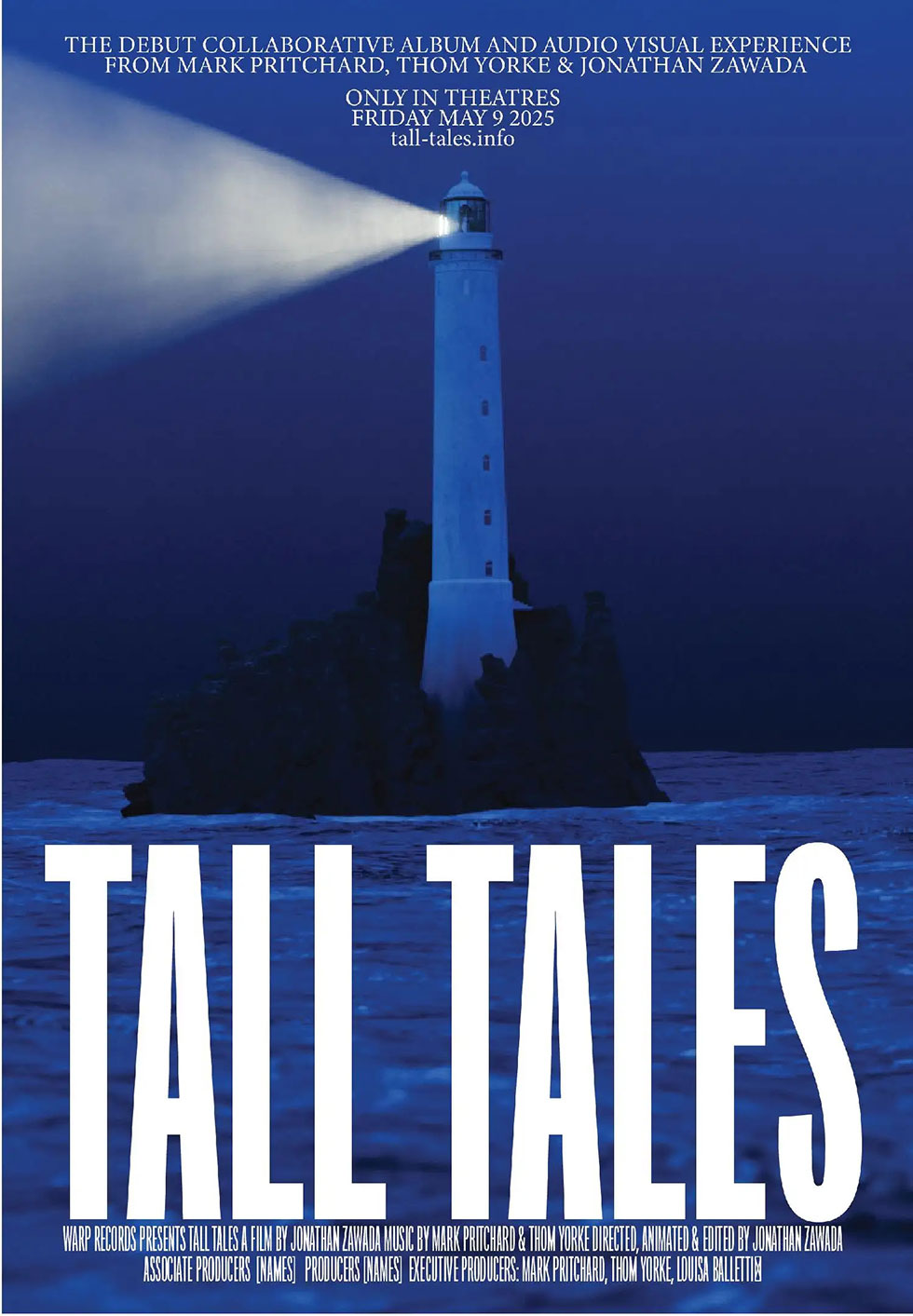




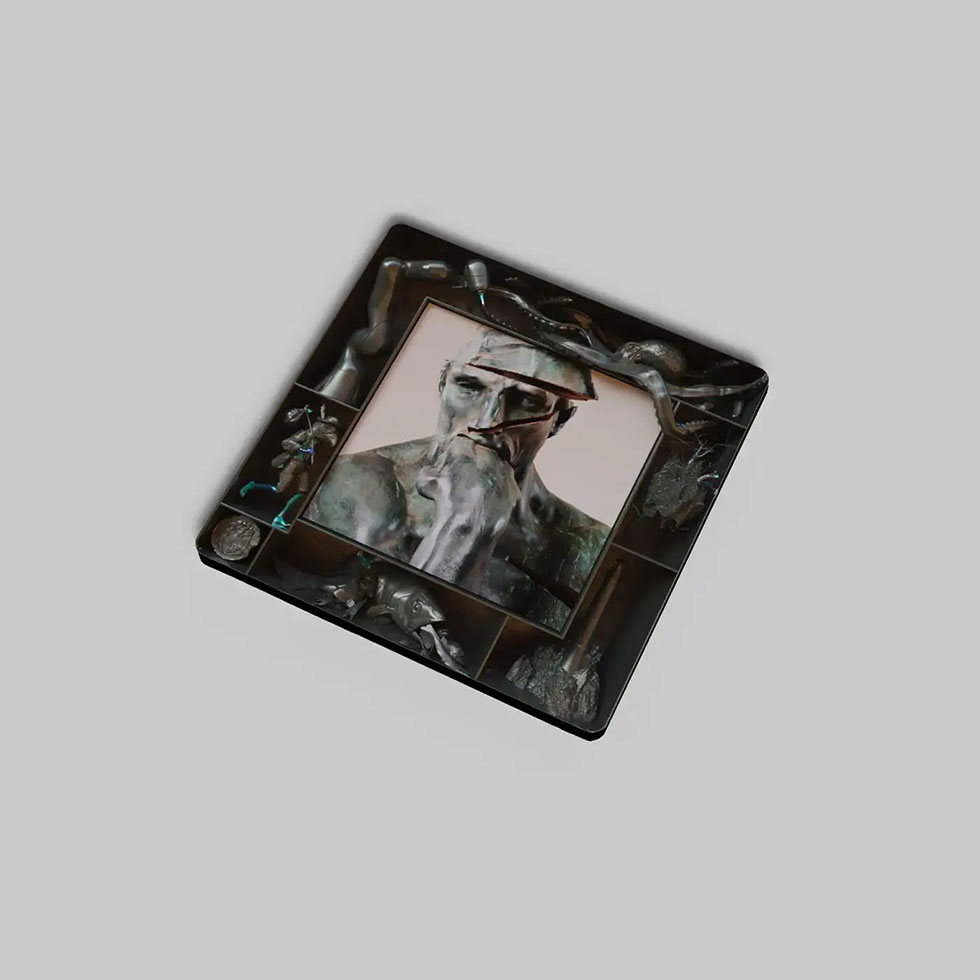










 Masaya Fantasista
Masaya Fantasista モンゴルのアンダーグラウンドにもアクセスするIR
モンゴルのアンダーグラウンドにもアクセスするIR



