ダンス・ミュージックで使われるレフトフィールドという言葉はとてもざっくりとしている。ハウス、テクノ、ヒップホップ、ドラム&ベース、ダブステップなど、何か特定のジャンルを指しているわけではないけれど、そのいずれにもレフトフィールドと呼べる領域は存在していて、レコード店でのポップなどにこの言葉が添えられる作品には、おしなべて共通した雰囲気が漂っている。
それを「自由で実験的」と言ってしまえばそれまでだが、最も重要なのは作品のどこかにダンスフロアとの接点が必ず残されている点だ。なぜなら「レフト」が存在するためには「センター」という前提が必要で、ダンス・ミュージックの「センター」に位置するダンスフロアという起点があるからこそ、レフトフィールドとしての意義が明確になるからだ。
起点から遠く離れるほど異質になっていくが、それでもやはりフロアで機能し得るこの手のトラックはDJにとって非常にプレイのしがいがあるもので、上手くセットに組み込めば驚くほど新鮮で不思議な体験をもたらしてくれる。踊る側にとってもドラミングにおけるシンコペーションのように、そこにはズレによる心地よさがある。今回ここに選んだのは、前回とは違うかたちで素敵なレフトフィールドぶりを響かせている5作品だ。
Dynamo Dreesen, SVN & A Made Up Sound - Untitled - SUED
 ダブステップ・シーンから火が点いた2562ことア・メイド・アップ・サウンドは近年、そのイメージから離れていくように、尖った実験性を持ってダンスフロアに面白い提案を投げかけている。レフトフィールド・サウンド筆頭レーベル〈スード〉から発表したこのコラボレーションもそのひとつ。
ダブステップ・シーンから火が点いた2562ことア・メイド・アップ・サウンドは近年、そのイメージから離れていくように、尖った実験性を持ってダンスフロアに面白い提案を投げかけている。レフトフィールド・サウンド筆頭レーベル〈スード〉から発表したこのコラボレーションもそのひとつ。
Don't DJ - Gammellan - Berceuse Heroique
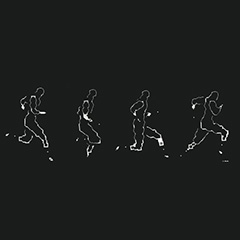 ドント・ディージェイという名前からもレフトフィールドぶりが伝わって来る彼は、デビューから一貫してポリリズムによるミニマルな陶酔性を探求している。中でも特にこの”ガムラン”は出色の仕上がり。
ドント・ディージェイという名前からもレフトフィールドぶりが伝わって来る彼は、デビューから一貫してポリリズムによるミニマルな陶酔性を探求している。中でも特にこの”ガムラン”は出色の仕上がり。
PST & SVN - Recordings 1 - 4 - Recording
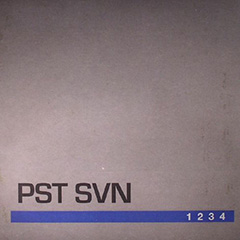 何度も制作を共にしているポーン・ソード・タバコ(PST)とSVNのふたり。簡素な4つ打ちリズムの中に潜むロウなテクスチャーとじんわりと滲み出てくるトロピカルなムードによる反復の快楽がたまらない。
何度も制作を共にしているポーン・ソード・タバコ(PST)とSVNのふたり。簡素な4つ打ちリズムの中に潜むロウなテクスチャーとじんわりと滲み出てくるトロピカルなムードによる反復の快楽がたまらない。
Frank Wiedemann - Moorthon EP - Innervisions
 00年代を代表するアンセム“レイ”を生んだアムの一員、フランク・ヴィーデマンの初ソロ作品に収録されているトラック。電子音による特異なセッション空間とグルーヴを実現している。
00年代を代表するアンセム“レイ”を生んだアムの一員、フランク・ヴィーデマンの初ソロ作品に収録されているトラック。電子音による特異なセッション空間とグルーヴを実現している。
The Durian Brothers / Harmonious Thelonious / Don't DJ - Diskanted - Emotional Response
 ドント・ディージェイ、そして彼が参加するプロジェクトであるザ・ドリアン・ブラザーズ、ひび割れたトロピカルサウンドが特徴的なハーモニウス・セロニウスの楽曲をコンパイル。その共通項にあるのはやはりポリリズム。
ドント・ディージェイ、そして彼が参加するプロジェクトであるザ・ドリアン・ブラザーズ、ひび割れたトロピカルサウンドが特徴的なハーモニウス・セロニウスの楽曲をコンパイル。その共通項にあるのはやはりポリリズム。




























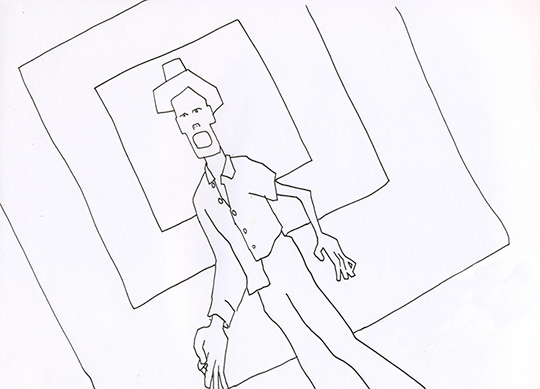



 D.A.N.
D.A.N.


