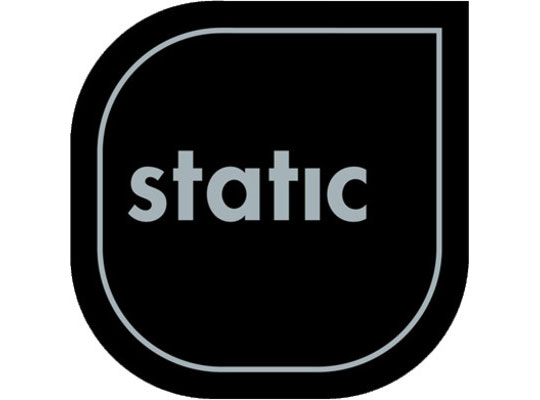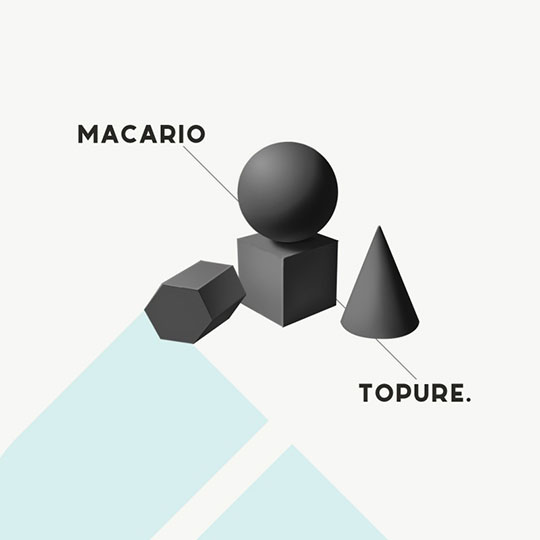まだまだGW圏内!
いま公開中、もしくはもうすぐ公開の注目映画をいくつかご紹介いたします。

© Final Cut for Real Aps, Piraya Film AS and Novaya Zemlya LTD, 2012
アクト・オブ・キリング
監督/ジョシュア・オッペンハイマー
配給/トランスフォーマー
シアター・イメージフォーラム 他にて、全国公開中。
ドキュメンタリー映画としては……いや、ミニシアター系のなかでも、異例の動員となっているらしい。本作については水越真紀さんと紙エレキングで対談したのでそちらをご参照いただきたいが、そこに改めて付け加えるとすれば、やはりこれだけ世界的にも評価された上に多くの映画好きの心を掴んだのは、これが非常に含みのある、映画についての映画となっているからだろう。すなわち、映画はどういうところで生まれるのか、どうしてわたしたちは映画を観ることを欲望するのか? 幸運なことに僕は監督にインタヴューする機会に恵まれたのだが、そこで尋ねるとこんな風に答えてくれた。「映画というのは、現代でもっともストーリーテリングに長けたメディアです。この映画では、人間が自分を説得するためにどのように“物語るか”ということに関心がありました。インドネシア政権も、嘘の歴史を“物語って”いるわけですから」。『アクト・オブ・キリング』は、虐殺の加害者たちが自分たちの過去を自慢げに“物語る”様をわたしたちが「観たい、知りたい」と思う欲望を言い当てているのである。つまり、それが映画の罪深さであり、同時に可能性であるのだと。わたしたちはその欲望を入り口としながらも、思わぬ領域までこの「映画」で連れて行かれる。
この映画で何かが具体的に解決するわけではないが、政治的であると同時に優れてアート的で示唆的だという点で、歴史に残る一本となるだろう。ヒットを受けて、都心部以外の上映も次々と決まっている。ぜひ目撃してほしい。

©2013 AKSON STUDIO SP. Z O.O., CANAL+CYFROWY SP. Z O.O., NARODOWE CENTRUM KULTURY,
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., TELEWIZJA POLSKA S.A. ALL RIGHTS RESERVED
ワレサ 連帯の男
監督/アンジェイ・ワイダ
出演/ロベルト・ヴィェンツキェヴィチ、アグニェシュカ・グロホフスカ 他
配給/アルバトロス・フィルム
岩波ホール 他にて、全国公開中。
もし10代、20代に「いま上映している映画で何を観ればいいか」と問われれば、僕はこれを推薦したい。ポーランドの超大御所、アンジェイ・ワイダによる〈連帯〉のレフ・ワレサ(正しい発音はヴァウェンサ)の伝記映画……というと、堅苦しいものが想像されるかもしれないが、これが非常に熱い一本となっているのは嬉しい驚きだ。政治的にはワレサと袂を分かったらしいワイダ監督だが、ここでは彼の歴史的な功績を描くことに集中しており、彼の傲慢さも含めてエネルギッシュな人物像が魅力的に立ち上がっている。本作ではイタリア人女性ジャーナリストによるワレサへの有名なインタヴューが軸になっているのだが、そこでふたりがタバコをスパスパ吸いながら遠慮なくやり合う様など、どうにも痛快だ。高揚感のある政治映画はある意味では危険だが、そこはワイダ監督なので労働者……民衆を中心に置くことに迷いはない。そして80年代のポーランド語のロックとパンクがかかり、ワレサのダブルピースが掲げられる。かつての理想主義、そして政治参加という意味で、スピルバーグの『リンカーン』と併せて観たいところ。

© 2013 UNIVERSAL STUDIOS
ワールズ・エンド
酔っぱらいが世界を救う!
監督/エドガー・ライト
出演/サイモン・ペッグ、ニック・フロスト 他
配給/シンカ、パルコ
渋谷シネクイント 他にて、全国公開中。
サブカル好きにもファンが多い、『ショーン・オブ・ザ・デッド』、『ホット・ファズ』チームによる新作。高校時代は輝いていたが中年になって落ちぶれた主人公が幼なじみを地元に集め、かつて達成できなかった12軒のパブのハシゴ酒に挑戦するが、町はエイリアンに支配されていて……というB級コメディ・アクション、そしてどこまでも野郎ノリなのはこれまで同様。そこに無条件に盛り上がるひとも多いみたいだけれど、僕はこの「(男は)いつまでもガキ」な感じに完全に乗ることはできないし、プライマル・スクリームの“ローデッド”ではじめるオープニングもちょっとベタすぎると思う。が、書けないけどラストである反転が用意されていて、それは本当に感心した。マイノリティというのはべつに、「人数が少ない」ことではないし、また「虐げられた同情すべきひとたち」でもない。それは選び取る立場なのだ……という決意。その1点において、僕はこの映画を支持する。イギリスの音楽もいろいろかかります。
予告編
© 2013- WILD BUNCH - QUAT’S SOUS FILMS – FRANCE 2 CINEMA – SCOPE PICTURES – RTBF (Télévision belge) - VERTIGO FILMS
アデル、ブルーは熱い色
監督/アブデラティフ・ケシシュ
出演/アデル・エグザルコプロス、レア・セドゥ 他
配給/コムストック・グループ
ヒューマントラストシネマ有楽町 他にて、全国公開中。
90年代のサブカル系少女マンガと近い感覚を指摘するひともいてたしかにそうなんだけど、フランス映画らしくバックグラウンドにはっきりと社会が描かれていることは見落としてはならないだろう。あるふたりの女同士のカップル(「レズビアン」であることを強調はしない)の蜜月と別れを3時間に渡って辛抱強く描くのだが、それぞれが属する異なる社会的階層がその土台にある。美学生のエマはアーティストである種のエリートだが、主人公のアデルは一種の社会奉仕的な立場としての教師という職業に身を捧げていく。ある苛烈な愛を描きながらも、そこからむしろ離れたところで使命を見出していくひとりの若い女性の感動的な歩みを映している。それぞれの立場を無効にするのが激しいラヴ・シーンなんだろうけど、それが過度にスキャンダラスなまでに絵画的に美しく描かれているかどうかは、正直判断しがたい。が、それ以上にラスト・カットのアデルの歩き去る姿、それこそがこの映画の芯だと僕は感じた。その瞬間のための3時間だと。
予告編
Photograph by Jessica Miglio © 2013 Gravier Productions, Inc.
ブルージャスミン
監督/ウディ・アレン
出演/ケイト・ブランシェット、サリー・ホーキンス、アレック・ボールドウィン 他
配給/ロングライド
5月10日(土)より、新宿ピカデリー、Bunkamuraル・シネマ 他にて全国公開。
ここのところヨーロッパで軽妙なラヴコメを撮っていた印象のウディ・アレンだが、これもまた彼のシニカルさの純度を研ぎ澄ましたという意味で、あまりに「らしい」一本。いや、『それでも恋するバルセロナ』(08)辺りと比べても、あの最後のカットの虚しさを引き伸ばしたものだとも言えるだろう。セレブ暮らしだった女がその虚栄心ゆえに落ちぶれていく様を、ただただ「まあ人間こんなもんだよ」という認識であっさり描いているのだが、それでもケイト・ブランシェットのエレガントな壊れ方はパフォーマンスとして優れている(相変わらず発話が素晴らしい)。それを肯定も否定もせず、そこに「在るもの」として簡潔に見せてしまうために彼女の力が必要だったのだろう。80歳目前のアレンのこの冷めた見解にはある意味呆然とするが、しかしある種の救いを今後の彼の作品に期待するのも見当違いなのかもしれない。
予告編

 メインステージの前でくつろぐ参加者たち。芝生でリラックス © Elisa Lemus
メインステージの前でくつろぐ参加者たち。芝生でリラックス © Elisa Lemus 楽器販売のブース © Miho Nagaya
楽器販売のブース © Miho Nagaya 雑貨とレモネードを販売するブース © Miho Nagaya
雑貨とレモネードを販売するブース © Miho Nagaya  ブランコもあった © Miho Nagaya"
ブランコもあった © Miho Nagaya"  フードトラックが並び、充実した各国料理が食べられる © Miho Nagaya"
フードトラックが並び、充実した各国料理が食べられる © Miho Nagaya" VANSが提供するスケート用ランページも © Miho Nagaya
VANSが提供するスケート用ランページも © Miho Nagaya ティファナ出身のフォークシンガー、Late Nite Howl © Miho Nagaya
ティファナ出身のフォークシンガー、Late Nite Howl © Miho Nagaya 雑誌VICEの音楽プログラム、NOISEYが提供するステージ © Miho Nagaya
雑誌VICEの音楽プログラム、NOISEYが提供するステージ © Miho Nagaya メヒカリ出身の新鋭テクノアーティストTrillones © Elisa Lemus
メヒカリ出身の新鋭テクノアーティストTrillones © Elisa Lemus 会場はペットフレンドリー © Miho Nagaya
会場はペットフレンドリー © Miho Nagaya NRMALのスタッフたちは黒尽くめでクール © Miho Nagaya
NRMALのスタッフたちは黒尽くめでクール © Miho Nagaya マティアス・アグアヨとモストロのステージが始まる頃には満員に © Elisa Lemus
マティアス・アグアヨとモストロのステージが始まる頃には満員に © Elisa Lemus マティアス・アグアヨ © Miho Nagaya
マティアス・アグアヨ © Miho Nagaya コロンビアのLa mini TK del miedo © Elisa Lemus
コロンビアのLa mini TK del miedo © Elisa Lemus