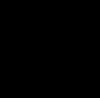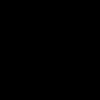ここ数年のヒップホップで僕が衝撃を受けたひとつは、いまさらながらDJスクリューだった。ヒューストンのこのDJは2000年に他界しているので、正確に言えばDJスクリュー再評価とその影響力に心奪われるものがあったということだ。気になったのは、どろっとスローにミキシング(エディット)する手法的なことだけではない。その独特の音響は、リスナーにある種のイメージ、ある種の感覚を誘発する。それは、いわゆるハキハキとした前向きさとはほど遠い感覚だ。どうにもこうにもならない。カフカの『城』に登場する測量士のKのようだ。つまり、いつまでたっても城には辿り着けない。いや、Kと違うのは、辿り着こうとしていないことだ。そして、Kのように、辿り着かなくてもその過程には、さまざまな出来事が起こりうる。
辿り着けなさという点において近しい感覚を、いよいよ台風の目になりつつあるDOWN NORTH CAMPのひとり、ISSUGI(MONJU/SICK TEAM)の、ISSUGI名義でのセカンド・アルバム『EARR』からも感じる。2009年にリリースされた最初のソロ・アルバム『Thursday』のアートワークにある彼のスケボーが暗示するように、動きはあって、場面はいろいろ変われども、『EARR』にも目指すべき「城」がない。城には向かわず、そこに向かわずして過ごしていることのほうが重要なのだ。そのことは、彼のCDにリリック・シートがないこととも関係しているように思える。シャイというよりも、本能的に、リリックから啓発的な意味を見いだそうとする行為を拒んでいるのだろう。
全15曲、計33分の男前のフロウが詰まった1枚、『EARR』には、ソウル、ルーツ・レゲエ、ジャズ、ほかにも古い録音物の音がサンプリングされ、ルーピングされ、エディットされている。基本ミニマルで、ダブからの影響が注がれ、ときにJディラ風でもあり、ビートは際立っているが、ここにも(ある意味坂本慎太郎的な)反ドラマ的な抑揚のなさがある。S.L.A.C.K.や仙人掌、Mr.PUGも参加しているが、意味よりも音が耳に入ってくるという具合だ。初めて1枚通して聴いたときに覚えた言葉は「ただハイになりたい」というフレーズぐらいで、実際の話、曲そのものが陶酔的だ。要するに、音的に言って、SICK TEAMから引き伸ばされたものが『EARR』にはある。『Thursday』を軽く越えている。
出だしが良い。レトロなR&Bからクラシックの弦楽器の演奏が交錯し、揺れながら、はじまる。トラックを担当しているのは16FLIP(昨年、アルバム『SMOKYTOWN CALLIN』を発表)、ブダモンク(Budamunk)はキーボードで2曲、パンピーもミックスで参加しているが、すべての音を手がけている16FLIPの貢献は大きい。メロウなソウル・ヴォーカルを華麗にチョップする"GET BLUN"、ビートとラップがリズミックに絡みつく"MANY WAY"といった先行発表の曲をはじめ、"FUTURE LISTNING"の瞑想的なビート、リー・ペリー的な音響の妙技を見せる"EYEWALL"、単調さの美学を貫く"BULLET"、インダスリアル調の"FIVE"、"SHADOW LIKE A MONSTA"のブロークン・ビーツ風の展開も面白い。
「良い歌だけじゃ満たせない心」と、"ONE ON ONE"というアルバム終盤の力強いビートを持つ曲で、ISSUGIはラップしている。そして、自分が「煙に巻かれた住人」であると言っているが、彼はその「煙に巻かれた」状態を良しとしている。もちろんダブル・ミーニングだ。ひとつは言うまでもないことだが、もうひとつを僕なりに解釈すれば、「良い歌」に表象されるもの、つまり「城」、目指すべき場所、いわゆる世間でいうところの頂点とされるもの、端的に言えば、そうしたものに距離をおいているということだ。むしろそういったものごとに、警戒心が働いているのではないかと思われる。クールである。繰り返すが、彼の出自はバトルMCだ。時代のなかで、目指すべき場所の変化がここにも如実に表れている。one for the money, two for the showは、いまやセピア色である。
もしも『EARR』のなかに、落ち込んだ人生に勇気を与えてくれると思わせられるような言葉があれば、もっとたくさんの数を売りさばくこともできるのだろう、が、しかし、裏を返せば、城には辿り着けなくてもいいじゃないかと言っているのが『EARR』だ......とSORA君に言ったら「いや、それは違いますよ」とまた言われてしまうのだろうか。コーラを飲みながら。
 二木信評論集 ──しくじるなよルーディ
二木信評論集 ──しくじるなよルーディ