MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Simian Mobile Disco - インディ・ダンスはテクノをめざす
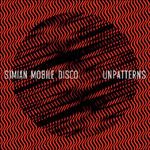 Simian Mobile Disco Unpatterns Wichita Records/ホステス |
ロックが不況である......というのは、いかにも白々しいクリシェであるが、しかしそういったお手軽な悲観を使いたいときも、正直、なくはない......。三田/野田世代の『ele-king』読者であれば、あるいは言うかもしれない。「そんなもの90年代後期からずっと死にっぱなしじゃないか......」
いやだとしても、ゼロ年代のなかごろ、いわゆるインディ・ロックに活気が感じられた季節がたしかにあったのだ。少なくない人が、それをダンス・ミュージックとの交配の季節として振り返る。LCDサウンドシステム、ラプチャー、あるいはシミアン・モバイル・ディスコ(以下SMD)。その後、ニュー・エレクトロの新勢力がむしろロックの巨大さを取り入れていった。SMDは、その分水嶺とも言える存在だった。
そして、ポスト・ダブステップの拡張、あるいはジュークの登場がシーンに新たな風を吹かせているなか、SMDのフルレンス・アルバムが届いた。シリアスなテンション、冷え冷えとしたシンセ・アンビエンス、そしてミニマルな展開がビート・プロダクションを通底している。アンチ・クライマックスの美学......ここに愛想笑いの類はない。サービスのようなアップリフトもない。早い話、誤解の余地を排したストイックなテクノ・ミュージックが硬質な音色を叩き付けている。『Attack Decay Sustain Release』(2007)のアッパーさや『Temporary Pleasure』(2009)の弾けるような乱雑さの記憶からすれば、季節の変わり目を実感せずにはいられない、というのもたしかだ。
彼らはいま、どこにいるのだろう? 当時の活況、それは音楽的な交配ではなく、単にダンスとロックにおけるリスナーの重なりがあっただけではないか、その錯覚を自覚できていないだけではないか、という声もある。不躾ながらも、そういった所感を含めてSMDのふたり、プロデューサーとしてはここ数年トップ・クラスの売れっ子ぶりのジェイムズ・フォード、そしてジェイムス・ショーに話を訊いた。
結果から言えば......彼らのポップ・ミュージック、そしてシーン(という概念がまだ有効ならば、ということだが)に対する認識は、実に中立的である(途中、ややトンチンカンな質問にも真摯に答えてくれた)。彼らは変化を受け入れているし、何も背負っていない。そのニュートラルな姿勢は、ある種達観めいてもいる。そう、私はS.L.A.C.K.によるあの象徴的なリフレインを思い出す。ただミュージックのみ、ただミュージックのみ......。
シーンは確実に変わったと思う。「ダンス/ロックの融合」みたいなのってまずあんまり上手くいかないし、結局そこの地域で根付いているロックの要素が混じったダンス・ミュージック、っていうものになってしまっている。
■あなたたちの出身でもあるSimianは、歌とメロディを大切にしたインディ・ポップのバンドだったと思うのですが、ダンス・ミュージックへの傾倒というのは、何がきっかけとなったのでしょう?
SMD:Simianをはじめるずっと前からダンス・ミュージックは大好きだった。歌とメロディを大事にしながら同時にダンス・ミュージックにも傾倒するっていうのは当然可能だよ。
■なるほど。ちょっと古い話をさせてください。『Attack Decay Sustain Release』(2007)におけるあなたたちの初期のスタイルは、ロック・ミュージックとエレクトロニック・ミュージックのクロスオーヴァーである、という言い方が当時、少なくなかったと思うのですが、こうした見方には賛同できますか?
SMD:まったくもって不賛成だよ! 僕らが作ってきたのはいつだってダンス/エレクトロニック・ミュージックなんだ。『Attack Decay Sustain Release』にはギターも生のドラムも入ってないし、ロックの要素は全然なかった。あれって、ちょうどあの頃はダンス・ミュージックがいろんなロック/インディ・バンドとそのファン達に人気が出てきた時期だったからそのシーンと関わりがあっただけで、それ自体が僕らのスタイルだったってわけじゃないよ。
■わかりました。ところで現在、ポップ・ミュージックは細分化していると、私たちの国ではよく言われています。つまり、異なるジャンルや異なる価値観はお互いに関わらないよう、細かく分断されている、と。こうした見方を、あなたたちは共有しますか?
SMD:イギリスではむしろ逆だと思うよ。いまは違うジャンル同士の交流が盛んだし、とくにダンス・ミュージックの間ではそれが顕著だね。
■なるほど。ゲスト・ヴォーカルのパレードとなった2009年の『Temporary Pleasure』もそうでしたね。そこから一転して、2010年の『Delicacies』で、あなたたちはミニマルなテクノ・ミュージックへとスタイルの比重を大幅にずらしたようにも思えました。ヴォーカル・パートがなくなり、曲の長さも8分ほどに長くなりました。当時、何があなたたちを変化させたのでしょう?
SMD:『Delicacies』は、DJのための音楽を作るっていうことに特化したプロジェクトだった。僕ら自身もDJするときにテクノをよくかけるから、自分たち自身のための音楽でもあった。だから新しい方向性っていうのじゃなくて、サイド・プロジェクトっていう方が近いね。どのバンドも自分たちのスタイルを変えて進化させていかなきゃいけないと思う。同じようなアルバムを2回作るなんてことはしちゃいけないんだ。
■私もそう思います。さて、では本題です。新作の『Unpatterns』を聴かせてもらいました。『Delicacies』よりもさらにストイックなエレクトロニック・ミュージックで、ミニマルなビートが心地よいですね。ヴォーカル・パートは、歌というよりは声の素材、という小さい扱いになっている。また、ビートは以前よりもソフトなタッチになっているように思えます。これらの変化は意識的なものですか?
SMD:うん、かなりいい表現だね。確かに僕らはこのアルバムを控えめで抑えたものにしたかったし、ヴォーカルはカットアップやループしてミックスすることで楽器のように使っている。さっきも言ったように、『Delicacies』とはまた違ったアルバムを作りたかったんだ。前のアルバムからの要素はいち部残しつつも、同じような思い切りクラブっぽいレコードにはしたくなかった。
■どの曲も、たんにアップリフトというだけでなく、沈鬱なフィーリングを時間をかけてときほぐしていく、といった趣があるように思います。自分たちは変化したと思いますか?
SMD:典型的なダンス・ミュージックの美学って、ゆっくりと盛り上げていつまでもクライマックスに達しないままずっと続いて行ったり、緊張感を引き延ばしすぎだったりする。そういう盛り上げて、落としての繰り返しの手法はもう過去数年でやりつくされているんだ。だから僕らはそこから抜け出して、なにかもっと新しいことがやりたかった。
取材:竹内正太郎(2012年5月15日)
| 12 |
Profile
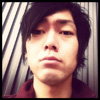 竹内正太郎/Masataro Takeuchi
竹内正太郎/Masataro Takeuchi1986年新潟県生まれ。大学在籍時より、ブログで音楽について執筆。現在、第二の故郷である群馬県に在住。荒廃していく郊外を見つめている。 http://atlas2011.wordpress.com/
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE

