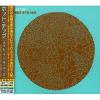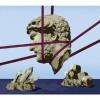MOST READ
- Columns 大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち」を振り返って
- 別冊ele-king 音楽が世界を変える──プロテスト・ミュージック・スペシャル
- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ
- Loraine James ──ロレイン・ジェイムズがニュー・アルバムをリリース
- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース
- KMRU - Kin | カマル
- Squarepusher ──スクエアプッシャーのニュー・アルバムがリリース
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Deadletter - Existence is Bliss | デッドレター
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- ele-king Powerd by DOMMUNE | エレキング
- HELP(2) ──戦地の子どもたちを支援するチャリティ・アルバムにそうそうたる音楽家たちが集結
- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- Free Soul × P-VINE ──コンピレーション・シリーズ「Free Soul」とPヴァイン創立50周年を記念したコラボレーション企画、全50種の新作Tシャツ
- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース
- Cardinals - Masquerade | カーディナルズ
- Laraaji × Oneohtrix Point Never ──ララージがワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの来日公演に出演
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
Home > Interviews > interview with Hot Chip - ダンスとポップが好きな理由――ホット・チップ、インタヴュー
2006年のセカンド・フル・アルバム『ワーニング』は、ホット・チップの名を広く世に知らしめるとともに、こんにちまでのバンド・イメージを決定することになった代表作である。アレクシス・テイラー(ヴォーカル)の叙情的なソング・ライティングと、ジョー・ゴッダード(シンセサイザー)の乾いたサウンド・メイキングは、同時期にフェニックスが提示したようなダンス・フロア仕様のガレージ・ロックに交差する、エレクトロニックなディスコ・ポップの軌道を描いた。
しかし〈DFA〉との邂逅によってスマートなダンス・アルバムとしてのアウト・プットを得たこの作品や、つづく『メイド・イン・ザ・ダーク』などの背後には、おそらくつねに2004年のデビュー作『カミング・オン・ストロング』がドグマとして意識されていたのではないかと思う。いま聴けば瀟洒なポップ・ソング集といったたたずまいのその作品は、実際にはそれぞれにマイナーなセンスを持っている彼らがなぜこんにちまでポップな表現にこだわってきたのかということの、ひとつの根拠となるようなアルバムである。
キミの両手にあるエンターテインメントの世界
腕の長さくらいの世界
"モーション・シックネス"
 Hot Chip In Our Heads Domino/ホステス |
エンターテインメント(ポップ)の世界といっても、それは卑小なきみの両腕の長さに収まるものだ......ホット・チップには、つねに自らの拠って立つ場所に対するアイロニカルな認識があった。アイロニーとしてのポップというのは、それじたいはありふれた批評意識であるが、移り変わりのはやいポップ・ミュージックのシーンにあって実践をつづけることはむずかしい(また、その実践が目的化してしまっても意味がない)。
5作目となる本作『イン・アワー・ヘッズ』で、彼らははじめてメンバー外の人間をプロデューサーとしてむかえた。それは彼らがなぜポップを志向し、ホット・チップというバンドをつづけているのかということの意味を整理するためではなかったかと思う。各メンバーはすでに優れたサイド・プロジェクトを持っていて、そこで自由にそれぞれの嗜好を試している。
ホット・チップとはすでにただやりたいことをやるプロジェクトという以上のなにかだ。その互いのバランスを塩梅するのが今回のプロデューサー、マーク・ラルフということになるだろう。 "ルック・アット・ホエア・ウィ・アー"や"ナウ・ゼア・イズ・ナッシング"など今作には思いきってR&B調の歌ものトラックがいくつか収録されている。ながく聴いているリスナーには少々カドが取れたように感じられるかもしれないが、次のステージをめざすアルバムとして、誠実でリアルなヴィジョンがある。むしろよりひろく新しいリスナー層によって咀嚼されていく作品ではないだろうか。ドラムマシン担当のフェリックス・マーティンはほのぼのとした人柄をしのばせながら答えてくれている。
ダンス向きのサウンドにしたいと思ったし、押し出しの強い、シングル向きなサウンドというね。ダンスフロアでもいける、クラブでもいける、そういうものを目指してたんだ。
■『Warning』まではホーム・レコーディングが基本スタイルで、前作『One LifeStand』もその原点に戻る作風でしたが、今回はマーク・ラルフとともにスタジオで制作が進められたのでしょうか?
フェリックス:これまでもアルバムのなかで3、4曲はスタジオでレコーディングしてたけど、1枚通して1箇所のスタジオでレコーディングするっていうのは初めてだった。レコードのサウンド的な面で必要だと思ったんだよ。そこに僕らの友だちのマーク・ラルフが来てくれて、プロデュースやレコードのエンジニアリングを努めてくれたんだ。共同プロデューサーとしてね。当然、彼はいろんな「おもちゃ」を持ってるからさ。音楽的なおもちゃをね。
■レコーディングの模様を教えてください。
フェリックス:今回は時間をかけてじっくりと、去年の8月から今年の1月、2月くらいまで休み休みしながらやっていたんだ。あまり締切のこととかも考えずに、自分たちに作れる最高の音楽にすることだけを考えて。これまで作ったレコードのなかでもっともミックスやサウンド的に満足しているアルバムになったと思う。今回のスタジオはクラブ・ラルフというところだった。いままでやってたみたいに、家で半分作ってきて、っていうのもできたと思うけれど、せっかく機材がたくさんあったからね。ホーム・スタジオだとそうはいかないし、そばに何でもわかる人がいてくれて作業するほうがよっぽどわかりやすい。実際にできあがったものを見ても、やっぱりはっきりと違うと思った。ここが違う、って明確に名指しできることではないけれど、たしかに違いはあると思う。より大きく、よりひろがりがあると思ったよ。
■音色もアレンジも豊富で、情緒的なソングライティングが基調となった前作『One Life Stand』に対して、今作はよりハードでディスコ寄りな作品であると感じます。制作にあたってメンバー間ではそうしたコンセプトが共有されていたのでしょうか。
フェリックス:そう、ダンス向きのサウンドにしたいと思ったし、押し出しの強い、シングル向きなサウンドというね。ダンスフロアでもいける、クラブでもいける、そういうものを目指してたんだ。それが僕らにとって大事なことだったから。それだけじゃなくて"ルック・アット・ホエア・ウィ・アー"や"ナウ・ゼア・イズ・ナッシング"のように内省的な曲もあるけど、それはアレクシスが書きたいと思う曲だったんだ。それもアルバムのいち部だし、それがなかったらホット・チップじゃない、と思うんだよね。ハウス・ミュージックとクラブ・ミュージックとのラヴ・アフェアがあってこそのサウンドだと思ってる。
■『イン・アワ・ヘッズ』というタイトルがアルバムの内容を指したものだとすれば、いまあなたがたの頭のなかや音楽は、とてもすっきりと整理されているように思われますが、いかがでしょう?
フェリックス:そうだね、実際は歌詞から取ったんだけど。1曲目の"モーション・シックネス"のなかに出てくる歌詞なんだ。それから、最後の曲にも出てくるかな。このレコードを聴いている70分くらいの間は、僕らの頭のなかが少しのぞけるよ、という意味もあるね。アルバムのタイトルをつけるときに、単純にシングルとか、アルバムの曲のタイトルにするのはイヤだったんだ。もう、それはやりつくしちゃったからね。
■"ルック・アット・ホエア・ウィ・アー"や"ナウ・ゼア・イズ・ナッシング"といった、R&B的でときにブルージーですらあるナンバーは、これまでのホット・チップからすれば異質なキャラクターを持っていますね。作品のなかでも絶妙なタイミングではさまれます。これらはどのように生まれてきた曲なのですか?
フェリックス: "ルック・アット・ホエア・ウィ・アー"は僕らがアメリカンR&Bを聴くのが好きなことから生まれた曲だね。古いデスティニーズ・チャイルドとか、Rケリーとか。この曲はアメリカでシングルとしてアピールすると思うんだ。"ナウ・ゼア・イズ・ナッシング"はアレクシスが途中まで書いて、いちどやめて、もういちど書き直したといういきさつがあるんだよ。ちょっとビートルズ風というかポール・マッカートニー風でね。僕らはみんなマッカートニー・ファンなんだよ。
取材:橋元優歩(2012年6月14日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE