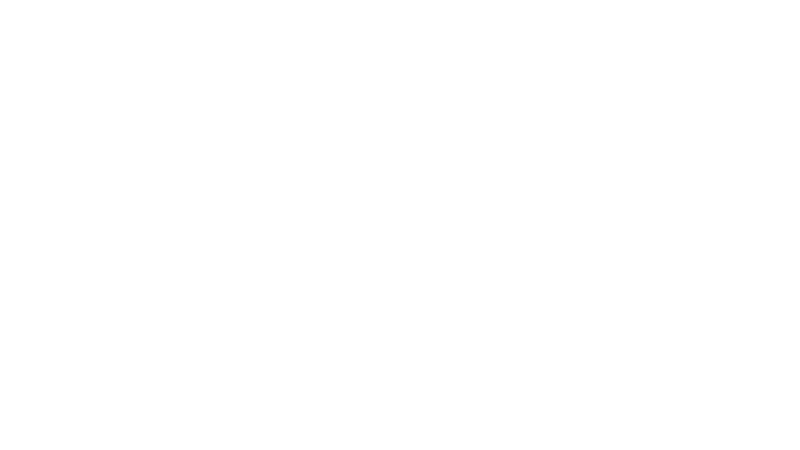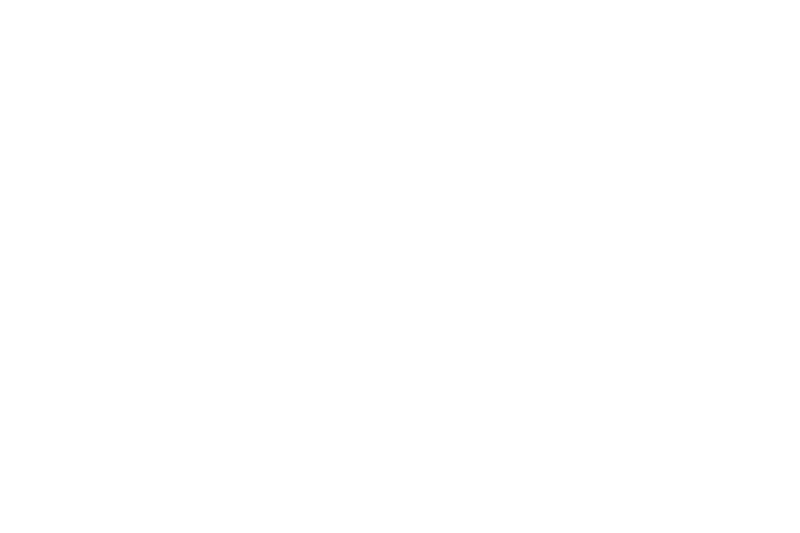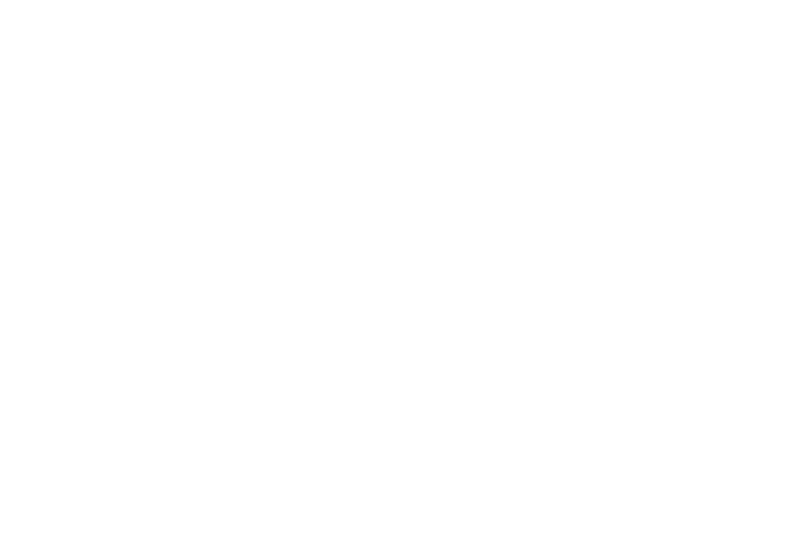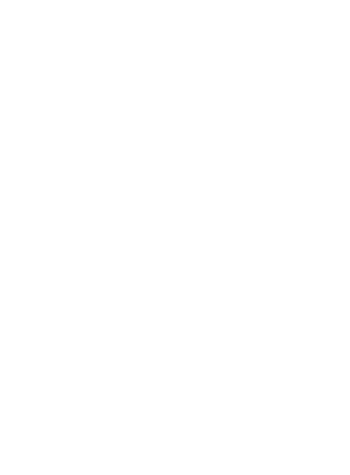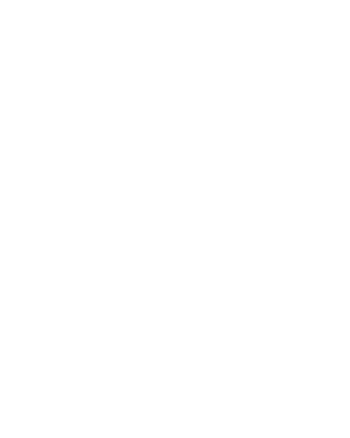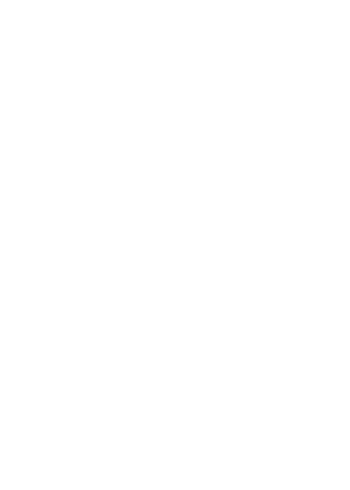ロンドンの高橋勇人からはいっこうにレヴュー原稿(NONのコンピ/sound patrol原稿)が送られてこないけれど、先日ロンドンの坂本麻理子さんから以下のようなリンクが送られてきた。
日本ではあまり知られてないが、今回ガーディアンはW杯特設ページにて、すべての日本戦を(もちろんイギリス人が)日本語で実況していたのである。リンクを読んでくれればわかるように、なかなか熱い。この実況者、世間から非難を浴びたポーランド戦も感情的にはかんぜんに日本の側だ。
https://www.theguardian.com/football/live/2018/jun/28/2018w
日本戦の実況をイギリス人の日本語で読むというのも21世紀的で面白いといえば面白い。ベルギー戦で、あんなルカクのような怪物がいるチームを(マリーシア=ずる賢さ、ナシで)ギリギリまで追い詰めた日本代表は、いっきに国際的な評価を高めたけれど、じっさい、いままでW杯で日本が評価されたことといえば、サポーターが席をたつときゴミを持って帰るだとか、そんなことぐらいだったので、今回の評価というか、試合を通じて世界にインパクトを残せたというのはほとんど初めてのことだったんじゃないだろうか。
音楽の世界でも、今世紀に入って日本の音楽がいままで以上に、エキゾティシズムとしてではなく純粋に作品として評価されてきていると言われている。が、そのひとつの発火点に、たとえばWIREのような左翼系知識人が関わっているメディアが、おそらく英米中心主義に対するアンチも込めてだろう、それ以外の文化圏の音楽を積極的に取り上げ続けていることがあると思う。日本だけが評価されはじめたわけではない。同じように、東南アジアも南米もアフリカもオセアニアもカナダも中東も。
しかしながら、たとえば昨日挙げたイタリアのテクノのコンピレーションの参加アーティストのほとんどがUK(ないしはNYないしはベルリン)のレーベルから作品を出している。これは、アンダーグラウンドのシーンにおいて長い時間をかけて培われてきたものがあるからだろうな。
W杯の事実上の決勝戦というのは、だいたいベスト8からベスト4あたりにあるものだ。今夜……というか深夜から朝方にかけての2試合は、そんなような試合だ。今大会のひとつの山場だろう。盛り上がりたい人は、ON-Uサウンドとシュガーヒル(オールドスクール・ヒップホップのリズム隊)との融合体、タックヘッドによる1987年のこの曲を聴いて気合いを入れましょう。
Tackhead - The Game