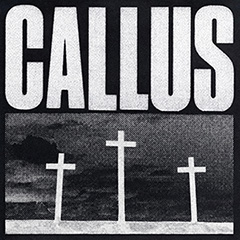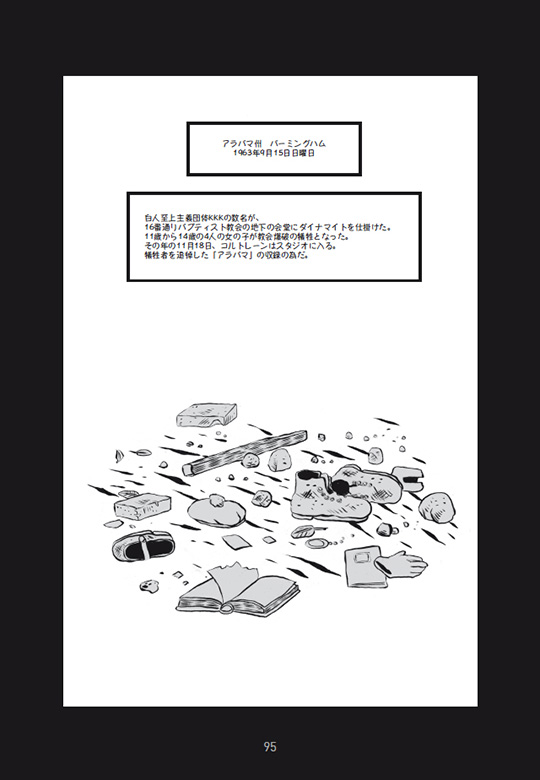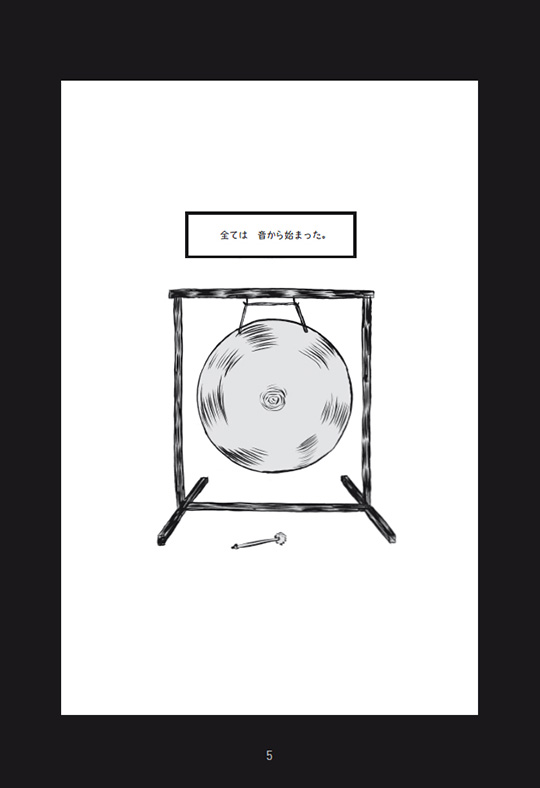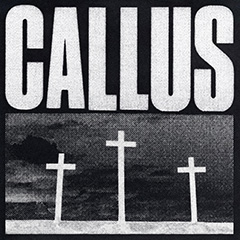 Gonjasufi Callus Warp / ビート |
いまの日本でこの音楽を聴くと、“汚さ”に違和感を覚えるだろう。すっかりお馴染みのシティポップ・マナー、これをやっておけば誰からも嫌われないだろうというネット時代の倦怠、保守的で、品性が良いだけのkawaii国では、ドレッドヘアーの汚らしいラッパーの歪んだサウンドは、まず似合わない。
逆に言えば、小綺麗な日本のシーンに居場所がない人にとっては、ゴンジャスフィの『カルス』から広がる荒野は心地良いだろう。汚さ……というものがなくなりつつある世界において、西海岸の(異端児)ラッパーは、4年ぶりの新作で、照りつける太陽と砂漠のような怒りをぶつけている。トム・ウェイツが幻覚剤を通して西海岸のビートを摂取したような、錆びたサンプルで歌うブルース歌手、悪夢と人生を賛歌するような、いろいろな感情が入り混じったなんとも魅惑的なアルバムである。ぜひ、聴いて欲しい。こんなサウンドもありなんだと、ひとりでも多くの人に知ってもらえたら幸いだ。
俺はオバマに投票するね(笑)。トランプになっても、ヒラリーになってもダメだ。いまのアメリカは、解決すべきものがたくさんあると思う。TVやインターネットがなければ、もっと良い世界になるはずなんだよ。
■2010年にあなたに取材したとき、あなたは「政治は大嫌いだし、政治にはいっさい関わりたくないと思っている」と話してくれました。11月に大統領選を控えていますが、今回は支持したい候補者がいなくて困っている人が多いと聞きました。
ゴンジャスフィ:たしかに選択肢はないな。俺はオバマに投票するね(笑)。トランプになっても、ヒラリーになってもダメだ。いまのアメリカは、解決すべきものがたくさんあると思う。戦争もそうだし、人種間の緊張感もそうだし、メディアに大きく左右されている部分もあると思うね。TVやインターネットがなければ、もっと良い世界になるはずなんだよ。皆、自分の判断ができる。政治には、いまだに関わりたくないね。ファック・ノーだ(笑)。
■この4年、いったい何をされていたのですか?
ゴンジャスフィ:体調をくずしていたから、そのリカバリーに1年くらいかかったんだ。その治療で強い薬を摂ったしていたから、死にそうにもなってさ。で、そこからまた回復しなければならなかったし、手術やいろいろ大変だったんだ。
■ヨガのほうはいかがですか?
ゴンジャスフィ:ヨガはもう2年くらい教えていない。引っ越したのもあるけど、いまのヨガ業界にもウンザリしていたんだ。ヨガ講師がインスタグラムをやったり、そこで人気になるのも良いケツをしたヨガ・インストラクターだったり、ヨガは「人からどう思われるか」ではないのに、外見を気にしたり、ステータスでヨガをやっている奴が多いんだよ。ヨガとは何なのかを本当にわかっていない。ヨガを教えてはいなくても、ヨガを好きなことは変ってないけどね。
■どこか、他の文化圏への旅行をされた経験などの影響はありますか?
ゴンジャスフィ:ギリシャに行っていくつかショーをやったけど、それ以外はアメリカを出ていない。あまりこれといった影響はないな。これからの予定は、12月にヨーロッパに行くんだ。そのあと、来年もツアーがある。もう1枚、春に出したいと思っているレコードがあるから、その準備もしないといけなくてね。〈ワープ〉からリリースされるんだけど、それもGonjasufiのレコードなんだ。
■では、どのようなきっかけがあって本作は制作されていったのでしょうか?
ゴンジャスフィ:制作をはじめたのは2013年、いや、2011年だな。ヴェガスで制作をスタートしたんだ。曲のなかには、2004年にサンディエゴで作りはじめたものもある。ギター・パートが出来ていて、あとから1年くらいかけてセッションで発展させていったんだ。
通訳:音楽制作は2011年からずっと続けていたのですか?
ゴンジャスフィ:前作が出た後から、ずっとレコード制作はしていたんだ。でも、2012年に病気になって、そこから制作のスピードが遅くなっていった。で、2014年にまた作業を再開して、トラックを仕上げはじめて、2015年にアルバムを完成させた。あと、音楽活動は常にやっていたんだけど、音楽業界からは離れていたね。業界がイヤになってね。でも、音楽そのものへの愛が変わったことはない。あのジェイ・Zの一件があってから(2013年、ジェイ・Zがゴンジャスフィの曲をサンプリングした)、早くレコードを出せとまわりりがうるさかったんだ。でも俺自身はその準備が出来ていなかった。金のために音楽はリリースしたくなかったし、そんなことしたら、音の出来の悪さにがっかりするリスナーも出てくるだろうしね。
■元キュアーのパール・トンプソンが参加していますが、1980年ぐらいのUKのポストパンク、しかもゴス的な感覚というか、ノイジーでダークな衝動を感じましたが、いかがでしょうか?
ゴンジャスフィ:そういった音楽からも影響は受けているよ。最近もよく聴いているんだ。最初は、自分でギターとドラムを演奏して作っていたんだけど、ギターの部分が自分ではうまく表現できなくてフラストレーションがたまっていた。指が思うように動かなかったんだ。そこで、彼に依頼することにしたのさ。
通訳:あなたはこのアルバムの方向性をどのように考えていますか?
ゴンジャスフィ:ただただ、俺は正直なアルバムが作りたかった。俺の中身がそのまま表れている作品をね。あと、音的にはダークでディストーションの効いた作品を作りたかったというのはあったな。それと、痛みが表現された作品。俺は、フェイクな内容なものを作ることは避けたかったんだ。ララララ~なんて、エレヴェーターで流れているような音楽は作りたくなかった(笑)。まあ、作ろうと思えば作れるぜ(笑)。めちゃくちゃ良いR&Bレコードを作れる自信はある(笑)。絶対に金になるだろうな(笑)。
■いま、痛みを表現したかったとおっしゃいましたが、強いて言うなら、今回は怒りのアルバム? 苦しみのアルバム?
ゴンジャスフィ:選べないな。どっちもだよ。いまだに怒りはあるし、苦しんでるし(苦笑)。
通訳:どんな怒りや苦しみを未だに抱えているのですか?
ゴンジャスフィ:子供を育てる環境もそうだし、金銭問題もそうだし、自分のまわりのことすべてさ。俺はミリオネア(金持ち)じゃないからな。でも、レコードには愛もつまっている。ネガティヴなエナジーを音楽を作ることによってポジティヴに変えているんだ。
■“Afrikan Spaceship”や“Shakin Parasites”のようなインダストリアルなビートからはマーク・スチュワートを思い出したんですが、お好きですか?
ゴンジャスフィ:誰? わからないから答えられない(笑)。ははは。
通訳:ポップ・グループの人ですよ。
ゴンジャスフィ:ホント知らないんだ。
■たとえば“Carolyn Shadows”や“The Kill”など、今回のアルバムの重苦しさ、こうしたエモーションの背後に何があったのかを教えてくれますか?
ゴンジャスフィ:難しい質問だな。どの曲にも同じアプローチで望んだし、同じ感情が込められていると思う。俺のソウルが込められているんだ。それがブルースってもんだろ? そのソウルは、“ファック・ユー”でもあるし、“アイ・ラヴ・ユー”でもある。そのふたつは紙一重だからな。
で、何があったんだっけ……"The Kill"の歌詞を振り返ってみるから、ちょっと待っててくれよ。あれは……正直わかんねえな。歌詞を書いているときって何も考えないんだ。俺って説明出来ないんだよ。そのとき感じている痛みだし、それを振り返ること自体も痛みなんだ。母親と話しているときも説明を求められて、俺、ぶちぎれるんだよ(笑)。ゴッホにだって、何でその絵を描いたのかなんて訊かないだろ(笑)? そこから何を自分が感じるかが大切なんだ。いちいち説明を求められると、気が滅入るんだよ。俺の母ちゃんは、俺の大ファンだけどな。両親とも仲は良いけど、母ちゃんの方が近い。「この曲が好き」とか、毎日メールしてくるしな(笑)。でも、はいはいって感じで流すんだ(笑)。
母親はサンディエゴに住んでいるから、俺は年に2、3回くらい帰るようにしてる。子供が俺の子供しかないから、彼女を孫に会わせるのは大切だと思って。母親って好きなんだけど、ずっとはいれない。わかるだろ(笑)? 俺の人生初のコンサートは8歳で、衣装も全部母ちゃんががデザインしてくれたんだ。頑張れと楽屋の前で励ましてくれた。観客席からも応援してくれている姿が見えたし、彼女は俺のすべてだな。この話をしていたら、泣きそうになってきたよ(笑)。
どの曲にも同じアプローチで望んだし、同じ感情が込められていると思う。俺のソウルが込められているんだ。それがブルースってもんだろ? そのソウルは、“ファック・ユー”でもあるし、“アイ・ラヴ・ユー”でもある。そのふたつは紙一重だからな。
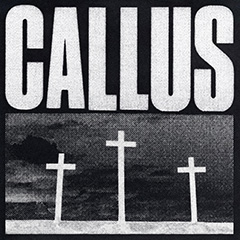 Gonjasufi Callus Warp / ビート |
■あなたは、スーフィーやトルコなど、中東文化を取り入れるのも早かったと思うのですが、今日の音楽の世界では、わりとそれはひとつのトレンドにもなっています。苛立ちはありますか?
ゴンジャスフィ:いいことだと思うぜ。知られることで音楽も広がるし、受け入れられるのはいいことだと思う。
通訳:トレンドを追うこともありますか?
ゴンジャスフィ:いや、きらいだな。君はどう?
通訳:私はたまにのってしまいますね。
ゴンジャスフィ:いまは何の流行にのってるんだい?
通訳:グリーンスムージーとか(笑)?
ゴンジャスフィ:ははは! 出た! 俺はパープルじゃないと飲まないね(笑)。ベリーが入ってるから美味しいんだ。グリーンは激マズ。ファック・ノーだな。マジで無理(笑)。芝生なんて入れやがってさ。とくに胃が空っぽの時は無理だな(笑)。
■政治的に言えば、今日ではイスラムへの偏見はさらに増しています。そうした偏見への怒りは、今回の作品の主題にはありますか?
ゴンジャスフィ:そうだな……もちろんそれがテーマになっているものもあるし、すべての曲に入っている。“Maniac Depressant”は、宗教や人種に関しての怒りが歌っているし、“Krishna Punk”も、人びとの関係について歌っている。アメリカ全体の問題がこのアルバムではテーマになっているんだ。
■“Krishna Punk”は曲調も一風変わっててユニークですが、歌詞には、たとえばなにが綴られているのでしょうか?
ゴンジャスフィ:この曲では、“組織”についてが歌われているんだ。歌詞を思い出してみるから待ってくれよ。「共同体を崩し……世界を救え。組織を消して、テレビをなくせ。そうすれば自由になれる」そんな感じだな。俺たちが組み立ててきてしまったものを崩せ、みたいな内容。フリースタイルさ。俺にとっては、フリースタイルで歌う方が簡単なんだ。昔からやってきたからな。サンディエゴやLAのアンダーグラウンドは皆そうなんだよ。
■『カルス』というタイトルは、どこから来たのでしょうか? そこにはどんなメッセージが込められていますか?
ゴンジャスフィ:自分の心臓の周りにスペースを作っているんだ。世界からの攻撃から自分を守っているのさ。俺というより、世界が俺の心に“たこ”を作った。でもそれは美しいことでもある。純粋なものをを守ることが出来るからね。俺は、敵を近くに置いたりはしない。近くに置くのは家族だけ。同時に、俺は悪から逃げることもしないんだ。それよりも、向こうが目を背けるまでじっと見ていたい。あと、悪というのは男のエナジーだと最近気づいたんだ。神は女性のエナジー。男は命令して何かをさせようとするけど、女は全体を見てバランスをとろうとする。男にはマッチョなエゴがあるんだ。神は男という考え方は、捨てるべきだね。
■“Your Maker”や“Prints Of Sin”のようにヒップホップ・トラックを発展させたような曲もありますが、今回の作品のなかにフライロー周辺からの影響はありますか?
ゴンジャスフィ:ないね。彼と俺の音楽に近いものは何もない。でも、彼自身のことは大好きだけどな。彼は俺の人生を変えたし、借りがたくさんあるんだ。まわりの奴らが俺にビビっていたときも、スティーヴ(フライロー)は温かく接してくれた。サウンドの影響はないけれど、やりたいことをやるという彼の姿勢には確実に影響を受けているね。彼も繊細だし、俺も繊細。人生短いんだから、大胆にいかないと。人間皆繊細だし、自信もない。でも、その氷を崩していかないといけないんだよ。
■前回の取材で、「ジミは世界いち最高にクレイジーなマザー・ファッカー野郎さ」とあなたは話してくれましたが、とくに今回はその影響が強いと思いますか?
ゴンジャスフィ:ジミは前ほどは聴いていない。でも、俺は彼の演奏を見てから、演奏と歌をすぐにはじめたんだ。彼はいまだに大きく影響を受けているし、彼のあの特有のリズムとあのリズムと同時に歌うことが出来る才能は、本当に素晴らしいと思う。あれは、やろうと思うとすごく大変なんだ。あの時代にそれをやったのもすごいし、しかも左利きでもある。あれは神だな。彼とマイルズ・デイヴィスとプリンスの3人はそう。デイヴィッド・ボウイもそうだな。
■あなたがジミ・ヘンドリックスのアルバムでいちばん好きなのは、『Axis: Bold As Love』ですか?
ゴンジャスフィ:そうだな……『Axis: Bold As Love』だと思う。
通訳:それは何故?
ゴンジャスフィ:わからないけど、俺が聴いてきた経験でそう思うんだ。この質問はいままで聴かれたことがなかったから、すぐにはわからない。ジミ・ソングだったら、“Voodoo Child”だな。
■前作のときと違って、現在カリフォルニアでは大麻は合法です。こうした状況の変化は新作にどのように関係していますでしょうか?
ゴンジャスフィ:もちろん制作中は吸ってたさ。体調も崩していたから、薬としても使っていた。でも、いまは吸ってないんだ。半年は吸ってないね。1、2年やめようと思ってる。実は、『A Sufi and a Killer』のときはほぼ吸ってなかったんだ。今回は、スロー・ソングのときはだいたい吸ってた。でも、いまは酒も飲まないし、飲むとしてもビール6缶を3ヶ月で飲み終わる程度。酒を飲むとリカバリーに時間がかかるし、身体が拒否するんだ。サンディエゴに帰ったときに一杯飲んだりはするけど、それも5ヶ月に1回とかだしな。ワインも好きだけど、カミさんが妊娠してるし、いまは飲んでない。俺、長生きしたいんだよ(笑)。いまは子供がいるしな。子供が産まれるまでは、40歳くらいまで生きれればいいと思ってたけど、いまは80歳まで生きないと(笑)。60歳になって腹が出て、シワだらけになったとしても、俺はシャツを脱いで上半身を見せるぜ(笑)。女がどう思うかなんてどうでもいい。じゃなきゃ、いまだってヒゲをはやしてはいないしな。ないほうがハンサムって言われてるんだ(笑)。でも、カミさんはありのままの俺を愛してくれているからそれでいいのさ。
■あなたはヨガのインストラクターですが、多くの人はヨガをやるべきだと思いますか?
ゴンジャスフィ:全員やるべきだ。それに、子供や身体障害者、病人たちにはタダで教えるべきだと思うね。学校のカリキュラムやリハビリ、刑務所のプログラムに取り入れるべきだと思う。俺の娘もやってるし、平和な気持ちを得るには必要なものだと思うから。週3~5回はやりたいね。このレコードの売上金で、ジョシュア・ツリーにヨガ・スタジオを作ろうと思って。ただし俺は、ヨガで金もうけしようとは思わない。ただ、ヨガを広げたいだけなんだ。
■いま世界は転換期を迎えていますが、このような時代に、「ぼくたちに何ができる」と思いますか?
ゴンジャスフィ:ヨガさ(笑)。インターネットとテレビを消して、自然に注目すること。人に合わせるんじゃなくて、自分自身を持ち、自分が受けた恩恵をまた別の人に送り、親切の輪を広げていくことだね。世界や周りを変えるより、まず自分を変えればいい。皆がそれに集中すれば、世界なんてすぐに変わるさ。
通訳:ありがとうございました!
ゴンジャスフィ:ありがとう。またな。