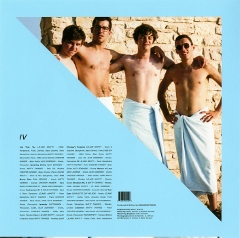MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > BADBADNOTGOOD- IV
バッドバッドノットグッドほど憎らしくも共感する同世代のバンドはいない。僕が彼らと同世代の人間だからこそ反発を感じるし、同時に彼らの音楽に共感もし、感銘を受けてしまうのだ。
バッドバッドノットグッド(以下BBNG)には、どこか憎みきれないようなキャラクター性があるし、それはジャズという高い演奏技術を必要とする音楽のハードルを、すこし下げてくれたことと関係しているのかもしれない。「自分にもできるかもしれない」と思わせ、我々の音楽に対する意欲を刺激してくるのである。
最初にBBNGを知ったのはたぶん3〜4年くらい前、オッド・フューチャーのタイラー・ザ・クリエイターとのスタジオ・セッション映像を、ユーチューブで偶然見つけたことがきっかけだった。その頃の僕はUCD率いるヒップホップ・バンド、ザ・ブルシットにドラマーとして加入したばかりで、マーク・ジュリアーナやリチャード・スぺイブン、シゲトやクエストラヴといったような、マシン・ビートのグルーヴを人力で再現しようとするようなドラマーを追いかけていた。機械的なビートのニュアンスを取り込み、人力で再現しようとする発想が、当時の僕にとってはとても興味深かったし、同時代の音楽で一番クールに見えたのだ。
そんなようなことをしている人たちを漁っていくうちに見つけたのが、先述した動画であったのだが、初めて見たときには正直言って、いけ好かないヤツらだと思った。タイラー・ザ・クリエイターとのコラボレーションによって一躍知名度を上げたたという経歴や、トロントの音楽大学出身というわりには粗く聴こえてしまう演奏技術、おふざけで豚のマスクを被ってしまうようなセンスがハナについてしまったのだ。ゆえに2014年にリリースされたアルバム『Ⅲ』は軽く聴き流しただけ。彼らに対してのジェラシーを抱きつつ、しかしながら気にはしつつ……、というスタンスであった。
印象が変わりはじめたのが、ゴースト・フェイス・キラーとのコラボ・アルバム『サワー・ソウル』を聴いてからだ。それまでのバンド・サウンドのヒップホップとは一線を画す、言うなればサンプリングの元ネタとなるようなソウルの曲を、スライスしないでそのままループしたようなトラックに驚いた。そしてなにより、ドラムのアレックス・ソウィンスキーが叩くビートの、いわゆるディラ直系の訛ったビートではなく、フィルが走ってつんのめってしまう、ミッチ・ミッチェルを彷彿とさせるグルーヴ感が新鮮だったのだ。とくに新しいことをやっているわけでもないのに、ラップが乗っかることによって、新鮮なヒップホップ・サウンドになることに驚き、彼らに対する印象が変わった。こんなことが出来るようなヤツらなのかと。
そして、新作『Ⅳ』である。これには参った。BBNGの持つ、ロバート・グラスパー系とは違う独特の空気感や演奏のドライヴ感もさることながら、録音物としての完成度も更新されている。クラシック然とした雰囲気も感じとれるが、彼らはジャズ×ヒップホップの枠組みから自由に、既存ジャンルに囚われない音楽を作り上げているのだ。
『Ⅳ』において印象的なのは、卓越した演奏技術を持っていないからこそ引き立つ、アンサンブルの妙である。とくにヴォーカルをフィーチャーしたトラック、“タイム・ムーヴス・スロウ”や“イン・ユア・アイズ”において、それが顕著に表れている。この2曲においてBBNGは決して派手な演奏はしておらず、バッグ・バンドに徹している。あくまでもヴォーカルを引き立てるためのクールな演奏だ。
しかしながら、おそらく本作から新メンバーとして加わった、リーランド・ウッティーによるストリングス・アレンジや、オーヴァー・ダビングされたギター(これもウッティーによる演奏。“イン・ユア・アイズ”においてはマンドリンの音も聴こえる!)やキーボードが絶妙に配置されており、ブラシによって刻まれる16ビートやメロディックなベースラインも合わさって、一聴するとシンプルだが、聴けば聴くほど計算しつくされたアレンジであることがわかるつくりになっている。
リーランド・ウッティーがBBNGに正式加入したことによるサウンドへの影響がかなり大きいことは言うまでもないかもしれないが、サックスだけでなく、ギターやヴァイオリンなども演奏できるという彼のマルチなスキルは、確実に『Ⅳ』の録音物としての完成度を高めているだろう。“チョンピーズ・パラダイス”では、管楽器のオーヴァー・ダビングによって、ジャズの空気感を残しつつも、スタジオ・レコーディングでしか出来ないことをしている。
また、ヤマハのアナログ・シンセサイザー、CS60と管楽器のアンサンブルを聴いているだけで恍惚的な気分になってくる。同曲や“スピーキング・ジェントリー”などで垣間見える、シンセサイザーと管楽器のアンサンブルの絡みはオランダ出身の若手ギタリスト、ライナー・バースの“オフ・ザ・ソース”などでも感じとれるが、これはインディ・ミュージックとジャズとの邂逅による響きとも言えよう。
上記の3曲や、アルバム表題曲である“Ⅳ”などを筆頭に全体的に70年代テイストに仕上がっているように聴こえるのは、楽曲の構造が起因していることはもちろんであるが、録音・ミックスも大きく影響しているのではないだろうか。BBNGの作品全般にも言えることだが、とくにドラムの音においてそれが顕著だ。ヒップホップを通過したバンドとは思えないほどバス・ドラムの音量が控えめだし、スネアのチューニング具合や、ハイハットの音がやけに大きかったりするようなところが、70年代のあの音像を彷彿とさせるのである。
BBNGのドラマー、アレックス・ソウィンスキーがこのような意図をもって演奏していることは、彼のドラムセット遍歴を追えば、おのずと見えてくることでもある。ライヴ映像で確認する限り、初期のBBNG(2012年ごろ)ではタムはフロア・タムのみで、サンプル・パッドを導入している。
このセッティングはおそらく、ダル・ジョーンズ、クエストラヴをはじめとするヒップホップ系ドラマーの流れを汲んでいると思われる。
しかしながら、近年になるにつれ、サンプル・パッドをスネアの横に置き、ハイタムを導入することも多くなってくる。
些細な違いではあるが、ハイタムを導入することによって、よりロック・フィーリングな(つんのめった)タム回しや、よりヴォーカル・バッキング的な軽いフィル・インの演奏を可能にするのである。
このセッティングの遍歴は、『Ⅲ』においてヒップホップ・ドラム的なアプローチを模索していたことと、『Ⅳ』において70年代のジャズ・ロック感を演出するのに一役買っていたことと対応している。
BBNGが『Ⅳ』において提示するのは、ランプやウェザー・リポートらが遺したヒップホップ・トラックの元ネタになるような曲を、あえてやってしまう面白さなんだと思う。ジャズがヒップホップやR&Bと結びついているからこそできる、最先端の回帰的アプローチなのである。近年のジャズ・シーンやヒップホップ・シーンを経験しているからこそ、トラックの元ネタとなる音楽をやってもそのままにはならないし、むしろそれが面白いということをBBNGが証明したのである。
アルバムに収録された曲を1曲ずつ見ていくと、参照元となるジャンルが異なっていたり、統一性がないようにも思えるが、実際アルバムを通して聴いてもみると違和感がないこのセンスは、時代やジャンルを並列的に見ることができる、インターネット世代だからこそ可能な構成の妙なのではないだろうか。
今後、彼らの後を追うようなバンドや音楽が出てくるだろう。僕らの世代が過去を参照しながら新しい音楽を作り上げていく──この感じが最近気持ちよくてしょうがない。いま、そんな同世代の音楽が、バッドバッドノットグッドが、とてもクールだ。
菅澤捷太郎
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE