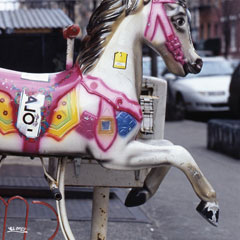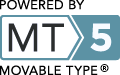ヒップホップの歴史を紐解けば、ハイプ・ウィリアムスという名前に出会う。ハイプは、ミュージック・ヴィデオにおいてラッパーをローアングルで撮った映像作家で、つまり、ラッパーを必要以上にでっかく見せた作家だ。USヒップホップ史には「ハイプ以前/ハイプ以降」という言葉さえある。UKのディーン・ブラントと名乗る男性とインガ・コープランドと名乗る女性が自分たちのプロジェクト名になぜ彼の名前を選んだのかは、いまところ秘密のままである。名前を盗用するにしても、なぜそれが「ハイプ・ウィリアムス」だったのか……、真っ当に想像していけば、ヒップホップ的映像の型=クリシェを作ったことへのおちょくり、パロディ、たんなるジョーク、シニカルなユーモアだったとなる。クリシェを弄ぶこと、おちょくることは、ディーンとインガのハイプ・ウィリアムスの作品に共通した態度だった。だが、そこにはリスペクトもあるように感じさせてしまうところが、彼らのややこしさでもある。
それはドープでサグなイメージをバラ撒きながら、じつは頭で聴く音楽ということだ。他界した天才フットボーラー/戦術家のヨハン・クライフは、サッカーを足ではなく頭でやった人だった。ハイプ・ウィリアムスにとっての音楽も頭で作るものだった。彼らの音楽は基本インストだが言葉は欠かせないし、言葉は両義的に思えた。そもそも彼らは自身の名前からバイオからすべてをでっち上げて登場したのだから。
ハイプ・ウィリアムス解散(?)後、しばらくディーン・ブラントなる名義で活動を続けていた彼だが、昨年からベイビーファーザー名義を使いはじめている。ほかにも@jesuschrist3000ADHD名義とか……ややこしい。覚えられたくない、というわけではない、覚えられたいけれど通常の覚え方では覚えられたくないということなのだろう。
で、baby fatherとは未婚の父を意味する言葉で、スコットランドのヤング・ファーザーズを意識してなのか、あるいは本当に彼が未婚の父なのかはわからない。とにかく彼は2015年にディーン・ブラント名義で『Babyfather』なるアルバムを〈ハイパーダブ〉から配信のみでリリースすると、配信のみでベイビーファーザー名義の『UK2UK』、2016年の1月にはARCAが参加した曲「Meditation」を〈ハイパーダブ〉からフィジカル・リリース、さらに『Platinum Tears』を無料DLでリリースしている。そしてここに〈ハイパーダブ〉からフィジカル・リリースのアルバムのお出ましである。
「これが私に英国人であることの誇りを与えます(this makes me proud to be British)」という言葉からはじまり、言葉はアルバムのなかで何回も繰り返される。移民の子として生まれ、クラブで働き、苦労しながら俳優になったイドリス・エルバの言葉で、彼にとって(そしてディーン・ブラントにとっても)〝英国人としての誇り〟〝英国人としてのアイデンティティ〟を覚えるのはクラブ・カルチャーであり、音楽というわけだ。ディーン・ブラントにしては、まっすぐなメッセージである。
実際、新作の『BBF』は途中なんどか引き裂かれながらもUKブラック・ダンス・ミュージックのタフさにおいて楽観的な結末へと展開する。ディーン・ブラント名義の、2012年の〈ヒップス・イン・タンクス〉からの作品、2014年の〈ラフ・トレード〉からの作品では、バラードを歌ったり、フォークをやったり、ゲンズブールをへろへろにしたような歌を歌ったりと、わけのわからない方向に走った彼だが、『BBF』の特徴は、彼が明らかにクラブ・カルチャーに寄っていることだ。
ヒップホップ・ビート、レゲエのダンスホール、ブレイクビート、グライム、ゲットー・ミュージック……いかにもUKらしい、初期マッシヴ・アタックのような、UKの雑食的クラブ・カルチャーから聴こえる多彩なビートの数々、そしてベースとメランコリーがある。Micachuが歌う曲は、マッシヴ・アタックにトレーシー・ソーンが参加した“プロテクション”を彷彿させなくもない。ARCAが参加した“Meditation”もリズムはダブ/レゲエだ。ジャマイカ色はところどころに出ていて、アルバムで躍動するリズムからは、移民が作ったUKのストリート・ミュージックへのシンパシーを感じる。アートワークで描かれている、再開発されたロンドンの嫌みったらしいほど高級で美しい光景に消されているロンドンを描いているのだろう。
日本でOPNがこれだけ評価されて、(まあ、OPNにクラブというコンセプトはないので比べるのも間違っているのだけれど、同じ時期に注目されたエレクトロニック・ミュージックとして、しかも欧米ではOPNと同じように高評価だというのに)なぜ日本ではハイプ・ウィリアムスが……ディーン・ブラントが……という思いがぼくにはずっとある。あまりにもUK的な捻くれ方が日本では受けない原因なのだろうか。ライヴにおけるストロボもボディーソニックな音響も、頭を使わせる仕掛けも、ぼくに言わせればハイプ・ウィリアムスのほうが上だった。
まあ、取材を受けるわけではないし、過去の数少ない取材でも嘘ばかりだったし、ディーン・ブラントはわかりづらいアーティストのひとりではあるが、この新作は思いのほかダイレクトに響く。何かの間違いで怪しげなラジオ局の電波をキャッチしてしまった、しかもそのラジオ番組では現代の、最高にハイブリッドなUKダンス・ミュージックがかかっていたと、そんな感じのアルバムで、英国人でなくても楽しめる。ひとりでも多くの人に聴いて欲しい。