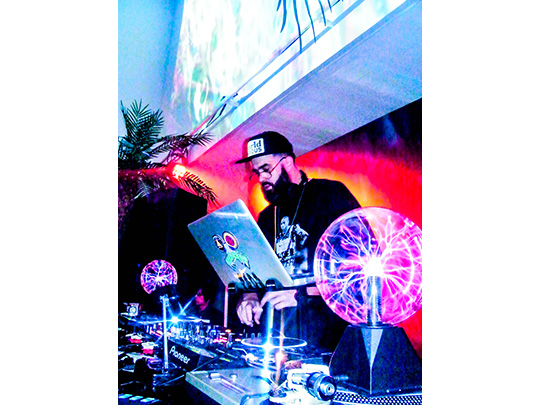MOST READ
- 別冊ele-king J-PUNK/NEW WAVE-革命の記憶
- ele-king Powerd by DOMMUNE | エレキング
- 『90年代ニューヨーク・ダンスフロア』——NYクラブ・カルチャーを駆け抜けた、時代の寵児「クラブ・キッズ」たちの物語が翻訳刊行
- FESTIVAL FRUEZINHO 2026 ──気軽に行ける音楽フェスが今年も開催、マーク・リーボウ、〈Nyege Nyege〉のアーセナル・ミケベ、岡田拓郎が出演
- 早坂紗知 - Free Fight | Sachi Hayasaka
- 二階堂和美 - 潮汐
- Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs - Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs | テレサ・ウィンター、バースマーク、ゲスト、エイモス・チャイルズ
- interview with Flying Lotus フライング・ロータス、最新EPについて語る
- Jeff Mills with Hiromi Uehara and LEO ──手塚治虫「火の鳥」から着想を得たジェフ・ミルズの一夜限りの特別公演、ゲストに上原ひろみと箏奏者LEO
- 大友良英スペシャルビッグバンド - そらとみらいと
- 別冊ele-king 音楽が世界を変える──プロテスト・ミュージック・スペシャル
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Yoshinori Sunahara ──74分のライヴDJ公演シリーズ、第二回は砂原良徳
- interview with Acid Mothers Temple アシッド・マザーズ物語 | 河端一、インタヴュー
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- Columns 大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち」を振り返って
- KMRU - Kin | カマル
- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ
- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース
Home > Interviews > interview with Prince William(Fade To Mind) & Miles, Martinez(Subtrança) - ベース・ミュージック新時代
〈FTM〉と〈ナイト・スラッグス〉はふたつでひとつのレーベルだと思う。僕たちはビヨンセやリアーナ、クラシックなR&Bに大きな影響を受けている。エモーショナルな歌が大好きだ。ブレンディーのレコードは去年のお気に入りだな。ジェシー・ウェアもわるくないけど、彼女の場合はスタイルに重きがあるよね。僕はエモーショナルなものが欲しい。メアリー・J. ブライジのように。
■ングズングズも含め、〈FTM〉のみなさんのDJプレイはダンスを強く希求するハイエナジーなものでした。本誌でも工藤キキさんが〈GHE20G0TH1K〉(ゲットーゴシック)の客のファッションについて「90'Sのレイヴの独自の解釈?」と表現していましたし、PROMの甲斐さんも「まるでレイヴだった」と話してくれました。あなたたち自身は、たとえばかつてのレイヴ・カルチャーないしはセカンド・サマー・オブ・ラヴに対して憧憬はありますか?
マイルス・マルチネス:僕個人的にはオリジナル・クラブ・ミュージックというのは、ヨーロッパではなくアメリカ発祥のそれであって、シカゴ・ハウス/シカゴ・ジューク/デトロイト・テクノなどかな。初めて好きになった音楽はヒップホップで、それからすこし違う文脈でハウスやテクノを知るようになった。
プリンス・ウィリアム:僕も初めはヒップホップから入ってデトロイト・テクノのようなものを知った。でもエズラはまったく違くて、彼はヨーロッパのクラブ・ミュージックに入れ込んでいた。彼も僕もドラムンベースは大好きだし鍵となる影響を受けているし、ドラムンベースは僕のなかでヒップホップとテクノとを繋いでいる橋なんだけれど、僕がヒップホップに入れ込んでいる一方で、エズラはR&Bに入れ込んでいた。ラジオでかかる音楽を実験的なテリトリーに引き込みたいというアイディアがあったんだ。ヨーロッパの国営放送では実験的なレコードがかかるよね。それはただのポップではない。アメリカのラジオは崩壊したシステムで成り立ってる。DJに金を払わなければいけない。良いレコードをつくってラジオでかけてもらうということがアメリカではありえないんだ。
はじめてレイヴが起こった頃に僕は14歳だったし、レイヴはヴィジュアル面でとてつもなく大きい影響があったこともたしかだ。フライヤーとかモーション・グラフィックとか、エズラもアート・ダイレクションにすごくレイヴカルチャーの影響を受けているよ。
マイルス・マルチネス:そう、そのとおり。
プリンス・ウィリアム:でも同時に、90年代のレイヴ・カルチャーは逃避主義的すぎた――ディプレスやデジャヴからの逃避。僕らはひとびとに触れあいがあってほしいし、「いま」を生きてほしいんだ。クラブの外に出たとき自分たちがどこにいるのかを認識してほしいんだ。なにも日々の仕事から離れさせようとか落ち込んでいるのをカヴァーするとかではなく、僕は気分の沈みをクリエイティヴィティに変えるのを助けたいんだ。僕らのメインドラッグは珈琲だよ(笑)。
■カフェインもなかなかですからね。プリンスはコンセプトについて語ると一貫していますし、〈FTM〉が逃避ではなく、いま現実を生きる活力としてのダンスを主張しているというのがよくわかりました。それでは、最近聴いた音楽でよかったものと、うんざりしたものを教えてください。
プリンス・ウィリアム:インク。インクだよ。僕たちのもっとも好きな音楽だし、とてつもない影響をもらっているし、新しいアルバム『ノー・ワールド』はつねに車でプレイしている。
不満をいうなら、トラップだね。あれはカウンター・カルチャーじゃないと感じるし、事実あれはアメリカのラジオでかかっている。たとえば、ビヨンセがトラップに乗った音楽がある、一方でトラップのインストゥルメンタルだけの音楽がある。どっちがほしいだろう? 僕はビヨンセが欲しい。わかるかな。僕はトラップのインストじゃなくてビヨンセがあればいい。それにトラップはサザン・スタイルのヒップホップだ。でも南部じゃないひとたちがたくさんトラップを作っているでしょう。そんなのはリアルじゃないよ。ただのトレンドだ。
マイルス・マルチネス:僕はDJラシャドが好きだな。新作はもちろん、古いのも。クドゥーロも好きだし、グライムも好きだし......なんていうかな。
プリンス・ウィリアム:マイルスはとてもポジティヴだからね。
マイルス・マルチネス:はは(笑)。好きじゃないものは聴かないから。音楽雑誌も読まなくなったし、欲しいものをは自分で探すようにしてる。僕はングズングズが大好きだし、ジャム・シティもキングダムもファティマ・アル・カディリも......シカゴの音楽も、マサクーラマンも、E+Eとかも...とにかく友達はすばらしい音楽を作るし、それが好きなだけだよ。
■それでは最後の質問です。あなたたちが日本にくるまえ、2年前に、震災と原発の事故があったことはご存知ですよね。日本国内の市民である僕たちでさえ安全だとはとても言えないのですが、そんななか自国を離れ、わざわざ日本に来るのは不安ではなかったですか?
マイルス・マルチネス:この世界では日常的に汚染だとか放射線とか僕たちにはわからないクレイジーなことが起きているし、いつも死に向かっているようなものだよ。それに、日本にはいつだってまた行きたいと思う場所で、それは事故のあとも変わらないよ。
プリンス・ウィリアム:僕が思うに、〈FTM〉は恐れではなくポテンシャルによってここまで来ることが出来た。僕らのクルーが恐れについてどうこう話をすることすらないよ。日本はすばらしい場所だし、いつだってサポートしたいと思うカルチャーがある。アメリカでもカトリーナのあとのニュー・オリーンズとおなじで、僕たちはそこに行ってお金を回してカルチャーを取り戻したいと思ったし、実際、日本の経済的な状況は前に来た時よりもおおきく変わったのを今回は肌で感じることもできた。
ストリート・カルチャーもおおきく変わったね。前に来日した時はコンビニに入れば『smart』とかストリート・ファッションの雑誌がたくさんあった。でももうそういうのが見られないよね。ストリート・カルチャーはもっと狭くなってしまった。みんな年を重ねてソフィスティケイトされた。でもそれは悪いことじゃなくて、ただシフトが起こっただけだと思う。
とはいえ、実際に住んで生活をしている人とアメリカにいる僕とでは経験としてまったく違うのだろうと思う。(311の頃)日本の友達にはすぐ電話したんだけど、僕はとても心配だったよ。
災害時にすぐにメディアがポジティヴな話題に切り替えたり、人びとの間で実際に被害の話ばかりするのが良くないという風潮があったというのは、やっぱり日本の文化的な面も大きいと思う。そこには悪い部分もあるかも知れないけれど、僕はそれは日本の良い部分でもあると思うんだ。恐れの話をしてもしょうがないというときもある。それはポテンシャルと自信を生む事もあるし、このように気の利いた社会というのはそういうメンタリティによって支えられているとも思うんだ。だから僕たちはまた機会があれば日本に来たいし、出来る限りサポートしたいと思っている。ここの文化からはすごく影響を与えられているから。
■なるほど。これからも〈FTM〉を躍進させて、僕たちを思いっきり踊らせてください! ぜひまたお会いしたいです。今回はありがとうございました。
取材:斎藤辰也(2013年5月28日)
Profile
 斎藤辰也/Tatsuya Saito
斎藤辰也/Tatsuya Saito破られたベルリンの壁の粉屑に乗って東京に着陸し、生誕。小4でラルク・アン・シエルに熱狂し、5年生でビートルズに出会い、感動のあまり西新宿のブート街に繰り出す。中2でエミネムに共鳴し、ラップにのめり込む。現在は〈ホット・チップくん〉としてホット・チップをストーキングする毎日。ロック的に由緒正しき明治学院大学のサークル〈現代音楽研究会〉出身。ラップ・グループ〈パブリック娘。〉のMCとKYとドラム担当。
INTERVIEWS
- interview with Flying Lotus - フライング・ロータス、最新EPについて語る
- interview with Autechre - 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE