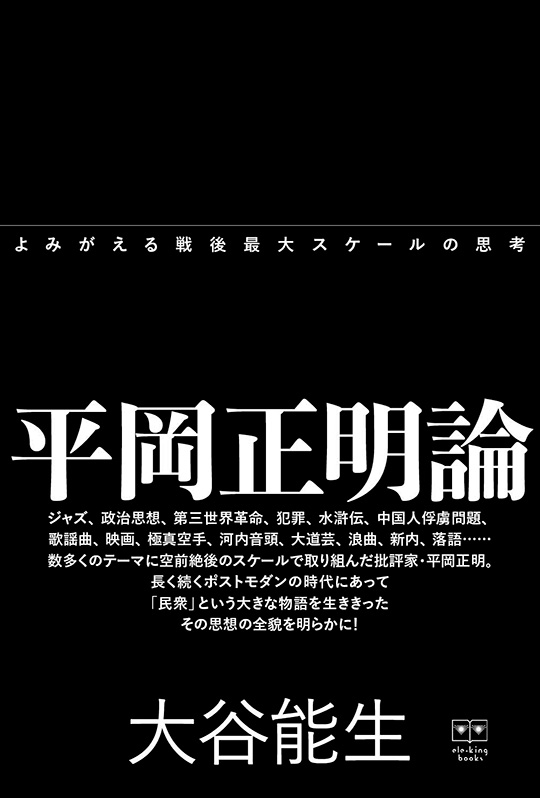MOST READ
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
- Columns 内田裕也さんへ──その功績と悲劇と
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- Squarepusher ──スクエアプッシャーのニュー・アルバムがリリース
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース
- Cardinals - Masquerade | カーディナルズ
- xiexie - zzz | シエシエ
- Laraaji × Oneohtrix Point Never ──ララージがワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの来日公演に出演
- Columns 2月のジャズ Jazz in February 2026
- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her | アマンダ・ホワイティング
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- heykazmaの融解日記 Vol.4:如月⊹₊⋆ “15” EPリリースしたよ๋ ࣭ ⭑
- PRIMAL ──1st『眠る男』と2nd『Proletariat』が初アナログ化
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- Geese - Getting Killed | ギース
- 対談 半世紀を経て蘇る静岡ロックンロール組合
- DJRUM - SUSTAIN-RELEASE x PACIFIC MODE - 2026年2月7日@WOMB
- P-VINE × FRICTION ──フリクション公式グッズが、Pヴァイン設立50周年企画として登場
Home > Interviews > interview with Yo Irie & Yosio Ootani - ひねてない、凝ってない!
凝っているように聴こえるとしたら、反省しきりですね。自我が出過ぎているということだから。「凝っている」とか「ひねたアレンジ」とか言われると、「しまった!」と思いますね。(大谷)
 入江陽 - 仕事 Pヴァイン |
■僕も『仕事』に対しては、すごくポップな印象を受けました。というか、「このヴォーカルならかなりリズムが凝っていてもポップスになるだろうな」という印象です。『仕事』も、トラック自体はわりと凝っていると思うんですが。
大谷:凝ってる?
■途中でリズムが変わるとか、そのレベルですが。あとは、途中でリヴァーブのバランスが変わるとか、4小節だけちがうリズム・パターンが入るとか。でも、こういうリズムの凝りかたって、じつはあまりなされていない印象がするんです。しかも、それなりに尖っているとされているバンドこそ、かなりリズムのパターンが単純だったりする。
大谷:そういうの、全部打ち込みにすればいいのにね。あ、バンドだからダメか。叩いたってことにして、全部切り貼りでやるとか。
入江:メタリカとかグリーン・デイとかって、音のいかつさを出すためにアルバムは打ち込みらしいですね。そういう文化も並行してあるけど、やはり生っぽさが魅力なんでしょうね。
大谷:だから、バンドなんだよ。その人に叩かせなきゃバンドじゃないの(笑)。魂的な部分で。
■海外のロック・バンドはわからないのですが、海外のブラック・ミュージックに関して言えば、けっこう複雑なことをしてもポップスとして成立しますよね。入江さんは好きなアーティストにディ・アンジェロの名前を出されていましたが、それこそディ・アンジェロのような人だったら、どれだけ複雑なことをしてもディ・アンジェロの歌になっちゃうわけですよね。そういう歌い手の強みってあると思うんです。一方で、大谷さんがいるから言うわけではないのですが、今年のジャニーズのアルバムはのきなみリズムが複雑化しました。だから、ヴォーカルなりキャラクターなりがしっかりとしていれば、音楽的に複雑でおもしろいポップスはできると思うんです。その意味で『仕事』というアルバムは、ポピュラリティがありつつ、でも細かく聴き込むと、トラックなりヴォーカルの乗りかたなりがとてもおもしろいアルバムだと思います。その点、大谷さんはどうですか。
大谷:まず、ヴォーカルありきで。歌がよく聴こえるようにアレンジしました。でも、俺はトラックが「凝っている」って言われるとよくわからないんだよね。このくらい普通じゃないか、って思う。だから、凝ってないよ。わりとシンプル。まあ、たくさん聴いたなかで、あのアルバムのアレンジが凝っていると言うんだったら、それは、ずっとサイゼリヤに行っている人がロイヤルホストに行って美味く感じる、実際は大したちがいはないけど、みたいなことでしょう(笑)。だから、味が複雑だと言われたら「そりゃそんなもんでしょう」と答えるしかない。もちろん手をかけているのは事実ですけど、それは素材を活かすためです。だからむしろ、凝っているように聴こえるとしたら、反省しきりですね。自我が出過ぎているということだから。「凝っている」とか「ひねたアレンジ」とか言われると、「しまった!」と思いますね。
■たとえば、ヴォーカルなしでインストのブレイクビーツとして聴いたら、シンプルなほうですよね。でも、ヴォーカルが乗ったうえで聴くと、複雑だという印象になっちゃうかもしれません。
大谷:そういうふうになるとは思うんです。でも、歌がよく聴こえる状態で「曲を聴くとひねってある」とか言われてうれしいかと問われたらぜんぜんうれしくない。でも、“鎌倉”とかやっぱりリズムが変だから、言われても仕方ないのかなとも思う。ただ、本人としてはこれがいちばんいいと思って作っているので、その意味でシンプルだと思っているんです。
■それはよくわかります。僕自身も、入江陽というアーティストのアルバムは、ヴォーカルを売りにしたポップスとしてあってほしいと思っています。だから、「ひねたアレンジ」という言いかたで、いわゆるインディーズに押しこめたくはないですよね。
大谷:70年代後半から現在にいたるまで、日本の歌謡チャートに入っているものは、たぶんワタシ、普通にほぼ聴いているんですよ。誰がなにをアレンジしてなにをしたかということも、あとになってから研究しているんで、だいたいわかってるつもり。筒美京平がどれだけどのように同時代のブラック・ミュージックを取り入れているか、とか、それが75年の時点で日本でどう響いたか……みたいなことに関しては3時間でも4時間でも話せる。超楽しい(笑)。で、90年代まではずっとあった同世代のブラック・ミュージックと緊張との関係が、2000年代に入ってスポッと、日本のメジャーなサウンドから消えるんですよ。あたらしいグルーヴをどう取り入れて、どのように日本のウタものにするか、という工夫とアレンジが聞こえなくなった。しかも、その前の世代である、ジャズ・サウンドとの格闘みたいなものも減ってくるわけです。
たとえば、サザンオールスターズがメジャーになってから、どんどん消えていくラインがある。78年~81年あたりの、歌謡曲とブラック・ミュージックのアレンジが結ばれていた時期というものが、僕にとって印象深いんです。松田聖子が誰のアレンジでなにを歌うとか。しかも、それが商業と結びついていて、けっこう厳しいアレンジがたくさん入っている。僕はいまだに、ああいう状態が戻ってきてくれればいいなと思っている派で、それはバンドじゃ無理なのかなあ、と。サザンとかアルフィーとかは、そういう歌謡曲のなかにいるからわたし的にはOKなわけ。職業作家みたいな人が消えちゃったんですよ。いや、いまでもいるんだけど、その人たちが孤軍奮闘という状態になっている。
■職業作家のメンツが更新されていないですよね。
大谷:そう。でも、いまだとアイドルやボカロのほうで、新しい人がどんどん出てきているかもしれない。期待してます。私はどちらかというと職業作家組だと思っているので、入江くんを使ってそういうことをしたかった、というのがこのアルバムのモチヴェーションですね。2014年に男性のソウル・シンガーとして、インディーズでデビューする。そのプロデューサーとして、トラックメイキングをする。韓国には普通にいそうだけど。だからK-POPと同じように、これらの楽曲はなんとかしてポップ・チャートに送りこみたいんですけど、いかんせん、そういう状態には動きにくい状態になっていると思う。「インディ」でという肩書きがついてしまうということは、少し違和感があるうえに、売り手もラクしてるんじゃないか。「小さい箱に入れてるんじゃねえぞ!」という気持ちありますね。まあ、仕方ないんだけどね。音だけ聴いてもらえれば、歌謡曲のラインにつながっているとはわかると思うんだけど。
入江:職業作家について個人的に思うのは、お茶の間のみんなは知らないけど海外にあるおもしろい音楽を伝えていた、ということです。ちょっと斬新かもしれないサウンドを取り入れて紹介するということがあったと思うんです。でも、いまの作家の人がコンペに出すときは、どうやったら使われるかを重視している感じがします。どうしたらバズるか、みたいな。
大谷:自分の好きなことは自分でやろうとか、分けて考えているのもかもしれないけど、それがあまりおもしろくないんだよね。
歌心みたいなものはそんなに強く意識していたことはないです。
響きとかリズムの話なら盛り上がれます。(入江)
■Jポップ/歌謡曲という話が出ましたが、リスナーとしての入江さんは、日本のポップスでどういう人が好きだったんですか?
入江:あまり僕は嫌いなジャンルはなくて、思いつくままに名前を出しはじめると、話がなんでもアリになっちゃいそうです。aikoさんとか好きですよ。ミスチルも普通に聴いていたし。でも、どこがすごいと思って聴くか、ということについては、チャンネルが変わっていった気はします。aikoさんとかは、歌が強くて好きでしたね。
■もともと、歌モノが好きだったんですか。
入江:もともとは現代音楽がやりたかったんです。たとえば、ラヴェルとかストラヴィンスキーを聴くと、こんなにリズムが複雑なのにどうしてこんなに聴きやすいんだろうとか思うんです。現在は歌モノではなく映画音楽でも、かなり普通の曲が流れている感じがします。もっと、豊かな響きとかいろんなリズムを若い頃から聴いていないと、耳が貧しくなっちゃうんじゃないかとか思っていました(笑)。以前は、そういうことを考えながらインストの曲を作っていました。だから、歌心みたいなものはそんなに強く意識していたことはないです。ただ、オーボエとか他の楽器をするよりも、歌をうたっているほうが音楽のパーツとして生き生きとしているような気がして、歌うようになったんです。
そういう感じなので、あまり歌手としてどうとか、歌詞をどうしようとか、そういう気持ちはないですね。好きになる歌手の人は楽器として声がいい人なので、そっちのほうが気になっていましたね。歌詞の世界も好きなんですが、トータルのバランスを見ている気がします。aikoさんとか沢田研二とか。ブッチャーズに対してもロック文化に心酔できるわけではなくて、サウンドや響きが好きという感じです。だから、響きとかリズムの話なら盛り上がれます。
大谷:そうだよね。だから、「Jポップでなにが好きですか」という質問自体に違和感があるよ。「今年流行った歌謡曲でなにが好きですか」とかならわかるんだけど。「どのアーティストが好きですか」とか言うけど、ポップスというのは作家じゃないわけ。流行ってそのへんに流れているものでしょう。好き嫌いではなく、あるものというか、覚えているものというか。「ピンクレディーが好きです」という感じが、すでにポップじゃなくて、2000年以降だという感じがする。「Jポップの誰が好きですか」って言われると、「あいつらをアーティスト扱いですか(笑)」と思うわけ。アートはアートで好きだし必要。だけど、チャートに上がっているものは毎日毎日主食のように聴くものであって、メジャー・チャートのサウンドは作家で聴いているわけではない。
誰が流しているのかも誰が歌っているのかもわからないけど流れている、そして、それを好きになる、という状態に対する渇望がわたしにはものすごくある。(大谷)
Jポップという話になって、なんか、いつのまにかそういう感じがなくなったなあと。「音楽」というのは作家性が強くて、きちんと作ってあって、それを聴いて一生暮らすことができて……というものとして、全部の音楽が「アーティスト」が作るものになった。それはそれでいいですよ。でも、誰が流しているのかも誰が歌っているのかもわからないけど流れている、そして、それを好きになる、という状態に対する渇望がわたしにはものすごくある。現在はそういうことがないから。それがないことに対して、ものすごいイライラするわけ。他の人がイラつかないのが不思議なくらいですよ。「誰々の何々です」とかいう言いかたがあるじゃないですか。そういうのめんどくさい。辛うじて癒してくれるのがジャニーズだけだからね。
入江:ちゃんと作った良いものがヒットすれば、それが売れ線だという方向に文化が変わってきますよね。
■その話はすごくおもしろいですね。メジャー・チャートについて作家の話でしか会話できないような現状があって、その状況が気持ち悪いということですね。
大谷:そうそう。「勝新の映画がいいね」っていうのは、単に映画館に行って観ているだけでしょ。やっているから行く、というのが健康なわけですよ。
入江:僕の場合、好きな音楽は全部後追いだったので、そのさびしさはあるかもしれないですね。たしかに自然に入ってくるほうが健全かもしれません。
大谷:子どもの頃に適当に映画見て、頭に残っていて、「あれよかったなあ。なんだったっけ」と思い出したら『E・T』だった、とか。わかりにくいか(笑)。まあ、そういう無意識的なものに対する欲求があるんだよね。だから『仕事』も、そういうほうに向かって作っていました。
■そのメッセージは感じましたよ。
大谷:でもそこで、「凝っている」とか「ひねっている」とか言われると、やっぱりダメだったかと思っちゃうんだよ(笑)。もっとスカッと聴けたほうがよかったかなあ、とか。
■間違いなく「ポップス」という印象はありましたが、うーむ。
大谷:でも、作家性で音楽を語ることが普通になっていることに対する苛立ちが強いんですよ。
■なるほど。僕も芸能文化やノベルティ文化が好きなのですが、そんな自分からしても、『仕事』に対して大谷さんのアーティスト性みたいなものを感じてしまうところがありました。
大谷:そうかあ。それは、こっちの修業が足りないという感じです。
取材:矢野利裕(2015年1月21日)
Profile
 矢野利裕(やの・としひろ)
矢野利裕(やの・としひろ)1983年生まれ。ライター、DJ、イラスト。共著に、大谷能生・速水健朗・矢野利裕『ジャニ研!』(原書房)、宇佐美毅・千田洋幸編『村上春樹と一九九〇年代』(おうふう)などがある。
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE