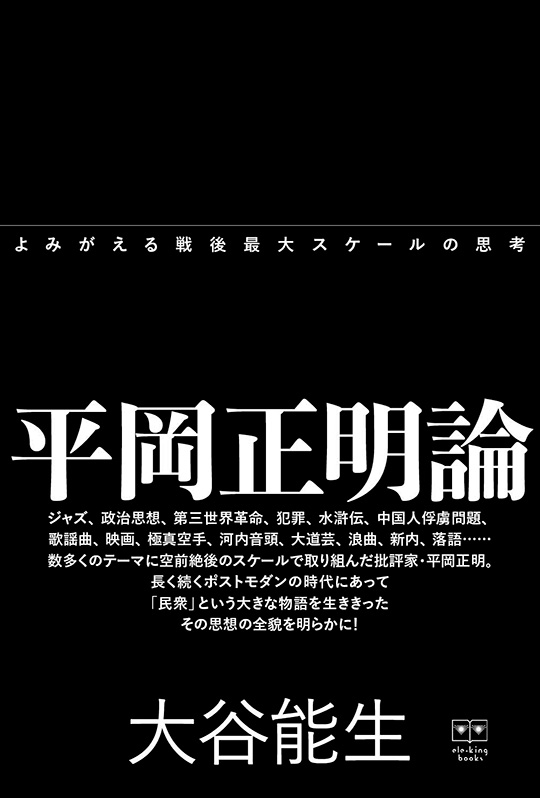MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Yo Irie & Yosio Ootani - ひねてない、凝ってない!
魅惑の声をもつシンガー・入江陽の新作アルバム『仕事』が早くも話題だ。大谷能生をプロデューサーとして迎え、OMSB(SIMI LAB)、池田智子(Shiggy Jr.)、別所和洋(Yasei Collective)などといった豪華ゲスト陣が参加した本作では、その音楽性が確実に進化/深化している。ヴォーカルをはじめ、リズムやアレンジなどサウンドはとても豊かだ。
とはいえ見落としてならないのは、『仕事』という作品の、堂々たるポップスとしてのたたずまいである。ソウル、ジャズ、R&B、ヒップホップ、ダブステップなど、あらゆる音楽性を飲み込んでなお、ポピュラーソングとして強い。『仕事』の最大の魅力は、そこに尽きる。そして、それを支えるのは、入江陽という類まれなるヴォーカリストの力に他ならない。
本インタヴューでは、入江陽と大谷能生に話を訊いている。新作アルバム『仕事』についてたずねつつも、いつしか話題は、日本におけるポップスのありかたにまで広がった。妙な細分化のしかたをしているニッポンの音楽シーンのなかで、ポップスはいかにあるべきか。本作が標榜する「ニッポンの洋楽」は、なにより正統的な歌謡曲ということなのかもしれない。本インタヴューは、音楽論にしてクリティカルな文化論、文化論にしてクリティカルな音楽論である。
■入江陽 / Irie Yo
1987年生まれ。東京都新宿区大久保出身。シンガーソングライター、映画音楽家。学生時代はジャズ研究会でピアノを、管弦楽団でオーボエを演奏する一方、学外ではパンクバンドやフリージャズなどの演奏にも参加、混沌とした作曲/演奏活動を展開する。のちに試行錯誤の末、シンガーシングライターとしてのキャリアをスタートさせ、2013年10月にアルバム『水』を、2015年1月には、音楽家/批評家の大谷能生氏プロデュースで2枚めのアルバムとなる『仕事』をリリースした。映画音楽家としては、『マリアの乳房』(瀬々敬久監督)、『青二才』『モーニングセット、牛乳、ハル』(サトウトシキ監督)、『Sweet Sickness』(西村晋也監督)他の音楽を制作している。
前回のアルバムはアレンジがすごく説明的だったと思います。でも今回は、大谷さんがアレンジにも関わっているので、すべてをやらなくてもいいという気持ちがありました。(入江陽)
 入江陽 - 仕事 Pヴァイン |
■『仕事』が店頭に並びはじめていますが、今作の手応えはどうですか。
入江陽:前作からすると、かなりサウンドが変わっていると思いますが、いい進化だったと思いますね。前回のアルバムはアレンジがすごく説明的だったと思います。「こういうリズムの上にこういうメロディなので、こういうコード進行を聴いてほしい」みたいな。でも今回は、大谷さんがアレンジにも関わっているので、すべてをやらなくてもいいという気持ちがありました。
■ある部分は大谷さんなどに任せてしまって自分は歌うだけだ、と振り切った感じがあったのですね。
入江:かなりありましたね。
■『仕事』は大谷能生さんプロデュースということですが、入江さんは大谷さんに対してどのようなイメージがありましたか。
入江:大学時代に『貧しい音楽』(月曜社)を読んだのが初めてです。大谷さんにはいろんな側面があると思うのですが、演劇の音楽をされているという面が気になっていました。
■なるほど。大谷さんは入江さんに対するイメージはなにかありましたか。
大谷能生:ロック・バンドの人ではない、とか? 自分がロック・バンドって未経験で、まわりにもそういう知り合いが少ないので、正直「バンド」がいまだによくわからないんですよね。18~19歳くらいでバンドを組んで、一蓮托生で活動して、アルバムが出せて、小さなバンに乗って週末にツアーに行って、毎週スタジオに入るとか、そういうことをやったことがない。日本の多く――僕の見た感じだと大雑把に言って8割くらい――のインディーズは「バンド」が基本スタイルですよね。で、前作の『水』を聴いたときに、入江くんはいわゆるシンガーとかソロでできる人だと思って、インディではめずらしいんで、そういうタイプの人だったらぼくもいっしょにできそうということで、今回のような組みかたになりました。
■『水』を聴いても、入江さんのヴォーカルとコーラスの魅力はすごいですよね。僕自身は、『仕事』はどちらかといえば、R&Bという印象が強いです。現在、インディ・シーンみたいなものがなんとなくあるとして、そこではシティ・ポップのブームなんかも言われますよね。もしかしたら、『仕事』もそのような聴かれかたをする可能性があるかもしれませんし、ライヴハウスなどでバンドと対バンすることもあるかと思います。入江さんご自身は、ジャンルとかシーンとかについて考えるところはありますか。
入江:大谷さんのバンド話にも通じるのですが、最初は人気のあるバンドを聴いて「これいいな」とか「こういう人を呼ぼう」とか思っていたのですが、詳しくなっていくにつれて、自分は“バンド編成でのアレンジやバンドの文化がすごく似合うタイプ”ではないのかも、という疑問も感じていました。もちろん好きなバンドもたくさんあるのですが、良い悪いではなくて、そこにはストライクしていないんじゃないかと強く思いましたね。ただ、『水』を作っているときはそんなに自覚していませんでした。〈試聴室〉さんに声をかけてもらえたことが本当にうれしかったので。
大谷:いまの話は「インディ・シーン」というか「インディ・ロック・シーン」だよね。それで、そのインディーズのロック・バンドのなかに入って、みなさんと仲良くなれるかと言われれば、俺は仲良くなれないんじゃないかなあーと思う。あっちも俺のほうは嫌いだし、用事なんかないと思うし。
入江:いや、そんなことはないですよ。
大谷:そんなことないだろう(笑)。下北のライヴハウスとかで5バンドくらいブッキングされていて、あいだに「大谷能生」って混じっていたら迷惑だと思うよ(笑)。それで20分ずつくらい演奏して、「ありがとうございます」って帰っていくわけでしょう。
入江:たぶん、そうことに違和感を抱えている人も多いと思いますよ。むしろ、そこにどハマりしているバンドやアーティストがいるということはそういう文化が根づいているんだと思います。
大谷:そっちの人はそっちの人で楽しくやっている感じがするね。もう、純文学雑誌みたいな、『早稲田文学』とか? みたいなものに似てるというか、よく知らないけど(笑)。みんながそうならばなんの問題もない。パイがもっと大きくなるといいとは思うけど。
トラック・メイキングの仕事は楽しい。でも、曲のフレームがすでにあって、あとはよく聴かせる、ということだけなので、やることはシンプルですよね。(大谷能生)
■今回、大谷さんのプロデュースはどのようなかたちでおこなわれたのでしょうか。曲によってもちがうとは思いますが、たとえばトラックなどはどんな感じで関わったんですか。
大谷:どんな感じだと思いますか?
■曲によってちがう印象がありますが、いちばん大谷さんっぽいと思ったトラックは“仕事”ですね。ミックスと音の配置が大谷さんっぽいと思いました。ただ、生楽器のサンプルもあったので、スタジオ・ミュージシャンもいたのかなとか想像しましたね。
大谷:あれは、もともと山田光くんの曲で、彼がやっているライブラリアンズってユニットのアルバムに入っていて、その時点でもう曲がよくできていたので、あまりいじっていないですよ。ちょっとリズムを強くして、ダブステップというか、ちょい前のUKクラブ側に寄せました。だから、リミックスに近いですね。
入江:ちなみに山田くんの原曲はMVがYouTubeに上がっているのですが、それは全部『水』からサンプリングした音でできているんですよ。
大谷:だから“仕事”は、僕のクセはちゃんとつけましたが、山田くんの曲。ビートだけね、自分の感じです。
■たしかに、どちらかというとビート感が大谷さんっぽかったです。
大谷:まあ、私のサウンドになってはいますね。
■あと、“フリスビー”とかも意外と大谷さん色が強いのかなと思いました。
入江:あれはリフとリズムとメロディだけありましたね。早い曲がなかったので、作ろうと思ってデモを大谷さんにお送りしたんですよね。
大谷:もう少しBPMを上げてもよかったかもね。ちょっとずつ上げたんだけどね。基本として弾き語り+リズムぐらいの曲があって、あとは全部こちらがやりました。トラック・メイキングの仕事は楽しい。でも、曲のフレームがすでにあって、あとはよく聴かせる、ということだけなので、やることはシンプルですよね。もともと曲があるから、無理に捻り出した感じはゼロです。“やけど”とか、デモがよくできていたんで、パラ・データもあったからそのまま素材を使わせてもらったり。
■最初に、アルバム全体のイメージなどはあったんですか。
大谷:ないです。だけど、ポップスのアルバムにはしたかった、最低2万枚ぐらい売れるような(笑)。でもそれは、大きなことを言っているわけではなくて、「しっかりしたポップスが欲しいし、そういうものを作ってます」ということなんです。さっきの話ともつながりますが、インディ・ロックだと2万枚ではなくて2千枚ですよね。そこからだと、どうしたってお茶の間までは行かない。「お茶の間」ってもう存在しないと思うんですけど(笑)、基本、わたし、テレビとかラジオで聴ける歌謡曲が好きなんですよね。
■その話は個人的にはとてもおもしろいです。芸能が好きか、バンドが好きか、ということですね。
大谷:というより、バンドは芸能のサブ・ジャンルだという感じだね。もちろん、ロックでも好きなものはありますが、入江くんはそういうタイプではないなーと思ってて。でも、ロックをいまやったらおもしろいかもね。考え直した。誰かバリバリの若いロッカーとか捕まえようかな(笑)。なんか、こわれものみたいな人の面倒みたりして(笑)。
■なるほど。そういう意味では、大谷さんのキャリアのなかにバンドはなかったんですね。
大谷:ロック・バンドはゼロですね。
■オルタナに見られる感じはありそうですけどね。
大谷:オルタナね。みなさんが思っていることとぜんぜんちがうと思いますけどね。日本のポピュラー・ソングは大好きで、その流れのなかで仕事をしようと思っているんです。だから、筒美京平か内田裕也かと言えば、筒美京平ですね。内田裕也はすごく好きで憧れるけど、自分では無理だなという感じ。あんなのマネできないからやめたほうがいいよ。内田裕也のコピーしている人がいたら、すごいかっこ悪いじゃないですか。
入江:「内田裕也じゃなさ」が際立ちますよね。
大谷:そうだよね。「こいつは内田裕也じゃないんだな」ということばかりが目立って、むしろおもしろいかもね。なんにせよ、ポップスの仕事がしたいなあということをつねに思っていて、それはこれからもたぶん変わらないです。そのときに、シンガーとして伸びしろがある入江くんをこっちに引っぱり込もうと思ってはじめたわけです。
取材:矢野利裕(2015年1月21日)
Profile
 矢野利裕(やの・としひろ)
矢野利裕(やの・としひろ)1983年生まれ。ライター、DJ、イラスト。共著に、大谷能生・速水健朗・矢野利裕『ジャニ研!』(原書房)、宇佐美毅・千田洋幸編『村上春樹と一九九〇年代』(おうふう)などがある。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE