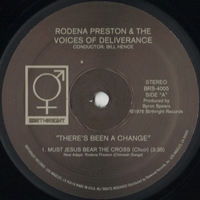日本のベース・ミュージックについて改めて考えてみると、「ベース・ミュージック」という言葉を日本人が使いだしたのは東では〈Drum & Bass Sessions〉、西では1945 a.k.a KURANAKAが率いる〈ZETTAI-MU〉に代表される方々が支えてきた「ドラムンベース」や「ラガ・ジャングル」の登場以降だと推測される。
しかし、近年では「ベース・ミュージック」という言葉の意味にかなり広がりを持つように進化し続けていると思う。もともとは海外でマイアミ・ベースやゲットー・ベースなどのヒップホップやエレクトロからの流れが「ベース・ミュージック」と言われだしたのがはじまりだろうし、「DUB STEP」という言葉にある「DUB」についてはもっと昔から存在する手法だ。
そんな「ベース・ミュージック」の言葉が持つ深いポテンシャルに注目し、日本におけるベース・ミュージックの現在進行形を体験できる貴重な機会があったので、少々時間は経ってしまったが、レポートしようと思う。
〈Outlook Festival〉とは、ヨーロッパはクロアチアにて数日間に渡って開催され、世界中のアーティストやDJ、そしてサウンドシステムが集結する世界最大級のベース・ミュージックの祭典だ。その錚々たるラインナップには、リー"スクラッチ"ペリーやマックス・ロメオやジャー・シャカといった、生きるレゲエ・レジェンドたちからスクリームやデジタル・ミスティックズなど、最先端ダブステップ・アーティストが一斉に名を連ねる。
ある日、Part2Style Soundの出演するクロアチアの〈Outlook Festival〉に同行したeast audio sound system(イーストオーディオ・サウンドシステム)のtocciの体験談として「BASS MUSICは体で体感する音楽である。しかるべきサウンドシステムで鳴らせば、その重低音は肌から伝わり、体のなかを振動させ、ついには喉が震えて咳き込むほどの音楽だ」という見解を、過去にサイトにアップしていたのを読んで、自分の目を疑ったのと同時に「体感してみたい」という思いが芽生えた。その個人的な思いは「Outlook Festival Producer Competition」という、勝者はクロアチアへのチケットを手にすることができるコンペに自作曲を応募する形でぶつけてみた。仲間や応援してくれたみんなのおかげもあって、数多く存在するファイナリストまでは残れたものの、結果としては敗北に終わり、悔しい思いをしたのも記憶に新しい。
そんな〈Outlook Festival〉の日本版がPart2Style とイーストオーディオ・サウンドシステムによって、今年も開催されると知ったのは春のはじまりのころで、それを知ってからは毎日のように「Outlookを体験したい」と心のなかで連呼したが、どうしても行きたい思いとは裏腹に、諸事情により今回のフェスへの参加を諦めていた。
その矢先、小説家であり、ライターであり、大阪の夜の飲み先輩であるモブ・ノリオさんから一本の電話がかかってきた。
以前、モブさんにとあるパーティで会ったときに酒を飲みながら〈Outlook Festival Japan Launch Party〉がいかなるものかと熱く説明したことがあり、そのときに何度も「それにはお前は行かなあかんやろ」と言われたが、「行きたいですねぇ......」と返すのが僕の精一杯の返答だった。それを察しての電話口だった。「〈Outlook〉行くの?」と聞かれ、「めちゃくちゃ行きたいですけど、もう諦めました」と返すと「行かんとあかんときっていうのは、どうしても行かんとあかん。お前、ああいうことを自分で書いといて、いかへんつもりなん? それはあかんぞ......あのな、エレキングで取材の仕事をセッティングしたから、行って来てレポートを書いてみぃへんか? 文化を体験するって行為は絶やしたらあかんで」
涙がでるほどの奇跡が起きた。僕のなかで行かない理由はなくなった。
5月26日、TABLOIDの隣にある、日の出駅に着いたときに、まず驚いた。改札を通るときに重低音の唸りが聴こえてきたからだ。駅から会場までの近さも手伝って、初めて行く会場への方向と道のりを重低音が案内してくれた。会場の建物がどれなのかは、低音の振動でコンクリートが「ピシッ」と軋む音でわかった。ついに ここに来ることができた、と胸が高まった瞬間だ。
会場に入り、さっそくメインフロアであるホワイト・アリーナへ向かうと、先ほどの駅で聴いた重低音の唸りがSPLIFE RECORDINGSがかけるラガ・ダブステップだったことがわかる。そびえ立つモンスター・スピーカーたちの城から発せられるその音は、「爆音」なんてものではなく、まるで生き物のようにスピーカーから"BASS"が生まれ、フロア中を駆けめぐった後、壁を登り、遥か高い天井で蠢く、「獣帝音」と言えば伝わるであろうか。そう、これがイーストオーディオ・サウンドシステムとTASTEE DISCOが繰り出す、メインフロアの音だ。驚いたのは、出番が終わったあとにSPLIFE RECORDINGSのKOZOから聞いたところによると、これでまだ50%ぐらいの音量だというのだ。驚きとともに、100%の音量を出したときに自分は正気でいられるのだろうか? 建物は大丈夫なのだろうか? などと、少しの不安と緊張感を抱くとともに、武者震いをするかのように心を踊らせた。
大阪から到着したばかりで腹がすいていたので、メインフロアの後方にあるFOODブースへと向かった。
DUUSRAAのカレーを注文し、待っているあいだにおもしろい出来事があった。テーブルの上に置いてあった誰かのカクテルのカップが、重低音の振動で勝手に動き出し、なかに入ってあるカクテルが噴水のようにしぶきを上げ、こぼれだしたのだ。それぐらい、建物自体が振動していたということだ。
知人の皆と、久しぶり感がまったくない(1ヶ月前に会ったばかり)挨拶やジョーク等を交わし、会場全体をウロウロとまわるうちに最初の狼煙が上がった。Part2Style最重要ユニット、ラバダブマーケットの登場だ。Erection FLOORと名付けられたフロアで鳴り響く、姫路は最高音響サウンド・システムの音も、サブ・フロアという陳腐な言葉では片づけられない、まさしく最高の音だった。その音は暖かく、どれだけの音量で鳴っていたとしても耳が疲れない、例えて言うならマホガニーサウンドだ。しかし、鳴っている音量はかなりのもので、ここのフロアが階段を登った2階にあったのも手伝ってか 振動が床を伝い、足から体全体が震え、まるで自分がスピーカーになったような錯覚すら覚えた。そんな最高音響でのラバダブマーケットのライヴは、フロアの反応も最高だった。Dread Squadの"Sleng Teng International Riddim"にジャーゲ・ジョージとMaLが歌う"Digital dancing mood"~e-muraのJUNGLEビート本領発揮の"Bubblin'"~突き抜ける"MAN A LEADER"の流れは、正にリーダーが告げるこのフェスの本格的開始合図だった。そしてその勢いは櫻井饗のエフェクターを駆使した多彩なビートボックス・ライヴへと継がれていった。
ホワイト・アリーナへ戻ると会場にも人が溢れ返っていて、LEF!!!CREW!!!が、フロアにいるオーディエンスをハイテンションでガンガンにロックしていた。休憩しようと外へ向かう途中にグラス・ルームではDJ DONが、まだ生まれて間もないベース・ミュージック、ムーンバートンのリズムで"Bam Bam"をプレイしていた。僕もよくかけるリミックスだ。ついつい休憩のつもりがまたひと踊りすることに。Jon kwestのアーメンブレイクを切り刻んだムーンバートン(これまた僕もよくかける)など、ニクイ選曲にTRIDENTがパトワのMCで煽る。108BPMという、遅いような早いような不思議なテンポに錯覚してしまい、ついつい踊らされてしまうのがムーンバートンの魅力だろう。
外の喫煙ブースでマールボロのタバコをもらい一服してからなかへ戻ると、さっきのグラス・ルームでは函館MDS CREWのボス、SHORT-ARROWがSUKEKIYOのMCとともにジャングルをプレイしていた。同じく函館から来ていたKO$は今回、カメラマンとしてもかなりいい写真を撮っていたので、是非チェックしてほしい。ここでも先ほどラバダブマーケットのライヴでも聴いたDread Squadの"Sleng Teng international"が聴けたし、時を同じくしてホワイト・アリーナではTASTEE DISCOがスレンテンをかけていた。
この〈Outlook Festival Japan Launch Party〉の興味深いポイントとして、「ベース・ミュージックに特化したフェスティヴァル」ということでは日本ではかなり早いアクションだということだ。以前からPart2Styleは"FUTURE RAGGA"というコンセプトのもと、コンピュータライズドなレゲエをやっていたし、ジャングルやドラムンベースはもちろんのこと、最近ではダブステップやクンビアも自分たち流に消化して発信していたし、ムーンバートンを僕が知ったきっかけはMaL氏とNisi-p氏がふたりで作ったミックスだった。それらやその他もろもろを総じて、ベース・ミュージックと日本内で呼ばれ、波及しだしたのは ごく最近のことであり、まだまだ発展途上といえる段階だろう。スレンテンのベースラインは、この新しい試みのなかでも 互いに芯の部分を確かめ合うように呼応する不思議な信号や、電波のようにも聴こえた。
時間が深まっていくなか、eastee(eastaoudio+TASTEE)が本領を発揮しだしたと感じたのはBROKEN HAZEのプレイだった。重低音が何回も何回も、ボディブローをいれてくるように体に刺さりまくる。激しいビートとベースで、まるでボクシングの試合でボコボコにされ、痛いどころか逆に気持ちよくなってしまう感覚だ。パンチドランカー状態になってしまった体を休めに、バー・スペースへ行きDUUSRAA Loungeの音が流れる中、友人と談笑したりした。
上の階では、ZEN-LA-ROCKとPUNPEE、そしてファンキーなダンサーたちによってオーディエンスが熱狂の渦と化していた。音の振動によってトラックの音が飛ぶトラブルもなんのその。
「皆さん、低音感じてますか? Macも感じすぎちゃって、ついつい音が飛んじゃいました。低音はついに800メガヘルツに到達! Everybody say BASS!!」とトラブルすらエンターテイメントへと変換させる話術は、お見事の一言では片づけられないほど素晴らしく、ごまかしや隠すことの一切ない、正に全裸ライヴだと実感した。ZEN-LA-ROCKは独自にこのフェスティヴァルをレポートしているので併せて見てほしい。
楽しいライヴを満喫した後は、D.J. FULLTONOを見にグラス・ルームへと移動する。個人的にエレクトロやシカゴ・ハウス、ゲットーベース等を2枚使いでジャグリングをガンガンやっていた頃を知っているだけに、いま、日本のJUKE/JIT第一人者として〈Outlook Festival Japan〉に出演していることが不思議であり、同じ大阪人として嬉しくもあった。彼がプレイしている時間のフロアは、このフェスのなかでもっとも独特な空気を放っていただろう。矢継ぎ早に、時にはトリッキーに繰り広げられるJUKEトラック、"FootWurk"という超高速ステップ、難しいことは言わず自然体な言葉でフロアを煽るMC、仲間たちお揃いのBOOTY TUNE(FULLTONO主宰レーベル)のTシャツ、ブースに群がるクラウド、汗だくになりながらも、次々とフットワークを踊り、DJブース前のフットワークサークルを絶やそうとしないダンサーたち、出演者、観客、スタッフ、なんて枠組みは取り払われたかのように、そこにいる皆で夢中になってフロアを創った時間だった。その素晴らしさは、FULLTONOが最後の曲をかけてすぐさまフロアに飛び出し、さっきまでDJをしていた男がいきなり高速フットワークを踊りだした時に確認できた。僕にはその姿が輝いて見えた。
メインフロアに戻ると、Part2Style Soundがいままで録りためたキラーなダブ・プレートを惜しげもなくバンバン投下しフロアをロックし続けていた。そのスペシャル・チューンの連発にフロアのヴォルテージが高まりすぎて、次の日に出演予定のチャーリー・Pが我慢できずにマイクを取ったほどの盛り上がりだ。そしてその興奮のバトンとマイクは、DADDY FREDDY(ダディ・フレディ)へと渡された。高速で言葉をたたみかけるダディ・フレディのライヴは圧巻であった。何回も執拗にライターに火を灯せ! とオーディエンスに求め、フロアは上がりに上がった。早口世界チャンピオンは上げに上げた後、だだをこねるように「もう行っちゃうぞ?」とフロアに問う。フロアは声に応え、ダディ・フレディを放そうとはしない。チャンピオンはノリノリでネクスト・チューンをうたい終えた後、またフロアに問う。「おれはもういくぞ!?」と。もちろん皆は声に応える。するとチャンピオンはノリノリで「ワンモアチューン!」と、まだまだ歌い足りなさそうだが、やはりチャンピオン。どのアクトよりも怒涛の勢いを見せつけた、素晴らしいステージだった。
チャンピオンの勢いに圧倒された後に続いて、特別な時間がやってきた。
DJ、セレクタのセンスと腕が問われる真剣勝負、サウンド・クラッシュ。今回、かなり楽しみにしていたイベントだ。NISI-Pの司会によってルール説明が行われ、場内は緊張感に溢れた。今回のルールとして、はじめにくじ引きで第1ラウンド出場者である3組の順番を決め、1ラウンド目はダブ・プレートではない曲で3曲ずつかけ、次ラウンドの順番が決まる。第2ラウンドが「Dub Fi Dub」(ダブプレートを1曲ずつかける)の流れだ。第2ラウンドで決勝進出の2組が決まり、ファイナルラウンドで一対一の対決となる。
第1ラウンドの一番手はHABANERO POSSE(ハバネロ・ポッセ)だ。普段からイーストオーディオ・サウンドシステムの音を研究しているだけあって、音の鳴りはピカイチだった。ガンヘッドのDJにFYS a.k.a. BINGOのMCの勢いもハンパなく、スピーカーとオーディエンスを存分に震わせた。続いて、JUNGLE ROCKがプレイするジャングルはレゲエのサウンドマンの登場を物語る。サウンドクラッシュはレゲエから発生した文化だ、と言わんばかりにフロアに問いただす。最後に登場したDEXPISTOLSは、なんとレゲエ・ネタで応戦し、エレクトロの先駆者が異文化であるクラッシュへの参戦表明を見せつけたことで、このサウンドクラッシュがいままでのどのサウンドクラッシュとも違う、斬新なものであるかがわかっただろう。今回のサウンドクラッシュの見どころとして、ヒップホップやエレクトロの文化やレゲエの文化などが、カードの組み合わせによって異種格闘技戦となっていることも、おもしろい試みだ。
肩慣らしともいえる第1ラウンドを終え、いよいよ本番、ガチンコ対決となる第2ラウンドへと続く。トップバッターはDEXPISTOLSだ。第1ラウンドのときとは、やはり気合いの入り方が違い、ダブプレートには自身たちの曲にも参加している、ZeebraとJON-Eがエレクトロのビート上で声をあげ、DEXPISTOLSがDEXPISTOLSであることをオーディエンスに見せつけた。
続くはHABANERO POSSE。ムーンバートン・ビートにのるラップの声の持ち主に耳を疑った。なんと、Zeebraのダブ・プレートである。まずは「ベース好きなヤツは手を叩け!」と、"公開処刑"、そしてビートがエレクトロへと急激にピッチが上がり、DEXPISTOLS自身がZeebraをフィーチャーした"FIRE"のダブへと展開し、DEXPISTOLSへ向けたレクイエムを送る。逆回転のスピンの音が少し短くて、思ったことがあった。「あれはもしかして、レコードかもしれない......。」その盤はアセテート盤と呼ばれる、アナログレコードをわざわざカットして鳴らされたものであるのも、block.fmで放送された後日談にて確認できた。HABANERO POSSEは、ぬかりのない綿密な作戦と、業が成せる完璧な仕事を僕らに見せつけたのだ。
ラストのジャングル・ロックは、アーメンブレイクと呼ばれるジャングル・ビートに、猛りまくったMCで問う。「さっきも、V.I.Pクルーがかかってたけど、V.I.Pクルーって言ったらこの人だろ!?」と、BOY-KENがうたう様々なクラッシュ・チューンでレゲエの底力を見せつけた。
ファイナルラウンドに駒を進めたのは、HABANERO POSSEとJUNGLE ROCKの2組だ。本気の真剣勝負の結果である。誰もそこに異論を唱える者はいなかったと思うし、オーディエンスの反応にも間違いなく現れていた。戦うセンスと実力だけがものをいう、音と音のぶつかり合い。それがサウンドクラッシュという音楽の対話だ。
ファイナルラウンド、先行はJUNGLE ROCKだ。「おれがこのダブとるのに、いくら使ったと思ってんだよ!」と意気込みを叫び、ダブを投下した。鎮座ドープネスとリップ・スライムからはPESとRYO-Zという、豪華なメンツにフロアは沸きに沸いた。そして後攻にHABANERO POSSE。なんとその場のゲストMCにSEX山口を迎え、マイクでフロアに物申す。「おれらの敵はJUNGLE ROCKでも、DEXPISTOLSでもない。本当の敵は、風営法だ!」なんと、YOU THE ROCKがラップする"Hoo! Ei! Ho!"のダブだった。
優勝は満場一致で、HABANERO POSSEが受賞した。展開の読み、選曲、音像、すべてにおいて郡を抜く存在だった。本当に、普段から音の鳴りを研究した努力の賜物だったと思うし、あの時間にあのダブ・プレートを聴いた時の、ドラマのような展開に感動した。近年、風営法を利用した警察が、文化を発信している場所となるクラブを摘発していることへの、強烈なアンチテーゼを意味するメッセージでもあった。クラバーたちの真の戦いとなる風営法を、サウンドクラッシュという戦のなかで伝え、勝利という名の栄光を掴んだ、真のチャンピオン誕生の瞬間だった。
この頃には酔いもできあがってしまって、BUNBUN the MCのライヴではPart2Styleのメンバー、DJ 1TA-RAWがカット(バックDJ)をやっているにも関わらず、大阪のオジキの大舞台を応援したい気持ちで僕もDJブースにノリこんでカットをやるが、酔った手がCDJの盤面に当たってしまい、ズレなくてもいいリズムがズレてしまって、「WHEEL UP!Selecta!」とすぐにお声がかかり、ネクストチューンへ。大変、お邪魔いたしました。。もちろん、ライヴはいつにも増して、大盛況であった。酔いも深まる中、タカラダミチノブのジャーゲジョージをフィーチャーしたDJにシビれ、朝を迎えた。
[[SplitPage]] 2日目はひどい2日酔いのなか、昨日が夢のような1日だったため、目が覚めてもまどろみ状態がなかなか覚めなかった。そんな状態で、酒を飲む気分になれなかったので、この日はレッド・ブルだけを飲んで過ごした。
会場に到着して、ブランチに虎子食堂のごはんを食べようと、真っ先にフードブースへ足が進む。フェジョアーダという黒豆ごはんを注文し、知人と一緒に「初めて食べる味ですねー」なんて話しながら、美味しくいただく。ふと、ブースの方へ向くと、Soi Productions(ソイ・プロダクションズ)がスタートダッシュのドラムンベースをブンブン鳴らしていた。会場の音も、昨日よりも開始直後からよく鳴っている印象だった。考えたら昼の2時だ。鳴らせる時間には鳴らさないと、サウンドシステムがもったいない。目もスッキリ覚めるほどのベースを浴びて、2日目がはじまったことを改めて確認した。
バー・スペースではDJ DONがクンビアを気持ちよくかけている。今日はどうやって過ごそうかな? とタイムテーブルを見ながら周りを見渡す。ここは〈DUB STORE RECORDS〉や〈DISC SHOP ZERO〉がレコードを販売しているフロアでもある。ふと見ると、E-JIMA氏がレコードをクリーニングするサービスなんてのもあって、もしレコードをもってきてたら、超重低音でプレイする前にキレイにしたくなるだろうな、と思ったりした。
入り口付近のグラス・ルームではKAN TAKAHIKOがダブステップのベースの鳴りをしっかりとたしかめるように、自作曲も交えながらプレイしていたり、2階へ行くと、DJ YOGURTがスモーキーで渋いラガ・ジャングルをかけていて、最高音響で聴くアーメン・ブレイクは体にスッと馴染みやすく刺さってくることを確認したり、NOOLIO氏との久々の再会がグローカル・アリーナで太陽を浴びながら聴くグローカルなハウスだったり、ホワイト・アリーナに戻っては、G.RINAの生で聴く初めてのDJにテンションが上がってしまい、BUNBUN氏とふたりしてかっこええわ~なんて言いながら楽しい時間はあっという間に過ぎていく。
グラス・ルームでワイワイと楽しそうにやってたNEO TOKYO BASSの姿は、誤解を招くのも承知で書くと、やんちゃな子どもたちが はしゃいでいるようにも見えて、その楽しそうな姿に、ついついこっちまで指がガンショットの形になってしまった。クボタタケシのクンビア・ムーンバートンを交えたセットも素晴らしかった。この時にかかっていたKAN TAKAHIKOの"TOUR OF JAMAICA"のエディットはこのパーティ中に最も聴いたチューンのひとつだ。
Tribal Connection(トライバル・コネクション)の1曲目は、ジャングル・ロックの昨日の決勝戦のチューンだった。昨日のバトルの雰囲気とはうってかわって、パーティ・チューンに聴こえたのもセレクター、DJとしてかける意味がかわって聴こえたりもして、趣が深かった。悔しそうに、そして楽しそうに。深いジャングルの時間だった。続くJxJxはグラス・ルームをファンキーに彩るムーンバートンで、大都会の夕暮れの時間を鮮やかに彩った。
そうこうしている内にはじまったPart2Style Soundが、確実にメインフロアを唸らす。興奮もピークに近づいてきたところで、やってきたのはCharlie P(チャーリー・P)だ。まだ若いらしいが、堂々としたステージはベテランのようで、スムーシーに唄うその声は、ときに激しく、ときにまとわりつくように耳から脳へとスルリと入ってくる。続いて登場したSolo Banton(ソロ・バントン)は先日、大阪で見た時よりもキレがあり、"Kung Fu Master"や"MUSIC ADDICT"など、堂々としたステージングでオーディエンスをグイグイ引き寄せる。そして時には、ソロとチャーリーが交互に歌ったり、お互いの声質が異なることによるスペシャルなブレンド・ライヴを展開した。かなりマイクを回しあっただろう。時間が終盤に近づくにつれ、グルグルと回るマイクをもっと回せと口火をきったのはRUMIだ。"Breath for SPEAKER"の「揺らせ! スピーカー!」のフレーズで、正にスピーカーとフロアを存分に揺らした。すかさずソロがたたみかけるようにうたう、すると今度はなんと、CHUCK MORIS(チャック・モリス)が出てきては「まんまんなかなか、まんまんなかなか、ド真ん中!」と、すごい勢いで登場し、「たまりにたまった うさばらし! Outlookでおお騒ぎ!」と、けしかけては、「ハイ! 次! ソロー!」とソロ・バントンにマイクを煽る。ソロがすかさず歌い返すも、Pull UP! ちょっと待ったと、いきなり現れた二人のMCに たまったもんじゃないソロはなんと、ダディ・フレディの名を呼んだ。「ジーザス、クライスト!」とダディフレディが一言、そこからのトースティングは即座にフロアを頂点へとのし上げた!!! ダディ・フレディは会場に集まった皆と、Part2Styleに感謝を述べ、よし、マイクリレーしよう!と閃き、なんとスペシャルなことか、ダディ・フレディとソロ・バントンとチャーリー・P、3人の怒涛のマイクリレーがはじまった。これにはフロアもガンショットの嵐!! 最高のスペシャルプレゼントステージだった。Nisi-pが「もう一度、3人に大きな拍手を!!」と叫ぶと、会場は拍手大喝采に見舞われた。
SKYFISHがクンタ・キンテのフレーズを流したのはその直後だ。ラスコの"Jahova"にチャック・モリスが歌う、"BASS LINE ADDICT"。続くRUMIのアンサーソング"BAD BWOY ADDICT"と、さすが、UK勢にも引けをとらないふたりのコンビネーションがフロアをぶちかました。今回のフェスで誰が一番のアクトだったかなんてことは、到底決められないけども、個人的にBASSを浴びる、いや、BASSをくらったのはNEO TOKYO BASSのときだ。腹にかなり直撃で受けてしまい、なんというかお腹のなかで内臓が揺れているのだ。いや、いま思い返せばそれが本当だったかはわからない。しかし、記憶していることは、体のなかが、なかごと、ようするに全身震えていたのだ。音が凶器にも感じた瞬間だった。ずっとフロアで聴いていたから低音には慣れているはずなのに、NEO TOKYO BASSがエグる、BASSの塊に完全にKOされてしまった。
メインフロアを出た後、グラス・ルームでは、KEN2D-SPECIALが"EL CONDOR PASA"を演奏していた。どうやらラスト・チューンだったらしく、もっと見たかったが、そこで久しぶりの友だちと会い、話をしながらINSIDEMAN aka Qのかけるディープなトラックに癒された。少し外で休憩した後はクタクタだったのもあり、グローカル・エリアの帽子屋チロリンにて少し談笑したりした。すぐ隣にあるグローカル・エリアで見た1TA-RAWから大石始への流れはトロピカル・ベース~ムーンバートン~クンビア~民謡と、自然に流れるダイナミクスへと昇華され、僕が見たグローカル・エリアでは一番のパーティ・ショットだった。そして最後に見たのは、OBRIGARRD(オブリガード)だ。ハウスのビートから徐々にブレイクビーツ、クンビアへとビートダウンしてく"Largebeats"~"Ground Cumbia"の流れは素晴らしく、個人的にエンディング・テーマを聴いているような、寂しく、狂おしい瞬間だった。
僕の〈Outlook Festival 2012 Japan〉Launch Partyは、こうして幕を閉じた。
いまになって思い返してみても、なんて素晴らしく、楽しい体験だったのだ。体験したすべての人たちが、それぞれの形で、記憶に残る2日間になったと思う。そして日本のベース・ミュージックにとっても、キーポイントとなるような歴史的な2日間だったのではないか。
出演していた あるアーティストに「今回出演できて、本当に良かった。もし、出演できていなかったら、自分がいままでベース・ミュージックを頑張ってきたことはなんだったんだろう? と、思っていたかもしれない」という話を聞いた。もちろん、自分も「出たいか?」と問われたら、即答で「出たい」と答えるだろう。それほどまでに、魅力溢れるパーティだ。個人的に思う〈Outlook Festival 2012 Japan Launch Party〉が残した大きな功績は、アーティストやDJたちが「次も出演したい」と、または「次は必ず出演したい」と、いわば、「目標」を主宰たちが知らず知らずのうちに創ったことだろう。その目標を叶えるためにも、来年、再来年と、また日本で〈Outlook Festival〉が開催されることを、切実に願っている。
Part2Styleとイーストオーディオ・サウンドシステム、会えた方々、関係者の方々、そして体験する機会を与えてくれた「ele-king」の松村正人さんとモブさんに最大級の感謝をここに記します。
追記
そしてこの夏、Part2Style Soundが2011年に引き続き、本場はクロアチアで開催される〈Outlook Festival 2012〉に出演する。本場のベース・ミュージック フェスティヴァアルに2年連続で出演し、何万人といった海外のオーディエンスを熱狂させることを思うと、同じ日本人としてとても誇らしい気分にさせてくれる。
きっと彼らはまた素晴らしい音楽体験を得た後、その景色を少しでも日本へと、形を変えて伝えようとしてくれるだろう。
進化し続ける「ベース・ミュージック」。未来のベース・ミュージックはどんな音が鳴っているのだろうか。
僕はその進化し続ける音楽を体感して追っていきたい。