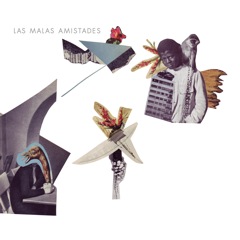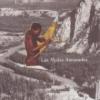MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Las Malas Amistades- Maleza
僕の生まれ育った町は、全国でも有数のサッカーどころとして知られている。小学校に入学すると、クラスのほとんどの子供は、3年生になると学校に唯一あった運動部のサッカー部に入る。運動場にはゴールがあり、昼休みにはサッカーをやる。このようにサッカーが盛んであることは、ただその人口が多いというだけの話ではない。そのスポーツに対する考え方も多様化し、深まることも意味する。僕の生まれ育った町には「外に出さないサッカー」を目指している指導者がいる。そう、つまり、ピンチのときもDFは外に出さない。極論すれば、コーナーキックはサッカーの本質ではないという発想だ。スポーツが勝負事であることを念頭におけば無茶な考えに思われるかもしれないが、スポーツを芸術と見るなら、創造的で、前衛的な考えだ。外に出さないサッカーが目指すのは、足(あるいは肩や頭)が手のように自由に動き、ボールを自在に扱える世界だ。
もっともこの前衛的な発想は、勝利至上主義の前で一掃される。ゆえに少年サッカーという、それでもわりと勝利至上主義から自由な領域で試される。僕はスポーツは、やるのも見るのも好きだが、オリンピックでいまひとつ面白くないのは、勝ち負けにしか脚光が当たらないことだ。柔道が良い例。僕が日本の柔道を好きなのは、僕が南米のサッカーが好きなのと同じ理由からで、そこに美学があるからだけれど、オリンピックではその美学は弱点となり、相手はそこを突いてくる。勝負事としての緊張感はあるが、美学の点では面白くない試合ばかりだ(※この話と清水エスパルスが勝てないこととは関係ありません)。
ラス・マラス・アミスタデス(悪友という意味)は1994年、コロンビアのボゴタにて、1994年に映画科に通う学生によって結成されている。結成当時はセルジュ・ゲンズブールとキャプテン・ビーフハートに影響されたそうだが。『VICE』という雑誌が「スペイン語で歌っているヤング・マーブル・ジャイアンツみたいだ」と書いたので、そのフレーズが日本でも広がっているようだが、実際はヤング・マーブル・ジャイアンツというよりはキャレクシコに似ている。複数のアコースティック・ギターのアンサンブルを基調とした漂泊の感覚を持ったDIYミュージックだ。
このアルバム『マレサ』は、〈オネスト・ジョンズ〉からは3枚目となるが、2007年に『パティオ・カツオ』というアルバムが3枚目のアルバムだとBBCは書いているので、BBCを信じるなら本作が4枚目となる(初期の5~6年の録音を編集した『ラ・ムジカ・デ・ラス・マラス・アミスタデス』が最初のアルバムだという)。
〈オネスト・ジョンズ〉から初めてのリリースとなった2005年の『ハーディン・インテリオール』や『パティオ・カツオ』では、カシオトーンやドラムマシン、玩具っぽいパーカッションなどを駆使している。音楽はよりローファイで、遊び心があり、トン・ゼーっぽくもある。が、新作『マレサ』は勝手が違う。ほとんど全編に渡って、アコースティック・ギターの音(たまにハーモニカ、控え目に電子音や鍵盤、パーカッションなど)で構成されている。3分から1分ほどの短い曲が28曲も収録されている。
アングロサクソン文化圏において、スペイン語のポップは、クンビアやキューバ音楽のような伝統的な音楽と違って、音楽としての面白味がよほどなければ受け入れられないとBBCは言っている。ラス・マラス・アミスタデスは、広く言えばトロピカリア(トロピカリズモ)の相続人でもある。スペイン語を知らない僕に歌詞の中身までは知りようもないが、レーベル側は音と歌を聴けばわかると言っている。希望とメランコリー、そして怒りが聴こえるでしょう......と。
『マレサ』は70年代前半のカエターノ・ヴェローゾのような美しさを持っている。ラテン的な感傷が時代の生々しい風のなかから聴こえる。僕はこのアルバムの1曲聴いて、買うことに迷いはなかった。ラス・マラス・アミスタデスの音楽と同様に、サッカーや柔道も美さを忘れないで欲しい。メダルの数ばかりを報道するテレビの醜悪さを見ながらつくづくそう思った。ちなみに『マレサ』とは、雑草という意味。
野田 努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE