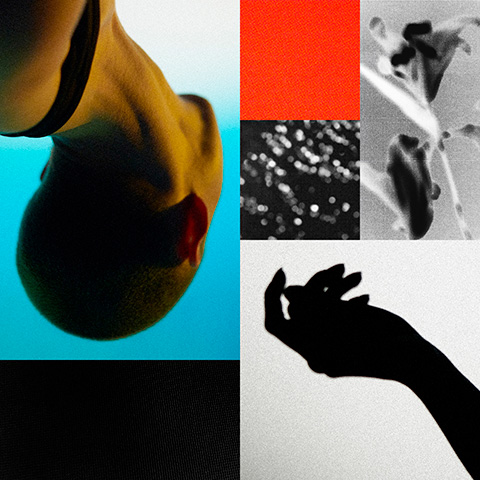Jeff Mills & Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música Planets U/M/A/A Inc.
|
まず確認しておくべきことがある。ザ・ウィザード時代に高速でヒップホップをミックスし、その後URのメンバーとしてヨーロッパを震撼させ、ソロでミニマル・テクノのフロンティアを切り拓いたあのジェフ・ミルズが、なんと今度はクラシックに取り組んだ! という意外性が重要なのではない。彼が幼い頃からSF映画などを通してクラシックに触れてきたであろうことを想像すると、今回のオーケストラとの共作がこれまでの彼の音楽的志向から大きく外れたものであると考えることはできない(実際この10年、彼はオーケストラとの共演を何度も重ねてきた)し、そもそもジェフ・ミルズのルーツであるディスコやハウスがいわば何でもアリの、それこそロックを上回るくらいの雑食性を具えたジャンルであったことを思い返すと、今回のアルバムがエレクトロニック・ミュージックからかけ離れたオーケストラの生演奏とがっつり向き合っていることも、これと言って驚くには値しない。ポルト・カサダムジカ交響楽団との共同名義で発表された新作『Planets』は、あくまでもこれまでの彼の歩みの延長線上にある作品である。だから、ちゃんとグルーヴもある。
とはいえ、ではこの新作がこれまでの彼の作品の焼き直しなのかと言うと、もちろんそんなことはない。アルバムを聴けばわかるように、このオーケストラ・サウンドとエレクトロニクスとの共存のさせ方は、以前のジェフ・ミルズ作品には見られなかったものである。徹底的にこだわり抜かれた細部のサウンドは、テクノ・ファンには「オーケストラでここまで表現できるのか」という驚きを与えるだろうし、クラシック・ファンにはかつてない新鮮な余韻と感歎をもたらすだろう。ホルストを踏まえた「惑星」というコンセプトにも、ジェフ・ミルズ独自の視点が導入されている。それに何よりこのアルバムには、黒人DJが白人ハイカルチャーの象徴たるオーケストラをコントロールするという文化的顛倒の醍醐味がある。
本作を制作するにあたりジェフ・ミルズ本人は、クラシックでもエレクトロニック・ミュージックでもない第3のジャンルへと到達することを目指していたそうだが、彼は1999年の『ele-king』のインタヴューで非常に興味深い発言を残している。「かつて僕は、スコアを書ける人間に自分の音楽を書き取らせようとしたことがあった・でも彼にはそれが出来なかった。というのもそこには、彼が上手く当てはまるような言葉にカテゴライズ出来ない要素がたくさんあったから」。要するに、ジェフ・ミルズの音楽をエンコードすることなどできないということだ。今回『Planets』で編曲を担当したシルヴェイン・グリオットは、しかし、見事にその不可能を可能にしてしまったということになる。だがそこで新たな困難が生じてしまった。プレイヤーがそのスコアを完全には再現できないのである。すなわち、オーケストラはジェフ・ミルズの音楽をデコードすることができないということだ。ゆえに彼は「譲歩」を強いられるが、まさにその折り合いのつけ方にこそ「第3のジャンル」の片鱗が示されていると言うべきだろう。だからこそ彼は本作に2枚組という構成を与え、オーケストラ・ヴァージョンとエレクトロニック・ヴァージョンを並置したのである。ジェフ・ミルズはいまコード化の可能性と脱コード化の不可能性とのはざまで、自らの音楽を更新しようと奮闘している。何しろ彼はこの作品を、100年先の人びとへも届けようとしているのだ。
クラシックやエレクトロニックのどちらでもない第3のジャンルのような音楽にまで到達できれば、と思いながら制作したね。
■今回の『プラネッツ』は、2005年の『ブルー・ポテンシャル』から始まり、10年以上にわたって続けられてきたオーケストラとのコラボレイションの集大成のような作品で、ジェフさんにとっても念願の作品だと聞いています。クレジットでは「作曲:ジェフ・ミルズ、編曲:シルヴェイン・グリオット」となっていますが、このアルバムはジェフさんが原曲を書き、シルヴェインさんが編曲して、それに基づいてポルト・カサダムジカ交響楽団が演奏をおこない、それを録音する、というプロセスで作られたのでしょうか?
ジェフ・ミルズ(Jeff Mills、以下JM):プロセスについてはいま言ったことで間違いないけど、編曲をする段階で編曲者のシルヴェインとすごくいろいろな話し合いを重ねたね。話し合いの内容は具体的なアレンジ方法というよりは曲のコンセプトについて、たとえば惑星がどういったもので構成されているかといったことについてで、物質的なことも含めて音として表現したいと思っていた。たとえば土星であれば、その輪の重要性や、あるいは輪が凄まじいスピードで廻っているということに関して、「それはテンポに反映するのがいいのではないか、ならば土星はいちばんテンポを早くしよう」というふうに、コンセプトや科学的な事実をどういった形で音に反映するかということを話し合った。その話し合いの後、シルヴェインが編曲し、また変更点を話し合うといったやりとりを何度もおこない、曲を完成させていったんだ。
■ホルストの「惑星」は神話がもとになっていますが、ジェフさんは科学的なデータに基づいてシルヴェインさんと曲を作っていったのですよね。神話の場合だと、たとえば「マーズは戦の神なので曲を荒々しく」というふうに曲のイメージがなんとなく想像できるのですが、惑星の物質的な要素を曲に反映させる場合は、いまおっしゃったような「土星の輪の回転速度をテンポに反映させる」といったこと以外に、どういったパターンがあるのでしょうか。
JM:僕もホルストからの影響は受けているよ。どういうことかと言うと、(僕は)実際の神話をもとにしてはいないけど、ホルストがそういった考えをもとに作曲したというそのことに影響を受けた。惑星に対してどういう見方をするかということを勉強した。僕の場合は、科学的な事実に基づくとともに、「僕たちが惑星をどのように見ているか」ということに重点を置いている。たとえばネプチューン(海王星)やプルート(冥王星)のような太陽系の端にある星というのは、いまだにわからないことが多くあって非常にミステリアスなんだけど、自分たち人間がまだすべてを把握できていないというその事実を音として表現したんだ。もう少し具体的な例を挙げれば、ガスで構成されている惑星、天王星や海王星は表面がはっきりと識別できないので、曲の雰囲気を軽くしてみたり、逆に岩石でできているような惑星は足元があるので、しっかりとしたソリッドな雰囲気で曲作りをおこなった。
■なるほど。科学的な事実に基づいているとのことですが、個人的にはこのアルバムを聴いていて、たとえば8曲目の“マーズ”からは戦のイメージを思い浮かべたり、10曲目の“ジュピター”からは神々しさのようなものを感じたりしました。それはあらかじめ聴き手がそういう神話を知ってしまっているためかなとも思ったのですが、神話ではないにせよ、ある程度はジェフさんも意識して、人間が持っている惑星のイメージや見方を曲に込めていらっしゃったと考えてもいいのでしょうか?
JM:君の言う通りで科学的な事実だけに特化したわけではなく、普段から影響を受けているSFであったり、宇宙科学はもちろんのこと、たとえば火星に関する映画であったり、実際の惑星の写真であったり、人間が蓄積してきたものすべてから影響を受け、作曲をおこなった。宇宙科学の話で言うと、今後人類が火星に行くかもしれないという段階に来ているので、そういったこともいろいろと考慮しながら曲を作ったよ。
■今回のアルバムはポルトガルのポルト・カサダムジカ交響楽団との共同名義となっています。ジェフさんはこれまでも様々なオーケストラと共演されてきたと思うのですが、今回一緒にアルバムを制作したポルト・カサダムジカ交響楽団が他のオーケストラと違っていたところがあれば教えてください。
JM:ポルト・カサダムジカ・オーケストラとは『プラネッツ』を制作する以前に別の作品で共演したことがあったんだ。その際に非常に良い印象だったことと、そのコンサートが大成功だったこともあって、オーケストラのマネージャーからも「また何か一緒にやりたい」という話をもらった。そのときちょうど『プラネッツ』を制作していたので、こういう作品を制作しているという話と、一緒にレコーディングしてみないかという話を伝えたところ、今回の共同制作が実現したんだ。
■6曲目“アース”を聴いていて、管楽器奏者の息継ぎ(ブレス)の音が効果的に使われているように感じました。またこの曲は他の曲とは違って唐突に終わり、すぐ次の曲に移りますよね。「地球」は私たちの住む星なので、やはりこの曲には他の惑星とは異なり何か特別な意味合いや思いが込められていたりするのでしょうか?
JM:アレンジャーとの話し合いの際に強調したことは、もちろん「地球」は僕たちがいちばん慣れ親しんでいる星なので、何かなじみのあるような音をシンプルな形で表現したいということだった。地球自体は太陽系の中でも比較的若い星であり、その若さというものを表現したかったし、地球はまだ進化し続けているので、はっきりとした結末を迎えるのではなく、アンフィニッシュな感じの曲作りをお願いしたんだ。曲自体の長さもあまり長くならないよう心がけた。僕がオリジナル・スケッチを制作した際は、わりとおとぎ話のような雰囲気を持たせ、子どものようなイタズラ感のある音作りをしたんだけど、それは地球がまだ若い星であることに注目したからなんだ。
■少し「地球」での出来事についてお伺いしたいと思います。去年アメリカで大統領選挙がおこなわれ、デトロイトでは失業したりした貧しい人たちがトランプに票を入れたという話を聞きました。まさにいまそのトランプが大統領に就任して、さっそく中東やアフリカからの入国を禁止する大統領令を発しています。彼はこれからもそういった政策をどんどん実行していくのだろうと思います。ジェフさんは昨年末『ハフィントン・ポスト』紙のインタヴューで、人種差別に関して「もう手遅れだ」というようなことをおっしゃっていましたが、このトランプの時代に何か私たちにできるポジティヴなことは残されていると思いますか?
JM:イッツ・ア・メス(めちゃくちゃだ)! この先4年間ローラー・コースターのようにいろいろなことが起こるだろうね。大統領たる人物が自分の好き勝手なことを躊躇せず発言しているけど、発言の細かい内容がどうこうではなく、そのような事態になってしまっているというモラルの低下がいちばんの大きな問題だと思っている。国のトップに立つ人物がそのような行動をすることによって、みんなに(悪い)例を示してしまっている状況だ。まだ大統領が就任して日が浅いから、これからそれがどのように影響していくのかはまだはっきりとは見えていないけど、みんなの雰囲気がいままでとは少し異なっているような印象を抱いている。インターネットの力もかなり大きいと思うけど、個人個人が好き勝手なことを発言してもそれが許されるという状況で、ますます洗練とは逆の方向に向かってしまった。その結果がどのような形になって現れるのか、はっきりとは言えないけれど、今後しばらくはこのような状況が続いてしまうのではないかと思う。ポジティヴなことは考えられないね。
[[SplitPage]]
僕が強調したかったのは「ミックスする」ということと「ミックスされた結果がどのようなものになるのか」ということなんだ。
■ではまたアルバムについての話に戻りたいと思います。12曲目“サターン”の打楽器は、とてもテクノ的あるいはエレクトロニック・ミュージック的な鳴り方をしているように聴こえました。終盤から電子音が乱入してきますが、弦楽器がピッツィカートでそれと呼応・並走して、エレクトロニクスと生楽器との間におもしろい共存関係が成立していると思いました。16曲目の“ネプチューン”でもピッツィカートが電子音のように使われていますよね。今回このアルバムを制作するにあたって、オーケストラの奏でるサウンドをエレクトロニックなサウンドに「近づける」、「似せる」というような意図はあったのでしょうか?
JM:どちらかと言うとクラシカルな音とエレクトロニックな音がうまく融合して、区別がつかないような音像にしたいというのが最終的な目標だった。特に太陽から離れていった、太陽系の端にある惑星に関しては、そういったミクスチャーをより強調していくことを心がけている。むしろクラシックやエレクトロニックのどちらでもない第3のジャンルのような音楽にまで到達できれば、と思いながら制作したね。
■なるほど。なぜこの質問をしたのかと言いますと、もし「近づける」ことが意図されていたのであれば非常に興味深いと思ったからです。実際は「似せる」ことではなく両者の区別がつかなくなることを意図されていたということですが、オーケストラ・サウンドをエレクトロニック・サウンドに「近づける」ことは、たとえば「人間がAIを模倣する」というような関係性に近いと思ったのです。一般的には機械やエレクトロニックなものは人間や自然を模倣して作られたものですが、それが逆転しているという関係性はおもしろいと思いました。もしそのような逆転があるとするならば、人類の未来のあり方としてそのような状況についてどのように考えますか?
JM:その考えはとてもおもしろいね。自分が考えていたのは2017年といういま人間が置かれている状況、つまり「ミックスされている」ことを表現したいということだった。人類が進化するにつれて性別や人種などいろいろなものが混じっていったということ。アメリカという国の成り立ちを踏まえても、「ミックス」という考え方を表現したかった。もうひとつ考えていたのは、与えられた情報をいかに有効活用するかということ。今回の『プラネッツ』に関しては科学的な情報を自分に取り込み、そこから何か新しいものを生み出すというような方法をとった。それは様々なことを伝える考え方で、僕が強調したかったのは「ミックスする」ということと「ミックスされた結果がどのようなものになるのか」ということなんだ。
■細かい音を連続で鳴らすときに、エレクトロニクスの場合はひとつの音をすぐ止めることができると思うのですが、生の楽器の場合は構造上どうしても残響が生じてしまいますよね。アルバムを聴いていると両者のその差が揺らぎのようなものを形成しているように感じて、それはたとえば宇宙空間の無重力などを演出しているのかなと思いました。エレクトロニクスとオーケストラを共演させる際に最も苦心したこと、苦労したことは何ですか?
JM:揺らぎのようなものについてだけど、今回の作品では「旅」がメイン・テーマになっていて、宇宙は無重力空間だから、太陽から徐々に離れて太陽系の外に向かっていくということを止めることはできないんだ。そのため(演奏が)沈黙(サイレンス)する状態がないようにすべてが延々と繋がっているような曲作りをした。その際に浮遊感のようなものを演出するため、いろいろな工夫を施している。苦心したことに関しては、ひとつには楽譜を作っていく段階で、特に後半の“ウラヌス”、“ネプチューン”、“プルート”は譜面が難しくて、ミュージシャンが演奏するのに苦労した部分が多々あったこと。あまり難しくしすぎると(オーケストラのメンバーが)ミスなく演奏できないということが起こりえるので、そのあたりは多少の譲歩があった。そういう意味では、レコーディングだと1度きりのパフォーマンスと違って何度も演奏し直すことができるし、ポスト・プロダクションでそれぞれの音を多少調整することもできるから、レコーディングに関しては比較的スムースにおこなえたよ。もうひとつ、難しいというか大変だったのが、僕自身の楽譜というものがないから、自分で演奏するパートはもちろん、他のミュージシャンの演奏する音をすべて暗記して本番に臨まなければならなかったということだね。それに、(自分には楽譜がないので)決められた中である程度即興的に演奏しなければならなかったこともすごく苦労した。
いまこれを聴いてくれる人たちはもちろん、自分が100年前に作られたホルストの「惑星」を聴いていまでも楽しめるように、この『プラネッツ』も100年先に生きている人びとにも聴いてもらえるのであればいいなと期待しながら作ったんだ。
■最終曲の“プルート”は終盤にノイズが続き、それが唐突に途切れて、その後15秒の沈黙(サイレンス)を経てトラックが終わりますよね。他方、ディスク2のエレクトロニック・ヴァージョンの方の“プルート”はフェイドアウトしていく終わり方です。オーケストラ・ヴァージョンの不思議な終わり方を聴いたとき、それまでアルバムの冒頭から旅を続けてきた人が急に宇宙という広大な空間に放り出されるような印象を抱きました。宇宙船なのか他のものなのかはわかりませんが、人類が自らの技術力に頼って最後の冥王星まで辿り着いた結果、難破してしまうようなイメージ、つまりある種のバッドエンドを想像したのですが、それは深読みでしょうか? なぜこのような形でアルバムを終わらせたのですか?
JM:“プルート”の終わりにあるノイズは、太陽系を出たところにカイパーベルトという宇宙の塵のようなもので構成されているリングがあるんだけど、それを塵=ホワイトノイズとして表現している。15秒のサイレンスについては、たしかに僕たちが実際に聴くことのできる形での音楽はそこで終わっているけれど、マスタリングの際に沈黙の部分を可能な限りレヴェルを高くして何度も何度もサイレンスを重ねることで、そこにじつは非常に高いレヴェルのサイレンスがあるようにしたんだ。もしもそこに沈黙ではなく音を配置したとしたら、スピーカーが飛んでしまうようなレヴェルの沈黙になっている。それはつまり、自分たちが知っている太陽系というものを出てしまった後は本当に未知の世界で、何がそこに潜んでいるのかわからないから、非常に注意しなければいけないという警告の意味があるんだ。なのでここで終わってしまった、ということではないね。
■ジェフさんは先ほどこのアルバムは「ジャーニー」がテーマであるとおっしゃっていましたが、頭から順番に通して聴いてみると次々に惑星を訪れていくような映像が頭に浮かびます。そこで旅をしているのは一体誰、または何なのでしょうか? 人類なのでしょうか? それともたとえばボイジャー探査機に搭載された人類の情報を刻んだレコードのような、人の思いや願い、あるいはメッセージのようなものなのでしょうか?
JM:旅をしているのは基本的に人間だ。誰のためにこれを作ったのかということを説明すると、いまこれを聴いてくれる人たちはもちろん、自分が100年前に作られたホルストの「惑星」を聴いていまでも楽しめるように、この『プラネッツ』も100年先に生きている人びとにも聴いてもらえるのであればいいなと期待しながら作ったんだ。この作品はそういう未来を見据えた考えに基づいている。“ループ・トランジット”という、惑星と惑星の間を旅するというコンセプトのセクションが9つあって、その箇所は現在の人間の知識では基本的に無の空間として認識されると思うんだけど、いまの人間の能力では何も見えず、何も聴こえず、何もわからないだけであって、もしかしたら何百年も経った後にはそこに何かがあるということを人間が発見するかもしれないよね。そういったことが起こりうるということを期待しつつ作曲したんだ。
■このアルバムはオーケストラのサウンドがメインになってはいますが、いくつかの曲からはいわゆる普通のクラシックの曲からは感じられないテクノやダンス・ミュージックのグルーヴが感じられました。それは意識して出されたものなのでしょうか? それとも自然と出てきたものなのでしょうか?
JM:僕のオリジナル(・ルーツ)としては、やはりグルーヴ(・ミュージック)から入っていったので、グルーヴについては入れ込めるところには可能な限り入れたいと思っている。アレンジャーのシルヴェインももともとジャズのピアニストなので、彼自身ファンキーなことはできるし、ふたりでできる限りそういった要素を入れることを試みたよ。
■このアルバムはCD2枚組になっていて、2枚目には1枚目の楽曲のオリジナル・エレクトロニック・ヴァージョンが収録されていますよね。両者を聴き比べるとその違いが際立ったり、いろいろなイメージが膨らんだりしておもしろいのですが、なぜこのような2枚組という形態にしたのでしょうか? 『プラネッツ』というアルバムはオーケストラ・ヴァージョンだけでは完結しない、ということなのでしょうか? それとも2枚目はあくまでボーナスあるいは参考資料のような位置づけなのでしょうか?
JM:(2枚組にしたのには)『プラネッツ』という作品の全体像をみんなに把握してもらいたいという意図があった。オリジナル・エレクトロニック・ヴァージョンの方もボーナスという位置づけではなくて、作品に欠かせない存在だ。あえてオリジナルのトラックをみんなに聴いてもらうことで、「クラシカルなアレンジをすることでそれがどのような変化を遂げたのか、どの部分が取り上げられてどの部分が取り上げられなかったのか」ということをいろいろと考えてもらったり、評価してほしいという意図があるんだ。