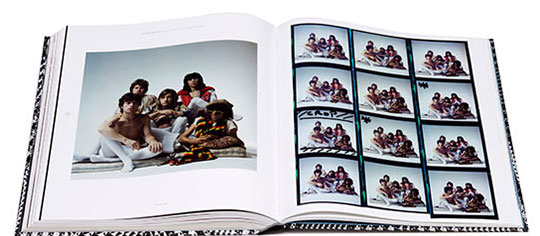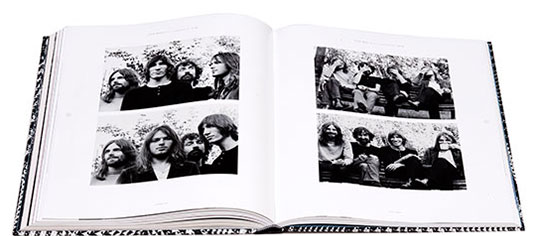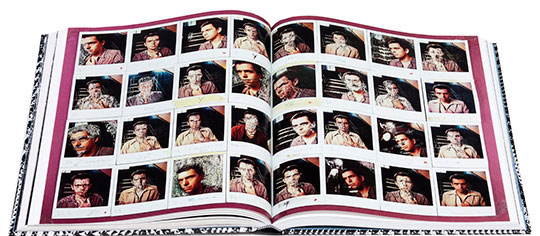DJ20周年の年、2014年は素晴らしい年でした。感謝の気持ちをこの10曲に(順不同) 2014/12/16
 1 |
Thomas Gandey, MATOM, Matthew Edwards - Piano Two Variation Four (Original) - Planet E Communications |
|---|---|
 2 |
Adam Beyer - The Nature of Keys (Original Mix) - Truesoul |
 3 |
J. Axel - Recreation (Original Mix) - Plastic City |
 4 |
Vince Watson - Freq (Original Mix) - Planet E Communications |
 5 |
Juju & Jordash - Clean-Cut(Original Mix) - Dekmantel |
 6 |
Mat.Joe - The Soul Inside (Original Mix) - Off Recordings |
 7 |
Agrande - Kelang (In Session Mix) - GR8 AL Music |
 8 |
Markus Fix - Geischa (Original Mix) - Cocoon Recordings |
 9 |
Legowelt - Disco Rout (Deetron) - Cocoon Recordings |
 10 |
Osunlade - Envision (Ame Remix) - Innervisions |
まだまだ続くDJ道!21年目もどーぞよろしくお願い致します!!
>>DJ FUMI Schedule
2014
[12月]
12/20 DJ FUMI 20th ANNIVERSARY SPECIAL "en21" x "皆殺し" @福岡 今泉 BlackOut
12/31-01/01 "VQ Count down NYE party" @Nimbin (Australia_Nimbin)
2015
[01月]
01/02 "3rd Eye Productions presents "Indigo Evolution New Years Festival" @2hrs from Byron Bay
01/04 "Buddah Bar with Dachanbo" @Buddha Bar (Australia_Byron Bay)
01/16 "Dosen't Matter" @New Guernica (Australia_Melbourne)
01/23-26 "Rainbow Serpent 2015" @Lexton (Australia_Victoria)
[01/24 05:30-07:00 Saturday Morning on the Sunset Stage]
01/31 "MACHINE" @MY AEON (Australia_Melbourne)
[2月]
02/13-16 "EARTH FREQUENCY FESTIVAL" @Ivory's Rock (Australia_QLD)
[Friday Night]
02/21 "Vitamin Q" @AVALON (Australia_Gold Coast)
[3月]
03/06-09 "Maitreya Festival 2015" @TBA (Australia)
[Saturday Night]
03/21 "RESPONSE" @東京
03/28 "TBA" @北海道