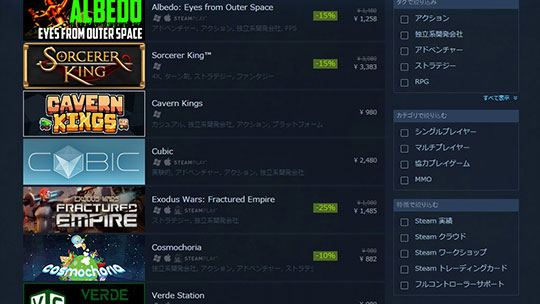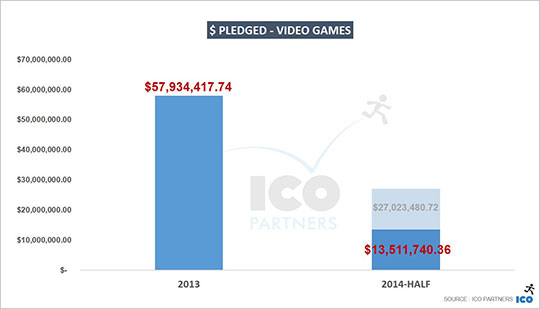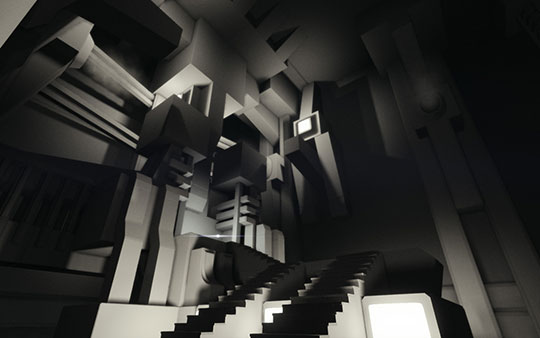直感的な感性を持つアーティストのひとつの特徴として、彼らは曲というものを自分とはべつに存在するひとつの生き物と見なし、その存在の証人となることができる、ということが挙げられる。究極的には音楽作りという行為自体の外側に立ち、音楽が生まれるプロセスの神秘に魅入られ、そしてそのプロセスの中に吸い込まれていくことができるのである。
──ジョー・ヘンリー
(ミシェル・ンデゲオチェロ『ウェザー』ライナーノーツより)
僕はいま、16FLIPの直感力とヒップホップへの一途な情熱と求道的な姿勢が無性に気になっている。直感力に関していえば、この、東京のヒップホップ・シーンを代表するひとりであるビートメイカーのリズム、グルーヴ、サンプリング・センスにたいして使われる“黒い”という形容詞以上の“何か”をそこにあるのではないかと感じている。
長年ヒップホップを徹底的に掘り下げてきた音楽家が、だからこそ何かを突き破りつつある、その過程をいま聴いているのかもしれない。けれども、直感はその人間の経験と知識から生み出されるもので、他人がそれを完璧に理解し、共有するなど無理な話だ。自分の耳だけを信じて、彼の音楽を聴いていればいいとも思うが、どうしても気になる。だから、話を訊いてみることにした。
きっかけのひとつは1年ほど前の出来事だ。2013年10月某日、とある渋谷のクラブでDJした16FLIPは、ドクター・ドレとスヌープの“ナッシン・バット・ア・G・サング”とギャングスターの“ロイヤリティ”を何気なくスピンした。これまで何十回、もしかしたら百回以上は聴いたであろうこの2曲のクラシックが、まったく別の輝きを放って耳に飛び込んできたことに僕は震えた。
90年代のUSヒップホップの音響やリズムが、2013年の耳を通して新鮮な感覚を呼び起こしただけではなかった。この感覚は何だろうか? そのときたしかに、「16FLIPにしか聴こえていない音とグルーヴ」を感じて、その後あらためて16FLIPのビートに関心を抱くようになった。
 06-13 16FLIP DOGEAR RECORDS |
ISSUGIや5LACKやMONJUをはじめ、BES、KID FRESINO、JUSWANNA、SICK TEAMといった数多くのラッパーやグループへのトラック提供で知られるこのビートメイカーは今年、2006年から2013年までに制作したトラックを収めたセカンド『06-13』と3枚のミックスCD(『OL'TIME KILLIN' vol.1』『OL'TIME KILLIN' vol.2』『SKARFACE MIX』)を発表している。すべてのトラックを手がけたISSUGIのサード・アルバム『EARR』のインストのアナログ盤『EARR : FLIPSTRUMENTAL-2LP-』のリリースも予定されている。
まったくもって派手な宣伝や露出はないものの、16FLIPの音楽と存在は街にじわじわと浸透しつづけている。ファンの彼に対するまなざしは本当に熱い。すごいことだ。
取材は今年の5月後半におこなった。ここでの僕の望みはふたつ。16FLIPのファンはより深く彼のことを知る手がかりにしてもらえればうれしい。そして、16FLIPを知らない人はこのインタヴューをきっかけに彼の音楽に耳を傾けてくれたならばありがたい。
リー・ペリーとかマックス・ロメオとか、レゲエの人たちが、わけのわからない年代で区切って作品を出したりするじゃないですか。“86-92”みたいな感じで。
■最初にトラックを作ったのはいつで、きっかけはなんだったかという話から訊かせてもらえますか。
16FLIP:友だちのDJの家にMPCがあったんですよね。中3か高1ぐらいですね。で、そいつがいないときとかに遊びで作っていて、MPCを自分もほしいなって。それがきっかけだと思いますね。たぶん、自分で作るのがいちばん新鮮に感じてたと思うんすよね。そういう経験がなかったから。だから、やりだしたのかもしれない。でも、作らない時期もかなりありましたね。ちょこちょこ作ってたんですけど、あんまり上手く行かねぇなって。で、MONJUの作品を出すかってなったときに、またちゃんとやりだした感じだと思います。オレのトラックで、MONJUで1曲録ったら、わりとしっくりくるっていうことになって(笑)。それが、『103LAB.EP』(2006年)の“THINK”っていう曲なんです。その曲のトラック違いのやつがあって、それを最初に作ったんです。そこから、『103LAB.EP』を作る流れになったような気がします。
■16FLIP名義で最初に世に出たトラックは、JUSWANNAのEP『湾岸SEAWEED』(2006年)に入ってる“東京Discovery”と“ブストゲスノエズ”なんですよね。
16FLIP:そうなんすよ。仙人掌の家に遊びに行ったときにメシア(THE フライ)も遊びに来たりしてて、そのときにトラックを作ったような気がしますね。レコーディング・スタジオに連れていってもらってミックスしてもらって、スタジオで爆音で聴いてたのを思いだすっす。いま思うと参加するチャンスをくれたことに本当に感謝してます。
■『06-13』は、2006年から2013年までの作品を集めたアルバムですよね。2007年からにすることもできたわけだし、ベスト的な作品にすることもできたわけですよね。どうしてこの期間に絞ったんですか?
16FLIP:ベスト的なことを書いてくれている人も多いんですけど、自分はベストを出してるっていう気持ちはなくて。リー・ペリーとかマックス・ロメオとか、レゲエの人たちが、わけのわからない年代で区切って作品を出したりするじゃないですか。“86-92”みたいな感じで。そういう気分で出したつもりなんです。アルバムの題名を付けるのも好きなんですけど、題名は最終的にあってもなくてもいいかなって思ってる自分もいるんですよ。2006年に作ったトラックは一曲ぐらいしかないと思うんですけど。
■それはどれですか?
16FLIP:たぶん、“Oitachi”だけですね。
■選曲の基準みたいなものはあったんですか?
16FLIP:基準はいつも直感なんですよね。「いまはこの曲だな」みたいな感じですね。だから、1ヶ月とか2ヶ月経ったら違う曲を選ぶと思うし、1年かけて十何曲選びましたとかじゃなくて、「出すか」って決めて、パッパッパッパッパッみたいな感じで選びましたね。
■ほとんどが2分以内、長くても3分ぐらいのトラックばかりですよね。サンプリング一発で、いい意味で遊びの感覚にあふれた作品集だなって感じました。ダブ的というか、ノリだけじゃないけど、ノリを大事にしてる感じがすごく伝わってくるというか。
16FLIP:そうっすね。最近、前よりもDJとして呼んでもらえる機会が増えて、それが作るときにいろいろ活かされてるなって自分では思うんですよね。DJ的感覚で一枚のものをまとめたいっていう気持ちがすごいありましたね。だから、自分の曲でDJやってる感じっすね。
■“NEWDAY”も入ってますよね。仙人掌くんにインタヴューさせてもらったときに、「自分が客演した曲のなかで印象に残っている曲は?」って訊いたら、真っ先に挙げてきたのがこの曲だったんですよ。
ISSUGI feat.仙人掌“NEWDAY”
16FLIP:それはあがるっすね。(仙人掌と)こないだ話したんすけど、まじでいままで何曲フィーチャリングしたかすぐには把握できないくらいあるよねって言ってたんですよね。基本的になにをサンプリングしてトラックを作ったとか、あんまり憶えていないんですけど、“NEWDAY”に関してはまじでわかんなくて。そういう系のトラックなんですよね。いまはもう作れないだろうし、オレはトラックに関しても2度と作れないものが好きなんですよね。
■まさに直感というか、瞬間の閃きの人なんですね。
16FLIP:しかも、その直感がそのときで消えちゃったらそれでべつにいいと思ってますね。
[[SplitPage]]いけるときは、たぶん10分ぐらいでいけますね。時間かけてもいいものができるっていうのは、オレのトラックにはないんですよ。
■YouTubeにトラックを作っているときの映像がアップされてるじゃないですか。いつもああやってひとりで作ってるんですか?
16FLIP:だいたいそうっすね。あとは友だちの家とか大阪とか行ったりしたときもたまにトラック作ったりしてるんですよね。DJやりに行ったときとかに。
Making beat with 16FLIP/ "Smokytown callin" comingsoon
■へぇぇ。それは、MPCを持ってくんですか?
16FLIP:いや、大阪に〈Fedup〉っていう、いつも行ったときお世話になってるお店があって自分たちのCDとかも置いてもらったりしていて。その横が〈Fedup〉のスタジオになっていてMPCとかもあって、遊びに行ったら使わせてくれるんすよね。C-L-CとかDJ K FLASHとかが「いいネタあったで」みたいな感じで教えてくれるから、「おお、ヤベェ! じゃあ、作ろう」って、作ったりしてますね。『II BARRET』にも大阪で作ったトラックが入ってますね。“No more ballad”のトラックです。
■他にも〈Fedup〉で作ったトラックはたくさんある?
16FLIP:ありますね。大阪で10曲以上は作ってるんで、それをまとめてCDを出そうと思ってます。MPCがあればどこでも作れますね。ニューヨークに行ったときも、スクラッチ・ナイスの家で一週間に10曲ぐらい作って楽しかったっすね。
■早くて1曲何分とかで作れちゃいますか?
16FLIP:いけるときは、たぶん10分ぐらいでいけますね。時間かけてもいいものができるっていうのは、オレのトラックにはないんですよ。そういう作り方は自分に合ってないですね。だから、できたトラックに手も加えないっすね。
■ほんと潔いですよね。そういえば、遅ればせながら、16FLIP VS SEEDA『ROOTS & BUDS』(SEEDA『花と雨』を16FLIPが全曲リミックスした作品。2007年発表)を聴きました。評判だけはまわりの友だちから聞いてて。でも、あの作品は手に入りにくいし、中古でも高値じゃないですか。いや、とにかく、あのクラシックを完璧に16FLIPの世界に塗り替えているのに驚いたし、すごくかっこよかったです。あの作品はどういう経緯で作ったんですか?
16FLIP:当時、ナインス・ワンダーがナズの『ゴッズ・サン』(2002年)をリミックスしたアルバム(『ゴッズ・ステップサン』(2003年))を聴いて、それがかっこいいと思ったんですよね。トラックメイカーがラッパーのアカペラを使ってリミックス・アルバムを作って名を上げるハシリ的な感じだったと思うんですよ。それ以前もそういうのはあったかもしれないけど、ナインス・ワンダーはそこらへんのやり方がなんかかっこよくて。その後PUGが面白いこと考えてきたんです。『花と雨』が出たときに〈HARVEST SHOP〉で買うと特典でアカペラのCDRがついてきたんですけど、ちょうどMONJUの『BLACK DE.EP』(2008年)を出すのが決まってた時期で、「その前に一発カマしたほうがいい」みたいなことを言ってて。それで、もちろんSEEDAくんにも許可をもらって作ったんですよね。16FLIPを知らない人もSEEDAくんのリミックス盤だからってことで聴いてくれた人もたくさんいたと思うし、SEEDAくんには感謝してますね。
■いまだに聴けていない人が多いのももったいないし、いま再発しても大きな反響があるんじゃないかと思ったぐらいです、ほんとに。
16FLIP:まじっすか!? それはありがたいです。
■はい。さっきも話に出ましたけど、最近はDJもよくやってますよね。手前味噌ですけど、僕が16FLIPくんにミックスCD(『OL'TIME KILLIN' vol.1』『OL'TIME KILLIN' vol.2』。〈ディスクユニオン〉限定販売)の制作を依頼したのも、こうやってインタヴューさせてもらってるのも、そもそもは去年の10月に16FLIPくんのDJに打ちのめされたのがきっかけだったんです。あのとき、ドクター・ドレとスヌープの“ナッシン・バット・ア・G・サング”と、ギャングスターの“ロイヤリティ”をかけたじゃないですか。
16FLIP:はい、かけましたね。
Dr.Dre feat. Snoop Doggy Dogg“Nuthin But a 'G' Thang”
Gang Starr feat. K-CI & JOJO“Royalty”
■自分はあの2曲をこれまでさんざん聴いてきたんですけど、あんなふうに聴こえたことがなかったというか、まだ上手く言葉にできないんですけど、「16FLIPだけに聴こえてる音とグルーヴがあるんだな」って実感したんですよ。
16FLIP:それ、すげぇうれしいっす。かける人によって、同じ曲でも違って聴かせられるのがDJのおもしろいところだし、ライヴDJが同じインストかけるにしても、かける人によって感じ方とか威力がそれぞれ違うんですよね。そいつの醸すものがそのまんま出るんですよね。だから、ライヴも関係性が高いほうがいいと思いますね。
■関係性というのは、ライヴの出演者同士の?
16FLIP:出演者同士のではなくて、MCとライヴDJの場合っすね。人間の関係性もグルーヴだと思うんですよ。
■ああ、なるほど。そのDJのあとに話したときに、16FLIPくんが、「ヒップホップだけで、ヒップホップをあまり聴かない音楽好きの人をヤバイと言わせたい」みたいなことを言ってて、それが16FLIPの音楽をまさに言い表していると感じたんですよね。
16FLIP:やっぱり自分は、ヒップホップがいちばんカッコいいと思ってるから。まあもちろん……
■比べることじゃないけど……
自分の音楽がヤバイっていうよりも、自分の音楽を通したときに、「ヒップホップってヤバイな」ってならないとダメだとオレは思っていて。
16FLIP:そう、比べるものじゃないですけど、たとえばレゲエだったらレゲエがいちばんヤバイと思ってる人の音楽が聴きたいってことですね。自分にとってヒップホップは他には代えられないものだから。自分の音楽がヤバイっていうよりも、自分の音楽を通したときに、「ヒップホップってヤバイな」ってならないとダメだとオレは思っていて。自分がいろんな人のヒップホップを通して、ヒップホップの良さを知ったんで。そういう感じですね。
■16FLIPの音楽、ビート、トラックは、たとえばいまアメリカで売れている主流のヒップホップの派手さや煌びやかさとは真逆にあるわけじゃないですか。もちろん、アメリカにもそういうヒップホップはたくさんあって、ロック・マルシアーノやエヴィデンスのような人は主流や流行と関係ないところでずっと音楽を続けてきたと思うんですね。16FLIPもまさにそうだと思うんです。自分たちが主流や流行とは違う音楽をやっていることに迷いや不安を感じたことはなかったですか?
16FLIP:それはまじにないっすね(キッパリ)。
■ははははは。
16FLIP:そういうことを自分で考えたこともなかったですね。派手だとか、アンダーグラウンドだとか、そういうことを考えてないからっていうのもあると思います。流行のヒップホップのなかにもヤバイものはあるし、逆に、自分たちと同じスタイルというか、近いテイストでもダメなものは絶対あるから。どういうのが良くて、どういうのがダメかっていう基準が自分のなかにあるんです。たぶんそうなんすよね。だから、変わんないのかもしれないですね。
■その話で思い出したんですけど、2年前ぐらいの〈WENOD〉のウェブ・サイトのインタヴューで印象に残ってる発言があるんですよ。DJプレミアについて、「ブレる事を知らない人の音からでるパワーってすごくて」(https://blog.wenod.com/?eid=206126)って語ってるじゃないですか。いままさに16FLIPの音も円熟……というのは早い気がしますけど、そういう段階に入りつつあるのかなって感じるんです。
16FLIP:ピート・ロックでも、J・ディラでも、ティンバランドでもいいんですけど、ずっと続けているヤツの重みがオレは好きなんですよね。
■僕が16FLIPくんに清々しさを感じるのは、サンプリング・ネタの曲やミュージシャンやレコードに頓着しないところなんですよね。
16FLIP:そうっすね。オレ、ぜんぜんそういうの気にしないっすね。
■トラックメイカーやビートメイカーやDJのなかには、マニア気質の人たちもいるじゃないですか。16FLIPくんはまったく正反対でしょ。
16FLIP:同じネタでトラックを作っても、違う人間がやったら、絶対に違うものになるし、同じものは作れないじゃないですか。だから、誰々の曲を使ってるとか、オレはまったくどうでもいいんですよ。そういうとこには興味がないんですよね。
■だから、『06-13』でも他の人は避けそうなソウルやファンクの大ネタをためらいなくドッカ~ンと使ってるじゃないですか?(笑)
16FLIP:はい、ドッカ~ンっすね。だからオレ、レアかどうかとかって、すごく嫌いなんですよ。そんなの音楽の価値に関係ないんですよね。自分の良いか悪いかしか判断基準にならないんです。たとえば、5万円のレコードがあっても、オレが良いと思わなかったらDJでかけないし、逆に2円で買ったレコードでもヤバかったらかけますね。どんなネタを使っても、オレが作ったらオレの作り方になるし、DJでも、オレがかけたらオレのかけ方になるっていうのがわかってるんですよね。
■それを僕は去年の10月の16FLIPのDJに感じたんでしょうね。
16FLIP:そう感じてもらえたことがすげぇうれしいんですよね。それは自分にとって重要なことです。オレも人のDJのそういうところを感じてるし、それこそ“ロイヤリティ”を聴いて、「ああ、懐かしいね」で終わっちゃう人もいるかもしれないけど、オレにとっては永遠にヤバイ曲なんですよ。いつ聴いても良いんですよ。だから、その曲が有名だろうが、初めて聴く曲だろうが、関係ない。きっとそういうことなんですよね。
ワンループにこだわってるわけではないんですけど、最初はMPCのパッドが16個だったから、16FLIPにしたんですよ。
■ところで、16FLIPっていう名前は何に由来しているんですか? 16は16小節からきているのかなと思ったんですけど。そうだとしたら、16FLIPのワンループの美学へのこだわりを考えると、的を射ているなって。
16FLIP:ああ、たしかに。ワンループにこだわってるわけではないんですけど、最初はMPCのパッドが16個だったから、16FLIPにしたんですよ。自分にいちばん合ってるのは、そういうシンプルな名前だなと思って。いまとなってはなんでもいいかなって思いますね。けっきょく名前とかって、やってるヤツ次第でかっこよくも感じられるし、ダサくも感じられるから。あとはスケボーをやってたから、単純にFLIPっていう言葉が好きだったと思うんですよね。で、ヒップホップのトラックの作り方のなかにも、FLIPっていう言葉があったから、そのふたつを掛けたのかもしれないですね。ひっくり返すっていう意味もあるし。
■ISSUGIのファースト『THURSDAY』(2009年)に提供した“GOOD EVENING”ってインタルードはスケボーの音で作られてますよね。ほんとに美しくて瑞々しいインタルードですよね、あれは。
16FLIP:(スケボーの音を)入れてましたね。
■あのころから5年経ったわけじゃないですか。年齢とともに遊び方も変わったり、生活の変化もあったり、環境も少なからず変わったと思うんですけど、そういう変化は音に反映されたりしてますか?
16FLIP:う~ん……、環境はどんどん変わっていってると思いますけど、トラックを作ることに対しては、とくに変わってない感じなんすよね。もちろん聴いてる音楽もその時々で違いますし、生活の変化も音楽に影響してるとは思うんですけど。ただ、音楽に対して、昔より柔軟になったっていうか、理屈っぽさがさらになくなってきてるかもしれない。
■へええ、16FLIPくんが自分のことをそう考えていたとはちょっと驚きです。音楽に関して理屈っぽく考えていたとこもあったんですか?
16FLIP:いや、なんて言えばいいんすかね、そういう理屈とか関係ない自分でさえ、ちょっと理屈っぽかったのかなって思っちゃうときはあったかもしれないっすね。
■自分に理屈っぽさを感じたのはどういうところに? ヒップホップに対してストイック過ぎるとか?
16FLIP:いや、そういう部分じゃないんです。なんていうんだろう、昔はいまよりも硬かったっすね、グルーヴが。いまのほうがよりスムースになっていってると思うんですよ。そういう感じですかね。なんか、オレ、動物的になっていくのがすげぇいいと勝手に思ってて。
■ああ、なるほど。16FLIPくんが言うその言葉には説得力がありますよね。ただ一方で、こんなこと訊くのも無粋ですけど、一般的には、年齢を重ねると、たとえば家族のことだったり、お金のことだったり、若いころとは違った不安や焦りも生まれたりするだろうし、頭が固くなってしまうというのも一面ではあると思うんですよ。そういうことは感じたりしませんか?
16FLIP:でも、そういうことがあったとしても、音楽には及ばないというか、音楽には影響しないですね。生活の変化は音楽に影響はしてるんですけど、ヘンな音楽を作って、自分が空しい思いをするとしたら作んないほうがいいって思ってますね。余計な考えとかはいらないっすね。うまく説明できないんですけど、そうっすね、自分は自分の音楽がどんどん変化していくのがおもしろいし、それを楽しんでるんですよね。音楽は自分のやりたいことを100%出すのがいいと思いますね。それが前提ですね。
■16FLIPくんの音楽に対するストイックな姿勢に接すると背筋が伸びる思いがしますよ。
16FLIP:ほんとっすか?
■いや、ほんとに正直な気持ちです。オレとかやっぱだらしない人間だから(笑)。
16FLIP:そうすか?
■ははは。
16FLIP:いやー。
■やっぱり人間、いろんな欲もあるじゃないですか。
16FLIP:そうっすね。たしかに。
■16FLIPくんほどの人気があれば、一獲千金……じゃないですけど、もっとギラギラしてても不思議じゃないと思うんですよ。
16FLIP:一獲千金(笑)。ヘンなことしてヒップホップで一獲千金できると思ってないですからね。
■はははは。
16FLIP:もしもですけど、一獲千金する方法があるとすれば、たぶん自分のやり方を貫くことだと思ってますね。自分を貫かなかったら、一獲千金どころか、泥の舟に乗ってるようなものだと思うんですよ。音楽を長く続けるコツは、自分のスタイルを持って続けることだと思うんで。絶対。なんかヘンなことをやったら、自分の寿命を縮めるだけだと思うし、実際そうだと思うんすよね。だって、それでうまく行く人とかあまり見たことないし(笑)。そういう気持ちって人に伝わるじゃないですか。
■そうですね。音から伝わりますね。
16FLIP:わかるっすもんね。「あ、こいつ変わったな」みたいになっちゃうと思うんすよ。
俺のなかではラッパーやDJが“B-BOY”じゃなくなったときに、がっかりするっていうか、悲しくなりますね。「ヒップホップを捨てたなあ」みたいなときが。
■リスナーもそこは厳しく見てますよね。僕は、ファンやリスナーは薄情な一面もあると思っていて、自分が好きなミュージシャンやラッパーやDJのスタイルが変化したら、見捨てるときはあっさり見捨てたりもするじゃないですか。
16FLIP:俺のなかではラッパーやDJが“B-BOY”じゃなくなったときに、がっかりするっていうか、悲しくなりますね。「ヒップホップを捨てたなあ」みたいなときが。そうなっちゃったときに、自分のなかでは完全に終わると思ってます。
■たとえば、メソッドマンにしろ、ナズにしろ、あれだけポップなフィールドでも活躍して、ポップな曲も作って、カネも得ているけれど、いつまでもヒップホップしていて、カッコいいですよね。
16FLIP:カッコいい人はいますね。オレ、スヌープやっぱり好きですね。あと自分は、誰々の“この1曲”が好きっていうよりは、“その人”の作るものが好きだっていう感じなんですよ。だから、ミックスを聴いてくれる人とかも入ってる曲をそうやって聴いてもらえたら、うれしいっすね。
■“人間を聴いてる”という感じですかね。
16FLIP:そうっすね。あと、他の人が聴かなくなっても、自分が好きだったら聴いていればいいし、そういうもんだと思うんですよ、音楽って。
■16FLIPにとって、ヒップホップって何でしょう?
16FLIP:最終的には、曲を作ることが、自分のヒップホップを表現する行為と同じことだと思ってますね。DJにしても、ラッパーにしても、そうなんですよね。「自分のヒップホップはこういうもんだ」と思ってるものが出ちゃう、ただそれだけだと思ってます。
■実は今日、16FLIPくんに会う前にECDさんにインタヴューしてきたんですよ。本人はどう考えているかはわからないけれど、ECDは相変わらず、いまの16FLIPくんの言う意味での“B-BOY”なんだなってすごく感じて。
16FLIP:そうっすね。それはすげぇ思います。
■1960年生まれだから、今年で54歳ですよね。
16FLIP:まじでリスペクトですね。
■16FLIPくんは自分の音楽家としての未来を考えたりしますか?
16FLIP:自分もそれぐらいの歳までバリバリ音楽を続けて、54になってもニュー・アルバム出したいっすね。自分が54になったときは、いまよりヤバイと思ってますね。長く続ける存在が日本にたくさんいたほうがいいと思うんですよね。年取ってやらなくなっちゃうってことは、ヒップホップが根付いていないってことじゃないですか。その歳になっても音楽をやってるほうが自然だと思うし。若いヤツの音楽ももちろん好きだけど、50代とかオッサンしか出せないヤバさは絶対ありますからね。アレサ・フランクリンとかアンジー・ストーンの音楽にしてもやっぱ演奏とかまじでヤバイし、渋いじゃないですか。そういう人たちしか出せないもんがあると思うんですよ。
だから、オレが38ぐらいになって、アルバム出したとするじゃないですか。そのときに、はじめて『EARR』とかを聴くヤツがいてもいいと思うし、いつだって何を聴くヤツがいてもいいと思う。自分だって、いまはもう死んでいるヤツの昔の音楽をガンガン聴いてるわけじゃないですか。だからみんな、もっと好き勝手やればいいのにっていっつも思ってますね。もっと好き勝手やったほうがかっこいいものができるし。いまヤバくて、10年後もヤバイのが絶対いいっすね。そういう耳で自分は音楽を聴いてますね。自分がヤバイって思うものは、いまだけヤバイものじゃなくて、永遠にヤバイんです。
BEEF / MOSDEF (16FLIP REMIX)